
the engy 撮影=鈴木 恵
2014年結成で京都を拠点に活動してきたバンド、the engy。現体制の4ピースとなったのは2017年春で、まだ2年強のヒストリーにも関わらず、楽曲評価が高く、昨年(2018年)のSpotify主催イベント『Early Noise Night』やフジテレビ『Love music』の「Come music」などに出演。Apple Music「今週のNEWARTIST」に選出、Spotifyで複数のプレイリストにピックアップされるなど、ストリーミング世代を中心に“曲の良さファースト“で急速に支持を高めている。実際、現行のR&Bやヒップホップ、ファンクを軸に、生音のダイナミズムと打ち込みのスクエアなニュアンスを融合したサウンドスケープを構築。何より歌メロの強さが耳に残るのも魅力的だ。今回はメジャー第一弾作品となるミニアルバム『Talking about a Talk』リリースタイミングでメンバー全員インタビューを実施。洗練されたサウンドと、どこかほっこりするキャラクターのギャップに驚きを感じつつ、このバンドのユニークさの一端に触れられる会話になったと思う。
――山路さんと濱田さんは大学のサークルが一緒だったそうで。どんなカラーのサークルでしたか?
山路洸至(Vo/Gt/Programming):オリジナルを作って演奏しましょうっていうサークルでした。そこの会長だったんですけど、僕の代、一人しかいなかったんで自動的に繰り上がりでなったんですけど(笑)。その時に、ライブに向けて合宿的なことをしようと。でも合宿の宿をとるのが大変なので泊まらない合宿をしようとか、わけのわからんことを言って。「泊まらへんけどこれは合宿や」って(笑)。で、ベースの濱田はギター&ボーカルだったんですけど、「ベース弾ける?」って聞いたら「弾けます」って言ったんで、「じゃあお前弾け!」って。
――さすが会長(笑)。今回のフルアルバムを聴くと、山路さんってやっぱり歌うの好きな人なんだなって思いました。ザ・ボーカリストですよ。
山路:ほんとですか。そもそも歌は、好きは好きですけど、歌うまいとか、声がいいとかわからずとにかくにバンドを始めてみたら、声がいいって言われて。もともとギタリスト志望だったので、ギターを褒めてもらえると思ったら、歌を褒めてもらえたんで、“そっちですか?”みたいな感じになって。じゃあ頑張ってみようかな、と。喜んでもらえるならみたいな感じで始めたのが最初でしたね。
――バンドとしてはどんなことを軸に始まったんですか?
山路:ずっと変わらずにあるのは、とにかくかっこいいって自分らが思う曲を作ろうっていうことだけで。曲作りが好きなので、題材はなんでもよくて。すごくロックな曲を作るのも楽しいし、エレクトロの曲を作っても楽しいし、っていうのをやる中で、今こういうグルーヴっぽいのがきてるらしい、じゃあ一回やってみよう、みたいな感じで取り入れて行った感じでしたね。
――基本的に作詞作曲は全て山路さんですか?
山路:そうです。デモを僕が作って、みんなに聴かせて、で、みんなのテンションが上がったやつをやっていくっていう形ですね。
――そもそもの志向性は皆さんバラバラなんですか?
濱田周作(Ba):バラバラですね。
境井祐人(Dr):全然違うけど、結局全員、山路の作る曲と歌が好きっていうのはあるんです。
――いわば踊れる音楽でソウルやファンク、時にインディR&B的なものもある、だけどそれそのままじゃないというか。
山路:そうですね。僕はもともとリンキンパークとレッチリが大好きで、一生懸命歌ってたら「ブラックだね」って言われて、「一応聞きますけどコーヒーのことではないですよね?」みたいな(笑)。それはわかってますけど、一応、ミュージシャンですけど、ぐらいの知識で。「じゃあこういうの聴いてみたら?」って言われて「アラバマ・シェイクス知ってる?」って言われて、「人ですか? バンドですか?」みたいな感じでやって行ってた感じで。濱田とかはもう全然別の邦ロック、スピッツ、くるりとかが好きで。
濱田:このバンドを始めるにあたって、ブラックとかヒップホップを聴き始めた感じです。で、藤田さんは結構、ヒーリング的な。
藤田恭輔(Gt/Syn/Cho):はい。ビョークとかを一番聴いてて。
――ビョークはヒーリング系ではないのでは(笑)。
藤田:実験音楽とか環境音楽とか、そういうのがもともと好きで。
境井:どっちかというと技術畑から出てるんで、テクニカルなやつやったりして。でもバンドに入ってからは色々聴くようになりました。もともとドラムが楽曲に入ってる曲しか聴いてなかったんですけど、最近、打ち込みのドラムが入ってる曲であったり、ドラムがない曲も結構聴くようになりました。
――同世代でもみんな背景が全然違うんですね。
山路:そこを基準にメンバーを選んだんではないんで。“こういうのをしたい”っていうのがあってバンドを組むのが普通やと思うんですけど、「お前いける? じゃ、やって」みたいな(笑)。
――(笑)。プラス人柄?
山路:やっぱり、結局やってれば上手くなりますから、人は。

the engy/山路洸至(Vo,Gt) 撮影=鈴木 恵
曲を出してご飯が食べたい、出来るだけ美味しいご飯が食べたいです。
――ちなみにthe engyってどういう意味なんですか?
山路:これはですね“縁起いい”バンドになればいいなと思って、the engyにしました。誇らしく思います(笑)。
――意外すぎる(笑)。サウンドだけ聴くと、日本のバンドだと思えなかったりしますけどね。
山路:それは言っていただいて嬉しい部分ではあるんですけど。僕が通ってきた音楽がほぼ洋楽なんで、どっちかといえばそっちに寄せて曲を作る方が自然というか、曲作りのノウハウみたいなものもなくって、ライブハウスも見に行ったことなかったので。グラミー獲ってる人とかの曲を聴いて、“あ、こういう風に作るんや、曲って”みたいな。で、そこに勝負するわけです、Jay-Zとかと(笑)。
――ブルーノ・マーズとか?
山路:そうなんですよ。ブルーノ・マーズに勝てないんですよ。
――どうだったら勝ちなんですか?
山路:やっぱり“勝ったな”って思った時(笑)。作った時は“勝った”って思うんですけど、もう一回聴いたら負けてるんですよねっていう、勝負とかをして。ずっとそういう形で曲作りをしてたので、必然的に洋楽っぽくなってるのかな?っていう感じです。
――ビルボードトップ10みたいな人と戦うぞ!と思って曲作りを始めたのはいつからなんですか?
山路:それはギターを始めた時からですね。もうずっと戦い続けてるんで(笑)、人知れず。
――じゃあ基本的にはR&Bとかヒップホップを自然と聴くことになる?
山路:ああ、そうなってきますね。でも最近、トラックメイカーの人が、トラックをただ作る人じゃなくて、ちょっとプロデューサー的な立ち位置みたいな感じになってきて、ボーカルが誰であれ、例えばZeddが作ってるから“Zeddの新しい曲が出た”っていう、歌手じゃなくてトラックメイカーを先に聴く、みたいなところが増えてると思ってて。なので、そのトラックメイカー的なアプローチも増えてきてはいますね。
――トラックメイキング的な曲って単純にAメロ、Bメロ、サビみたいな構成じゃなかったりしますけど。
山路:でもそこでちょっと意識してるのは、ロックバンドっぽいって言われるところでもあると思うんですけど、サビはガーンときてほしいっていうのはありますね。そこは逆に邦楽っぽいところではあるかも、と思います。

the engy/藤田恭輔(Gt,Cho,Key) 撮影=鈴木 恵
僕的には音楽に完成形とかなくて。ギターの音を使って、この楽曲にどういう音を与えられるのかな、っていうところですかね。
――今回のミニアルバムに関してはほぼ新曲ですか?
山路:全部、このアルバムのために書いた曲ばっかりですね。曲づくりがそもそもしたかったので、ほっといたら曲ばっか作ってしまいます(笑)。
――「At all」はサンバっぽいリズムですが、打ち込みなんですか? それとも生?
境井:あれはパーカッション系の打ち込みが入ってて。あれは生でやってるというより、みんなの雑音みたいなのが入ってます。
――アイデアも面白いし、歌の存在感が強いからR&B的なものとしても聴くし。
山路:ああ、ありがとうございます。やっぱりこう、英詞で日本で勝負する以上、メロがいいっていうのが最低条件かなっていう気がしてて。何言ってるかわからんけども、エド・シーランぐらいフロウが気持ちいいとかは最低条件にしていかないと、絶対、「え? 日本語じゃない」って言われちゃうんで。
――元になる楽曲は山路さんが作っているけど、全員がアレンジャーかつプロデューサーという感じ?
山路:今回はちょっとレコーディング環境が変わって、より全部の音をちゃんと聴ける環境で作ったんで、音の重なりを計算して行った感じの曲が大半なんです。僕が作り込んで、「こういうフレーズがいいと思うんだけどどう?」って感じで投げかけて。やっぱやる以上、100%納得して弾いてほしいので、メンバーが納得できへんのやったら、変えてみようかみたいなやりとりをしつつ作った感じでした。
Sick enough to dance
――リード曲「Sick enough to dance」、これは日本語の乗り方が面白いし、ベースの主張が強いですね。
濱田:まさにです。色々エディットしてて、人力でできんのか?っていう要素はあります。
――レコーディングですからね。
山路:絶対に生の臨場感ではライブの方が優ってほしいし、熱さっていう面ではライブの方が優ってほしいんですけど、曲の完成度っていう面で見たときには、絶対、CDの方が優っててほしいんですよね。生でできることが100%やったら、ほんとに聴く側にそれが伝わるか?って言ったら全然そういうことじゃなくて、そこはレッチリとかも、一音ずつベースの音を上げて行ったりする感じで。要は100%この曲の完成度を伝えるために、サンプリング的に音を使ったりとか、生で叩いてもサンプリングして貼り付けてみたりとか、そういう加工は今回いっぱいしてますね。
――そのせいかハイブリッド感があって、いわゆるEDMとかトロピカルハウスを作るプロデューサーとは違う生音が鳴ってる。
山路:ああ、そうかもしれないですね。やっぱりバンド感を出したいので。
――藤田さんの現代音楽や実験音楽が好きな面は、ギタリストとしてthe engyではどう出てると思いますか?
藤田:もともと僕はギタリストになりたくてギターを始めたわけじゃなくて。一人でやってた時や前にバンドを組んでた時は、全部の音が手段というか、ボーカルの声もそうですけど、環境音楽も好きやったんで、その場の環境音だったり、偶然に起きちゃった音とか、そういうのも全部含めて、そのときの音楽っていう作り方でした。だから僕的には音楽に完成形とかなくて、完成度を上げるとかそういう感覚もあまりなくて。だからギタリスト的にというよりかは、ギターの音を使って、この楽曲にどういう音を与えられるのかな、っていうところですかね。
山路:それで言ったら、藤田さんの感じが出てるなと思ったのは「Have a little talk」っていう曲ですね。オルガンで始まって、ボーカルが乗って、昔のソウルやR&Bっぽいのかな?と思ったら、最後は結構ロックっぽくバーン!といく曲なんですけど、あれのギターのアプローチとかも最初、違ったんですよね。もっとロックっぽい感じというか、ギターっぽいギターを弾いてもらってて。「でももっと藤田さんの得意な感じとかあるじゃないですか」みたいな、「ディレイの音がフワーンフワーンって鳴るだけでいっちゃうんすよ、みたいなところあるじゃないですか? そういうのでいったらいいじゃないですか」って言ったらやってくれて。
一同:(笑)。
山路:フレーズで弾き分けるわけじゃなくて、ギターから出た音をフレーズとして使うみたいな。
藤田:そうですね。あれも正直、ディレイが発信していく感じとか、毎回違うんですよ。そういうのを取り入れると楽しいです。はい(笑)。

the engy/濱田周作(Ba) 撮影=鈴木 恵
「Sick enough to dance」は色々エディットしてて、人力でできんのか?っていう要素はあります。
――リード曲の「Sick enough to dance」はピアノバージョンも入ってますね。メロディがよりわかる。
山路:曲の土台の部分は3~4時間ぐらいでできたんですよ、全パート。でもサビメロだけ決まらなかったんですよ。で、“どうしよ?”と思ってたんですけど、レコーディングの締め切りが近づいてたんで、絶対に早くサビメロを出さなきゃいけなと思って、ライブをした後にスタジオにこもって、ピアノで弾きながらフレーズを作ったんです。で、僕以外の3人が飲みに行ってて、僕が「メロ出たら合流するから」みたいな感じで言ってたんですけど、メロが出なくて。そうしたら濱田と藤田が来てくれたんですよ、スタジオに。で、「これどう?」「これどう?」って、「ピアノで弾いたら全部良く聴こえるなぁ」みたいなことを言って(笑)、なんかこの曲って意外とピアノ合うんじゃない? みたいな。確かにめっちゃピアノ合うかも、こっち方面も行けんねや? と思って。で、サビメロが出たんですよね。
――なるほど。ピアノで作った方が原型なんですね。
山路:そうです、そうです。さっき日本語のハマり方が面白いと言っていただいたんですけど、実はトラックにハメて作ったんじゃなくて、ピアノにハメて作ったんですよ。そうすると、よりメロとして綺麗になるじゃないですか、ごまかしが効かないんで。で、日本語としても綺麗に響かないと、あまりにもヒップホップっぽいラップというか、オラオラ系のラップに行ったらおかしいし。でも、弾き語りにハマる日本語のラップっぽいフロウっていうことで、ピアノから作ったところがあったので、最後になんか弾き語りとか付けられないか? ってなったときに、それなら絶対、「Sick enough to dance」がいいです、って決めた感じですね。
――今回の曲の中で異色といえば「In my head」でしょうか。
濱田:それは間違いないですね(笑)。
山路:楽しかったですねぇ。でもこの曲が一番、時間かかったんですよ。この曲はデモに20時間以上かかったので。いつも方向性決めは早く終わって、展開とかに時間を割いていくんですけど、方向性決めにめっちゃ時間がかかった。もう最後、半ば半ギレで(笑)。ベースの低い音は、声なんです。
――あ、そうなんですね?
山路: “んーーーー”っていうお経みたいなやつに音程をつけて録ったものを機械で低くして、アナログの機械を通して、どんどん太くして、倍音を増やして歪ませてベースっぽい音にしていったっていう。そこに行ってからは楽しかったですね。
――この電話のやりとりのアイデアは?
山路:内容的には、いつもは人の話をちゃんと聞いてあげる人なんですけど、相手があまりにもワァワァ言うんで、もうブチ切れてしまうっていう内容で。「わかる? わかるやんな? そうやねんけど」みたいな感じをつけて、途中で「おい!」ってキレてもうて、そこから歌が始まるのは面白そうやなと思って、そこだけは最初にやったんですよね。
――この曲だけ、ちょっとポストパンク的なビートが混ざってるのも面白い。
山路:そうですね。ダーティな感じ。ヒップホップも好きではあるんですけど、僕はラッパーじゃないんで、ヒップホップみたいな曲をやるときにルールとして思ってるのが、まずトラックとして完全にかっこいいものであるということと、リリックが伝わらなくてもかっこいいフロウを出してるということを念頭に置いてるんです。なので、トラックとしてかっこいいものにまず仕上げなきゃっていう気持ちが強くて。いろいろ試していくうちに、この“んーーーー”っていう低い声のベースを軸に、もっとドラムは抜いていい、いなたく、ドン! バーン! でいい、最初はもうちょっと細かくツクツク叩く系のやつだったんですけど、もういらん、全部いらん、ドーン! バーン! でいいと。
――ナイスバランスです。加えて面白いのが山路さんの歌詞が意外と、ブルージーというか、現代の若者の憂鬱みたいなものがちゃんと描かれてると感じて。
山路:ああ、そうですね。幸せな歌ってあんまり書けなくて。もともとリンキンパークとかが好きなので、生きづらい、みたいなところを聴いてきて。結構、ラップとかやってて思うのは、なんで世のラッパーはこんなに言うことがあるんやろ? と。ものすごく長いじゃないですか?
――それはスタイルとしてもスキルとしても、言葉を詰め込んでいける音楽性だからですよね。
山路:そうですよね。でも言葉を詰め込むって思ったときに、幸せなことでそんなに出ないんですよね。幸せなのは僕が分かっていればいいことなので(笑)って思っちゃうタイプなんですよね。歌詞に落とし込んで表現したいのは、どっちかというと、うまくいかないとか、こうじゃないやろ? とか、でもそれを“これでいいのか? お前ら”って形で伝えるんじゃなくて、お話を作る感じで。こういうのでうまくいかへん人がおったとさ……みたいな(笑)。
一同:(笑)。
――それは洋楽の影響なのでは?
山路:そうかもわかんないですね。どうせストレートに言っても伝わらないですからね。英語で歌ってる以上。それよりは、そういう世界観がありまして、こういうことがありまして、っていうものとして書いてる感じですね。

the engy/境井祐人(Dr) 撮影=鈴木 恵
全然違うけど、結局全員、山路の作る曲と歌が好きっていうのはあるんです。
――非常に意外なバックボーンや作り方だったので驚きました。じゃあ最後に、the engyの近い目標と、壮大な夢の両方を聞かせてもらっていいですか?
山路:近い目標でいうと、グラミーかな(笑)。
一同:ははは。
山路:「ベスト・メガネ・ドレッサー賞」とかね(笑)。やっぱり、目標として全員にあるのは曲を発表して、飯を食うってことですね。それは当初から掲げていることで。そこで一貫して言ってたのは、曲を出してご飯が食べたい、出来るだけ美味しいご飯が食べたいです、っていうことで。
――楽曲評価が高いっていうと硬いですけど、どれだけ多くの人が直感的にいい曲だと思うかにかけていると。
山路:そうですね。芸術性と大衆性が結びつくっていうのが一個テーマではあるので、できるだけ自分らで突き詰めながら、聴いてもらったときに「ええやん!」っていろんな人に言ってもらえるのは目標ですね。でも、グラミーは小さい方、で、美味しい飯を食うのが大きい方の目標です(笑)。
取材・文=石角友香 撮影=鈴木 恵

hte engy 撮影=鈴木 恵
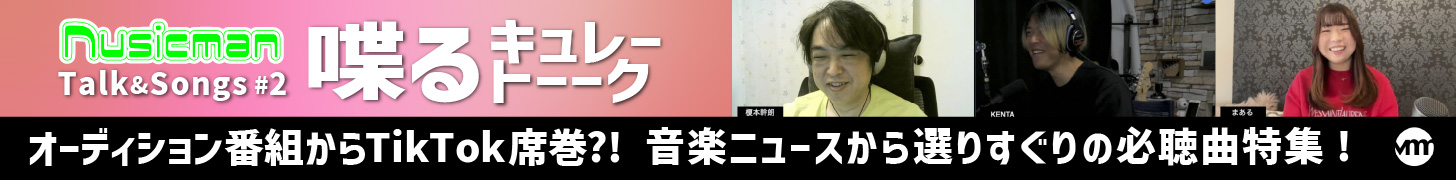

広告・取材掲載