
THE NOVEMBERS 小林祐介(Vo/Gt)、BAROQUE 圭(Gt) 撮影=大塚秀美
BAROQUEとTHE NOVEMBERSによる対バンツアー『BAROQUE × THE NOVEMBERS TOUR “BRILLIANCE”』がスタートした。THE NOVEMBERSの高松浩史(Ba)が現在、サポートメンバーとしてBAROQUEに参加していることもあり親交の深い2組だが、対バンツアーは約4年ぶりとなる。そのツアー開催を目前に控えた11月末の某日、BAROQUE 圭(Gt)とTHE NOVEMBERS 小林祐介(Vo/Gt)の対談を実施。刺激を受け合う両バンドの馴れ初めから、音楽的ルーツ、さらには意外な共通点でもあるフィギュアスケートの話題まで、興味の尽きない対談となった。
――『adbn』以来4年ぶりとなる東名阪2マンツアー『BRILLIANCE』が12月1日(日)からスタートします。前回のツーマンをどう振り返っていますか?
小林:僕らはいろんなジャンル……例えばCHARAさんもそうですが、とのコラボをしてきたんですけど、自分のルーツの一つであるにも関らずあまり交わることがなかったのがV系で。僕と高松(浩史/Ba。BAROQUEのサポートも兼任)の個人的に重要なルーツだったので、いま思えばそれまで交わらなかったのが不思議なんですけど。それが、あの時BAROQUEと、ただの対バンじゃなくて2マンツアーという形で見せられたことは、一つの大きな文脈が僕らの評価に加わった気がしていて。それ以降、“THE NOVEMBERSって、そういう印象が無かったけど元々(V系を)好きだったんだ? 聴いてみよう”という人がライブに来てくれるようになったりもしました。そして何よりTHE NOVEMBERSのファンの子が、BAROQUEの音楽自体に共鳴するのが、フロアで観ていても分かったんです。だから、“あ、やっぱり通じるところがあったんだな”と確信に変わったし、そこがすごくうれしかったな、という記憶があるのと。時を経て高松がBAROQUEに参加するとなった時には腑に落ちるところがあって、“絶対似合うな”と思ったんですよ。高松は素晴らしいベーシストで、THE NOVEMBERSで発揮しているセンスはその一部なんですね、いろんな引き出しがあるから。また別の部分をBAROQUEの中で発揮しているであろうし、BAROQUEと関わったことで彼が一表現者として成長していたり、可能性を広げてたりしているんですよね。それがまたTHE NOVEMBERSにいい影響を与えたりもしていて。高松……もう結構経つよね、いま何年?
圭:もう2年ぐらいだね。
小林:だから、また2マンをやろうという話が出る前から、“次に一緒にやる時は高松祭りになるな”という予感はしていて(笑)。お互いのバンドがいいふうに変化したり、新たな文脈が加わったりした上での再会なので、感慨深いを通り越して“すごく意味のあることがちゃんと実現できるな”という気持ちでいます。
――圭さんはいかがですか?
圭:……しかし、本当に上手く順序立ててしゃべるね(笑)。
小林:あはは、いやいやいや(笑)。
圭:頭の中で整理がされてる、さすが(笑)! 4年前の2マンは、僕らが2人体制になった本当に直後で。BAROQUEというバンドの歴史自体もすごく長いし、いわゆるヴィジュアル系のシーンで、それまでもいろいろと活動はしていたんですけど。やっぱりあのタイミングは、2人になってしまって一度リセットされた感じだったんですね。だから、“これから先どういうバンドをやりたいのか? BAROQUEをどう新しく、現在進行形のバンドとして進化させたいか?”という想いが一番大きかったタイミングなんです。THE NOVEMBERSは活動の仕方も音楽も、僕にとっては当時、近くにいる周りのバンドよりも、ヴィジュアル系が元々持っていた美学を持ち続けているバンドだなと思っていて。僕らは当然そのシーンにいるからそこがルーツであるし、そこを好きで来ているので、すごく一緒にやってみたい相手で。実際にやってみて、バンドとしての強さも感じたし、もちろん全然違うところと、ある意味接点があるところも感じたんです。だから、“これからどういう表現をしたいか?”と考えているあの時期に、ものすごくいい影響を受けましたね。その後セッションしたり、小林くんが言ったように高松くんが(サポートベーシストとして)来てくれて。ライブ自体はあれ以降一緒にやってないんですけど、高松くんを通しての話も聞くし、いろいろと活動を見て“あ、やってるな。ツッパッてるな”と(笑)。そういうのを見ていると励みにもなるし。だから、“次にまたやる時はお互い、成長したものを見せられたらな”とも思っていたので、また一緒にできることになって純粋にうれしいですね。
――確認ですが、『adbn』でのツーマンツアーで初めて結びつきができて、それを機に高松さんのサポート話が出た、という流れだったんですか?
圭:そうですね。全然面識はなくて、人を一人介して俺は個人的に「THE NOVEMBERSとライブやりたいんだけど、紹介してくれませんか?」と言っていたんです。
小林:そうだったね。
圭:それで突然THE NOVEMBERSのライブに行って、小林くんに無理やり会いに行って「どうも」と話し掛けた、みたいな(笑)。
――その時、小林さんはどう感じましたか?
小林:すごく端正な顔立ちの人が近付いてきたなぁ、と(笑)。それで挨拶したら“あぁ~! BAROQUEの圭くんか”となって。何より、僕の中では偏った前情報があったので……。
圭:(笑)。
小林:BAROQUEは芸歴も長くて、ものすごく若くして日本武道館まで最速で行った、とか。あとはとにかく、凶暴なエピソードみたいなのとか(笑)。
圭:暴れん坊なね(笑)。
小林:そうそう(笑)。僕らは、はんなりした、スッとしたBAROQUEの2人しか見てないから。前情報があった上で実際に会ってみて、“あ、そうか。今は一回り二回りして落ち着いたのかな”って。でも、やっぱりたまに見せる眼光の鋭さ、みたいなのが怜くんも圭くんもあるんですよね。キャリアが長いということと、その界隈のいろいろな常識を覆したり壊したりしてきた存在で、やっぱり同世代とはいえそこに歴史を感じて、“差があるな”とは正直感じたんですよ。僕らは、シーンの常識みたいなものと戦わずして、予め慣れた水の中で泳げるような環境があったんです。でもBAROQUEは、シーンの常識を更新して、下の世代に影響を与えたという話はすごく聞いていたし。だから、同世代ではあるんだけど、そういう“何かを変えて来た人たち”がいろいろなことを経て、今近いところにいるっていうか。辿って来た時間の濃さの違いはやっぱり、感じますね。だって、デビューしたのって10代の時でしょ?
圭:そうだね。2001年にスタートして、2003年にデビューしてるから。でも、今の小林くんの話を聞いて思うのは、音楽だけ聴いたらTHE NOVEMBERSのほうがよっぽど凶暴そう(笑)。
――美しい轟音を鳴り響かせていますよね。作品ごとに実験し、音楽性が変化している印象を受けるのですが、意識して壊そうと? それともその都度やりたいことをやったら自然に、という感じでしょうか?
小林:僕らは単純に飽き性なところがあるので、前作で自分たちがやったことを更新したい、変化したい進化したい、という気持ちで作品をつくってきたんですけど。いま思うことは、“自分がものすごくいいぞ”と思ったものをつくるだけだと、それって実家で一人でやっても意外と得られる満足なんですよね。それは根源的には大事な欲望ではあるんですけど。僕はもっとシーンとか、自分が社会とコミットしてきちんとコミュニケーションを取りたいんだということを、この1、2年実感することが増えたんです。“あ、やっぱり人に聴かせたかったんじゃん”“褒められたいんじゃん”とか、“アッと言わせたいんじゃん”という、『少年ジャンプ』みたいな欲望や挑戦心に気付いて。これまでの僕らは、いい意味で言うとそれに振り回されずに、でも悪い意味で言うと本当にのほほんとやってきてしまったんです。それがこの1、2年で、自分たちも最高だと思いつつ、それが自分たち以外のファンとかシーンとか、普段ロックバンドを聴かないような人もとにかくワッ!とするような、無視できないものをリボンを付けて届けたい、という気持ちがすごく強まってきています。
圭:なるほどね、面白い。その話を聞くと、俺たちは真逆で。始めたのが早くて、僕はまだ15歳で、中学を卒業してすぐバンドマンになったんですけど、ありがたいことにすぐファンの人が付いてくれて。だから、人生で初めて作った曲とかも世に残ってるんですよね。だから……まぁいろいろね、素行は悪かったりしましたけど(笑)。
小林:(笑)。
圭:悪くはありつつも、やっぱり作るたびに“ファンがどう反応するか?”という考えは常にあったし。次の曲を出したタイミングでどのぐらいまで登りたい、とかいう野心があり続けて、もうそれが当たり前になっちゃって。そのことに疲れた部分もありましたね。本当のアマチュアだった時期がない、というか。曲を作る=ファンの人に提供する、みたいな責任に変に縛られた部分はありました。だから、“俺はこれが好きだけど、ファンはどう思うだろう?”“これって受け入れられるか?”とか、“売れるのか?”とか。考え過ぎた結果、自分が何をやりたいのか?が結局分からなくなるという葛藤が生まれたこともありましたし。逆にいまになって、少しずつそこから解放されてきて。お客さんって、自分たちが思っている以上に、俺たち以上に俺たちのことを知っていたりもするから、上から見られないんですよね。勝手な予想でやったことが上手くいかない時もあるし、難しいね。これはちょっと大きな目標でもありますけど、自分が120%のそのままの姿で何かを表現して、それがエンターテインメントにもなって、誰かのためになれるというのが一番の理想ではありますよね。それはたぶん誰しも、きっと表現者だったら思うことでしょうけど。
小林:うん、そうだね。

THE NOVEMBERS 小林祐介(Vo/Gt) 撮影=大塚秀美
インプットするものはちゃんと選んでるけど、それ以外からもらっちゃうものには神様からのギフトみたいな感じがあるから、見過ごさないようにしてる。
――2バンドの共通点として、音楽を生み出すだけでなく、アートワークやプロモーションの仕方も含め、“それをどう届けるのか?”に至るまでこだわりがあり、美意識を徹底していく強い意志を感じる、というのがあります。
小林:アートワークを含めた美意識で言うと、こだわりはたぶん強いほうだよね、お互い。
圭:そうだね。
小林:以前Twitterで、告知のフライヤーの件(チェック前の不本意な状態で世に出てしまったこと)で圭くんが憤っているのを見て、“この感覚すごく分かる!”と思ったんだよね。たぶんファンからしてみたら……。
圭:どっちでもいいんだけどね(笑)。
小林:そうそう(笑)、情報が伝わってきさえすれば良いし。“どっちがどうなんだっけ?”という(差異の分かりづらい)ものが、自分たちにとってはとんでもなく重要だったりして。
圭:そうそう、“やっちゃいけないことやっちゃった!”ってなってた。
――“分かる!”という共鳴を小林さんはTwitterで発信されていましたよね。
小林:そうなんです。僕が共鳴しても“何言ってるんだろう?”みたいな流れになるのは分かっていたんですけど(笑)、とにかく分かりすぎる!と思って。つまり、“自分たちが作ったものにリボンを付けて届ける”という話にも通じるんですけど、人にものを渡す時に「これ買ってきたよ、はい!」と渡すのか、リボンを付けてスッと渡すのか、あるいは手渡しは気恥ずかしいから置いておいて、後で来た時にそこにある驚き、とか。
圭:分かる!
小林:渡し方によってものそのものの質すら変わってしまう、というか。音楽って目に見えないからこそ、それにまつわる周りが全部リボンになりうるわけじゃないですか?
圭:そうそう。まだ全然検品もできてないものが出荷されちゃった!みたいなことになると、責任取れなくなっちゃう、というかね。
――そういったこだわりが、“人に任せておけばいい些細なこと”ではなく、“美しさに直結する、欠かせないものなんだな”と感じられる出来事で、事態を見守っていました。
小林:そうですね、(音楽と)=ですからね。
圭:やっぱり、原理主義的な意味で本来のヴィジュアル系だなと思うんですよね、僕は。
小林:あぁ、そうだね。ドレスアップするということだからね。
圭:そうそう。ジャケットもそうだし、アー写はもちろん、全部に血が通っているというか。THE NOVEMBERSを初めて見た時にも俺はそう思って。僕は昔のヴィジュアル系オタクなんですよ。80年代、90年代とかの。
小林:あ、80年代も行けるの(笑)?
圭:うん。
――今やある意味形骸化した“お化粧しているからヴィジュアル系”という系譜ではない、原理的な部分での、ということですよね。
圭:本当にそうですね。今ヴィジュアル系はお茶の間に出ていって巨大になったので、変わってきていますけど。だから、小林くん自身はどう思うか分からないですけど、本当に最初の頃のLUNA SEAとか、ZI:KILLとかみたいな雰囲気だなと思ったの。皆黒い服着て。
小林:あぁ、ZI:KILLね。TUSK(Vo)さんね。
圭:そうそう。そういうポジパンやニューウェーヴが入った感じで。今のヴィジュアル系のバンドよりも逆にそういう初期のヴィジュアル系っぽい、みたいな。
小林:TRANS RECORDS(80年代前半に設立されたインディーズレーベル)みたいな。
――そういったルーツを持ちながら進化してきているお互いのバンドの音楽性について、最近はどうご覧になってますか?
小林:BAROQUEのこの間出したアルバム(『PUER ET PUELLA』)は、僕らの周りの、言ってみればロックバンドのシーンでも、「BAROQUEの新譜良くないか?」という声が、友だち規模で伝わってくるんですよ。
圭:あ、本当? うれしい。
小林:V系以外の食いつきがいいって友だちも言っていて。評価のされ方がお互い、徐々に拡張されてきてるなって感じる。「元々“こういうところ”にいたんだけど」の“こういうところ”のしがらみだけがどんどん無くなっていって、でも文脈は増えていって。“カッコ何々”みたいな注釈が無い状態で、ただ音楽を聴かれて一音楽として評価される場所が増えた、というか。そういう健全なところにいる印象がありますね、お互い。
圭:活動している場所でいえば、THE NOVEMBERSは『フジロック(FUJI ROCK FESTIVAL)』にも出たり、僕もファンの海外のいろいろなバンドのオープニングアクトをたくさん務めたりして、いろんな人に知ってもらってきてるバンドだと思うんです。やっぱり唯一無二ですからね、小林くんが作る音楽って。その時々、自分の中の興味とかモードはあるんでしょうけど、“ツッパッてるな”と思いますね(笑)。僕が言うのもなんですけど、よっぽど僕よりもツッパリだな、と思う。
小林:あはは!
圭:その力がある、というか。例えば、このご時世では全く見向きもされないようなジャンル感や時代感があったとして、それに小林くんが興味を持つとする。「でも、これがイケてるんだぜ?」と押し出す力がある、というか。「“ダサい”とされてるけど、いや、これだぜ!」というツッパリ感を感じるんだよね(笑)。
小林:そうね、トレンドから言ったら逆、みたいなのもあるからね。
圭:それを捻じ曲げる力がより強くなってる気がする。そこに周りが反応しているのも見えるし、アーティストとしてすごいことだな、と思いますね。
小林:光栄ですね。僕がどんな曲を作ろうが、“迷った末での作品です”の“迷ったプロセス”は誰にも見えないじゃないですか? ということは、僕の葛藤も紆余曲折もリスナーには関係ないわけで。そう考えると、“いいものを思うままにやるべきだ!”と言って作ったものと、“怖いよ~やっぱり守りにはいっとこう!”と思ってつくったものは、音楽的評価は別として、受け取られ方は“THE NOVEMBERSの新譜”という意味でフェアな状態なわけじゃないですか? だったらもう、自分がハンコをちゃんとバン!と押せるようなものじゃないと、後々自分が苦しいってことが分かりきっているんですよね。最後まで“これは私の音楽です、ドーン!”というハンコが押せるかどうか。その話に尽きてしまいますね。その勇敢さを持っていないと、作品が褒められてもけなされてもおろおろするばかり、というか。
圭:それはそうだね。
小林:ただ、最大公約数を探すための努力や苦労はどこまでもするべきだ、とも今は思っていて。これからは、“自分がやりたいな”と思う膨大なことの中に、“普段ロックとか聴かないよ”という人たちが何かのきっかけで急接近した時に、“この1曲だけは分かる”となる、その1曲をどうにかして探せないかな? という努力をしています。一生掛かるかもしれないですけど、その公約数を探すことは、人とコミュニケーションを取る上で“共通の話題ないかな?”と探すこと、“この髪型いいね”から話を始めるのと一緒かな?と思っていて。僕にその意思がなかったら永遠に無関係なままで終わっちゃうんですけど、その1曲があったら“見どころあるね”という感じでお互い、目が合って微笑み合えるかな、と。それによって未来が全然違うじゃないですか?
――そういう意識がここ1、2年で強まったということですが、何かきっかけがあったんですか?
小林:端的に言うと、きっかけはCHAGE&ASKAですかね。デビッド・ボウイが亡くなった1月に、飛鳥さんの非公式ブログを見たんですよ。それを機に曲をちゃんと聴いたことによって、僕の中では懐メロだったCHAGE&ASKAが、“ものすごく多くのヒット曲を出している偉大なアーティスト”という認識に変わったんです。この人はこんなにヒット曲を生み出していて、かつ、いろんな音楽が好きな僕にも分かる素晴らしさがある。ということは、CHAGE&ASKAというフィルターを通して、もっと言えばL’Arc~en~CielもDIR EN GREYもLUNA SEAも、ユーミンやスピッツも全部そうなんですけど、“じゃあ自分は、この人たちを通して、皆が好きそうなものが分かったりヒットさせたりするセンスをもう、持ってるじゃん”と。彼らは彼らのやり方でそういうものを作り出してきたから、僕は僕の中でその宝石みたいなものを見つける努力をしないと、ただの怠慢だな、という気持ちになったんです。力強いメンバーがいて、スタッフという仲間がいて、ファンが集まってくれるこの状況の中で自分がそれをこれまで怠っていたのは、なんとも恥ずかしいことだな、と。作りたい順に曲を作っていってアッという間におじいさんになってしまって、“次の次の曲がその宝石みたいな曲だったかもしれないのに!”となったらもう、悔やんでも悔やみきれない。だから、いろんな可能性を試す中で“公約数はどこかな?”というのを、最近は大喜利みたいにして考えています。
圭:なるほど、面白いね。
――そういった意識の変化は、前回のツアータイトルは儚く散る『adbn』だったのが、今回はもっと残るもの、永遠の輝き『BRILLIANCE』というベクトルに変わったこととも繋がっている気がします。
圭:タイトルは小林くんが考えてくれたんですよ。コメントにも書きましたけど、「どうする?」って2人で話し合って。「前のツアー名を継承する?」とも言っていたけど、お互いに「いや、ちょっと今回は違うでしょ」となったんだよね。
小林:そう、あの時は“季節外れに狂い咲く”みたいなのがすごくしっくり来たんだけどね。
――お2人のメンタリティーも変わったということですよね。
圭:うん、たしかに。
小林:いろんなものを経て今一番輝いてるぜっていう。“ここを基準にどんどん行くぜ!”みたいなモードに、30半ばにしてなれるのって……しかも対バンでですよ? それってすごいことだな、と。だから、今BAROQUEと2マンするにあたってどんな言葉が相応しいのかな?と考えた時に、輝くとかBRILLIANCEだなと思ったんです。BRILLIANT~とか、いろいろ候補はあったんですけど。
圭:決定するまでにはちょっと時間かかったね。
小林:そうだね。『adbn 2』にすれば、ファンは“あ、『adbn』の1があったんだ”という発見もあるし、“2回目だから3、4もあるかもしれない”という未来や連続性も表現できる。ですけど、やっぱり新しいことがいいなっていう。電話で話している時、「やっぱり、今が一番いいっていう態度は見せたいじゃん?」という共通の話題があったから、やっぱりそれに尽きるんじゃないかなって?
――タイトルだけで伝わってくるものが大きい2マンですね。実際のライブの内容はどうなりそうですか?
小林:絶賛準備中ですね。ちょっとした特別な楽しみ、みたいなことをやろうかなって。
圭:それは考えていますね、せっかくなので。ま、高松くんは共通だし。
――出突っ張りですね。
小林:そうですね、リハから本番まで(笑)。
圭:美学を持ってやっているのはたしかに一緒ですけど、(2バンドは)全然違うし、表現方法も違っていて、でも近くのヴィジュアル系バンドよりはオーバーラップするところがずっとあるんですよ、やっぱり音的にも。だからこそできることもたぶんあるし、ちょっと特別な2マンにはなりますね。僕たちも他では普段やっていないような音にもチャレンジしようかな?と思っています。
小林:ちゃんとクロスオーバーしてる、というのがライブの楽しみになるので、乞うご期待ですね。
――高松さんがBAROQUEでプレイされている姿を、小林さんはご覧になったことはあるんですか?
小林:僕、いつも面白いぐらい仕事が重なってしまって、行けてないんですよ。
圭:だから、この2マンで初めて観るんだね。
小林:そう。すごく楽しみですね。
圭:新鮮だと思うよ、いつも自分の横にいる人を客席から観るのって。
小林:しかも、THE NOVEMBERSファンからのタレコミによると、見たことのない高松がいるらしい、と……(笑)。
圭:それはね、間違ってない(笑)。
小林:高松はTHE NOVEMBERSの中でも特に、一番感情を表に出さないキャラなんですよ。そんな、言ってみればサイボーグみたいな高松が(笑)、BAROQUEの音楽とか表現の中で馴染んでいるうちに、自分の解放の仕方だとか、新しい楽しみを見出したんでしょうね。自分らの流儀の中だと出せなかったような高松の良さがBAROQUEで開花していて。それをTHE NOVEMBERSで披露してくれるのか?と思いきや、しないんですよ。
圭:あはは!
小林:「高松さ、お客さんのこと煽ってるでしょ? THE NOVEMBERSでもガッと行く時は高松も行きなよ!」と言うと、「いや、でもあれは圭くんがガッと行くタイミングで自分が行くから釣り合いが取れるわけで、いきなり俺がTHE NOVEMBERSでガーッとか行ったらおかしいでしょ?」って(笑)。逆に、“無理してやってることではないんだな”という証明ではありますよね。BAROQUEで無理してるとかじゃなくて、BAROQUEというバンドの中で自然とやることは、THE NOVEMBERSの中で自然と出て来ない以上は、やるべきじゃないんだよ、ということだから。今回対バンすることで、THE NOVEMBERSでも一瞬気が緩んで前に出ちゃう、とかはあるかも(笑)。
圭:そういうのは期待できるね(笑)。
小林:観てみたいね。
圭:いま、彼は一人で下手(しもて)を支配してますよ。前に出たり、キャラクターとしてもファンのいろんなものを受け止めたりしてますね。
――BAROQUEにおける高松像を披露しないにせよ、THE NOVEMBERSに対する何かしらの良きフィードバックはあるわけですよね?
小林:それはものすごくありました。演奏に対してのクオリティだったり、グルーヴそのもののクオリティに関して一ミュージシャンとして彼の中でのハードルがグッと上がったんですね。BAROQUEでは、例えば端正に整えられたアンサンブルみたいなものがあったとするじゃないですか? それを経験した彼が、今度はTHE NOVEMBERSに来た時、“もっとこうしたらこういうグルーヴにできるのに”というのが分かるから。“もっとちゃんとやりたい”という気持ちとか、“もっと良くできるでしょ?”という厳しさとか。そういった意味ですごく頼りがいのある存在に、日に日になっていきますね。

BAROQUE 圭(Gt) 撮影=大塚秀美
フィギュアの演技を観てると、ギターのフレーズと同じように感じる。綺麗に跳べるかどうか、でも表現がないとつまらないし……みたいな。
――圭さんは元々THE NOVEMBERSでプレイしている高松さんをご覧になっていて、BAROQUEで弾く高松さんにはどんな変化を感じますか?
圭:THE NOVEMBERSのライブを観に行って“いいベーシストだな”と思っていて、実際セッションをしてみてもいいベーシストだったんですけど、やっぱり、すごく進化してますね。ここ2年ぐらい一緒に演奏してるけれど、特に最近どんどん上手くなっていってるし。BAROQUEでのツアーが多かったので一緒にステージに立つ時間が長かったんですけど、一緒に成長もさせてもらってるなと思うし。今のBAROQUEは即興性が結構重要なんですけど、元々高松くんはそういうことはあまりやっていなかったらしいんです。スケールどうこうとか考えるタイプじゃないし、と本人も言ってたんですけど、今はいろいろ弾いてるよね?
小林:うん、そうだね。
圭:本当に短期間でどんどん成長していっているな、と思いますね。
――圭さん個人、またBAROQUEとしても影響を受ける部分はありますか?
圭:もちろん、ありますよ。まぁとにかくTHE NOVEMBERSも忙しいのに、本当に申し訳ないぐらい世話になってますよね。あまりライブを入れすぎると、小林くんには“ごめんね”と思いつつ……(笑)。
――2マンがどうなるか、とても楽しみです。ところで、お2人はライブ以外で会ったり食事をすることはあるんですか?
小林:うちのギターのケンゴ(マツモト)とはあったよね?
圭:あった、ケンゴくんと2人で飲みに行ったことはある。小林くんは忙しそうだからね。
小林:そうなんですよ、今は夜とかあまり出かけられなくなっちゃってるので……。
――そういえば、お2人ともフィギュアスケートをお好きという共通点もありますよね?
圭:羽生(結弦)くん好きだもんね。
小林:羽生くんは、返事の手紙が返って来たことがある!
圭:マジ!? 俺はフィギュアの演技を観てると、ギターのフレーズと同じように感じるの。緩急とか。例えばすごく難しいジャンプを観て速弾きみたいに感じる、とか。綺麗に跳べるかどうか、でも表現がないとつまらないし……みたいな。フレーズを聴いているように観ちゃうんだよね。あれを観ながらギターを弾くと、“分かる!”ってなる。
小林:シンクロした、みたいな?
――その様子を画として観たいですよね(笑)。
小林:圭くんのギターソロとフィギュアスケートとか、めちゃくちゃ耽美ですもんね。
――小林さんもフィギュアからインスピーションを得られているんですか?
小林:はい、僕は羽生くんをイメージして曲をつくったことありますもん。「Harem」という曲とか、『Fourth wall』というアルバムの「Ⅰ.Dream of VenusⅡ.children」という曲には、スケートリンクで少年が躍るという歌詞があって、それは羽生くんのことだったりします。羽生くんは僕をゾワゾワさせるんですよ!
圭:羽生選手のどういうところに一番惹かれるの?
小林:最初に好きになったのはまだジュニア時代の、本当に少年の時だったの。
圭:え~、そんなに前からなんだ?
小林:そう、キノコカットですんごくかわいい男の子がいると思って。羽生くんがどんどん力を付けていって、氷の上で目がガラッと変わる瞬間があった後にプーさんが降ってきてニコニコしたりするのを観て、「バーン!(と机を叩く) もう、かわいい!」みたいになって。
圭:あはは! やられちゃったんだ?
小林:そう(笑)。あとは何より、羽生くんのエッセイを読んで“この人は本当にプロなんだな”と。自分よりずっと年下の彼が達している境地はずっと高いところで。いま僕がようやく口にできるような、他人とのコミュニケーションについても、“表現がコミュニケーションなんだ”という考えをとっくに彼は口にしていて。“自分がスケートをすること、美しく舞うこと、それが誰かのためになると信じてる”みたいな強さも持っていて、“だから自分はもっと高く跳ばなきゃいけない”という表現に結び付くんですけど。だから、好きだな、かわいいとかいう目線では最早なくて、リスペクトしているんですね。
――圭さんは、羽生選手に限らずフィギュアスケートをお好きなんですか?
圭:うん、そうですね。誰か特定の選手をすごく好きというわけではないですし、常日頃から細かくチェックしているわけでもないですけど。羽生選手が一番魅力があるな、とは思っちゃいますけどね。
小林:一番強い人が一番美しい、というところに結び付いてるのがすごく爽快だよね。
圭:そうだね。あと、こういうバンドをやっているのもあって、やっぱり中性的な人が好きだというのもありますよね。目つきとかも。かわいらしいと思ったら急に、悪魔みたいな顔をする時もあって、あれはすごく音楽的に感じます。
――そういった、音楽以外のものからインスピレーションを得て表現活動されているところも、お2人の共通点かもしれないですね。
圭:普段そういうインスピレーションはあえて探してるの? 探さずに自然に?
小林:インプットするものはちゃんと選んでるけど、それ以外からバッ!ともらっちゃうものには神様からのギフトみたいな感じがあるからさ。そういうのは見過ごさないようにしてる。子どもがポッという言葉とか、ちょっとした風景とか。
――例えば、最近受けた刺激と言いますと?
小林:最近では、保育園に送り迎えしている時に、うちの子どもじゃないんですけど、別の子どもの言った言葉がすごく印象的で。外国人の女の子で、アフリカ系の地域の独特のダンスを見せてくれたんですよ。“変な踊り”とからかわれていて、“あ、喧嘩になるな”と思ったら、「これ、すごく楽しいから皆もやったらいいのに」と、その子はただ言ったんです。それで“あ!”と気付かされて。自分だったら、“いいな”と思っているものを「変なの」と言われたら一瞬イラッと来ちゃうなって。いつの間にかそういう発想が染み付いてるんだなと自覚したんですよ。でも、その子みたいに「一緒にやってみれば?」というのが最初の反応だったら、きっと世界広がるぜ?って。
圭:純粋に勧められるんだね。
小林:そうそう。それで、“自分が音楽でやりたいことってこっちじゃないか?”と。J-POPとかヒットチャートの中にポンッと入って、「すごく変わったことをやってる」と言われるとするじゃないですか? その時にいちいち「なんだと?」と怒るのではなくて、「これはこれでいいから、聴いてみたら?」と言える、フラットな目線を無くさないように気を付けないとな、と思ったんですよ。そういう当たり前のことに気付かせてくれるのは、子どものことが多いです。
――圭さんは最近、何から刺激を受けていますか?
圭:僕は、最近は人の表情が一番残るかな。これまではどちらかというと何かの作品からインスピレーションを受けることが多かったんですけど、いまはふとした人の表情とか、目とか。それで何かを思って。残ったそれを思い出して何かを作ったりすることが多いです。前みたいに何かを探ろうというよりはただフラットにいて、そうすれば普通に生きていても何か引っ掛かるので。それは自分のアンテナだな、と思うから。
――音楽にそれが結びついていく、という。
圭:そうですね、結び付きますね。
――特にどういう表情に心揺さぶられる、というのはありますか?
圭:特定のはないんですけどね。例えば、“この人今嘘ついてるな”と思う時もあるし。逆にすごく純粋な顔してるなと思うこともあるし。人間だし、どちらも全然OKで。音楽をやっているとふとした時にそれを思って、“あの目が言いたいことはこういう感じだな”と思って演奏する時もあります。
小林:ちっちゃい子どもの目とか、ビー玉みたいで怖くなる時あるよね。
圭:透き通りまくってるからね。でも、大人の心の迷いの目もまた、それはそれで味わい深いし、深みを感じるというか。面白いなと思いますね。
――では最後に、ライブに向けて、またはそれ以外でも、お互いに期待することを一言ずつお聞きできますか?
小林:単純に、いつも通りの自分たちをただ見せ合いたい、という気持ちですけどね。気負うことなく。
圭:そうですね。この間の11月11日に行われたTHE NOVEMBERSのライブをよっぽど観に行こうかと思ったんですけど、当日観てビックリするほうがいいかな?と(笑)。更にカッコよくなっているんだろうなと思っています。同世代のミュージシャンだしアーティストでもあるから、好きなようにやって、絶対お互いに刺激を受けるだろうし。そういう友だちがいて良かったなと思います。
――では、本番を楽しみにしています。今日はありがとうございました!
圭・小林:ありがとうございました!
取材・文=大前多恵 撮影=大塚秀美
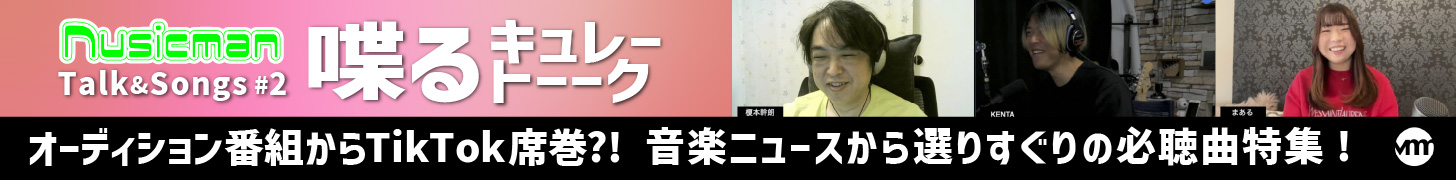

広告・取材掲載