
小宮正安氏(ヨーロッパ文化史研究家/横浜国立大学大学院都市イノベーション研究院教授)
2021年、11回目を迎える東京春祭マラソン・コンサートは、没後100年を迎えるメルヒェン・オペラの第一人者エンゲルベルト・フンパーディンク(1854-1921)や、彼の代表作《ヘンゼルとグレーテル》をはじめ、19世紀末に盛んにつくられた「メルヒェン・オペラ」にスポットを当てる。このマラソン・コンサートは毎年、生誕250年のベートヴェンや没後150年のロッシーニなど、その年ゆかりの音楽家や歴史的節目をテーマに、トリビア的なエピソードや東京春祭ならではのレアな演目を交えて音楽に斬り込むユニークなプログラムの一つで、今年も興味深いテーマを準備してくれた。
そこで企画構成を担当した小宮正安氏(ヨーロッパ文化史研究家/横浜国立大学大学院都市イノベーション研究院教授)に、「メルヒェン・オペラ」やその時代背景、コンサートの聴きどころを伺った。
なお今回のマラソン・コンサートは従来の1時間5部構成から90分3部構成に変更し、ライブストリーミングも実施。さらに幕間のYouTubeでは本編では、取り上げきれなかった話題などを配信するので、こちらも要チェックだ。

■統一ドイツという大言壮語な世界に誕生したメルヒェン・オペラ
――まずは「メルヒェン・オペラ」とはどういうものかについて、お話を聞かせてください。
今回は「メルヘン」ではなく、敢えてドイツ語の「メルヒェン」にこだわりました。日本語でメルヘンというと、女の子がお花畑で妖精と遊んでいるようなイメージがあり、英語の「フェアリーテール」、フランス語の「コント・ド・フェー」もどちらかというとその雰囲気に近いかもしれません。しかしドイツ語の「メルヒェン」は本来「小さな話」「小さな報せ」という意味で、そこにはかわいらしいものから怖いもの、暗黒、不思議な異世界的なもの、怪奇・猟奇的なものなどすべてが含まれる、なにかおどろおどろしいものもやってくるような言葉なのです。
次に今回の主役フンパーディンクが活躍していた時代――とくに19世紀後半から20世紀初頭は、市民社会や近代産業、近代科学が興った新時代で、そんな時代に荒唐無稽な「メルヒェン・オペラ」が生まれたというのもまた押さえていただきたい点です。
さらに19世紀後半の1871年はプロイセン王国を中心とした統一ドイツが誕生するという、歴史的な出来事がありました。それまで連合国家の体をなしていたドイツ語圏に誕生した初の統一国家でした。そもそもドイツ語圏では19世紀初頭のナポレオン戦争後、ドイツ統一の機運が生まれますが、オーストリア帝国とプロイセン王国などの対立もあり平和的には進まず、結局戦争を経ての統一となったのです。とはいえそれまでプロイセン、バイエルン、ザクセンなど、それぞれが小国家的に独自の歴史を刻んでいたため、すぐにはまとまりません。「ドイツ帝国」「ドイツ民族」は大言壮語な話でしかなく、統一ドイツという入れ物はできたがコンテンツがない、という状態だったのです。ではプロイセンやバイエルンといった小国家的枠を超えて、人々に訴えられるコンテンツは何か。それが「ドイツ語」であり、「音楽」でした。
この頃、ドイツ音楽界に君臨していたワーグナーは、結果的にその壮大なスケールの楽劇で「ドイツとは」「ドイツ人とは」という大言壮語な世界に一つのかたちを示すことになります。それに対し、「小さな物語でいいじゃないか」と背を向けて生まれたのがメルヒェン・オペラだったのです。しかし背を向けつつも、メルヒェン・オペラは結果的に、大言壮語な世界を補完する関係にもあったのです。

エンゲルベルト・フンパーディンク(1854-1921)
■メルヒェン・オペラが「ドイツ」の意識を浸透させる
――メルヒェン・オペラの存在がドイツ統一の歴史に関わっているというのは興味深いお話です。「大言壮語を補完する」という意味も含め、もう少し詳しく教えてください。
まずメルヒェン・オペラのモチーフとなる民間伝承をまとめ、また統一コンテンツとなるドイツ語研究者として注目されたのがグリム兄弟でした。日本では童話作家として有名ですが、彼等はもともと言語学者で、ドイツ語を研究する際にドイツ各地の民間伝承を集めました。それをまとめたものが『グリム童話集』です。大言壮語の時代に、この童話集、いわば「メルヒェン」にこそドイツ人の魂があるという動きが起こってきました。
また当時のドイツ家庭の一般的な娯楽の一つに、お父さんやお母さんがピアノなど楽器を弾き、子どもが演じるといった家庭劇や人形芝居がありました。そのための楽譜もたくさん出版されており、メルヒェン・オペラは小劇場に加え、家で広まったのです。大言壮語に背を向けて生まれたメルヒェン・オペラはドイツ語や民間伝承をモチーフとして家庭に浸透していくことで、結果的に「ドイツ」「ドイツ人」という意識を作り上げていくことに一役買ったわけです。
■ドイツ音楽界に聳えていた巨大な壁「ワーグナー」。そしてワーグナーを敬愛したフンパーディンク
――こうしたなか、フンパーディンク《ヘンゼルとグレーテル》はどのような位置付となったのでしょう。
先にも少しふれましたが、メルヒェン・オペラが盛んだった19世紀末のドイツ音楽界には、ワーグナーという巨大な壁が聳えていました。作曲のみならず自身で脚本も書き劇場プロデュースをし、オペラを「楽劇」に進化させたワーグナーの存在は革新的で、あまりに大きすぎました。古典的なスタイルの小作品や、家庭劇用のメルヒェン・オペラがたくさん生まれましたが、大作となるとワーグナーの二番煎じにしかならないという創作の悩みを、当時の作曲家たちは抱えていたのです。
フンパーディンクはワーグナーの弟子で、彼を非常に尊敬していましたが、やはり師匠の壁に苦しみました。そうしたなかで1893年、フンパーディンクは妹のアーデルハイト・ヴェッテの台本でメルヒェン・オペラ《ヘンゼルとグレーテル》を発表します。当時メルヒェン・オペラは未来のドイツ人――つまり子どもの教育にも格好の素材だという認識も得ていたため、物語はドロドロした部分を排除し、きれいに「漂白された」内容でしたが、それが非常に評判になりました。結局フンパーディンクはこの一曲だけの一発屋のようになってはしまいましたが、しかし現在でもメルヒェン・オペラとして演奏され続けているのは、この《ヘンゼルとグレーテル》だけかもしれません。ワーグナーの影響を感じさせる壮大でドラマチックな旋律もふんだんに盛り込まれ、とても聞き応えがある曲です。マラソン・コンサートでは、この《ヘンゼルとグレーテル》から拝借した台詞をサブタイトルとして用い、また主要な部分を抜粋してお聴きいただきます。

アレクサンダー・ジック画『ヘンゼルとグレーテル』
■第I部:「郷/民」/「ドイツ」の核をなす風土と人々の世界
――では第I部から第III部の聴きどころをお伺いします。まず第I部の「郷/民」のテーマは。
第I部はドイツの民間伝承の根幹をなすドイツの風景、そこに暮らす人々の姿を描いたものや、メルヒェン・オペラの元祖ともいえる作品を取り上げます。
元祖の一つがウェーバーの《魔弾の射手》。この曲には当時ドイツの一部であったチェコの森や風景、ドイツ的な舞曲や行進曲などがふんだんに盛り込まれています。
フンパーディンク《七匹の子ヤギ》は先にお話した家庭劇用の作品で、非常にレアな演目のひとつ。ベンデル《6つのドイツのおとぎの絵本》より「ブレーメンの音楽隊」も同様です。ラインベルガー《ドイツ讃歌》は、大言壮語の時代を象徴する曲として取り上げました。ランゲという作曲家は、今は忘れ去られてはいますが、この時代に古典的なテイストで小曲をたくさん書いたベストセラー作曲家の一人でした。ラハナー《森の響き》より「森の小鳥」は、ドイツの深い森と自然を表した曲です。

■第II部:「魔/異」/ヨーロッパ社会の矛盾が生み出す「魔」と「異世界」
第II部は「魔/異」ですが、また時代背景の話をしますと、19世紀後半は、19世紀中頃に勃興した市民社会が自由を手にして豊かさへ向かって突き進んだ結果、労働者闘争、民族問題、公害、恐慌など、負の部分や問題点、矛盾が露呈し始めた時代でもありました。「魔/異」はそうした行き詰まりの部分を反映したもので、もしかしたら「ステイホーム」で閉塞感も漂う我々の時代に通じるものがあるかもしれません。
ミュラー《ファゴット吹きのカスパール(あるいは魔法のツィター)》序曲、モーツァルト《魔笛》は「魔/異」に通じるメルヒェン・オペラの元祖として取り上げました。ミュラーもモーツァルトもオーストリア人ですが、ドイツ語の歌芝居(ジングシュピール)の元祖でもあります。
またこの時代に起こった民族問題――いわば「異」のやり玉に上がってしまったのがユダヤ人たちで、《真夏の夜の夢》を書いたメンデルスゾーンは、そのユダヤ系ドイツ人でした。しかし彼の一家は立派なドイツ人たらんとしてプロテスタントに改宗するなど、ドイツに同化し、名声を得ることになります。
一方、オッフェンバックはドイツを捨てフランスに移住したドイツ系ユダヤ人。彼のオペラ《ホフマン物語》は、「魔/異」を象徴するドイツ・メルヒェンの代表的な人物、E.T.A.ホフマンの小説によるものです。
第II部の注目は、そのホフマンの物語を原作としたライネッケ作曲《くるみ割り人形とねずみの王様》です。これはチャイコフスキーのバレエで有名な《くるみ割り人形》より前に、家庭用の音楽劇として発表されました。バレエの物語は先の《ヘンゼルとグレーテル》同様きれいに漂白されていますが、ライネッケ版はホフマン特有の怪奇的内容をそのまま描いています。この超レアな演目は、私のお話を交えたピアノの演奏でお聴きいただきます。

ぺーター・カール・ガイスラーによるE.T.A.ホフマン『くるみ割り人形とねずみの王様』挿絵
■第III部:「憧/夢」/ステイホームで見る夢と憧れの世界
第III部は先の第II部でお話した諸問題が噴出し、徐々に社会が崩壊していくなかで描かれた「憧/夢」の世界です。
これまでメルヒェン・オペラの元祖となる曲を各部で取り上げてきましたが、シューベルトは、元祖というよりはメルヒェン・オペラの本流の、最初の部分と言えるかもしれません。彼が生きていた時代はナポレオンの敗北により、ヨーロッパに保守反動の嵐が吹き荒れていました。言論統制が敷かれ、町では密偵が目を光らせているため、人々は家で過ごすことが多くなります。今の私たちでいう「ステイホーム」のなか、彼らは夢の世界に思いを馳せていました。ご紹介する《ロザムンデ/魔法の竪琴》序曲はそんな曲です。
シューベルトの精神的な継承者と言われるシューマンの作品からは《メルヒェンの情景》より 第3曲、第4曲を取り上げます。彼も晩年精神を病み夢と現実の世界をさまよった人です。J.シュトラウス2世のワルツ《千夜一夜》は異国への憧れを象徴する作品。ジークフリート・ワーグナーは偉大なるワーグナーの息子で、すっかり父親の影にかくれ、またその巨大な父の影と戦わねばならない悩みがあったのでしょう、現実を忘れさせるような夢世界を彷彿させる小曲を残しています。今回は《フルートと小管弦楽のための協奏曲》をお聴きいただきます。ヒラー《小姓と王女のバラード》は小姓と王女の叶わぬ恋を描いた物語をベースとしたピアノと語りのための作品で、叶わぬ恋の夢を描いたロマンチックなテイストが魅力です。
そして最後はフンパーディンクの《ヘンゼルとグレーテル》より 「夕べの祈り」~「夢のパントマイム」をお聴きいただきます。物語のクライマックスを飾るこの曲はとても壮大で美しく、行き詰まった時代に描き出された夢世界のような味わいがあります。

ジークフリート・ワーグナー(1869-1930)
ドイツ帝国という、産声を上げながらも輪郭が定かでないあやふやな国の中で、また世紀末の美しくも傾きが見える世の中で、人々はメルヒェン・オペラを通して日々の夢や楽しみ、喜びを見出してきました。今、私たちもコロナ禍や経済など、この先どうなるのかわからない様々な問題を抱えながら、日々を送っています。100年前のメルヒェン・オペラは、もしかしたら今の世の中の写し鏡のようなところがあるかもしれません。
――それがタイトルの「メルヒェンの時代へ…」でもあるのですね。確かに先行きの見えない時代ではありますが、写し鏡を通して音楽を愉しむ新しい切り口も見つかるかもしれませんね。ありがとうございました。

2019年の公演より Ⓒ東京・春・音楽祭実行委員会/高嶋ちぐさ
取材・文=西原朋未
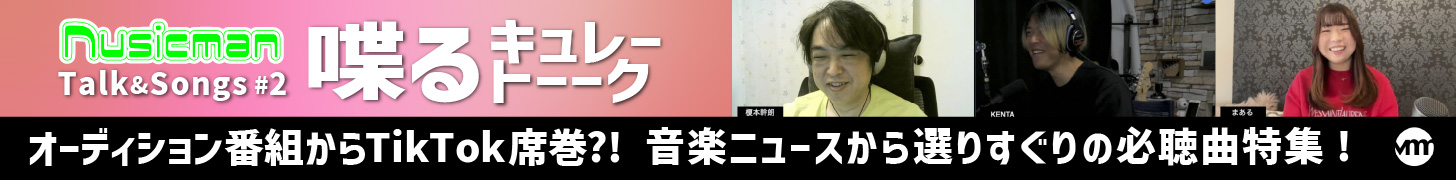

広告・取材掲載