
小西遼 撮影=風間大洋
バンド・CRCK/LCKSの中心人物であると同時に、他アーティストのサポートや楽曲提供など多岐にわたる活動で才能を発揮しているミュージシャン・小西遼が、昨年6月にリモート音楽制作プロジェクト・TELE-PLAYを始動させた。
その第1弾楽曲「あいにいきたい(feat. BASI, Chara, SIRUP, TENDRE and Ryo Konishi)」にはボーカリストだけでなく各楽器の演奏にも錚々たるミュージシャンたちが参加。特筆すべきは、新型コロナウィルス感染拡大によるライブやイベントの中止、外出自粛に端を発しながらも、当初から単発ではなく継続することを前提として企画されていたこと。また、発起人である小西自身はあくまでプロデューサーの立ち位置であり、楽曲制作や演奏からは一歩引いていることだ。
それから約1年。TELE-PLAY待望の第2弾楽曲「Prism」のリリースが発表となり、詳細は5月12日に解禁予定となっている。小西がミュージシャンとして、ひとりの人間としてが何を想い、このプロジェクトを立ち上げるに至ったのか。「あいにいきたい」を通し、その真意を訊くべく昨年収録したインタビュー記事を公開する。
――ここ数年、CRCK/LCKSだけでなくTENDREやmillennium parade、中村佳穂さんなど、いろんな方々の楽曲、活動で小西さんのお名前を目にする機会が増えてきている印象でした。TELE-PLAY始動以前はどんなモードで動いていたんでしょうか。
いろんなところにどんどん出て行こうというよりは、「作らなきゃな」という意識の方が強かったですね。日本に帰国した当初、CRCK/LCKSを始めた最初の2年くらいは、外に出て行くぞというので、1年のうちの300日くらいはライブハウスとかミュージシャン系の飲み会に行く時期があったんですけど。そのときに知り合った仲間たちと仲良くなって、一昨年くらいからもらえる音楽の仕事もだんだん増えてくる中で、点と点が繋がってきて。自分が何を作りたいか、何を作れるのか、みたいなところにフォーカスしてました。
あとはTENDREがどんどん人気になっていったりとか、CRCK/LCKSもいろんなお客さんに聴いてもらえるようになって、ライブの本数も増えていって。僕、もともと作編曲とかが好きでやっていたので、ライブの隙間に入ってくるサポートだったり他の制作のお手伝いだったりを、ひたすら良いクオリティで上げていくことに終始していたから、あんまり自分をどう見せるか?みたいなことは考えていなかったですね。
――創作意欲としてはどうでした?
創作意欲の上がり下がりみたいなものを感じたことがあまりなくて。どちらかというと普段から、表には出さないですけど僕はテンションの上がり下がりが激しい方なので、作れるときに作って、作れないときはインプットの時間にするように過ごしていました。まあ、あとは締め切りに追われて仕上げていくっていう(笑)。
――新型コロナ禍以降、音楽シーンが様変わりしたまま今に至るわけですが、ミュージシャンの動きとしては当初、星野源さんの「うちで踊ろう」のような試みがあったり、Save Our Spaceのように直接的に行政に働きかける動きもありました。小西さんはそういった状況をどう見て、どんな風に考えていたんでしょうか。
そうだな……あのときは本当にいろんな、ポジティヴな面だけじゃない、後ろ向きな考えも自分の中にはあって。音楽ビジネスのあり方としては一旦崩れたというか、誰も予想していなかったことが起きた訳なので、じゃあそれで音楽をいろんな人たちに届けていく道は閉ざされたのか?とか、ライブが無くなると音楽はダメになるのか?とか。
でも、常にそうではあるんですけど、どんな状況になったとしても生活というのは続いていくじゃないですか。その営みを途切れさせることは選択肢として無くて。生活が続いていく中で、プレイヤーとしてミュージシャンとしての僕は、演奏がしたい。いろんな人に何でもいいから届けたいっていう気持ちがまずありました。それはたぶん星野源さんにしてもTENDREにしても、どのミュージシャンにもあったから――(昨年の)3月4月は今までで一番、夜8時くらいからインスタライブがたくさん並んでいた珍しい1~2ヶ月だったと思うんですけど――そういうアクションに繋がったと思うんですね。
――はい。
僕自身はフォロワーが多いわけでもない、一音楽家でしかないので、そんな中で自分にできることって何なんだろうな?と思ったら、制作は好きなので面白いものが作れたらいいなと。僕が誰かに何かを伝えたいというのも気持ちとしてはあるんですけど、それよりもちゃんと作品にして届けること。それがただこんな状況だからって曲を一個ポンと作って終わりっていうのだと、あんまし動き出す意味がない……わけじゃないですけど、継続可能で一過性のものじゃないプロジェクトというか、プラットフォームになればいいと思ったんですね。
たとえば海外だと『Tiny Desk Concerts』もあるし、『Against The Clock』とか、いろんな映像メディアの作品があるんですけど、そういうちゃんといろんなミュージシャンに来てもらって、お互いのためになるような、お金の面においてもプロジェクトの質の面でも継続可能な“場所”を作りたくて。コロナが終わっても面白いコンテンツとして観続けられる場所になりたいし、コロナがあったからこの作品ができたというふうにはしたくない。あくまでキッカケの一つでしかなくて。新しく何かが生まれたというよりかは、僕らはあらためてこういう気持ちだったりとか、生活のこととか、もう一度大切なものを見直す時期だと思うんですよ、コロナの間って。
――まさにそうですね。
僕はいろんな人たちと音楽を作るのが好きなタイプで。自分の世界を構築しきるような、映画を一本作るみたいなことにもすごく憧れはあって、自分にもそういう面もあるにはあるけど、それだけの人間じゃないなと思っているので、いろんな人と作り続けていける場所が良いなと思って。
かつ、なんでかわからないですけど、自分は作家として参加せずにプロデュース、ディレクションとしてそういう企画をやってみたいと思った、というのが流れとしてはあります。だから、「何ができるのか」って考えたときに、リスナーの人に届けられるものとして「こういう気持ちを僕らはいま見つめ直して音楽にしてます」っていうことを、音楽とプラットフォームとでリーチしていきたいというか。多分、そういうことなんですよね。
ただ曲を作っていくだけじゃなくてプロセスも見せたいというのも最初から思っていて、メイキングやビハインド・ザ・シーン的なもの、営みみたいなところがもっと見えるようにしたかったんですね。日本のメイキングって、作り手本人よりも楽しさとかムードに焦点が当たっているようなイメージが僕の中にはあって。
――ツアーの打ち上げ映像とか、レコーディング中のオフショット的なものとか。
そうそう。映像作品のエンタメ性の延長のような。でも海外のものってもうちょっとドキュメンタリーチックで、制作の方に焦点が当たっている感じがして、そういうのも見せられたら面白いなって思ってました。

――この企画を思いついてから、まずはどう動いていったんですか。
とにかくいろんな人たちに連絡しました。あの頃はライブが無くなったぶん空いている時間はあったので、それを使って。やっぱり当たり前だけど、自分の思っていることが正しいのかって、人と話してみることでもう一度アイディアが吟味できたりとか、考えがブラッシュアップされていくことはあると思うので、別にミュージシャンに限らず、クリエイティヴの仕事をしている友達たちに結構ラフに電話して、「こう思ってるんだけどどうかな」っていう連絡をしまくったのを憶えてます。
――一番最初に声をかけたのは?
誰だったっけな……でもシンガーの3人――SIRUP、TENDRE、Charaさんには企画全体が固まりきる前に電話して、やってみたいことがあるんだっていう話をしてたと思います。
――ということは、当初から誰か1人をメインボーカルに立てた作品にするというふうには……
全然考えてなかったです。共同制作のものであること、僕が作った音楽にみんなが寄せてくるものではないというのは、早い段階から思ってました。僕はただの発起人で、“場所”にみんな来てもらうという。僕は場所を作っている一人でしかないというふうに思ったので、もちろん僕がメインで動いてますけど、最終決定やプロデューサーとして動ければいい。……なんでだろうな、結構最初の方から何人かで作ってもらうのが良いだろうと思ってましたね。たぶん、リモートで誰かと曲を作ったとしても、単純に構造としてどちらかのアーティストの曲になるだけだなと。それじゃないなと思って。
――それにしてもここまでパートごと、セクションごとに別々の方を集めたのはすごいです。
うん(笑)。元気になる曲を作りたかったんですよ。こういうときだからいろんな曲があると思うんです。寄り添う曲や慰める曲、怒る曲とか。普通に生活していれば喜怒哀楽はあるので、どの感情も音楽として良いと思うんですけど、僕は楽しくなりたいとか、安心したい、ホッとしたり明るくなったりする気持ちが良いなと思って。
一番最初、シンガーの人たちに僕からテーマをお渡ししたんですけど、コロナをキッカケとした、こういう距離を隔てた生活の中で浮き上がってくるものはあったはずで、いろんな物事がふるいにかけられたと思うんですね。その中で残っていく感情の中で、「寂しい」「会えなくて辛い」とかっていうのは、結局「会いに行きたい」というシンプルな欲望の話で、話すでも触れるでもいいですけど、“繋がり”を求めているんだなって。だから今回のテーマは“繋がり”にしたいです、っていう話をさせていただいて。
その時点で、じゃあいろんな人がいるのが良いよなって思ったのはあります。一人が一人に会いに行く話じゃなくて、みんながリモートワークで一堂に会して一つの音楽にワーッと集まることで、小さな村じゃないですけど、そういう場所を作れたらいいなと。その第一回だから、一人や二人じゃなくて盛大にやれたらいいんじゃないかなっていう。
――「会いたい」気持ちを歌った曲は古今東西にあって。でもその前提となる「会いたいけど会えないシチュエーション」はこれまで、遠距離恋愛だとかあるいは死別とかの限定的なものであることが多かった。こういう社会状況になってそれを誰しもが味わうことになったんですよね。だからこそ、とてもスッと入ってきたし、そこに優しさもあたたかさも感じて。
第一回で何を言うかはめちゃくちゃ大切だなって色々と考えていたんですけど、あんまり難しく大げさに言うよりはすごくシンプルなことだよなっていうのがありました。だからスッと入ったのであればそれはすごく嬉しいですね。
――「元気になる」という言葉がありましたけど、ワーッと騒ぐような元気ではなくて、気持ちがそっと晴れる感じというか、陽だまりのような、さりげないあたたかさがあって。
うんうん、そうですね。「誰かに会いに行こうかな」と思ってドアをガチャっと開けて出かけるときの、あのワクワク感。晴れた日の午後みたいな感じだったら最高じゃないですか。それが良いなと思っていたので、陽だまりとかそういうのは、僕もイメージとしてありますね。

――実際に制作がスタートしてからはトントン拍子に進んでいったんでしょうか。
やっぱり多くの人たちが関わってくれるので、いろんなやり取りがあって、運営チームと密に連絡を取りながら、みんながスムーズに作業できるようにやっていく大変さはもちろんありました。でも、「もっとこういうやり方があるんじゃないか」「いやそうじゃない」みたいなことはほぼ無く進んでいましたね。音楽のクリエイトとして、このクオリティの作品をこれだけの人数とやるという意味では、相当スムーズだったのではないかと思います。
――実際の期間としてはどれくらいですか。
曲作りとしてはほぼ1ヶ月ですね。最初にChara、SIRUP、TENDREのソングライター陣が集まって、僕がお題を渡して作り始めるところから、音が完全に完成するところまでは1ヶ月強なので、録り終わるまでは多分1ヶ月かかってないし、そう思うとめちゃくちゃなスピードで仕上がってますね。
ミュージシャンみんなの、そのときの気持ちというか、集中力と音楽を作ることに対する真摯さ、真剣さがそうさせたんだと思います。プロジェクトとしてはこれだけの人数が関わっていて大変なんですけど、このやり方に関する疑問は誰からも上がらなかったので。
――TELE-PLAYを通して初めて繋がったり、これまで関わりが深まったような方もいました?
曲の骨格を作っている3人とはアレンジを考えたりライブを一緒にやっているし、ミュージシャンのみんなとも仲は良くてお互いの音楽がどういうものかは把握していたんですけど。一緒に曲を作ったことは無かったですし、あらためて制作を一緒にするっていうのは、そう思うと大体が初めてだったのかな。
(挾間)美帆さんと吉田沙良、あと管弦楽器チームは僕がずっとお世話になってきてる人たちですけど、ギター、ベース、ドラム、キーボードは全員、制作という意味では初めましてだったから、すごく面白かったですね。どこにこだわりを持っているかとか、友達の、ミュージシャンとしてかっこいいところにあらためて触れていくことでもありました。
Charaさんと豪太さんは、この並びを見ると大先輩が2人いるっていう感じなんですけど、先輩を入れたかったからとかじゃなく、単純に、豪太さんはドラムプレイヤーとしてもトラックメイカーとしても超一流の人じゃないですか。今回、トラックメイクとしてはA.G.O (CIRRRCLE)、Shin Sakiuraっていう若手も入ってますけど、それをブラッシュアップしてくれるドラマーって誰なんだろう? ただサンプリングドラムじゃなくてちゃんとビートのことを分かって第一線でやっている人で……ってなると、豪太さんだなってパッと浮かんだんですね。
Charaさんも同じで、誰か一緒に曲を作ることをしてみたいってなったときに、Charaさんとやってみたいって。後から見ると先輩が2人入ってるなっていう感じはするんですけど、オファーの当初はあんまり意識はなかったですね。
――結果的に、この2人がいることによって、見え方が“特定の界隈が集まってやっていること”じゃなくなったのはある気がします。
それは本当に思います。やっぱり速いですよね、第一線でやっているミュージシャンの人は。アイディアのキャッチと、出てきている音楽に対する反応の速さっていうのはみんな素晴らしかったです。
――あとはMVがまた良いんですよ。
あれ、良いですよねぇ。
――魚眼レンズを通して見る感じの。
そう。映像チームもロゴデザインも、デザイン周りも多くの方達に手伝ってもらっていますけど、その中で一番最初にMVをどうするか?ってなって。この企画はそもそも曲だけ作るんじゃなくて映像ありきというのが一番最初にあって、むしろプラットフォームとして映像コンテンツを作るぞぐらいの感じだったので、ビジュアルはすごく気にしていたけど、状況としては映像チームにはかなり大変な状況というか。自粛期間で外にも出られない、人と集まれない中で、どうやって面白いMVを作るか。じゃあ魚眼でみんなに自撮りしてもらおうっていうところに辿り着いたんですね。
――実際に魚眼をお渡しして。
そうです。そこらへんもちゃんと映像の人がこだわりを持ってやってくれているので、それぞれの自宅の自撮りではありますけど統一感もでているし、あれは本当にセンスですよね。エッセンスとして魚眼が入っているんじゃなくて、魚眼がルールというか、魚眼縛りで一本撮りきるという。あとは魚眼って昔から映像手法として使われてますけど、ここまでやりきっているのは無いよねっていうところで、面白いものができたなと。
――たしかにサイケデリックさを演出したりとか、ライブ写真なんかで使われることはありますけど、この曲では窓のような、決まったフォーマットを通してそれぞれの様子を見ていくツールのように使われていて。
覗き穴ですよね。だから面白いですよね、向こうの家を覗いているのか、はたまたこちらが除かれているのかわからない、それだけでもちゃんと意味があるというか。映像も最後までちゃんと作りきれて、とにかく映像チームがめっちゃ頑張ってくれたなって感謝してます。
――MVや楽曲がラジオで流れたりサブスクで配信されたりしていく中で、広がりやリアクションなども実感しましたか。
本当にいろんな人たちに観てもらえてるみたいで。再生数もずっと上がり続けてますし、SNSの反応を見る限りでは“あたたかい曲”としてみんなに届いたんだなっていうことが、まずわかったので。そこはすっごい嬉しかったですね。
音楽にできることって、別に音楽を聴くとお腹がいっぱいになるわけでもないし、傷が早く治るわけでもないので……そういう効果もあるかもしれないですけど(笑)、少なくとも目覚ましい変化として現れるわけではない。でも音楽に唯一できるのは、想像力の部分でいろんな人たちの人生に関わっていけることだと思っているので。そうやってこの曲の「誰かに会いに行きたい」っていうテーマがいろんな人のところに届いて、“あたたかい”とか“みんなに会いたい”って思える気持ちのきっかけになれてるなら、みんなと作った甲斐が本当にありますね。
――公式サイトを見るとTELE-PLAYにはナンバリングが1~3まで表示されています。2、3に向けていま言えることなどあれば、最後に。
TELE-PLAYっていうくらいなので、離れてる距離がキーワードだと思うんですけど。最初に言ったように、コロナは一つの契機でしかないので、距離を隔てて作れること、距離があるから考えられることはまだこれからも全然あるし、コロナの状況もまだ続いていくだろうから、遠隔でやっていく中で面白いプロダクトを作っていきたいです。「え、こんな組み合わせ、聞いてないよ」「すげえよ」ってワクワクできるコンテンツと座組みを準備しているので、「あいにいきたい」とはまた違った形で作れるんじゃないかなと思います。
取材・文・撮影=風間大洋
小西遼の言葉通り、ついに第2弾のTeaser映像が公開された。
タイトルは「prism」。
前作とはまたひと味違う、壮大な映像とアレンジに仕上がっている。
5月12日のリリースまで参加アーティストは一切シークレットとなっており、この31秒のTeaser映像を見ながら想像を膨らませて待ちたい。
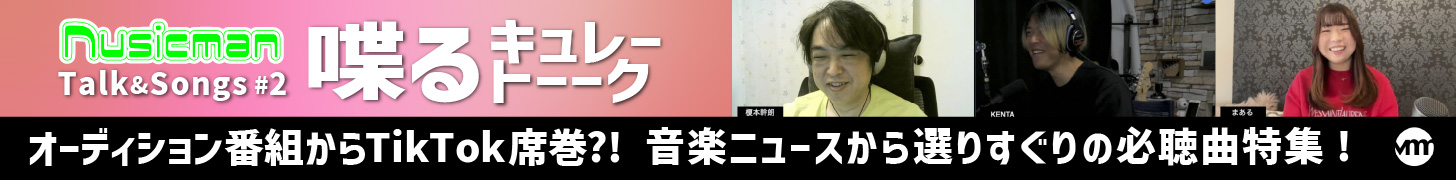

広告・取材掲載