
THE BOHEMIANS(L⇒R:平田ぱんだ/Vo、ビートりょう/Gt) 撮影=森 好弘
ポップなTHE BOHEMIANSをとことん見せつけることに挑んだ前作『the popman’s review』から一転、10作目のアルバムとなる『essential fanfare』は両極端な振り幅を意識したせいか、ロックンロールを追求しながらも、彼らの場合、ニュアンスに富んだものになることを、改めて印象づけるものとなった。コロナ禍の中でも焦らず、逆に自分たち本来のペースを取り戻したところが頼もしい。今回、インタビューに答えてくれた平田ぱんだ(Vo)とビートりょう(Gt)は決して声高に語ることはしないが、2人の言葉からは確かに今回のアルバムに対する手応えと自信が感じられる。
――2年前に前作『the popman’s review』をリリースするタイミングでお話を聞かせてもらったとき、“ポップなもので勝負しようという意気込みで作ったんだから、リリース後、活動が上向きにならなかったら、次はやさぐれたアルバムを作る”とおっしゃっていました。
平田:そんなことを言ってましたか。
――でも、今回の『essential fanfare』がやさぐれたアルバムにならなかったことを考えると……。
平田:上向いたんですね。
――その後のツアーも含め、しっかりと手応えを感じられたわけですね?
平田:大きくは変わらなかったですけど、普通に動員も増えたし、調子いいなと思った記憶はありますね。
りょう:いい感じでした。だからその後、コロナ禍になっちゃってもったいなかったです。
――そうなんですよね。そのいい感じを理想的な形で繋げられなかったところはあると思うんですけど、その中で、THE BOHEMIANSは今回のアルバムの制作も含め、どんなふうに音楽に取り組んでいったのでしょうか?
平田:まったりしてました。いつもはツアーを決めて、それに向けてアルバムを作らなきゃってやってるんですけど、そういう追いかけられている感がなくて、ヒマだから普通に作った曲を、みんなで練習していったらいっぱいできたんで、そこからどれを入れようかって作ったんです。今回、未完成の曲もなかったんですよ。THE BOHEMIANS史上最も余裕のある制作環境でした。結果、自然に2年にアルバム1枚のペースになってよかったです。今までは1年に1枚、必ず作らなきゃいけないプレッシャーがあったんです。これぐらいがいいなと思います。
――まったりした日々は心地好かったですか? 焦りや不安みたいなものはなかったですか?
平田:僕はまったくなかったですね。“やったー”と思って、家にいても、ゴロゴロしてても、むしろホメられるぞぐらいに思って、死ぬほどゴロゴロしてました。
――バンド活動、どうなっちゃうんだろうとは?
平田:まったく思わなかったですね。やりたくてやってるはずなのに、やらなきゃいけない、みたいな感じってあるじゃないですか。それはおかしい。こっちのほうが自然だと思いました。

――りょうさんはいかがでしたか?
りょう:ライブも含め、物理的に活動ができなかったから、できることをやるしかないというモードではありました。それで自然と曲が溜まっていった時期だったと思います。やれてないのは俺らだけじゃないですからね。
平田:それがいいんだよね。俺らがさぼっているわけじゃないぞって言い訳がいくらでもきいたので、まったりと曲を仕上げていけましたね。
――じゃあ、まったりとしながら、自然と曲作りに向かうことができた、と。
平田:趣味なので。バンドは割と趣味なので、どっちにしろやることはやるんだと思うんですよ。
――本来、あるべき形で音楽に向かうことができたわけですね。
平田:そうです。やりたくてやりました。
りょう:実は、内々では2枚のアルバムを同時に作るというコンセプトがあったんですよ。普通に全国流通のメジャーアルバムと、もう1枚、サブ的に通販と会場限定の、あんまり余計なことを考えない、うるさいだけの、ただのパンクロックアルバムを作ろうと考えていたんです。そしたら、曲がどんどん溜まっていって、そのうちに、どっちがどっちっていうコンセプトは要らないんじゃないか、と。普通に、いい曲を作ればいいんじゃないかってなって。2枚分の曲を作ったんですけど、結局、レーベルのボスの(山中)さわおさん(the pillows)を含め、いい曲ばかり入れた1枚を作ろうってなって、出来上がったのが今回のアルバムなんです。
平田:さっき言ってたやさぐれたアルバムって、サブの方を僕個人の希望としては、そうしたかったんですよ。それでやさぐれた曲も作ったんですけど、そんなに溜まらなかったので保留にしておきました。また今度でいいやって。

平田ぱんだ
幅の広いボーカリストなんです。実力があるんです。でもロックバンドのボーカルなので、ちょっと下手に歌うほうが僕っぽいと思ってます。(平田)
――前作の時は、曲作りはりょうさんを中心に進めていきましたが、今回は?
平田:ほとんどみんな会わずにいたので、それぞれに作りました。だから共作的なものが1曲も入っていない初のアルバムなんじゃないかという。
りょう:確かに。いちばん曲を作ったのは俺だと思うんですけど、俺の曲がめちゃくちゃ外されました(笑)。
――りょうさんとしては、当然、悔しいとか、残念とかっていう気持ちが?
りょう:ちょっとありますけど、売り物にするんだったら、いい曲を集めたほうがいいと思うんで。
――なるほど。じゃあ、作り方としては、それぞれに曲を作って、完成させて、メンバーに送ってという?
りょう:そうです。宅録で完成形に近いデモを作ってました。
平田:それを送り合って、バンドで集まったらもう練習って感じでした。
――今回、平田さんが作った曲は?
平田:「the reasons」「the ultra golden brave busters」「the erina」「the fanfare」「何の変哲もないロッケンロール」です。
りょう:「VINYL PRESS STONE」がキーボードの本間(ドミノ)君。それ以外は俺です。

ビートりょう
いつもどおり特にコンセプトも何もなく作詞作曲しているんですけど、結局、何も考えない方が人間性とか性格が出るってことだと思います。(りょう)
――確認なんですけど、今回、りょうさんがリードボーカルをとった曲ってありますか?
りょう:いや、ないです。それっぽいのありました?
平田:どれでしょう?
――いや、僕がTHE BOHEMIANSのことをわかっていないということになっちゃうのかもしれないですけど、本間さんが作った「VINYL PRESS STONE」とか。
平田:それは、本間ドミノという支配したがる人に何回も歌わされたんですよ。僕が歌ったやつだと、“イメージと違う。そんなの違う”って何回も歌わされたんで、僕本来のボーカルと違うのかもしれません。
りょう:どちらかと言うと、本間君のデモみたいな歌い方にされて。
平田:本間君がデモで歌ったとおりに歌わないといけなかった。
りょう:確かに平田君っぽい声じゃないかもしれない。
平田:恐ろしい男です(笑)。本間ドミノの曲があんまりアルバムに入らない理由はそれです。本間ドミノがうるさいから、あんまり僕は歌いたくない。だから選ばない(笑)。
――あと、「いとしの真理」と「図鑑」もいつもの平田さんとは違って聴こえましたが。
りょう:俺の曲だからっていうのがあるかもしれない。
平田:「いとしの真理」もビートりょうに隣にいてもらって、“気に入らないところがあったら言って”と言いながら録ったから、確かに普段の僕の歌い方じゃないのかもしれないですね。
りょう:基本的に、平田君は作者に寄せるっちゃ寄せるよね。
平田:寄せますね。僕は。
りょう:特にデモがあると、それを再現しようとする。
平田:それができる幅の広いボーカリストなんです。
りょう:いいように言うとね(笑)。
――いやいや、平田さんが歌っているんだとしたら、実際、歌っているんですけど、こういう歌い方もできるんだって、ちょっとびっくりだったんですよ。
平田:実は実力があるんです。
――うんうん。
平田:いや、頷かれても困るんですけど(笑)。
――こういうふうにやさしい歌い方をしても魅力的に聴こえるんだって。
平田:そうなんですよ。もっとホメてください。
――本来は、そういう作曲者のディレクションがなければ、いろいろな歌い方はしたくないんですか?
平田:したくないと言うか、ロックバンドのボーカルなので、もうちょっと下手くそと言うか、ちょっと下手に歌うほうが僕っぽいと思ってます。
――じゃあ、今回は、ボーカリゼーションの幅広さも聴きどころだ、と?
平田:でも、いつもそうなんじゃないかな。
りょう:そんなふうに言われて、初めて気づいたんですけど、そういった意味でも今回のアルバムは幅広いかもしれないですね。自分ら的には、いつもとあんまり変わらない作り方なんですけど、曲がアルバム2枚分ある中から選んだことに加え、準備期間も長かったので、曲をこなすまでの時間があったから、平田君の歌もそうだし、演奏もそうだし、曲それぞれに合わせたものになっているって、今、思いました。

意識はしてないですけど、アラフォーなんで。“あんな奴、クソだ”みたいな歌は、この年では歌いづらいです。(平田)
――THE BOHEMIANSが持っているいろいろな魅力を満遍なく表現したアルバムになったと思うんですけど、その中で、THE BOHEMIANSが博愛を歌っているようなところが印象的でした。
平田:意識はしてないですけど、アラフォーなんで、そういうことしか歌わなくなるんじゃないですか。“あんな奴、クソだ”みたいな歌は、この年では歌いづらいです。
――そういうことなんですか?
平田:いや、わからないです。無理やり答えるならそうなるってだけで。
――コロナ禍の中で思ったことがそれだったのかなと想像したのですが。
平田:みんな、とてもやさしい性格なので、コロナ禍とは関係なく、普通にそういう人たちだと思います。元々、そうだった気がします。
りょう:いつもどおり、特にコンセプトも何もなく、みんな、作詞作曲しているんですけど、結局、何も考えない方が人間性とか、性格とかが出るってことだと思います。平田君が言ったように年齢もあるのかもしれないし、意識はしてないけど、コロナ禍の影響もあるのかもしれないし。まぁ、そこに結びつけようと思えば、結びつけられるのかもしれないけど、それはそれで聴く人それぞれに好きなように感じもらえればいいと思います。
――アルバムに先駆け、「the legacy」とともに配信した「the erina」は、すでにファンの間で評判になっていますが、すごくいいラブソングだと思いました。
平田:40歳までにやり残したことをやっておこうと思ったんです。ギリギリかなと思って、30代の最後にこういうこともやっておこうって。これ、40歳を超えたら、キツいなと思ったんです。歌詞はともかく、曲調は本来、僕が作るような曲じゃないんです。サザンオールスターズみたいな曲を激しくやるってイメージなんですけど、そういうポップな曲調で少年みたいなことを歌うのは最後だと思ったので、禁じ手を使いました。二度と作りません。
――えっ、二度とですか?
平田:39歳でもう1回やるかもしれません。
――1曲目の「the legacy」から、「the reasons」「the ultra golden busters」とタイトルにtheが付く曲が並んでいて、そこに続く「the erina」にもtheが付いている。だから、erinaって何か名詞なのかと思ったら、女の子の名前で、そこにtheを付けるって、唯一無二、世界でたった一つの存在だと言っているってことじゃないですか。
平田:そういうことにしましょう(笑)。
――あ、違うんですか?
平田:ただ僕は曲のタイトルをバンド名にするのが好きなんですよ。だから、「the legacy」も、これ、ビートりょうの曲ですけど、“曲のタイトルが思いつかないから何かつけて”って言うから、“知らねえぞ”って言って、「the legacy」ってバンド名をつけたんですよ。だから、「the erina」のtheもバンド名につけるtheなんです。でも、これからは「the erina」のtheは、そっちで答えていきます。
――絶対、答えていってくださいよ(笑)。好きな女の子の名前に、たった一つの存在という意味でtheを付けるって、すごくロマンチックだなって思いながら聴いていました。そうか。違ったのか。
りょう:いや、その想像力は素晴らしいですよ(笑)。
――そこまで言われると、逆に恥ずかしいです。でも、THE BOHEMIANSは聴きながら、あれこれと想像が膨らむ曲が多いですよね。その「the erina」をはじめ、今回、THE BOHEMIANSが持っている叙情的と言うか、メランコリックな面が多めに出たのかなという印象もありましたが。中でも「バビロニアの世界地図」「いとしの真理」「図鑑」はノスタルジックなところもありますね。
りょう:そのへんは仮歌詞のままって言うか、もうちょっと推敲して、いいものにできるイメージだったんですけど、最初に出てきたものでいいんじゃないのかって仮歌詞のままの部分があるんですよ。そんなふうに言ったら、前向きじゃないと思われるかもしれないけど、そっちのほうが素直でいいんじゃないかなと思いました。音も含め、もうちょっとセンスのあるものにできると思ってたんですけど、時間をかけて作るものでもないな。これでいいだろうって。
平田:そんなにすらすら書いたんだっけ? 「バビロニアの世界地図」なんて、すごく考えたんだと思ってたからすごいなって、今聞きながら思いました。
りょう:いや、すらすらと書いたわけじゃないけど、無理やり言葉を当てはめたものをそのまま使ってるっていう。
平田:詩的でいいなと思いますよ。
――「図鑑」の《花の図鑑で見た 不可思議が並ぶ人以外の笑顔を》というフレーズはそういう捉え方をするんだ。すごいとな思いました。
りょう:そう言われるだろうと思いました(笑)。こういうインタビューで突っ込みどころになればいいなと思ったところもありましたね。歌詞を書く時は極力、変な歌詞がいいと思ってるんですよ。聴きながら、ひっかかるようなね。まぁ、バランスですけど。
――前作の時は、平田さんは1曲しか歌詞を書かなかったじゃないですか。でも、今回は平田さんが作った曲は、平田さんが歌詞を書いているんですよね?
平田:そうです。だから、久しぶりにレコーディング前に、歌詞を書かなきゃいけない期間と、絶対に歌詞がもっと良くなる期間がありました。イヤだなと思いました(笑)。結局、絶対にもっと良くなるんだけどなぁと思いながら、もうこれでいいやって、最初に作ったやつで出すんですけど。
りょう:みんなそうだよ。歌詞じゃなくても、メロディも含め、サウンド的なものでもそれはあると思いますけどね。どこかで線を引かないと、永遠にできないから。
平田:そうだね。
――今回、平田さんがこの歌詞、よく書けたと自分で思うのはどの曲ですか?
平田:まったく思わないですね。
りょう:そう言うと思った(笑)。
平田:「何の変哲もないロッケンロール」のようなバカバカしいやつのほうががんばって書いているんですよ。ちゃんと韻を考えながら。
りょう:これ、いいよね。
平田:こういうやつのほうが意外と大変と思ったので、これが一番気に入ってます。
――バカバカしいとおっしゃいましたけど、THE BOHEMIANS流の「イッツ・オンリー・ロックンロール」ですよね。たかだロックンロール、だけど、大好きだぜっていう。
平田:そういうことにしましょう(笑)。
――こういうノベルティソングっぽい曲は、そういう曲を作ろうと思って作るんですか?
平田:作ろうとして作りました。何の変哲もない3コードのロックンロールって、意外とTHE BOHEMIANSにはないんですよ。その上でちょっと言葉のリズムを気にして、作ったらいいんじゃないの? そういうナンバーが昔から欲しいと思ってたので、それを作りました。
――イントロのギターがエディ・コクランっぽくって思わずニヤリでした。
りょう:そのリフを作ったの平田君だよね。
平田:違う違う。これはメンバーに丸投げでしたね。
りょう:そうか。リフを作ったのは俺か。
平田:そうそう。“自分の中のロックンロールはこうだって思うように演奏してください”ってメンバーに丸投げしたら、こうなりました。“イントロはエディ・コクランにしてくれ”って言いましたけど、“(エディ・コクランの)「サムシング・エルス」のドラムで始めたい”としか言ってないです。“あとは好きにやってください”って言いました。
――あぁ、それでりょうさんがあのリフを考えた、と。
りょう:スタジオでやりながらできていった曲ですね。
――イントロのギターと言えば、「いとしの真理」は、デュアン・エディの「ピーター・ガン」風のリフからフォークロック調になるところが意表を突く感じで、やはり思わずニヤリでした。
りょう:あぁ、あそこは俺の中では映画の『007』のイメージだったんですよ。でも、そういうことですよね。
――「カンケイシャになりたくないっ!?」は、関係者としてライブを観ることが多い僕は耳が痛かったです。
りょう:いや、そういうことを言いたかったわけではないですよ。
――あ、そこはちゃんとわかっています。りょうさんが客としてライブを観に行った時の話ですよね。
りょう:そうです。クロマニヨンズのライブにイベンターさんから招待してもらって、何回か観に行かせてもらったんですけど、自分でチケットを買って観に行った時と全然違うと思ったんですよ。Zepp Tokyoの2階の関係者席で観るのと、ファンとして1階席で観るとの→のとでは迫力が。そういうことかと思って、自分が観たいものは、自分でチケットを買って観に行こうと思いました。だから誰かに対してどうこう言いたい歌詞じゃないです。THE BOHEMIANSのライブでは楽屋挨拶は全然気にせず来てください(笑)。
――でも、ライブ終演後の楽屋挨拶という習慣、本当に要るのかな(笑)。本当にいいライブだと思って、“ライブ良かったです”と言っても、演者はそう思っていない時がしばしばあるようで。
平田:それ、あるあるです。なぜだか良くなかった時のほうがホメられるんですよ(笑)。
りょう:難しいですよね。俺が友達のライブを観に行った時も何て言っていいかわからないと思いますもん。
――平田さんは観たいライブはチケットを買って行きたいタイプですか?
平田:完全にそうです。カンケイシャになりたくないです。この歌詞はけっこう共感できます。絶対チケットを買って行ったほうが楽しい。

インディーズの1stアルバムが“ジャパキン”なので、そんな愛称みたいに略して呼ばれたほうがかわいがってもらえそうな気がするんです。(りょう)
――全11曲は、どんなふうに選んでいったんですか?
りょう:さわおさんも交え、客観的に売れるアルバムを目指して選んでいきました。自分が作った曲が外されて残念と言いましたけど、たくさんある中からいい曲を選りすぐって、作っていくのが一番いいじゃないですか。健全な作り方だと思うんですけど、収録曲の倍以上の中から選んだのは初めてなんじゃないかな。すごく良かったと思います。
――前作以上の成果が期待できそうですね。リリース後はどんな活動をしていこうと考えていますか?
平田:今のところ、東名阪のツアーしか予定がないです。残念ながら。だから、動員云々ではアルバムの成果は判断できないですね。どうせ入場者数制限で、各会場100人ぐらいだろうし、そこは残念だと思います。
――それはそれとして、どんなツアーにしたいですか?
平田:いつもどおりだと思います。
――前回のツアーでは動員が増えたじゃないですか。その中でライブの取り組み方に対する考え方は変わりましたか?
平田:それはまったくないです。前のツアーよりもその年末の、いつもの『the pillows presents “COUNTDOWN BUMP SHOW!! 2019→2020”』の時の反応が全然違くて、野郎どもが前方にめっちゃ押し寄せて、女の子たちがかわいそうでした。それまでthe pillowsファンにそこまで受け入れられてなかったのに、俺たちが一番目に出たらめちゃくちゃ盛り上がって、“あ、これ、イケるんじゃね?”って自分たちのツアーの時よりもその時のほうが思いましたね。ただ、その後、コロナ禍になっちゃったんですけど。
――コロナ禍がなかったら、ライブのやり方を変えていたということですか?
平田:いや、変えると言うか、客の反応が明らかに変わってたので、自然に変わっていったのではないかなと思います。
――言ってもしょうがないですけど、そのままライブを続けていたらどうなっていたでしょうね?
平田:売れていたかもしれない。だから、言っておきます。コロナ禍のせいで売れなかったって(笑)。
――最後にアルバムタイトルの『essential fanfare』はどんなところからつけたのか教えてください。
平田:去年ずっと僕の中でlegacyという言葉が流行っていて、意味も言葉の響きもいいから、最初、『the best of legacy』ってつけたんですよ。ベスト盤みたいなタイトルがいいなと思ってたから。そしたら、さわおさんから“「the legacy」がリード曲だから、legacyって使わないほうがいい。アルバムのタイトルナンバーが別にあったほうがいいから、fanfareにしなさい”と言われたので、ベスト盤っぽいタイトルでfanfareに合う言葉はessentialしかないと思って、『essential fanfare』、なんていい言葉なんだと思ってつけました。我ながらいいタイトルがつけられたと思います。最初のタイトルをボツにしてくれて、さわおさん、ありがとうと書いておいてください。
――《見えない未来ばかりで》と歌う1曲目のタイトルが「the legacy」で、「the fanfare」の中にも《知らないとこで芽生えた未来のlegacy》という歌詞があるから、この2曲には何か繋がりがあるのかなと想像したのですが。
平田:ただの流行りです。「the fanfare」の歌詞の“legacy”のほうが先なんですよ。legacyという言葉をどこかに入れてやろうと思って、入れた後にさっきも言ったようにビートりょうから言われて、「the legacy」ってタイトルをつけただけで、何も考えてませんでした。
――りょうさんは『essential fanfare』というタイトルは、どう思っていますか?
りょう:いいタイトルだと思います。でも、最初、ただの『fanfare』にするって言ってなかったっけ?
平田:言ってなかったよ。
りょう:俺、“『essential fanfare』のほうがいいんじゃないの?”って言った記憶があるけど、 略してエセファンになるところがいいと思いました。
平田:それ、ずっと言ってんな(笑)。
りょう:俺らのインディーズの1stアルバムが『I WAS JAPANESE KINKS』でジャパキンなんですよ。そんなふうに愛称みたいに略して呼ばれたほうがかわいがってもらえそうな気がするんですよね。
平田:エセファンと略しなさいと書いておいてください(笑)。
取材・文=山口智男 撮影=森好弘


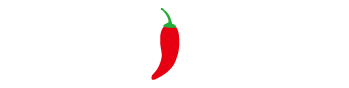
広告・取材掲載