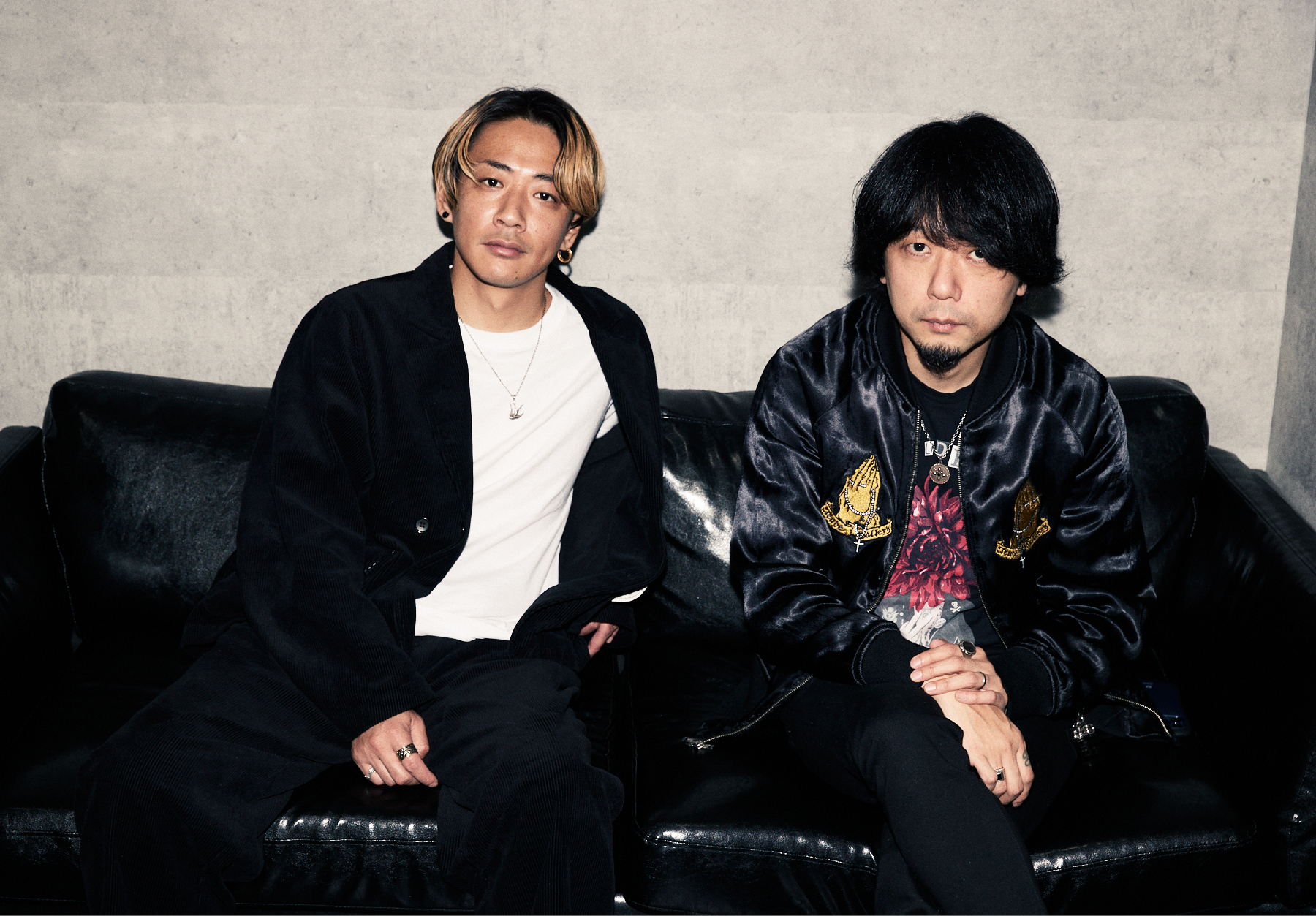
Nothing’s Carved In Stone・村松拓 / 生形真一 撮影=森好弘
その石に彫られていたのは、「転がり続ける」という強い意志だった――。Nothing’s Carved In Stoneの11thアルバム『ANSWER』は、2年2か月というバンド最長のインターバルを経て、新たな次元へと踏み込む意欲的な作品だ。生形真一と日向秀和がソングライティングの核心を成し、大喜多崇規が力強くリズムを支え、村松拓が曲に魂を吹き込む。新境地を拓くバンドの制作体制について、現代的なサウンド作りについて、言葉に込めたメッセージについて、そしてリスナーへの思いについて。生形真一と村松拓が本音を語ってくれる。
――今年を振り返ると、ツアーもできましたし、去年に比べたらバンド活動は充実していたんじゃないかな?と思います。
生形真一:そうですね。去年はライブがほぼできなかったから、ベストを作って配信ライブをやって、という感じだったんで。やっと今年はツアーもできて、野音もできて。野音、良かったですね。あれでも一応規制してたんですけど、すごいたくさん来てくれて、久々にやった感じしたよね? ああいう、たくさんのお客さんの前で。
村松拓:ほんとだよね。
――ライブもそうですけど、物販の列がすごくて、みんな歴代のバンTを着てて。僕らも「ああ久々だな」って思ってました。
生形:野音をやって、やっと……状況的にはまだまだですけど、なんか明るくなってきたなという感じはしました。
村松:ちょっとずつ、戻ってきたかなという感じだよね、周りも含めて。いろんな媒体の人とか、やっと動けるようになってきたんだなということを、すごくいい兆しに感じてます。
――あの9月19日の野音の時点で、今回のアルバムは完成していたんですか。
生形:9月の終わりまでやってたから、ギターと歌が多少残ってるぐらいの感じでしたね。今回はレコーディングの時期を2回に分けて、さらに配信曲も録ってるんで、わりと長い期間をかけて録ってます。年明けに出した「Bloom in the Rain」と、その次の「Wonderer」という曲は、同じ時期に録ってるんですよ。で、今年の頭に4曲ぐらい録って、後半に4曲録って、という感じですね。
――オリジナルアルバムは、2年振りですか。2年前はコロナ前だったし、制作環境もだいぶ違うと思うんですけど、どんな感じだったんですか。
生形:まあそういう状況もあって、最初のプリプロは街スタでやったりしてたんですよ。そうやって、各々で先にアイディアを固めちゃうやり方は、今回からだよね?
村松:うん。
生形:前は、4人で最初から入って、曲を作ってたんですけど。そうするとめちゃくちゃ時間もかかるし。
村松:効率悪かったんだよね。
生形:そうそう。今回は各々で曲のアイディアを固めてから、曲作りに入るようにしましたね。俺とひなっち(日向)の二人だけとか、拓ちゃんが一人で作って持ってきたりとか、そういう感じでやってました。
――その初めての作り方って、やってみて、どうでした?
村松:僕としては、曲を聴かせてもらうのが楽しみでしたね。二人(生形&日向)の曲が多かったし、わりと完成度の高い状態で上がってくるから、作曲者の意図が明確に感じられたんで。それをどうやってバンドに落とし込んでいくのか?ということを、オニィ(大喜多)と話したりしてました。だから、面白かったですよ。「ナッシングス、こういうことできるんだな」みたいな、いちファン目線みたいな感じもあったし。あとは、そのぶん歌に集中できたんで、どんなふうに表現しようかな?ということを、考える時間が多かったかもしれないですね。
――今回の『ANSWER』は、作り始める前に、言葉のコンセプトなのか、音像というのか、何かイメージはあったんですか。
生形:特にないですね。毎回思うのは、やっぱり新しいことをやりたいということと、それもやりつつ、自分たちが思うナッシングスっぽさも残したいなということがあって。でも最近思うのは、どんな曲をやっても、俺らがやればそれっぽくなるなという、そんなことを思いつつ作ってましたね。

――拓さんの、アルバム完成後の印象は?
村松:今までと客観的に比べて思うのが、うちって、曲とかメロディとかは真一の色が強くて、あとは各々のプレイスタイルというものでバランスを取ってたんですけど、今回はひなっちがメロディ、アレンジ、コード進行とかを、自分の頭の中で構築して練るようになったんですよ。ソングライティング・スキルを持った人がもう一人出てきたんで、要は、すごい強くなったんですよね。曲の持つ力が増したことを、すごい感じます。そこから真一と二人でスタジオに入って作ってたりしてるんで、突発的に勢いで作ってないというか、きちんと練り込んで、一個一個ベストの音を選んで作っているというところが、バンドとしては成長できたところじゃないかなと思います。
――生形さん、ひなっちを焚きつけたんですか。「曲書け」って。
生形:いやいや(笑)。それは、独立(※2019年10月にSilver Sun Records設立を発表)してから変わった部分もあるんじゃないですかね。たぶん、僕ら全員が。独立前は、俺がずっと所属していた事務所でやってたんですよ。そこで俺も、たぶん何かしら自分の責任感もあっただろうし、それが今は四等分になってるのかな?という気がしますけどね。四等分というか、各々の責任になるというか。本当にバンドだけの会社なんで。
――「これからは四等分だぜ」とか、話し合ったんですか。
生形:そんなこと話さないですよ(笑)。
――自然な流れなんですね。たとえば1曲目「Deeper,Deeper」って、どんな作り方をした曲ですか。
生形:「Deeper,Deeper」は、ひなっちが結構前に持ってきてたサビがあったんですよ。たぶん、『NEW HORIZON』の時にはあった。それを持ってきて、「ちょっと激しい曲作ろうか」って、だから最後のほうに完成した曲ですね。アルバムって、最初はわりとミドルの曲が多くなっちゃうというか、たぶんキャリア的な部分もあると思うんですけど、ミドルが気持ちいいなと思って作ってて、「最後はちょっと激しい曲作ろうか」みたいな感じになるんですよ。
――「Deeper,Deeper」は、どことなく、90年代ミクスチャーっぽさを感じました。
生形:ああ、でも最近の音楽を聴いてると、だいぶ増えてきましたね。そういう音楽が。ヤングブラッドってわかります? 新曲を出したんですけど、明らかにニルヴァーナから影響を受けたであろう曲を、今の音でやってるんですよ。あと、この間出たリンプ・ビズキットの新譜が、もろに2000年ぐらいの音だったり。別に「今それが来てるから」とか考えてないですけど、俺らが20代の時に聴いてた音楽が、若い子にとっては新しくなってきてるんだなって。ヤングブラッドなんてまだ24,5歳だし、そういう人たちが新しいと思って作ってるんだろうなということを、すごい感じますね。
――はい。なるほど。
生形:そこは俺らがめちゃくちゃ得意なところだから、世代的に。ただ、古いものの焼き直しじゃ駄目ですけどね。ちゃんと新しい音で作らないと。
村松:自分らの世代のフィルターを通したラウド感、って言うんですかね。そういうものはずっと表現してきたことだし、そこは消化しつつ、今どこに向けて投げてるか?と言ったら、海外に向けてとかじゃなくて、まず日本の人に聴いてほしいなという思いがあるから。日本で今いろんな音楽を聴いている人たちの耳に届くようになってほしいなって思ってました。すごい洋楽っぽい音像というか、めっちゃ分離が良くて、めっちゃ広くて、下もけっこう出てるんだけど、今のチャートに乗るような音楽を聴いてるティーンの子たちにも、ちゃんと聴いてもらえるような音になってるんじゃないかな?というところが、僕は良かったなと思ってます。特に「Flame」とか「Walk」とか、そういう感じになってると思うし。

――生形さんも、「今の若い世代の耳に届くものを」ということは考えますか。
生形:それは自然と多少は考えちゃいますね。やっぱり流行りの音ってあるものだから。ただそこに、あまりにも迎合しちゃうのも好きじゃないから、自分たちらしさを出しつつ。でもやっぱり、サウンドがでかいよね。
村松:でかいね。
生形:さっき言ったみたいに、ここ数年の世界のメインストリームにある音楽は低音をすごい出すんですよ。
村松:すごいよね。
生形:ただ、それを闇雲に出してもしょうがない。そのへんはエンジニアの人が詳しいし、信頼してるんで、そういうサウンドはけっこうやってもらってるかな。曲っていうのは、なんだかんだ、いつの時代も変わらないと思ってるんですよ。ビートルズの時から。あとは、サウンドとアレンジをどうやってるのか?ということだと思ってるし、それは邦楽もそうだと思ってるんで、そのへんは考えたかな。考えたというか……。
村松:自然とやるんだよね。
生形:そうだね。メンバーがわりと新しいもの好きなんですよ。特にひなっちと拓ちゃんは。俺はロックに偏ってるけど、ひなっちはR&Bとか、ヒップホップとか大好きだから、それをうまいこと混ぜ合わせて作ってると思います。古いものが駄目とかは思わないけど、同じことやってるよりは、音質にしても何しても、毎回更新していったほうが面白いんじゃないかなと思います。
――拓さんは、新しいものに注目するタイプなんですね。今回、拓さん主導の曲ってどれですか。
村松:9曲目(「We’re Still Dreaming」)ですね。アコギの音が入ってるやつ。その時ちょうど、コロナに入って1年経ったぐらいだったと思うんですけど、ソフトシンセを揃えて、いろいろ遊んでた時期だったんですよ。遊びでインストの曲を作ったりして、打ち込みの勉強をしたんですね。オービタルっていうエレクトロの人のものを聴いて、どんなふうになってるのかな?って研究しながら。今回、それがちょっと生きたところはあるかもしれない。「We’re Still Dreaming」はヘリオスみたいな、ヒップホップをベースにしているチルアウト系の音をベースにして、うちのバンドでできたらいいなというのをイメージして作りました。そこらへんを目指していくと、さっき言った90’s感っていうものがより出るかなと思って、今っぽくなるかな?みたいな感じでした。
――音の積みが、すごく精密なんですよね。細かく聴けば聴くほど。
村松:バランスがいいんですよね。ハッとする感じがあるというか、生形のメインリフがありつつ、アコギが両サイドから出たり、片方から出たり、出なかったり。そこはエンジニアさんの力がでかいとは思うんですけど。
――非常に精密に作ってる音楽だなって、あらためて思います。もともと、そういう感じでしたっけ。
生形:俺は、めちゃくちゃ考え込むタイプです。
村松:一生、曲書いてるよね(笑)。
生形:ただね、今言った「We’re Still Dreaming」の、真ん中とか後半に流れてるリードみたいなギターは、感覚で弾きました。そういうほうがいいなと思う時はそう弾くし、曲によって分けてますね。フリーセッションの良さももちろんあるし、でもそればかりやってても誰にも理解できないものになっちゃうし、それが必要なところに使うという、そのへんはけっこう分けましたね。「We’re Still Dreaming」のギターは、俺の感覚としては、ブラーとか、ゴリラズとかなんですよ。ゴリラズって、アコギの中にいきなり変なギターを入れたりとか。
村松:多いよね。
生形:ゴリラズって結局、ヒップホップと、ロックと、ポップスの融合じゃないですか。そういう気持ちで弾いた感じではありますね。
――納得ですね。精密かつ、肉体的なミクスチャーというか。
生形:ナッシングスの、俺が思う面白さって、どこか冷たい部分があるとか、精密な部分があるとか、そういうところだと思っていて、そこは無くそうと思っても無くなんないというか。ずっと出てきますね、どこかしら。

――生形さんのお気に入りとか、うまくいったなという曲は?
生形:俺は、「No Turning Back」。最近個人的に、ギターの音にめちゃくちゃこだわっていて、それがうまくいったなと思うのが「No Turning Back」のリフなんで。曲もすごい良くできたなと思ってるし、サビでリズムがハーフになるんですけど、ゆっくりになってない感じがするというか、メロディとかの兼ね合いで、ハーフになってもスピード感が失われないのが、すごくいいなあと思ってます。
――拓さんは?
村松:俺は、全部好きです。
――そこをなんとか(笑)。
村松:そうだなあ、「Beautiful Life」は好きですね、突き抜けてて。あとは「Deeper,Deeper」かな。1回しか出て来ないメロディがけっこうあって、そういう曲、すごい好きなんですよ。ほかにあんまりないと思うし、僕らのオリジナリティがすごい溢れてる曲だと感じます。
――そして、リリックについても、聞きたいんですけどね。拓さんが書いたのは――
村松:新しく書いたのは、「Flame」と、「We’re Still Dreaming」と、英語の曲2曲ですね。今回は、歌詞に悩みました。すごい時間かかっちゃって、メンバーに相談したりだとか。
生形:「Flame」とかね。
村松:「Flame」1曲だけで、3か月ぐらい書いてたんじゃないかな。歌のメロディに言葉をはめるのって、感覚の部分を僕は重要視してるんですけど、どんなふうにはめるのか、人によって感覚が違うんで、そこを生かして歌詞を書いてきたつもりだったんですね。英語っぽく聴こえる日本語の当て方って、あるじゃないですか。
生形:サザンオールスターズみたいなね。
村松:そういうの、僕は得意なんですけど、そこから脱却して、もっとストレートに歌詞を当ててみようという話が、メンバーともあったりして。それにチャレンジしてたんですけど、全然できなくて(笑)。「すごいわかりやすい歌詞が書けた」と思ってメンバーに投げても、あんまり反応がなくて、「あれ、おかしいな?」みたいなことを、3か月か4か月ぐらいやりましたね。何とか頑張って、いい形に収まったと思うんですけど。
生形:それは、俺ら二人の間でもそうだし、全員ともやってたしね。
村松:単純に、僕の感性と、一般的な感性とが違うんですよね。そこをなんとか、もっといろんな人に聴いてほしい思いがあったんで。要は、ひとりよがりの歌詞ではなくいろんな人に響く歌詞にしたくて、みんなに協力してもらって、時間をかけて書きましたということですね。みんなには迷惑かけちゃったけどいい曲になったし、たぶんこれから歌詞を書くのにもいいんじゃないかな?という経験でしたね。
生形:俺は今回、3曲かな。「Recall」「Beautiful Life」「Walk」の3曲。いつも2曲か3曲、歌詞を書くんですけど、今回は全部日本語か。
――「Beautiful Life」は大事な曲じゃないですか。メッセージ性のあるワードに、がつんと来ました。
生形:なんか、思ったよりも反応が良かったです。俺は、「Beautiful Life」がすごいポップな曲だなと思ってて、だからギターの音でめちゃくちゃ歪ませたりとか、ちょっと変なテイストを入れたんですけど、けっこうポップなのに、聴いてくれる側の人たちはみんなこういう曲好きなんだなって、ちょっと、考えをあらためた曲ですね。歌詞も含め、すごくわかりやすく書いたつもりなんですけど、「意外とみんな、こういうの、嫌じゃないんだな」って。
――それはつまり、ナッシングス的にはポップすぎるんじゃないか?という懸念があったと。
生形:と、俺は思ってました。
――そしたら、全然OKだった。
生形:たぶん(笑)。TOSHI-LOWさんがいい曲だって言ってくれたんで大丈夫(笑)。
――それは心強い意見です(笑)。「Beautiful Life」は祝祭感のある、歓喜の輪が出来る曲だなあと、ライブで聴いても思いました。3曲とも、前に進んで行くイメージが歌詞にあると思います。
生形:前から言ってるんですけど、あんまり書くことがないんですよ。ないというか、伝えたいことって何があんのかな?と思うと、自分が若い頃とか、今でもそうですけど、すごい後押しされた曲とかを思い浮かべるんですよね。そうすると、ほぼそういう曲になるので、そういうものを見直しながら考えますね。

――拓さん、歌詞を書く時に、昔から大事にしていることは?
村松:何ですかね? 今回は書き方を変えましたけど、やっぱり「正直に書くこと」じゃないですかね。あんまり取り繕わずに、気持ちの吐露というか、自分の等身大の言葉が出てくるように、というふうには思います。
――野音のMCで、「最近は、自分らのリアルを追求しつつ、みんなのことを思いながら(歌詞を)書いている気がする」と言ってましたよね。それって、最近になって生まれてきた感情ですか。
村松:それは、独立してからですね。環境が変わって、周りに人がいてくれてることのありがたさを本当に感じたし、やっぱりその中にお客さんのこともあったので。自分らとしては、現状維持をせずに変化し続けてきたつもりなんで、そんなにメジャーなこともしてこなかったんですね。ポップで、突き抜けていくようなもので、人に届くものであってほしいという思いはあるけど、やっぱり自分らの好きなことしかしてないから、それでも、そこについてきてくれるお客さんのことを思うようになったんですよ、独立してから。それで『By Your Side』というタイトルにしたりとか。
――ああそうか。そうですね。
村松:何て言うのか、自信過剰な言葉に取ってほしくはないんですけど、ロックスターに憧れて、若い頃に自分を形成してきたんで、僕らを今見てくれてる人たちにとっても、自分はそうでありたいというか。そういう気持ちが強くなってきたという意味もあります。
――納得です。最後に、『ANSWER』というアルバムタイトルは誰が?
村松:それは僕が。
――歌詞を読むと、「Answer」「答え」というワードが、あちこちに出てきますね。
村松:まさにそうで、歌詞に「答え」がよく出てくるということと、あとはさっき話したように、自分たちの環境がだいぶ変わった部分もあって。今だからこそ、バンドとしては一皮むけて先に進みたいなと強く思うし、このアルバムを作る時に、メンバーそれぞれにもそういう思いがあったと思うんです。歌詞を書くにしても、デモを作るにしても、ドラムを叩くにしても。それはスタッフもそうだと思うし。だから今この現状で一番良い答えというか、バンドとして出せる最善の答えがこれなんじゃないかな?と思って、『ANSWER』というタイトルにしました。……こんな深いこと言ってもね、そんなに伝わんないと思うんですけど(笑)。とにかく、聴いてほしいですね。
――強い言葉ですよね。
村松:ガツンと来ますよね。そこもなんか、いいかなと思って。これから始まる映画のタイトルとしては、いいっすよね。一本のストーリーとして。
――生形さん。作り終えて、「まだ先へ進めるぞ」と?
生形:そうですね。「いいアルバムできたな」って、毎回ですけど、今回も思います。最初に言った、ちゃんと新しいこともできてると思うし、今の音にもなれたかなと思うし、いっぱい聴いてほしいですね。本当に思うのは、たくさんの人に聴いてほしいよねということです。
取材・文=宮本英夫 撮影=森好弘


広告・取材掲載