
エリック・クラプトン
4年振りとなるエリック・クラプトンの来日公演が4月15日(土)に日本武道館にて開幕した。本記事では、初日公演の公式ライブレポートをお届けする。
2019年の春以来ちょうど4年ぶりとなるエリック・クラプトンの武道館公演がついにスタートした。3年にもわたって世界を翻弄しつづけたコロナ禍はまだ完全に終息してはいないものの、ようやく出口に近づいたことを実感できるこの時期に実現した、まさに待望の武道館公演である。今回の来日中に、クラプトンがロイヤル・アルバート・ホールとともに愛しつづけてきた日本武道館でのライヴの通算回数が100に到達することもあり(本人はあまり意識していないかもしれないが)、文字どおり満員のオーディエンスで埋まった八角形の空間には祝祭の空気が満ちていた。聞くところによると、冷たい雨にもかかわらず、かなり多くの人たちが開演数時間前から会場周辺に集まっていたという。
「間もなく開演」のアナウンスのすぐあと、客電が落ちると、大きな拍手と歓声のなか、クラプトンが、ファンにはもうすっかりおなじみの顔ぶれのミュージシャンたちとともに登場し、淡いクリーム色(オリンピック・ホワイト)のストラトキャスターを手にとる。そして、強烈なインパクトで最初の音を響かせた。「ブルー・レインボウ」とタイトルされたそのオープニング曲は、マイナーのインストゥルメンタルで、一つひとつのフレーズから、そして曲全体から、鎮魂、追悼、懐古といったイメージが伝わってくる。例によってまったく語られなかったため(そして筆者不勉強のため)、現時点では「おそらく未発表のオリジナル」としか紹介できないのだが、5月に予定されているジェフ・ベック追悼公演や次のスタジオ録音アルバムにもつながるものなのではないだろうか。指弾きであったことも、なにかを示唆しているかもしれない。
いずれにしても、オープニングにインストゥルメンタルを据えるという構成は、なんとも新鮮なものだった。かつてなかったことではないだろうか。そして、その完成度の高さと、とてつもない音圧、表現力の豊かさら、あらためてエリック・クラプトンという音楽家の凄さを実感させられた。また、美しいギターを抱えてステージ中央に立つその姿は、先月末に78回目の誕生日を迎えているというその年齢を、疑わせるほどのものだった。
ほぼソロ・パフォーマンスに近い形で「ブルー・レインボウ」を弾き終えると、そこからは、心から信頼するミュージシャンたちとのセッションを楽しむように、終始笑顔を浮かべながら、自身の代表曲やブルースの古典をつぎつぎと聞かせていった。ギターのドイル・ブラムホールⅡ、キーボードのクリス・ステイントンとポール・キャラックはそれぞれに密度の高いソロを聞かせ、ベースのネイザン・イーストと、前回来日時から常連となったドラムスのソニー・エモリー、そして、2人の女性シンガーがしっかりと彼らを支えていく。
まずは、1989年発表の『ジャーニーマン』から「プリテンディング」。ここ数年オープニングの定番となってきた曲で、力強いイントロのリフが、現在のクラプトン・バンドの充実ぶりを教えてくれる。つづいてデレク&ザ・ドミノスの名盤『レイラ』にも収められていた「キー・トゥ・ザ・ハイウェイ」と、「フーチー・クーチー・マン」。どちらも、クラプトンが長く、大切に、つねに敬意を払いながら歌い、弾きつづけてきたブルースの古典だ。
のっけから予想をはるかに上回るパフォーマンスの素晴らしさに耳を奪われていたため、ここでようやく気がついたのだが、今回のステージはじつにシンプルなもので、ピンスポットはほとんど使われず、全体がほぼ同じ明るさでオーディエンスの前に浮かび上がっている。これも、クラプトンのバンド意識、メンバーたちを大切にする気持ちを示すものといえるのではないだろうか。
「フーチー・クーチー・マン」を終えると、クラプトンがGmでレゲエのリズムを刻みはじめ、そこにネイザンが高音部で弾くアドリブで加わっていく。「アイ・ショット・ザ・シェリフ」だ。後半、鋭角的に切り込むような長いソロをたっぷりと聞かせてくれたクラプトンがストラトキャスターをマーティンに持ち替え、ここからは、アコースティック・セット。
椅子に腰を下ろすとクラプトンは、長い空白期間をへて日本に戻ってこられたことの喜びを語り、そして、武道館の音を賞賛する。「来日中に100回」と書いたが、現時点でロイヤル・アルバート・ホールは約200回であり、それがどれほど意味のある数字がわかっていただけるだろう。もちろん音だけではなく、そこに集うファンとの交流も含めて、ということである。
アコースティック・セットの1曲目は、ロバート・ジョンソンの「カインド・ハーティド・ウーマン」。弦の震えが目に見えるようなマーティンの繊細でしかも力強い音が武道館に響き渡る。その瞬間をクラプトン自身も楽しんでいるのだ。2曲目は、スタンダードの「ノーバティ・ノウズ・ユー・ホエン・ユー・アー・ダウン・アンド・アウト」。『レイラ』にはエレクトリック・バンドのヴァージョンで収められ、その後、『アンプラグド』であらためて注目されるようになった、あの曲だ。ここでは、クリス・ステイントンのピアノとポール・キャラックのハモンドも大きくフィーチュアされていく。
アコースティック・セット3曲目は、クラプトンにもっとも強い影響と刺激を与えた白人アーティストの一人で、ちょうど10年前に亡くなったJ.J.ケイルの「コール・ミー・ザ・ブリーズ」。クロスロード・ギター・フェスティヴァルに取り組むようになってからのクラプトンは、亡くなった友人たちへの想いをライヴでさり気なく表明することが多くなっているのだが、もちろんこの曲からも、その気持ちが伝わってきた。
つづいて歌われた「サム・ホール」もそういった曲の一つで、いわゆる義賊を歌ったこのトラディショナル・フォーク・ソングを彼は、2月にジェリー・ダグラス(ドブロ・ギターの名手)のコンサートに客演したとき、ジェフ・ベックへの追悼として演奏していた。武道館では「ニュー・ソング」と紹介していたので、これもまた、次のスタジオ録音アルバムにつながるものなのかもしれない。
軽くレゲエのリズムを導入した「ティアーズ・イン・ヘヴン」で、ポール・キャラックが、クラプトンの親友で昨年亡くなったゲイリー・ブルッカーの名曲「青い影」のあのフレーズを弾いていたことも忘れられない。
アコースティック・セットの最後は、『ロックダウン・セッションズ〜ザ・レディ・イン・ザ・バルコニー』にも収められたオリジナル・インストゥルメンタルの「ケリー」。長年ツアー・スタッフとして貢献し、2021年に亡くなったケリー・ルイスに捧げられた曲で、やはり、そこにいるべきであった人への深い想いが伝わってきた。
このあと、ふたたびオリンピック・ホワイトのストラトキャスターを手にしたクラプトンは、ジョージ・ハリスンと共作した「バッジ」で緩急自在のギターを堪能させてくれたあと、「ワンダフル・トゥナイト」をさらりと聞かせ、そして「クロスロード」、「リトル・クイーン・オブ・スペイズ」と、ロバート・ジョンソンの名曲をつづけて歌い、そのまま「レイラ」のイントロへと進んでいった。Cに転調してからの後半ではドイルにスライド・ギターを任せたものの、それ以外の重要なリフはほとんど自ら弾き(しかも力強く歌いながら)、圧倒的な存在感を示した。個人的には、まさに“jaw dropping”であった。
ソニー・エモリーのパワフルなドラムスに導かれて「レイラ」を終えると、全員がいったんステージ袖に向かい、再登場後のアンコールは、 2013年のクロスロード・フェス前後から定番になったジョー・コッカーの「ハイ・タイム・ウィ・ウェント」。優れたシンガー・ソングライターでもあるポール・キャラックがリード・ヴォーカルをとりながら、パフォーマンス全体を指揮していく。ファンにはもうおなじみの流れだと思うが、ここでもまた、メンバーを大切にしながら、一人のメンバーとしてステージに立つ時間を楽しむ姿が、印象に残った。
文=大友博
撮影=土居政則
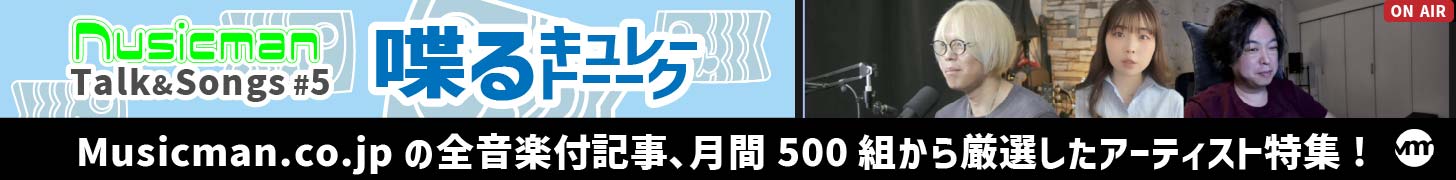

広告・取材掲載