
THE ORAL CIGARETTES 山中拓也(Vo.Gt)、中西雅哉(Dr) 撮影=ハヤシマコ
2023年、THE ORAL CIGARETTESはライブバンドとしての確固たる姿を見せつけてくれた。特に今年後半は『WANDER ABOUT 放浪 TOUR 2023』でライブ尽くしの日々。そんななか、10月25日にはデジタルシングル「YELLOW」をリリース。今作はバンド初のドラマタイアップとして、TVドラマ『マイホームヒーロー』の主題歌にも決定。楽曲はすでにツアーでも披露されているが、これからの彼らのライブで大きな存在感を放つであろう、愛しくも切ない壮大なバラード曲となっている。2024年のツアー予定も次々と決まり、ライブバンドとしてさらなるモチベーションを高めつつあるなか、山中拓也(Vo.Gt)と中西雅哉(Dr)にシングル曲や『WANDER ABOUT ABOUT 放浪 TOUR 2023』に込めた思い、さらに来年の対バンツアーや気になる次回作の気配についてもたっぷりと語ってもらった。
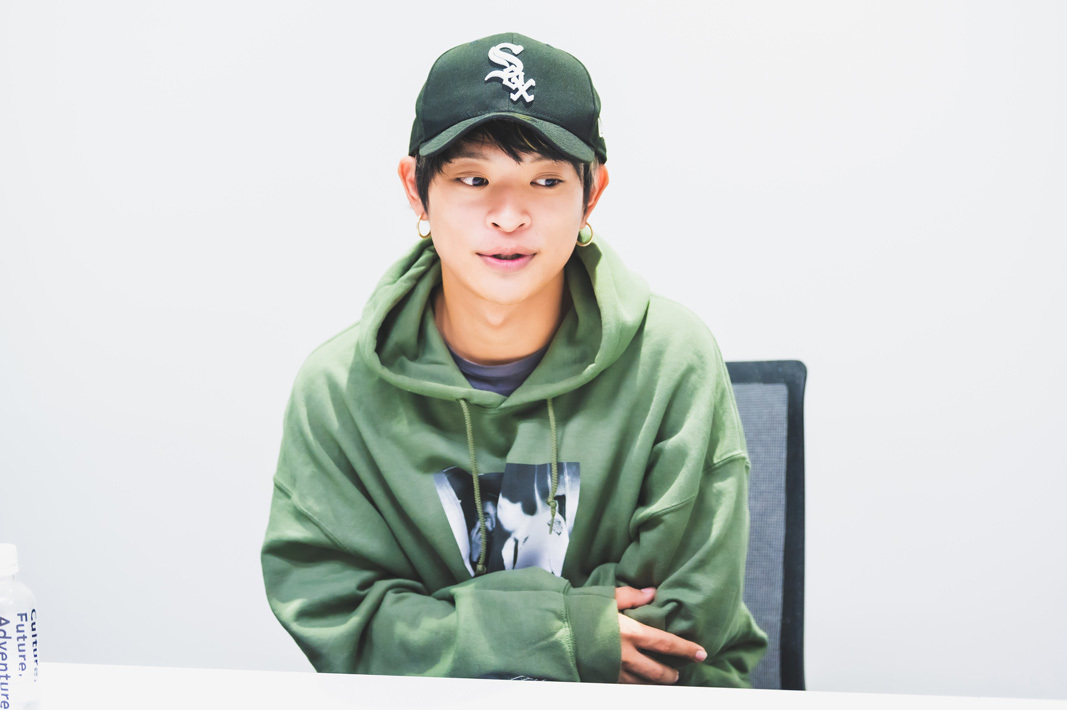
山中拓也(Vo.Gt)
ドームクラスでもライブハウスでもライブができるバンド、
両立できるカッコよさを目指したい
――2023年、THE ORAL CIGARETTESは目まぐるしいスケジュールでライブを展開していますよね。とくに『WANDER ABOUT ABOUT 放浪 TOUR 2023』は全国のライブハウスを細かく巡っていくツアーで。ツアーの合間に大阪でお会いできることに驚きました。
山中拓也(以下、山中):『WANDER ABOUT 放浪 TOUR 2023』(以下、『放浪ツアー』)のツアーでは北海道や九州をがばっと回ってきて。大阪にもイベントなんかでちょこちょこ来てはいたんですけど、すごく久しぶりですね。
――つい先日には九州のツアーを回り終わったばかり。本当に『放浪』という名前がぴったりの過密スケジュールで。
中西雅哉(以下、中西):ほんとに放浪でしたね(笑)。つい一昨日に九州、沖縄でのツアーが終わったばかりで。
――今回のツアースケジュールを見たときは本当に驚きました。地方のライブハウスをくまなく巡る、そのキッカケは何だったんでしょうか。
山中:やっぱりコロナ禍ですよね。友達のライブハウスの店長が苦しんでいる姿も見てきたし、ライブハウスそのものがいくつも潰れたという話を聞いて。ライブハウスの活気を取り戻したいというのが最初のキッカケです。
――ライブバンドならではの想いですよね。それでもやっぱり気になるというか、ツッコミを入れたいのがそのキャパです。最もミニマムな会場で約180人。しかもそれが福岡というそれなりに大きな都市。すでにアリーナクラスの会場を埋めてきたTHE ORAL CIGARETTESからすると、かなりの冒険ですよね。
山中:そうですね。その180人のキャパは「LIVE HOUSE Queblick」という福岡のライブハウスで、昔から店長に可愛がってもらってて。最初はZepp Fukuokaだけスケジュールに入れていたんですけど、どうしても外したくないってチームにワガママを言って。
――Zepp Fukuokaは約2000人入る会場なのでギャップがすごいですよね。200人前後のキャパでのライブは、ここ数年ではあまり機会はなかったのではないでしょうか?
山中:そうですね。コロナ禍でお客さんとの距離も離れていたし、俺らもコロナ禍以前にはバンドの規模感を意識していたこともあって、アリーナクラスの会場でライブをする回数が増えて。お客さんとの物理的な距離感がどんどん大きくなっていたんですよね。でも、今回のツアーでお客さんの温度感というか「やっぱりこれやったんや」と、直に体感できる瞬間がライブハウスにはすごく多くて。ライブをしている実感や熱量もとにかくすごいんですよ。

中西雅哉(Dr)
――今回の『放浪ツアー』ではバンドの機材もメンバー自身で運搬、セッティングしているんですよね。
中西:現実的に考えると、この規模のツアーでライブハウスを回るということはこういうことだよと、マネージャーからリアルな数字の話をされてて。
――いわゆる大人の事情ですね。
中西:そうです(笑)。でも、俺らの覚悟の上だし元々インディーズ時代にやっていたことではあったので。デビューしてからは楽器にしろ音響にしろ、プロの方たちが周りについてくれるようになったことで学んできたこともある。インディーズのスタイルに戻ったときに、自分たちでできることが増えていることも楽しくて。チームの楽器テックさんといろんなことを試しながらやっていくことも楽しかったですね。ツアーはバンドにとって成長していく場所でもある。それがライブの現場以外、オフのときでさえもスタッフとメンバーの関係性がツアーを追うごとに成長してて。「ツアーしてるな」という感覚が今まで以上にありましたね。
――ドラムはアリーナクラスとライブハウスの違いはもちろん、会場ごとに音の響きなど微調整がすごく多いですよね。
中西:今回はメンバー全員が普段の楽器機材とは別に、小箱用の機材を準備したんですよ。普段の僕のドラムはすごく大きいので、それもかなりミニマムにして。それでも、キャパが180人くらいの会場だと「それでもデカイよ」とか言われちゃったんですけど(笑)。「それが必要最低限なんです!」とか、やり取りも自分たちでして。『放浪ツアー』前には、この機材じゃないとダメだっていう考えになりつつあったんですけど、最低限の機材でも演奏ができるメンタルとか対応力も鍛えられてよかったですね。
――自分自身に余裕を作れるツアーでもあったんですね。
中西:アリーナクラスのステージに戻ったときでも、そういった経験が活きてくるんじゃないかなという感じますね。

――『放浪ツアー』ではフロントアクトを入れてのツアーを展開していましたよね。
山中:コロナ禍をキッカケに、ヒップホップシーンがすごく盛り上がったイメージがあったんですよね。周りの友達もヒップホップばっかり聴いてて、ロックシーンがどんどん衰退していく感じがあって。俺、よくライブハウスにお客さんとして遊びに行ったりするんですよね。そこでお客さんが4、5人しかおらんのに、「こんなカッコイイバンドいんのにな~」とか、良いバンドを発見することもかなり増えてて。でも、このまま盛り上がらない、この子たちが最前線のシーンに出られないのはすごく悔しくて。俺らも全然名前が出てない頃からSiMとかHEY SMITHとかが俺らのことをフックアップしてくれて。自分たちがそれをやる世代になってきたのかなという思いもあったんです。それでライブハウスに観に行って、その場で声かけて。相手からは「いいんすか!?」みたいな感じで言われたりして(笑)
――いきなり拓也さんがライブハウスにきて、一緒にツアー回ろうって声を掛けられるなんて若手バンドマンからしたら驚きでしかないですよ(笑)。
山中:そういう関係性を今から作る。俺ら自身が俺らのファミリーみたいなものを作っていくことは、俺ら自身の心も豊かになっていくんちゃうかなと。それで若手バンドマンみんなとツアーを回ることにしたんです。
――アリーナクラスでライブができるようになった今、バンドとしてさらに成長するためにどうすべきか。試行錯誤することもあるのではないでしょうか。
山中:実際、その悩みにはブチ当たっていて。ドームという次の目標はもちろんあります。そこに向けて、ドームクラスでもライブハウスでもライブができるバンド、両立できるカッコよさを目指したいとは思うんです。でも、規模感を優先してしまうことで、バンドのスタイルが変わったりとか、ダサいことをやってしまうのだけは絶対に嫌で。もっと自分たちがやりたいことを突き詰めて。その結果、ドームでのライブができたら万々歳。でも今はそれよりも先に、ロックシーンで爪痕を残すことのほうが自分たちのスタイルに合ってるんじゃないかなと思いますね。バンドが成長するためにどうするかを悩んだ結果、振りきれた感覚がある。よりやりたいことができるようになった気がしますね。
――中西さんはバンドに加入して、今年で10年。バンドが成長するスピード感はどう感じていますか。
中西:メジャーの世界を知る前は、華やかなイメージもあったんですよ。でも実際に自分たちがそこに足を踏み入れたら、そんなたやすい世界でもなくて。メジャーデビューってスタートなんですよね。最初のワンマンツアーは売り切れるか売り切れへんかというのを必死にやっていたし、目の前のものを地道に、着実にクリアしていって辿り着いた結果がアリーナツアーとかで。浮足だった感じも全くなかったし、THE ORAL CIGARETTESはずっと地に足をつけてやってきている感じがずっとあったので。頭のどっかで、いつかバンドはレーベルや事務所から切られるよというような話も先輩から聞いてきてたし、どこかで疑っている部分も多少はあって。もしそうなった時は4人だけでも活動できるようにせなあかんなというのはずっと頭の片隅に意識はしてて。そういう思いがメンバーみんなにあったからこそ、道を踏み外さずにちゃんとここまで来れたというのは感じてますね。周りからはすごい速さでアリーナ行ったなと言われたけど、僕らとしては全然早いとも感じてなくて。
さまざまな伝え方を持って生まれたシングル「YELLOW」

――積み重ねてきたものがあるからこその結果ですよね。バンドがさらなるステップアップを期待されるなか、今回新しいシングル「YELLOW」がリリースされました。今作はどのタイミングで制作されたんでしょうか。
山中:『放浪ツアー』の前ですね。
――今回は初のドラマタイアップで、『マイホームヒーロー』という作品はマンガが原作です。私も漫画のほうをずっと読んでいたんですけど……、実写にしても大丈夫なのかと心配になるほどの内容で……。
山中:俺も全く同じこと思ってました(笑)。
――ですよね(笑)。タイアップの話が来たときはいかがでしたか? メンバー全員がタイアップの話が来る前からこの作品を知っていたんですよね?
山中:好きな作品やったから楽曲を担当するプレッシャーみたいなものはすごくあったし、中途半端なものを出されへんという気持ちもめちゃくちゃあって。絶対に外さないためにも、曲作りをするなかで何回も監督の青山貴洋さんとの打ち合わせを重ねて。
――これまでにもアニメ作品のタイアップなどはいくつかありましたが、今回の楽曲制作ではこれまでと違う試みなどはありましたか?
山中:違った点でいうと、この作品自体がいろんな伝え方を持っているんですよね。1の伝え方、2の伝え方、3の伝え方、受け手によって捉え方が変わってくる作品だなというのをすごく感じてて。いつもなら、この作品はこういう曲だろというのを俺らのなかで決めて、1曲だけを投げるやり方をしていたんです。でも今回は3パターンぐらい方向性の違う楽曲を提出して。そこから監督に選んでもらう方法を取ったんです。
――複数パターンを作ろうというのはメンバー内で話し合って?
山中:それは俺の判断だったんです。自分でもちょっとわからない部分があったんですよね。狂気性を表現していくのが正解なのか、そこの裏にある愛情みたいなものを表現していくのが正解なのか。それだけでも楽曲のジャンルが変わるから監督の意見を聞いて。監督の中で流れている楽曲ってどのイメージなんやろうと、結構ディスカッションしましたね。
――これまでのアニメ作品のタイアップだと、作品の始まりや終わりに楽曲が流れるものがほとんどですよね。でも、ドラマ作品だとシーンの合間に流れたりすることもあるじゃないですか。そういう楽曲の使われ方をイメージしたりしましたか?
山中:そうですね。だから別パターンとかも作ったんですよ。「YELLOW」の楽曲パターンで、弾き語りから入るとか、するっと音だけで声がないものから入るパターンとかも一緒に使って。それをドラマ制作の方たちに好きに使っていただくようにしてて。おっしゃっていただいた通り、楽曲が入ってくるタイミングだったりはすごく大事だったので、まさやん(中西)もわざわざもらった動画資料に音ハメして。こんな感じになるよと動画を送ってくれたりして。
――中西さんはドラマ制作の方ですか?(笑)
中西:ハハハ(笑)。僕、動画編集が好きでよくやってるんですよ。だから監督と打ち合わせをしたときに、1話目のこのシーンの何秒目から流したいんですという話をもらってて。
――楽曲を使うシーンについても、青山監督からかなり細かく話があったんですね。
中西:その後のストーリーではいろんな使い方をしていくと思うんですけど、「1話目のここが一番大事なので」という話を聞いてたんですよ。そのシーンで曲が流れて、出演者の人たちのセリフもそこからまだまだ続いていく。これはどういう風に楽曲が聴こえるんやろうなと悩んで。僕たちは歌が作品やけど、ドラマとしては映像が作品になる。それの邪魔はせんようにと視覚的にも考えたりしましたね。

――今までにない楽曲の作り方ですよね。3パターンの楽曲を制作したとのことですが、今回バラード曲の「YELLOW」を選んだのは青山監督の存在が大きいですか?
山中:そうですね。超ロックチューンな狂気じみたガチガチの曲も送ったりはしてたんですよ。でも、監督の意見としては狂気性もあるけど、その中にある愛みたいなものが最終的に伝えたいテーマだという話を聞いて。そういうテーマに沿って書いてみますと出来たのが「YELLOW」で。
中西:最初にあげてきたデモのメロが良すぎたんですよ。良い楽曲というか、「THE ORAL CIGARETTESらしい」というのは実は自分たちでもはっきりと答えが分かっていない部分もあって。周りから「THE ORAL CIGARETTESってこうだよね」と言われて、僕たちはそう捉えてもらえるんやと参考にはなるんですけど。自分たちの楽曲がドラマで使われて、なおかつ監督の意見もあるなかで、自分のなかではこういう感じで拓也は攻めてくるかなというのはある程度想像はするんです。でも、やっぱり毎回そこを超えてくる。ここはちょっと~とかはなくて、これでいったら絶対大丈夫でしょ!というメロが出てきてたんですよね。
――お互いに絶大な信頼感がありますよね。「YELLOW」のメロはそれこそTHE ORAL CIGARETTESらしいなと感じました。
山中:そう言ってもらえたら嬉しいですね。
――そのメロディに対して、ビートやリズムをどうするか。ドラマのイメージもあるし、いつも以上に悩んだのではないでしょうか。
山中:すごい紆余曲折があって。最初はパソコンのDTM上で作っていくなかである程度のメロや空気感、雰囲気は掴めたんですけど、最終的にここまでのエモーショナルさが欲しいというハードルを越えるのがめちゃくちゃ高くて。ある程度想像はできちゃったんですよね。これくらいにはなるだろうと。でも、実際に作業を進めるとそこまで到達させることがなかなかできなくて苦しくなって。で、メンバーに連絡をいれて、ここまで完成させたけど、ここから先がだいぶ行き詰まってるから、いっぺんスタジオに入って、みんなが出してくれる生音を浴びてから次の構成を考えたいと伝えて。で、音を鳴らし始めた瞬間に、DTMでやってた感じとは全く違う感覚が降りてきて。やっぱりメンバーの音を聴いて作ったら、自分が想像しなかったものが生まれるんだなと。そこから完成まではすごく早かったですね。
――メンバー4人で音を合わせたらしっくりくる。いつだってライブを重要視してきたバンドだからこその感覚ですよね。『放浪ツアー』の前にその感覚を体感すると、そこからライブに懸けるバンドのテンションにも変化が起きそうですよね。「YELLOW」はすでにライブでも披露されているんですよね。
山中:『放浪ツアー』の1か所目から披露していますね。
――お客さんの反応はどうですか。
中西:『放浪ツアー』の北海道編はまだリリース前だったので、みんな会場で初めて耳にして。THE ORAL CIGARETTESのファンって、拓也のメッセージ性もそうだけど、バンドが発信するものを出来るだけ鮮明に受け取ろうとしてくれるファンが多いんですよ。初めて披露したときの「この記憶を忘れない!」みたいな姿勢もすごくて。リリースされてからも一緒に歌ってくれる人も出てきたりして。ライブで一緒に作っていく曲になるんかなとすごく感じますね。

――今作は歌詞もすごく印象的ですよね。作曲同様、『マイホームヒーロー』の影響はありましたか?
山中:サビの歌詞だけ先行して作っていたんですよ。俺らはライブハウスで、ライブでこの楽曲を披露する意味をどうしても考えてしまうので、『マイホームヒーロー』の主題歌ではあるけれども、曲の中でどういう風にして今の自分たちのメッセージをファンに伝えることができるのかというのをすごく考えて。
――タイトルの「YELLOW」という言葉も印象的ですよね。THE ORAL CIGARETTESのイメージは黒、赤とかくっきりとしたカラーのイメージがあって。黄色は暖色系カラーでもあり、信号機の警告を思わせる色でもある。このタイトルはすぐに思いついたものでしたか?
山中:そうですね。最初、監督と『マイホームヒーロー』で何を伝えたいのかディスカッションをしていたときに、狂気性とその裏にある愛をどうしても伝えたいと聞いて。いつもなら自分でゼロから曲を作るけど、すでに「1」がある状態。そこに自分たちがファンのみんなに何かを伝えることができるか、『マイホームヒーロー』という作品を観る人にもメッセージが残せるのかをまずは考えようと思って。そこで思いついたのが「YELLOW」だったんです。いつもなら曲のタイトルは後付けすることが多いんですよ。
――これまでの取材でも後付けするとお話されていましたね。
山中:今回に関しては「YELLOW」でいこうと決めた状態で進めていきましたね。
――その歌詞を歌う声もこれまでとは印象が違いました。これまでのバラード曲だと、少し低くて甘い音域で歌うものが多いように感じましたが、今作は突き抜けるような歌声が新鮮で。
山中:良い意味でも悪い意味でも、邪魔しちゃう可能性があると思ったのは本音で。ドラマのシーンで流れたときに、声の癖がすごすぎるかもと考えて作っていたんです。でも、楽曲ができたときに、そういう声を出さなくてもいいんじゃないかと単純に思えたのと、最近作ってきた楽曲のなかで自分の声質を試す機会がいっぱいあったんですよね。例えば「BUG」なら、サビとAメロはさらっとやってみようとか。アルバム『Kisses and Kills』くらいまでは自分の歌い方はコレや!と、一貫してどの曲にもその歌い方を当てはめていたんですけど、それ以降はいろんな歌い方をして、その場その場で表現していくことが自分の中ですごくしっくりときてて。今回はマイクも今までのレコーディングの中で一番たくさん種類を試したんですよ。このマイクはここの音域がうるさいから変えようとか、声質だけじゃなく、ボーカルの音がどう乗っているか、今まで以上に考えて作った気がしますね。
――ドラムで意識することや、これまでと違う変化はありましたか?
中西:デモの段階でのメロがすごく良かったし、スタジオでのセッションも経ての流れだったので、楽曲が完成した時に今までにないくらいに自然体でドラムが作れたなっていうのは感じましたね。以前までは、ベースとギターの面白い絡みに対してどうアプローチするかを考えながら作ったりすることも多かったんですけど、今回は拓也もデモの段階でこういうビートで、というイメージもあったからより明確に、崩すことなく作れましたね。振り返れば、とてもスムーズにできたし、今回のツアーで演奏しててもそれはすごくストレートに感じましたね。
ライブバンドである意識がより高く持てた1年。
来年はリスペクトを込めた対バンツアーへ

――『放浪ツアー』は来年5月まで一旦お休みで、これから年末のフェスシーズンが到来します。小さなライブハウスから、次は大きな会場でのステージが待っています。
山中:テンション的には延長戦でしかなくて。この何か月かずっとライブをしてきたことで自信にも繋がったし、自分たちはもちろん、お客さんも納得してくれるライブができるんやろうなと思ってて。『放浪ツアー』でテンションを上げさせてもらって、12月はより大きな会場でフェスに出演する。小さな会場でやっていた空気感を大きい会場に持っていけるか。逆に楽しみですよね。
――ライブバンドとして無敵なイメージがありますね。
山中:逆だと思ってたんですよ。大きい会場でやれるから、小さい会場でもすごく余裕をもってやれると思ってた。でも、今回のツアーをやったことで気付けた部分もいっぱいあって。『放浪ツアー』がなかったらこの感覚には多分気づけなかったし、その行き来はすごく大切なことだなって思いますね。
――コロナ禍を経て、2023年はどのバンドも反動のようにものすごい数のライブ本数を重ねていますが、THE ORAL CIGARETTESは軍を抜いて多いですよね。
山中:マジでここ最近は2日に1回はライブをするペースで動いてましたね(笑)。
中西:むしろ、昔はこんなにやってたっけ?というくらい(笑)。
山中:メンタルと体もめっちゃ強くなったし。マサヤンと2人、ボーカルとドラムが特に大変なんですよね。マサヤンはヘルニアになってしまって、その状態でどこまで戦えるかという状況が続いてたし、俺もリハで全然声出ないなとなる日もあって。でも、夜になったら「イケるやろ!」というテンションが続く、その繰り返しで。そこで鍛えられたメンタルもありますね。昔やったらもうライブやりたくないと凹んで、スタッフに迷惑をかけていただろうなと。今はそんなに喰らうことがない。「絶対になんとかなる!」というメンタルが持てるようになりましたね。
――それはメンバー同士でも感じていますか?
中西:変に背負いすぎないようになりましたね。ライブでの演奏に関しては、メンバーそれぞれの個人戦でもあるんですよ。昔やったら「自分が頑張らないと!」というのがあったけど、いまは誰かが不調でも他のメンバーが頑張ろうぜっていう気持ちになってきてる。今日のオレは絶好調!誰かがトラブっても大丈夫!ていうのをステージ上でお互いに見合いながら演奏できる余裕が昔よりもあって。頼ったり頼られたり、メンタルにも余裕ができましたよね。
――2023年はライブバンドとして確固たる意志を持てた一年だったんじゃないでしょうか。
山中:バンドマン、ライブハウスの人間だということを再認識した一年でしたね。アンダーグラウンドとかオーバーグラウンドみたいな言い方は難しいけど、俺らはお茶の間層に届いている人たちとも一緒にライブをするし、そうではない人たちともライブをする。要は架け橋のような役割をしようと昔は思っていて。今もその気持ちはあるけど、それよりも今は自分たちがお世話になっているフェスシーン、ロックシーンを盛り上げたい。テレビには映らない、こういう世界があるんだよというのを示したい。そのシーンで存在感を突き詰めていこうとする1年を過ごしたなと思っていて。このシーンでしか感じられないロックの魂みたいなもの。学生時代にDragon AshやRIZEをライブハウスで観ていた時に感じていたものをもう一度思い出した感覚もあって。10-FEETやマキシマムザホルモンとか、先輩たちを改めてリスペクトもできて。バンドマンであること、ライブバンドである意識がより高く持てた1年だったなと感じますね。
中西:振り返れば、僕たちはコロナ禍前に過去最大のアリーナツアーを予定していて。それがなくなってしまって……。拓也の中ではそのツアーの後、次のビジョンも見えていて。それが道筋通りにいかなくなったこの2、3年があるんですよ。でも、振り返ると結局それが良かったのかなというように今となっては思える。この1年が特にそれを感じさせてくれたんです。『放浪ツアー』でもすごく大きなもの得られたし。まだこのツアーは来年も続いていくんですけど、来年、再来年とライブに向けてのバンドのスタンスとか、目標への向き合い方がすごく広がった。ファンに対しても、バンドが提示していくものに対して信頼感みたいなものが伝わったんじゃないのかな。より安心して自分たちのやりたいことをやっていける、そう感じる1年でしたね。

――その1年を締めくくるライブ、関西では毎年恒例となっているFM802が主催する『RADIO CRAZY』(以下、『レディクレ』)への出演が決まっています。
山中:今年はその後に東京でのイベントが決まっているんですけど、毎年レディクレで一年のライブを締めて実家に帰るのが定番だったんですよね(笑)。レディクレが一年の締め、今年一年もお疲れ様でした~という感覚が強くって。イベントの現場に行っても、FM802はもうホームみたいな感じ。家族みたいなスタッフの人たちがいてくれて、お客さんも「レディクレでオーラルは締めでしょ」みたいに思ってくれている人もいて。みんな一年頑張った、そのお疲れ様会みたいな感じで。
――イベントのテーマである「ロック大忘年会」、その言葉通りですよね。来年は対バンでのZeppツアーが決まっています。そのお相手はどうやらこれまでとは違う、先輩アーティストが出演するということですが。相手が誰なのか、めちゃくちゃ気になります!
山中:ですよね(笑)。交わっているようで、実は交わっていなかった人たちを呼びたいなと思っていて。俺らの青春時代にめちゃくちゃ聴いてきた、すごくリスペクトしている人たちです。対バン相手の1人にキッカケとなってくれた人がいるんですけど、自分たちにとってもエモいツアーになるだろうなと思っています。同時に開催するファンクラブツアーもかなり久々なので、めちゃくちゃ楽しみです。
――『放浪ツアー』でライブバンドとして自信をつけてきた今、また大きなステップアップになりそうですね。先輩アーティストとの対バンは緊張感もありそうですが。
山中:30歳も超えると緊張感はさほどないんですよ。でもこのツアーでは違う意味での緊張感があるというか……。俺たちの先輩バンドへのリスペクトが、そのバンドのファンのみなさんに伝わってほしくて。きっと俺らのファンと、そのバンドのファンは客層が全く違ってくると思うんですよ。でも、俺らはやっぱりファンファーストでありたいから、いつも通りのライブをする。それを「うわ~若いバンドやなぁ」と変に思われないか。「リスペクトの気持ちを持ってこのライブをやっています!」という思いが伝わったらいいなと。そういう緊張感のほうが大きくって。
――音楽に対しての想いがしっかりとあれば心配はなさそうですが。
中西:どのへんまでの先輩かにもよるんですよ(笑)。攻め具合もこのレベルまでなら大丈夫!という先輩と、どのレベルまで行っていいんでしょうか?と伺いをたてたくなる先輩もいる。これまで、そういうステージを経験してないんですよね。フェスの楽屋で話すのと、対バンでライブをするのとでは全く違う。そこはもう先輩のライブを観て、どう攻めるかを決めるしかないなと。
――今回はTHE ORAL CIGARETTESが主催ですからね。勝ち負けではないけど、自分たちのファンはもちろん、先輩アーティスト、そしてそのファンにも自分たちの本気を見せないといけない。どんなステージになるのか楽しみですね。シングルのリリース、ライブツアーと続くと、そろそろ来年にはアルバムも……と、期待しちゃうんですが。
山中:そうなりますよね(笑)。
――アルバムは前作『SUCK MY WORLD』が2020年の発表です。
中西:もう3年半経ちますか。
――そろそろかなと。
山中:考えてますやん(笑)
――ですよね(笑)。ファンのみんなはその情報を待っていますよ。
山中:その情報を待ってくれている人は、絶対にZeppツアーに来たほうがいいです!
――「番狂わせ」が期待できそうなコメントですね。
山中:「マジか!」ってなると思いますよ。
――年末のイベント、そしてZeppツアー、『放浪ツアー』と楽しみが尽きないですね。
中西:期待してもらえたら!

取材・文=黒田奈保子 撮影=ハヤシマコ


広告・取材掲載