
PERSONZ
40年というとてつもない時間を超え、今もなお前進を続けるバンドの生命力が激しくほとばしる。結成40年のアニバーサリーイヤーに、PERSONZが9年ぶりにリリースするニューアルバム『40th FLOWERS』。1月から連続配信されてきた「FLOWER OF LOVE」「DEAR YOU」「EVERY DAY IS A NEW DAY」「SING ALONG FOREVER」を含む全10曲は、懐かしさと新しさをミックスしたPERSONZの最高到達地点だ。6月からは全国9ヵ所をめぐるツアーも始まる。「PERSONZはライブが完成形」(藤田勉)という、40年目の回答を確かめる時は今だ。
――振り返ると、30周年から40周年の10年間は、どんな10年でしたか。
藤田勉(Dr):30周年で武道館をやったあと、ちょっと気持ちが落ち着いちゃった部分もあったんですけど、コロナ前ぐらいから、バンドとしてのライブが、ものすごく急カーブで良くなっていく実感を得ることが多くなったんですよね。特に何があったというわけではないんだけども、ライブに関するモチベーションがどんどん高まっていって、それはコロナ明けがやっぱり如実ですよね。やるたびに“最新ライブが最強!”みたいな感じでやれているので。お客さんとの一体感という意味でも高まる一方なので、もう今から次のツアーが楽しみでしょうがない、そういう感じがずっと続いています。
本田毅(Gt):今回のアルバムを作り始めたのは、去年ぐらいから始まっているんですけど、レコーディング、ライブ、レコーディングと、40周年に向かってどんどん上がっていく感じが、懐かしいなと思いました。忙しさがいい刺激になっているし、コロナ以降は特に、1本1本のライブがすごく大事だなということを、前よりも思うようになりましたね。そう思う気持ちで臨むので、自然といいものになっていると思うし、そういうふうに思ってやれるようになったことが、大きな違いかなと思います。なので、次もすごく楽しみです。

JILL(Vo)
――そしてついに、9年ぶりのオリジナルアルバムのリリースが、6月19日に決まりました。タイトルは『40th FLOWERS』です。
JILL(Vo): 40周年を言葉で言わなくちゃならないときに、何か象徴が欲しいと思って、“花”というキーワードが出てきたんです。これまでに花を一つ一つ咲かせてきて、40年目の花はどんな花になりますか?ということですね。コロナ後のライブで、お客さんがあれだけはじけてくれるのは、こちらから見ていると本当に大きな花束を見ているみたいなものだから、みんなで祝いましょうという意味も込めて。ただ、曲に関しては、今までとは全然違う作り方をしているんですよ。さぁ、説明は誰が?
藤田:渡邉さんどうぞ。
渡邉貢(Ba):いつもは僕が簡単なデモテープを作って、それをJILLさんに聴いてもらって、歌詞ができたところでみなさんにも聴いてもらって、各々が自分のパートのアレンジをする形でやってきたんですけど。今回は曲作りの段階で、和音とメロディだけで作って、それを藤田くんに渡して、リズムトラックをまず入れてもらう。だから、どういうビートになって返って来るかがわからない。返って来るプロセスで、“この曲のBメロはもっとシンプルにしたほうがいい”とか、アドバイスをもらって、今までは一切そういうことは聞かなかったんですけども、今回は藤田くんの言うことを全部聞いてみようと思って、言われた通りに直して、また渡す、そういうキャッチボールをしました。そこでOKが出たところで、僕がベースを弾いて、JILLさんに聴いてもらう。JILLさんが大丈夫と言ったら、本田さんに渡してギターを入れてもらう。
藤田:僕はプログラミングでドラムを作ったんですけど、ほぼドラムに関してはその時点で完パケです。曲の世界観の土台を任された感じでしたね。
――新しいやり方ですね。どうでした? やってみて。
藤田:面白いです。ただ、最初の一筆を書き始めるまでがけっこう悩むというか、和音とメロディだけのデモを聴きながら、自分の部屋の練習用のドラムで叩きながら、ああでもないこうでもないって、煮詰めていくような作業ですね。
――今回そうしてみようと思ったのは、何か理由があったんですか。
渡邉:基本的なやり方は変わったわけではないんですけど、順番を変えたというか。要は、僕の作るデモテープは、よく言えばシンプル、悪く言えばいい加減にできているので(笑)。JILLさんに聴かせる前のイメージとして、もう少し完成に近づいている状態で聴いてもらったらどうなるんだろう?と。
藤田:という実験だよね。今回は。
JILL:でも、ギターがないからね。どういうこと?みたいな(笑)。
渡邉:でもね、音楽はだいたい、8割方はリズムですから。僕はそう思っているので、ドラムがちゃんとした状態である曲と、ない曲では、全然イメージが変わると思うんですよ。そういう実験ですね。
JILL:面白かったよね。昔からやっている、みんなでスタジオに入って一緒に作ってという、オーソドックスなやり方ではないので。だから手順もいいだろうし、無駄な時間がない。藤田さんは藤田さんで、普通にドラムを叩いているのではないけど、たぶん聴いた人は誰もわかんないと思う。“これ、生じゃないんだよ”と言っても絶対わかんない。これは、書くか書かないかはお任せしますけど。信じるか信じないか、みたいな(笑)。
――それはあなた次第(笑)。
JILL:そこをあえて説明するのもアレだけど、それを体験するのは、今度はライブになるわけだから。でもこのやり方ができるのは、うちのバンドだけじゃないでしょうか?とは思います。藤田さんがちょっとおかしい。できるのがおかしい(笑)。
藤田:でもね、前から打ち込みの曲はわりと多いので、そういう作業はよくやってきたんですよ。
JILL:タイミングも、普通にドラムを叩いているのと同じに聴こえるからね。
藤田:そこはね、作り方の秘訣があるんです。
JILL:ライブでは、歌いながらリズムのセンテンスを体で表現するから、ベーシックなリズムがちゃんとしていれば、見えやすいというのは確かにわかります。普通だったら、現存で40年やっているバンドだったら、“スタジオ入ります。じゃあこういう曲で”とか、やっていくんだろうけど、そうでないのが今回は面白かったですね。しかも今は、やり取りもオンラインでできちゃうから。
――環境の変化も大きいですよね。
JILL:昔は、集まらないとできないからね。スタジオを借りて、ちゃんと全員で確認しながらというのは、ある意味では時間がかかるし。
渡邉:でもそういう経験があったから、今は安心して任せられるということですね。
JILL:ただ、最終的にはライブで表現しなきゃいけないからね。それは肉体でやるわけだから。
藤田:だから、プログラミングで作っているところは、自分の中で引っかかりはなくはないですけど。ただ昔から、生でレコーディングしていた時代から、結局PERSONZはライブが完成形だと思っているので。レコーディングされた音源はもちろんかっこいいですけども、ライブで表現することが、その曲の完成だと思ってやっていますので。

本田毅(Gt)
――その通りだと思います。本田さんは、今回の新たな制作方法をどんなふうに感じていますか。
本田:ドラムがどういう録られ方をしていたとしても、僕は僕のグルーヴで、“PERSONZはこうだろうな”というイメージのグルーヴがあるので、それで録っているんですね。たとえば、シンコペーションしていないところで、僕だけシンコペしたりとか。誰かに合わせるのではなく、ちょっとずらすということは前からしていて、それがスピード感になったりするんですね。
藤田:それ、今回のレコーディングですごく感じたの。僕がドラムを作って提出した時点では、ウワモノはまったく未知なわけですよ。それで完パケになったものを聴くと、自分が思っているアクセントに誰も乗っかってこない(笑)。
JILL:あははは。
藤田:でもね、よく考えると前から、なきにしもあらずだなと思ったんですけど、それによって厚みが出るんですね。みんなが同じ点に向かって行くと、合わせても、点で終わっちゃうんですよね。“全然合ってないんじゃないの?”というほうが意外と、スリーピースなのにすごい厚みが出てくる。
渡邉:いや、藤田くんのアクセントのある場所がおかしいんですよ、そもそも。二人は、ちゃんとしたところにアクセントを入れているだけ(笑)。
藤田:あれ?(笑) やっぱりこれはね、80年代のニューウェーブとかを聴いた人間は、こうなっちゃうんですよ。当たり前のところには、どうしても入れたくない。そういうところがあるんですよ。
渡邉:昔からそうだよね。ベースと、ドラムのキックのタイミングを合わせないとか、わざとやっていて、それが厚みですね。
JILL:もともとPERSONZのリズムは、普通にエイトビートですとか、そういうものとはちょっと違うので。そこに本田さんの、エフェクティブなギターが乗っかってくるのが、うちの醍醐味なんだろうとは思います。
――PERSONZサウンドの秘伝のタレみたいなものが、わかったような気がします。JILLさん、歌詞の話ですけど、配信曲を先に書いて、アルバム曲も書いて、かなり長い時間をかけて書いていったと思うんですけど、どんなことを思った時間でしたか。
JILL:アルバムというのは、あるところで曲が出揃って、(歌詞を)一気に書くことが多かったんですけど、今回は1曲1曲だから、半年ぐらいかかっていて、そこに至るまでの自分の心境がかなり出ている感じですね。(配信で)最初に出てきているのは、アルバムの柱になる曲だったけど、そのあとはバリエーションが出てくるので、そこに関しては、思ってもみなかった感じのものになっていると思います。そういう意味ではアルバムらしいというか、いろんな歌詞がありますね。

渡邉貢(Ba)
――「DEAR YOU」は、歌詞を読んだ渡邉さんが号泣した、というエピソードを聞いています。
渡邉:「DEAR YOU」は、曲を作った時点で、今までにないエモーションを感じていたので、すごくいい歌詞がついて、ツボに入ったというか。やっぱり日本のポップスって8割、9割方は歌詞ですね。ということに気づきました、この曲で。今までは、曲が6で歌詞が4ぐらいに思っていたんですけど、詞が8.5、曲が1、アレンジが0.5ぐらいですかね。それぐらい詞の重みをすごく感じて、いい曲には必ずいい詞がついているんだということに気づきました。
――「DEAR YOU」の、いなくなった人を大切に思う想いは、特にコロナ禍を通過した今はすごく沁みます。
JILL:うん。あとは年齢的なものもあって、自分たちが60を超えてやっているという時点で、20歳の時とは違うわけで。全体的にやっぱり人生とか、これからのこととか、生死に関してもそうだし、「FLOWER OF LOVE」は、生まれて繰り返すということを歌っていますけど、「DEAR YOU」は、失うものについて歌っているので、たぶんこの年齢で聴くとわかる人が多いかなと思います。人を亡くす悲しみとか、絶対みんな経験してるでしょう? 若い頃にはみんなまちまちで、経験してる人、その後に経験する人、いろいろあったかもしれないけど、だいたいの人はもうそういう経験をしているから。「DEAR FRIENDS」も同じですけど、みんなが自分のドラマの中に当てはめて考えられるものだったのかな?と思います。だから「DEAR FRIENDS」に対して「DEAR YOU」だったんだと思います。
――ある意味、対になっている曲ですよね。アンサーと言いますか。
JILL:「DEAR FRIENDS」は“友達たち”だけど、「DEAR YOU」は本当に“あなた”にと言っているものだから、みんなが、亡くした人を思いながら聴くということはあるのかなと思います。
――その次の配信3曲目「EVERY DAY IS A NEW DAY」はまた、希望の歌ですよね。
JILL:私はもともと、そういう歌しか書かなかったからね。だから、「DEAR YOU」みたいな歌詞を書くと落ち込むんですよ、すごく。それが起きてしまいそうな気がするから。もともと、あんまり悲観的に物事を考えないんだけど、歌詞にはマジックがあって、書いたあとに起きちゃうことがあるので。人との別れとか、つらいことは書かないようにと思っていたんだけど、たまたま2曲目で書いちゃったから、“ああ~”みたいな(笑)。書くとは思わなかった歌詞ですね。その反動で「EVERY DAY IS A NEW DAY」を書いたんだと思います。
――はい。なるほど。
JILL:でも(アルバム制作の)後半にできた曲は、逆にもうニューウェーブみたいな、初期の頃にやっていた曲みたいだったので、それっぽい感じがあるというか、それはそれなりの楽しみで書きました。歌詞は毎回、曲が来るたびに“どうしようかな”と思うんですけど、やっぱりコロナ後だし、あきらめないとか、夢を持つこととか、還暦を過ぎたとしても、そういうものがきっとあってほしいという思いがあるので、「DEAR YOU」も絶望ではないわけです。絶対に希望を歌おうということは考えていました。
藤田:「DEAR YOU」(の歌詞)は、あの曲に乗っけたのが良かったですよね。曲自体がすごくナチュラルで、優しいメロディじゃないですか。
JILL:暗くないもんね。
藤田:そこのマッチングが絶妙ですよね。歌詞だけ聴くと“う~ん…”って考えるけど、ライブで実際に叩いていると、もうひたすらグルーヴが気持ちいいというか、お客さんも本当に乗ってくれて、横乗りっていうんですかね。
本田:「DEAR YOU」は、先にネオアコツアー(※3~4月にアコースティック編成で開催した『HAPPY BLOOMING TOUR』)でやったのが良かったと思います。あそこで、小さい音でのダイナミクスの付け方を学んだので、そのあとにやったライブもすごく良かった。

藤田勉(Dr)
――配信4曲目の「SING ALONG FOREVER」も希望の歌で、JILLさんが歌い続ける理由みたいなものを、自然体でそのまま語った歌詞だと受け止めました。そして、アルバムリリース後には40周年記念ツアーが始まります。6月21日のZepp Nagoyaから、7月21日の東京・Zepp Hanedaまで、1ヵ月間で9公演のアニバーサリーツアーです。
JILL:さっき本田くんも言ったけど、ネオアコツアーは小さい音でやるから、ダイナミクスが歌しかないんですよ。普通だったらギターソロがあったり、盛り上げていくアレンジがあるんだけど、ネオアコだとそれもできなくて。もちろんその中にも色々なドラマ性はあるんだけど、それがあって、ようやくこの間、通常体のバンド演奏することがあって、やっぱりすごいなと思いましたね、アンサンブルが。みんなが一つになるというか、“ここでこう行きたい”というのがはっきりわかるので、やっていて気持ちいいし、見る人も、次のツアーでは絶対それはわかるんだろうなと思います。
――しかも、9年ぶりのアルバムからの新曲もたくさん聴ける。
JILL:新曲もほとんどやりたいんだけど、そうなると、一体全体、何時間になるんだろうなという、それがとても怖い(笑)。
藤田:周年の意味合いも大事ですしね。レコ発ライブというだけでもないし。
――逆に、どんなバランスでセトリを組んでくるのか、すごく楽しみです。どんなツアーにしたいですか。
藤田:先ほどもちょっと言いましたけれども、必ずいいライブになります。昔はね、ツアーが始まるときとか、ライブの前には緊張があったんだけど、今は本当に楽しみだけですね。お客さんと一緒に楽しみたい、心の底から盛り上がりたいという、そういう気持ちでいっぱいです
本田:今回、Zeppがけっこうあるんですけど、あんまり僕らはやったことがなくて。独特の、ロックなイメージがあるじゃないですか。ライブハウスとしては大きいけど、ロックな見せ方ができるというイメージがあるので、どういうふうにパフォーマンスしようかな? というのが楽しみです。いろんなシーンが作れると思います。
渡邉:今はちょっと裏方作業が多いので、オンステージのイメージはあまりないんですけれども、とりあえずきちんとやれるように、体を鍛えておこうかなと思います(笑)。あとは事故なく、怪我なくやれればいいかなと思います。
JILL:夏ですからね。夏は体力を吸い取られるので、見に来る方はエネルギッシュになるだろうけど、バテちゃわないように。しかも行程がね、けっこうハードなんですよ。高知の翌日が東京ですから。
渡邉:トランポ(機材トラック)さんが激走してくれるらしいですよ(笑)。
藤田:札幌、仙台、高崎もけっこうハードですね。
――4日間で3公演ですよね。すごい。
JILL:でも、瞬く間に過ぎるでしょうね。始まったら、終わりまで早いと思います。
渡邉:一本一本、大切にやりたいです。
藤田:初めてPERSONZのライブに、というか、初めてロックのライブに来たというお客さんが最近すごく多いんですよ。全国で、どこでもそういうことになっていて。
JILL:“初めての人いますか?”って聞くと、けっこう手が上がる。
藤田:今回もたぶん、たくさんそういう方が来てくれるんだろうと思うので、そういう人たちを本当に、PERSONZを好きにさせたいですよね。
――最近の、SNSや動画サイトへのメッセージを見ると、特に“JILLさんの声が凄い”“昔より出ているんじゃないか”という声をたくさん目にします。
JILL:私だけじゃなくて、メンバー全員、前よりスキルが上がっているんですよね。歳を取るとダメになるとか、声が出なくなるとか、楽器に関しても探求心がなくなるとか、そういうイメージがあるけども、実際のミュージシャンはそうではなくて。だって、未知のゾーンを歩いているわけだから。昔は、60までやっているなんて想像できなかったけど、そこは全然、“歳だからできない”ということは一個もないです。3日続けてやるとバテてしまうとか、そういうのも一切ないし、そのために日頃の準備もしているので。
――そうですよね。あえて口に出さずとも。
JILL:誰か一人がそうしていれば、絶対みんな刺激されるじゃないですか。馴れ合いで長くやっているわけじゃないから、そこに関してはすごくプロ意識が強いバンドだと思うし、次の6月21日からのツアーは、“えっ!?”ていうぐらい驚かせようかなと思っております。
――来てくれる方も、いろんな思いを持って来てくれると思います。
JILL:周年ということ自体が、みんながお祝いに来てくれるということだと思っているし、全部の箇所で“花”というモチーフを掲げて、私たちもお客さんも、全員がその花なんですね。それが華やかに、全員で咲くことが一番いいと思うし、咲かせるためには努力しないとね。お水をあげたり、いろんなことをして。散ってまた咲くという繰り返しをしているわけだから、いつかはまた変わっていくでしょうけど、そのエネルギーがあるうちは、“散っても咲かせる”ということかなと思いますね。
取材・文=宮本英夫 撮影=アンザイミキ

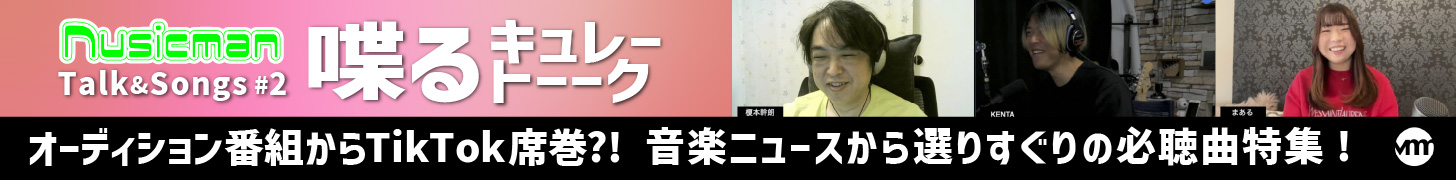

広告・取材掲載