
リハーサルより
パリに本拠を置くピアニストの務川慧吾が2024年8月、国内全国5都市をめぐる自身初となるリサイタルツアーを開催した。「芸術家と死」という重くも意欲的なテーマを軸とした演奏会は真夏の外気温にも負けぬほどに各会場を大いに熱狂させた。8月22日(木)に東京のサントリーホール大ホールで行われた公演の模様をお伝えしよう。
美しくも大胆なラインナップで挑んだ「死」のテーマ

リハーサルより
務川が満を持して構想した今回のツアープログラムのテーマは「死」だ。決してそれが副題のように明記されているわけではないが、事前のインタビューや務川自らが記したプログラムノート、メディア向けの自著原稿でもその言葉に明確に触れている。
プログラムを構成する作品の並びも実にユニークだ。前半にJ.S.バッハ「パルティータ第1番」全曲、ベートーベン「ピアノ・ソナタ 第17番《テンペスト》」の二題。そして、後半はショパン晩年の大作「ポロネーズ 第7番《幻想》」を筆頭に、フォーレ「ノクターン」第8番・第13番、そして最後にプロコフィエフ「ピアノ・ソナタ 第2番」 というものだ。
一つのプログラムの流れを通して「死」を様々な角度から捉えようとする務川。その死生観の多様性にどこまで聴衆を肉薄させられるかという課題に挑む美しくも大胆な発想のラインナップだ。哲学や文学にも造詣が深い務川ならではのプログラミングにおける文脈の冴えは心憎いまでに完璧だ。当夜の演奏は、その鮮やかな文脈を自身の演奏を通して三次元に立体化させ、客席の人々の心と知性にストレートに浸透させた。2時間20分にも及んだ当夜の演奏会を振り返ってみよう。
前半は“好き”を体現する王道二作品

前半プログラムの バッハ「パルティータ 第1番」とベートーベン「ピアノ・ソナタ《テンペスト》」。ここまでテーマ性が明確にされたプログラムにおいて、あえて冒頭の二作品は主題提起のような基調的存在となるものではなく、いきなり ‟閑話休題” 的なものから始めるところがいかにも務川らしい。一作品目の「パルティータ」は古典音楽をこよなく愛する務川の “好き” を体現するものだ。続くベートーベンもしかり。「ようやくステージで自信を持って弾ける」と自らを納得させられるようになった今だからこそ、この“好き”な王道の二作品を大切なリサイタルツアーのステージで演奏してみたかったそうだ。
6曲の古典舞踊から構成された「パルティータ 第1番」。一曲目のプレリュードは比較的ゆっくり目のテンポで一音一音を噛みしめるように、しかし大きな弧を描くように流麗な音を響かせる。テヌート気味に心を込めて紡ぐ音の粒立ちが美しく、透明感に満ちた優しい歌心がいかにも務川のバッハらしい。続く、アルマンドやクーラントではクラヴィチェンバロの音色や奏法を思わせる軽快な響きが心地よく、一連の装飾音における表現の洒脱さが、これらの作品が生まれた時代の典雅な空気感を雄弁に描きだしていた。務川はこの組曲について、「生活感すら感じられる、日常の中にある舞踊曲たち」と語っているが、力みも衒いもない自然体の演奏から生みだされる音楽はどこまでも純粋な喜びに満ちていた。
5曲目の(二つの)メヌエット。ダ・カーポ形式でメヌエットⅠとⅡが演奏されるが、中間に挟まれたメヌエットⅡの大胆なアーティキュレーションの取り方やアクセントの付け方に、古典楽器の奏法を極めたピアニストならではのバッハ演奏の妙味を余すところなく堪能する。そして、最終曲 ジーグ。ペダリングやダイナミクスによる表現を極限にまで抑え、華やかながらもミニマリズム的な要素を美しい和声感とともに際立たせていた。

続いて演奏されたのはベートーベン「ピアノ・ソナタ 第17番《テンペスト》」。冒頭の瞑想的でたゆたうようなアルペッジョから一転して性急で激しい動機の提示へと突入。務川はいつもには無いほどの激しい身体的アクションで印象づける。その後に続く展開部での劇的さにも、今までの務川にはない、何か一皮むけた力強いパッションが感じられたのは偶然だろうか。
再現部への橋渡しとなるAdagioからLargoへ、そして詩的なレチタティーヴォへと拡大された美しきアルペッジョによって描かれる幻想的な音のうつろいは、むしろ“幽玄”という言葉がふさわしい程に深みのある響きを燻らせていた。数回繰り返されるフェルマータの音が醸しだす余韻、そして時折、挿入される短い休止の空白の音価すらにも意志のある力強い言葉を湛えていた。詩的な理解にすぐれた務川ならではの含蓄のある緻密な演奏とともに、静と動の対立の妙など、情動の振れ幅の豊かさに終始、心を揺さぶられる第一楽章だった。
最終楽章においても、完璧な様式感の中で大胆不敵にダイナミクスを描き出し、感情の起伏の激しさを格調高く表現していた。抑制の効いた古典様式をしっかりと留めながらも、内面の情動に肉薄した演奏は、まるで一つの完成された自由形式の幻想曲を聴いているかのようでもあり、ロマンティシズムへの道を切り拓かんとするベートーベンの凄まじいまでの渇望や生き様そのものまでをも感じさせる情熱と個性にあふれる演奏だった。
務川いわく、前半プログラムは決して「死」というテーマに直結するものではないとしているが、死と隣り合わせの壮絶な人生を送ったベートーベンという作曲家に対し、真っ向から「死」というものを意識した凄みのある演奏であったことは間違いない。
「苦悶の中の一条の光」そして「死の予感」

そして、休憩を挟んでの後半プログラム。いよいよ、今回のリサイタルである「死」に焦点を充てた一つのストーリーが展開される。
一曲目 ショパン「幻想ポロネーズ」——拍手に迎えられ後半ステージに戻ってきた務川は、意外にもその余韻が覚めやらぬ間に序奏の和音の響きで会場を満たした。あたかも務川自身、あらゆる死のかたちに立ち向かう固い決意を、自分自身に、そして客席の聴衆に高らかに表明しているかのようだ。
前半部では激情と痛ましいまでに憂愁に満ちた思いが倒錯する様を、それらがあたかも表裏一体なのではないかと思わせるほどに巧みに、しかし効果的に繋ぎ紡いでゆく。二つの対立する感情をはっきりとした境界線を見出だせないほどに幻影的な曖昧さの中に表現したショパン円熟期の境地を、務川はいとも容易に自らの思いの中に手繰り寄せ、さらなる深淵へと導く。追想的な想いを秘めたフレーズでの自然な感情の発露もまた円熟のショパンの内面の世界の高貴さと霊感に満ちていた。
そもそもプログラム後半の冒頭に「幻想ポロネーズ」を持ってくる大胆な発想を持つピアニストは務川くらいだろう。しかし、ここにこそ鍵がある。この冒頭の一曲がこのポジションを得て提起したものは、「死を意識した作曲家たちの中に芽生えた一筋の希望」だ。務川は十代でこの作品に出合った頃からこの美しくも苦悶に満ちた作品の中に一条の光を見出だしていたという。「死は何かの始まりを意味するという思いもある」——と事前のインタビューで語ってくれたが、この思いから発展する “もう一つの” 死生観を後半で存分に描いてみたくなったのだという。
もし前半二曲目のベートーベンが正統なかたちでの死への対峙であると仮定するならば、ここからは「新たな出発点としての希望の光を纏う死のかたち」の断章が描かれてゆく。だからこそ、冒頭の作品はその基調・起点となる特別な一曲でなくてはならない。それこそが「幻想ポロネーズ」なのだ。冒頭序奏の二つの和音が織りなす一撃は務川にとって大きな意義と覚悟を持つものだったに違いない。

次なる ”死のかたち” はフォーレ「ノクターン 第13番」。フォーレのピアノ作品最後の一曲だ。作曲当時76歳。満身創痍の身体は間違いなく死を意識していたに違いない。前半の重厚なコラール風の和声感の中に潜む(老境の作曲家が抱く)死の予感と慰め、そして、その先に息づくほのかな希望の光——内声にまでもコントロールが及んだ厚みのある和声の一つひとつが描く音の響きからは、漆黒の闇の中に鼓動するかすかな光の美しさが垣間見えた。
アルペッジョが織りなす情動的な中間部への移行もまた驚くほどに凄みに満ちていた。忍び寄る死への絶望感とともに生への執着を感じさせる作曲家の強烈な思い。それらが表裏一体になってアルペッジョの流れの中に吞み込まれてゆく——その激流に務川は果敢に挑み、あえて作曲家の心の奥底に忍び込むかのように深く抉り出そうと抗う。しかし、荒ぶる流れは次第に祈りのように静かな思いへと変わりつつある——そんな束の間の激動の時の流れの中に描かれた光に包まれた理性の芽生えもまた美しくあり、フォーレと言う作曲家の生き様を描きだしているかのようだった。(13番の前にあえて同8番のような小品を挿入し対比させたのもの功を奏していた。)
”破壊的な” 攻めのピアニズム まさに”没入型”演奏会

リハーサルより
プログラム最後を飾るのは プロコフィエフ「ソナタ 第2番」。1912年、作曲家21歳の作品だ。多様な死生観の最後の断章は、若き革命的天才が表出した「破壊的な死」のかたちだ。務川は自らプログラムノートに「プロコフィエフが若くメラメラしていた頃の作品にも、また別の意味での死性を僕は感じる。『狂気と破壊の精神』がそこにはある。魂を芸術に投げ打った者には、常人には決して見えぬ世界が見えているのだと思う(プログラムノートより抜粋/一部筆者の編集)」と書き記している。
確かに帝政ロシアに生を受けながらもイデオロギーの変遷の真っただ中に多感な時を過ごした若き作曲家が、新たな世紀の音楽を予兆させる大胆な作品を生みだした時のセンセーショナルな衝撃は計り知れないものだったのだろう。務川が 「狂気と破壊の精神を感じる」と表現したのは実に意義深い。そこには、まさに(作曲家と弾き手の)両者が「魂を芸術に投げ打った者」だからこそ分かり合える ”何か” があるに違いない。
第一楽章――冒頭から力強さを露呈。ロマン派的な色彩を放ちながらも、プロコフィエフらしさの音楽的要素や語法をさりげなく、しかしグロテスクに際立たせる洒脱さがカッコいい。死を真っ向からではなく、少し斜めからサルカスティック(皮肉・風刺的)に眺める作曲家の視点が強烈に感じられ、務川が言う「狂気漂う破壊的な死性」から沸き出でるエネルギーがストレートに描きだされていた。
第二楽章では重音を轟かせながら執拗にダイナミクスをコントロールしてゆくその手法にメカニックな構築感がありありと表現されていた。しかし、“メカニック” という言葉の無味乾燥なイメージとは無縁の、モダニズムに裏づけられた精気あふれる色彩感の豊かさと、繰りだされる奏法の鮮やかさを通して、この若き作曲家が放つ天才性の萌芽が強烈に示唆されていたのは見事だった。第三楽章においてもロマンティシズムの薫りが理知的に漂い、みずみずしい音の響きと相まってよりいっそう不気味さを湛えていたのも印象的だった。そして、トッカータ風のパスピエともとらえられる最終楽章。コケティッシュな表情やカリカチュア的な語法など、あらゆる要素をリズミカルに聴かせ、まさに ”破壊的な” 攻めのピアニズムで全編を締めくくった。

重いテーマに挑んだプログラムの完結——最後は聴き手もプロコフィエフのエキセントリックなまでの強烈なエネルギーを弾き手と一体化して体感することで会場全体がある種のカタルシスへと導かれていた。そのような意味ではピアノリサイタルでは珍しい “没入型” の演奏会だったと言って良いのかもしれない。
同時に、ある種の問題提起にも満ちた刺激的な作品でこの日のプログラムが終えられたことで、聴き手側も “死” のかたちの変容があたかも無限に続いていくような感覚にさせられたのではないだろうか。死生観という答えのない世界を描きだそうとする務川が密かに心の中に抱いていたであろうその思いと余韻を会場の聴衆も強く受け止めたことだろう。
全プログラムを弾き終え、満場の拍手に応える務川。サントリーホールのステージ全面、四方向に向かって丁寧にお辞儀をする姿が印象的だった。鳴りやまぬ拍手に応えて ラヴェル マ・メール・ロワ から「妖精の園」(務川自身のピアノ独奏用編曲版での演奏)と、ショパン「英雄ポロネーズ」を演奏。最後はスタンディングオベーションの高揚感に会場全体が包まれていた。

終演後にはサイン会が開催された
取材・文=朝岡久美子 撮影=iwa
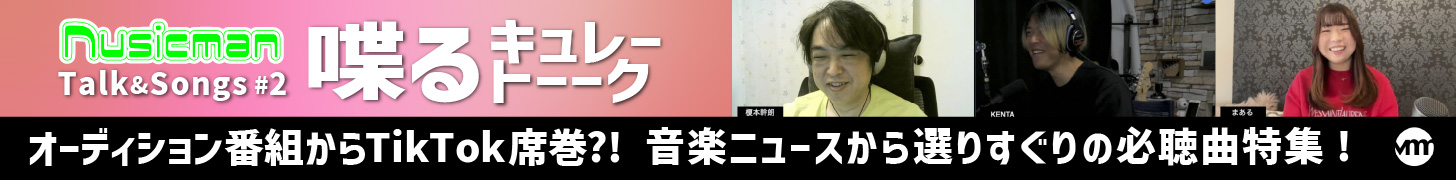

広告・取材掲載