
Nothing’s Carved In Stone
Nothing’s Carved In Stone “Live at 野音 2024” 2024.8.31 日比谷野外大音楽堂
最新が最高であるというのは、バンドに限らずあらゆる表現者の理想とするところだが、それは決して容易いことではない。モチベーションを保ち続け、アンテナを尖らせ続ける大変さはもちろん、キャリアを重ねれば重ねただけ、超えなくてはならない壁──過去の自分達が高く立ち塞がるものである。そんなことは重々理解した上で、この日何度も思った。Nothing’s Carved In Stoneは間違いなく、今なおキャリアハイを更新していると。
まず、全21曲のうち6曲が最新作『BRIGHTNESS』の曲たちだった。同作は7曲入りなのでセットリスト入りしなかったのは1曲のみということであり、リリースに紐づかないライブにおいてはけっこう珍しいケースだと思う。それだけ彼ら自身が自信を持っているであろうだけでなく、実際にどの曲もライブの流れにおける重要なポイントを任され、観客たちに歓喜とともに受け入れられ、大きな盛り上がりを生んでいたことは特筆に値する。

生形真一(Gt)
まずスタートダッシュを確固たるものとするべく2曲目に配された“Bright Night”では、ストロボ発光による強烈な逆光を背負いながら、ドライに歪ませた生形真一(Gt)のギターと大喜多崇規(Dr)の巧みなペダル捌きによるビートのラッシュがライブのボルテージを加速度的に上昇させていく。タイトな演奏の中にも生形や日向秀和(Ba)がしれっと差し込むテクニカルな演奏と、サビで一気にスケール感を増す展開が堪らない「Challengers」、アンコールでド級のアンセム感とともにエモーションをカンストさせた「Will」あたりも、新曲とは思えないほど必然性をもってライブを彩っていた。

村松拓(Vo/Gt)
5度目の日比谷野音ワンマンについて、村松拓(Vo/Gt)は「ここでやる意味っていうのは、みんなのため。それだけです」と言い切ってみせたが、その言葉を裏付けるように、バンドの歴史とともに歩んできたファンには特に嬉しい、レアよりな選曲も普段より多めだった。そもそもオープナーが「Overflowing」という時点でびっくりさせられたし、村松が風格たっぷりにハンドマイクで煽りながらでっかいコール&レスポンスを巻き起こした「Sing」、抑えの効いたCメロ部分で野音ならではの虫の音ともコラボする一幕もあったロックバラード「朱い群青」あたりも近年のライブで聴いた記憶がないセレクトである。

大喜多崇規(Dr)
ちょくちょくライブでやっている曲の中でも「キタ!」と歓喜するシーンはふんだんにあった。変拍子と超絶技巧の激突によってスリリングに上り詰めていく「Damage」は、彼らのレパートリーにおける“どうかしてる”タイプの曲を象徴する一曲であり、しっかり需要を満たされた人も多かったのではなかろうか。イントロでどよめきが起きていたのは、トリッキーなリズムパターンから真っ直ぐな8ビートのサビへ至る展開で開放感たっぷりの「Pride」。思いっきりスモークを撒き散らしてからの生形のソロも大きな見どころだった。最新型の姿とマニア心をくすぐる選曲の両方を、一本筋の通ったライブ運びで届け切ったところからも、年初の武道館ワンマンや『BRIGHTNESS』ツアーのさらに先を征く姿が観られたように思う。

日向秀和(Ba)
もうひとつ、この日のライブを特別なものとした要因は、晴れバンドの彼らには珍しい雨である。過酷さゆえに生まれる謎の一体感や、ステージから放たれる照明やレーザーに反射してきらめく雨粒の数々による美しい光景の数々……もちろん、降らないに越したことはないのは当然だが、数日前までは台風直撃の可能性もあり、実施の可否さえ2日前まで不透明だったことを思えば、音を鳴らし始めた途端に降りはじめてアンコールでいったん止んだ雨(その後また降った)を、まぁ特効の一種として受け止めてやってもいいか、というくらいの気持ちにさせてくれた。ただ、遠方からの参加者など天候によって来場が叶わなかったファンの存在があったのもまた事実で、しっかりそこへ言及する村松の誠実なMCからも彼らの心意気を見た想いだ。

Nothing’s Carved In Stone
アンコールまで全21曲を演奏し切ったうえで2時間に満たないという濃密ぶりも、ひょっとすると天候に配慮したものだったのかもしれない。もっとも、普段からあまり長々MCはしないし、メドレーのように曲間を空けずにどんどん演奏していくことも多いタイプではあるのだが、いつにも増して美味しいところがギュッと詰まっていたように感じられた。特に、「Mirror Ocean」までの“聴かせる”ブロックを終えたところで「お前らの心に届くように、一音一音、全部込めていくから」と宣言してからのロングスパートは見事。「Like a Shooting Star」に始まり、マッドでサイバーなダンスチューン「Idols」から、もはや主戦力となりつつある「Freedom」、待ってましたの「Out of Control」に、一体感に満ちたシンガロングで始まった「Dear Future」と、新旧織り交ぜながら涼しい顔して、けれど灼熱の演奏とともに走り抜けていく。とりわけ、曲に込めた意志を直接手渡すかのような説得力に満ち、曲を追うごとに迫力を増す村松のボーカルには目を見張るものがあった。
本編を締め括ったのは、ミラーボールの放つ光の粒に包まれながらの「The Silver Sun Rise Up High」。天候ゆえにそれまでじっとりした空気が充満していた会場にすっと風が吹き抜け、包容力たっぷりのメロディとともに場内が明るく照らされる様子は間違いなく、野音じゃなければ、雨の野音じゃなければ味わうことのできない瞬間。そして前述した「Will」と、華々しくフィニッシュを飾る「Isolation」までをアンコールで披露してライブは終了した。音も佇まいも精神もとことんタフに仕上げた強さだけでなく、最後の最後に「風邪ひかないようにね」と言い残していく優しさにもしっかり痺れてしまったのだった。
取材・文=風間大洋 撮影=RUI HASHIMOTO [SOUND SHOOTER]

Nothing’s Carved In Stone
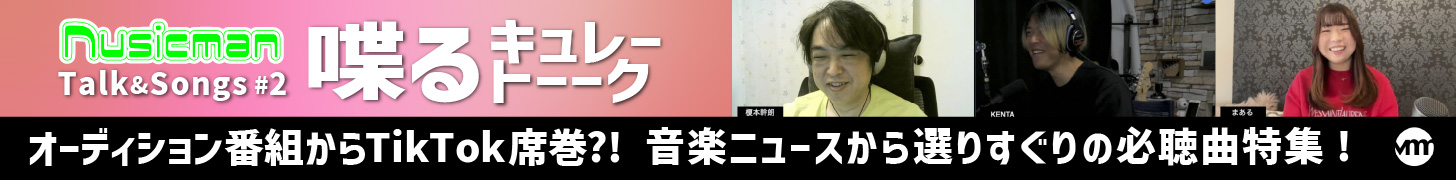

広告・取材掲載