
クジラ夜の街 撮影=大橋祐希
リアルの対語としてのファンタジーではなく、リアルとファンタジーが溶け合う新しい世界がここにある。クジラ夜の街、メジャー2ndフルアルバム『恋、それは電影』。通称「恋盤」。恋する気持ちと電影(映画、もしくは稲妻)をテーマに作り上げた12曲は、それぞれの物語を持ちながらやがて一つの壮大なサーガへと成長する、聴くほどにスリルと謎解きの快感が味わえるアルバムだ。楽曲も幅広く、激しいビートロック、ポップなダンスチューン、エモ度満点のロックバラード、初の完全打ち込み曲など、バラエティ度と完成度も過去最高レベルにある。長い長い制作期間の果てに、バンドはいかにしてこの新境地に到達したのか。4人の胸の内を聞いてみよう。
――今回は制作期間が相当長かったという話を聞いているので、まずはそのあたりから。どんな状況だったんでしょう。
宮崎一晴(Vo):制作のスタイルが今までとは違っていて、決まった本REC日を作るというよりは、推敲を繰り返して、長い期間の全部が本RECみたいな感じだったので。制作過程をロングタイムで考えていく方向にしたことで、いろんなインスピレーションを……どれだけ制作前に閃きを凝縮させたとしても、形になっていく過程で思いついてしまうものがどうしても出てくるので、そのリカバリーができやすくなるスタイルにしました。
佐伯隼也(Ba):ただ、レコーディング期間は長いんですけど、みんなでスタジオに入って作る時間はあまり取れなくて。家でベースを考えてきたものを早速録ろう、みたいな感じで、結構怖かったですけど、いいものができたなと思います。1曲目の「SHUJINKO」とか、ほぼ決まっていない状態からベースを作り上げたんですけど、その時に思った完璧なものを録れたと思います。「SHUJINKO」のベースは気に入ってます。
山本 薫(Gt):全部が出来上がってみて、より広い人に刺さるような曲たちが揃ったなという感覚があります。これまでは、アレンジやサウンド面で“ファンタジーを創るバンド”というコンセプトを強く意識しすぎていたところがあったと思うんですけど、そういうものをずっと作ってきて、自然と体に染み付いたから、強く意識しなくてもよくなったというか。“クジラ夜の街はファンタジーを創るバンドです”という土台ができた状態で、たとえばファンタジーを強く意識していない歌詞や曲を作ったとしても、それはクジラ夜の街の曲になるというか、自分たちの個性をしっかり持ちつつ、広く人に伝わるような曲たちができたんじゃないかな?という感覚があります。
――確かに。
山本:曲で言うと、「End Roll」が気に入ってます。これは完全にトラックを僕個人で作ったものなので、思い入れが強いです。
――初めての試みですよね。それは一晴さんが薫さんに託したんですか。
宮崎:このトラックは、実は2021年くらいにあったんです。コロナ禍であまり顔を合わせることができない時期に、歌の入る隙間もないようなトラックがポンと送られて来て、“これを歌ものにするぞ”ということになって。僕がそこに歌を入れて、薫に再度預けて、3年間くらいかけてアレンジしていったということです。
山本:このアルバムに入るか入らないか、ずっとふわふわした状態だったんですけど、レコーディングが終わる直前に“やっぱり入れましょう”と。完全に打ち込みの曲ではあるんですけど、やっと入れられたなという感じです。

宮崎 一晴(Vo,Gt)
――リリック的には絶対必要な曲だと思いますけどね。アルバムの流れの中で。
宮崎:裏リード曲ですね。『恋、それは電影』というアルバムは、恋の話であり、“電影”は“映画”という意味で、この曲は“恋心”プラス“映画”がテーマなので、完全に裏リード曲です。
――さっき薫さんが言った、“ファンタジーを創るバンド”ということを強く意識しなくなった、という点についてはどうですか。ソングライターして。
宮崎:僕もそこからの脱却を意識していたというか、そもそも僕が目指しているファンタジー観って、ただキラキラしているだけじゃなくて、“現実と表裏一体なんだぞ”というところは、歌詞でもっと露骨に出していきたかったんですね。サウンド感で言うと、より薫が自由になったなという感じがしていて、ギターのエフェクトで言うと、ディレイやシマーリヴァーヴとか、ファンタジー観で言うとあるあるなんですけど、そういったものから脱却して、がっつり歪ませて、音像はドライな感じでとか、そういう掛け合わせになっているので、いわゆるステレオタイプ的なファンタジー観からの卒業になったんじゃないかな?と。今までの人たちが紡いできた“ファンタジーってこういう感じだよね”というものから脱却して、独自の音でやっていくということが、今回はサウンド感と詩世界と共に結構出せたんじゃないかなと思います。
――なるほど。
宮崎:ファンタジーというもののステレオタイプに行きすぎると、かえってオリジナリティがなくなっていくと思うんですよ。AIに聞いたファンタジー観みたいなものになってしまうと、人間が幻想することとは乖離するというか、現実の中の幻想みたいなところになってくるので。そこでちゃんと、自分たちならではのファンタジーというものを考えれたんじゃないか?と思います。
――それは、このアルバムの非常に重要なポイントですね。
宮崎:(メンバーは)すでに、できる人たちではあったんですけどね。やっぱりどこかで考えちゃってたのかな?とは思います。
――それを今回は“伸び伸びやっていいよ”と言ったわけですか。
宮崎:というか、僕も言語化はなかなかできていなかったですけど、より自分のプレイヤーとしての個性と向き合ってくれた感じはしましたね。やっぱりバンドなので、そこまで各自の核心みたいなところに踏み込みすぎたくないし、プレイヤーが各自で高め合っていったものをぶつけ合うのがバンドかなと思うので。

山本 薫(Gt)
――ドラマーとしては、どんな思いがありました?
秦 愛翔(Dr):これはネガティブな意味じゃなくて、超ポジティブな意味なんですけど、ドラムってめっちゃアコースティックな楽器で、レコーディングって波形が見えちゃうから、自分の実力をいい意味でも悪い意味でも知る機会になるんですよね。そういう意味で言うと、このアルバムは僕にとってその時の全力だったし、自分でも納得いくものはできたんですけど、ただ波形で自分の音をちゃんと見ると、へこむこともあったというか。
――そうでしたか。
秦:今回のアルバムは特に、そこについて本当に考えさせられたというか、自分のドラムって何なんだろう?とか、自分はドラムが一番できることだけど、果たしてこれは本当に人に誇れるのか?とか、色々なことを考えたんですけど。でもやっぱり思ったのは、自分はドラムがちゃんと好きなんだなということで、すごく大きな意味で言うと、人生のターニングポイントだったなってめっちゃ思います。だからもう今は、この時も全力で自分が一番いいものを出せるように頑張ったけど、たぶんこの時よりは絶対上手くなってるんで、もう早くレコーディングしたいなって感じです。
――素晴らしいです。
秦:で、僕の一推し曲は「せいかつかん」ですね。この曲のドラムは自分ですごく好きで、なんでかと言うと、僕はプレイにも自信はあるんですけど、実は一番自信があるのが音作りなんですよ。この曲はドラムの音を全部自分一人で作ったんですけど、同業者の人に音作りに関して褒められることが多くて、この曲はめっちゃデッドな(反響、残響の少ない)音作りで、これを打ち込みを全く使わないでここまで綺麗にデッドにできるのって、たぶん同世代で僕ぐらいじゃね?とか思いますね。たぶん聴く人が聴いたら、絶対プロの人が音を作ってるでしょって思うと思うんですけど、“僕が作ってるよ”っていう感じです。
――それは誇っていいところじゃないですか。
秦:一晴くんが、こういうデッドな曲がすごい好きなんですよ。デッドな曲ってめっちゃ音作りが難しくて、プロがやるか打ち込みでやるか、どっちかなんですけど、僕は一人で全然できちゃうよ、任せなさいっていう感じです。
宮崎:これはすごく良かったですね。「失恋喫茶」(EP『青写真は褪せない』と本作に収録)の時もデッドで録って、ドラムは一番好きだったんですけど、それをちゃんと超えてきてくれた。「失恋喫茶」は90点くらいの感覚が自分の中ではあって、音作り的に完璧に僕の琴線に触れてるなと思ったんですけど、その時に出たちょっとしたアラみたいなものが「せいかつかん」で完全に整備されて、プレイを含めて、金物の鳴り方も最小限に抑えられていて、すごく聴き心地がいいので、めっちゃ自分の好きな音だなと思います。100点満点です。素晴らしいです。
秦:ドラマーが一番やるべきことって、お客さんがいいなと思うドラムを叩くことはもちろん大事なんですけど、メンバーの要求にちゃんと的確に応えるのがいいドラムのあり方だと思うので。そこはそのまま頑張りたいです。
宮崎:特にスネアですかね。「失恋喫茶」と「せいかつかん」でパチッと上がったのは。
秦:キモすぎるぐらいミュートするんですよ。
――ドラムは特に、テックさんがいるのが普通で、それだけで商売する人がいるぐらいだから、相当難しい仕事ですよね。
秦:テックさんには正直かなわないですけど、ただ、メンバーの要求に応えるという意味だったら、誰にも負けないんじゃないかと思います。
――一晴さん、プレイヤーを鍛えちゃいましたね。今回のレコーディングのやり方で。
宮崎:すごくいいと思います。でも絶対できる人たちだと思うので、もっと行けると思います。
――ベーシストからも、もうひとこと。鍛えられた感はありますか。
佐伯:そうですね。今までは、ベースとしての役割も果たしつつ、ハイフレットにいってキラキラとか、ソロっぽいことをやっていたんですけど、このアルバムは、結構ガチムチというか。
宮崎:すごいワードだ(笑)。
佐伯:ベースのガチムチ感が、「雨の魔女」はもちろん、「SHUJINKO」とか「星に願わない」とかも、結構綺麗なベースしてるんですけど、ガチムチなんですよ。自分的には。
――演奏の細部までこだわりまくったアルバム。そしてアルバム全体のテーマですけど、『恋、それは電影』という、恋と映画というテーマは、元からあったんですか。それとも、曲を作っている間に浮かび上がってきたものなのか。
宮崎:「恋盤」にしたいなという気持ちはあって、アルバムを全部ラブソングにしたいという気持ちですね。それってすごくわかりやすいテーマだし、僕はわかりやすいものがすごく好きなので。そして……そうですね、どういうことを話しましょうか。これに名付けたきっかけ、というよりは、これを作るにあたっての自分の心境の変化とか、そっちのほうがいいですか。
――そっちのほうがいいですね。お願いします。
宮崎 :だとすると……僕は、恋をしたんですよね。それが大きいです、このアルバムは。レコーディングの期間が長いんですけど、その中で、恋をしてない自分と、恋をしている自分とが、ばっつり重なっているんです。好きな人と出会うことが、制作期間の真ん中にあって、全く恋を知らない人間が、アルバムが完成するタイミングでは、恋をしている人間になっているんですよ。それが特に表れているのが「せいかつかん」という曲で、それが歌詞のテーマになっているんですね。ファンタジーなものを作るということが自分に合っている理由として、妄想がすごく好きだからこそ、実体験を飛び越えて、イマジネーションを働かせることによって、普通は行きつかなかったようなところまで歌詞が届くという良さが理にかなっているなと思って、ずっと書いていたんですけど。今回歌詞を書いていく過程で、恋という気づきがあって、それは素晴らしいものであり、自分の人生をより幸福にしていくものであり、視界が良好になっていくものだなという感じがしたんです。小さいものに対して幸福を感じられるようになって、“世界はこんなに素晴らしいものなんだ”という細部まで目が行き届くようになっていった。最初から視界が良好だったら気づけなかったものが、徐々に曇りが晴れていくことによって得た気づきである感じがしていて、夜明けという感じがします。
――それは非常に劇的な出来事ですね。
宮崎:バンドの名前はクジラ夜の街なんですけど、今まではそうだったんですけど、夜明けのようなアルバムになったなと思います。特に「せいかつかん」は、歌詞に関して……歌詞って、歌入れをする最後まで書き替え続けることができるもので、「せいかつかん」は、恋をする前と恋した後の詞世界がどちらも混在している楽曲になっていて、この曲を通してどんどん夜明けになっていく感じもありますし。今まではイマジネーションと自分が培ってきた知見のみで働いていたものが、今回はリアルタイムで得た感性がプラスされていると思います。
――ドキュメンタリーですね。
宮崎:そうですね。結構ドキュメンタリーチックになったなと思ってます。リアルタイムで自分が感じたことがエッセンスとして入っているという点で、すごく鮮度の高いアルバムだなと思いますし、自分の頭の中から引っ張り出してきただけではない、オンラインな感じと言いますか、他からのアウトプットが入っている、すごく開けたアルバムだなと思います。でも確実に自分の感じたことを、嘘なく歌っているなというのが全体を通してあるので、思ってもいないことは一切書いていないですし、常に正直さや実直さ、素直さみたいなものを制作過程では大切にしようということを考えて書いていきましたね。メロディも含めてですけど。
――はい。なるほど。
宮崎:恋というものが自分にとってどんどん身近になっていって、クリアになっていく過程で、詞世界も変わっていった感じです。「星に願わない」もそうですけど。
――「星に願わない」は明らかに、恋を知る者の歌詞。
宮崎:これは元々できていた曲なんですよ。姉の結婚式にあてて書いた曲だったので。その過程で、父が逝去したりですとか、自分が恋をすることによって、結婚というものが自分の中で身近になったりとか、家族愛とか、そういったものが制作過程に入って来ることによって、新たにCメロで書き加えた歌詞があったり、歌入れの時の思いが全然違ったり。「星に願わない」は、最初に姉の結婚式で歌った頃は、家族とはいえ他人の結婚をお祝いするだけの曲だったのが、より自分の心が近づいていったというか、詞に心が近づいていった感じがしています。他にも色々あって、逆に「それだけ」という曲は、17歳の時に書いた歌詞を、できるだけそのままの形で歌っています。これは高校生の時からある曲なんですけど。
――それって、ひょっとして、2曲目のインスト曲「きみは電影(Prelude)」の中でしゃべっていることですか。「17歳の時に書いた歌詞をリメイクして…」と、演奏の向こうで小さく聞こえる語りの中で。
宮崎:そうなんです。「きみは電影」で言っているのは、その次の曲「ホットドッグ・プラネッタ」のことではなくて、「それだけ」のことだというギミックがあって、そこに気づいてくださるとすごく嬉しいです。「ホットドッグ・プラネッタ」で歌っている、《昔の歌は歌わなくなった》という“昔の歌”は、「それだけ」のことだという、メタ構造みたいなものも楽しんでもらえたらと思っているので。
――それ、めちゃくちゃ面白い。でもここで書かないほうがいいかな。
宮崎:書いていただいて、全然いいですよ(笑)。
――それに気づいたらすごいですよね。リスナーが。
宮崎:そうですね、ぜひ気づいていただけたら。なかなか難しいとは思うので、気づかないとは思うんですけど。“ここ歌詞変わったんだっけ”というところも、「それだけ」の歌詞を以前とはちょっと変えているからで、その寂しさみたいなものを考えていただけたらなと思います。

佐伯 隼也(Ba)
――話を聞けば聞くほど、深いアルバム。今しかできないことばかり詰まっている。
宮崎:心境の変化のグラデーションが、制作過程と完全にぶつかったので、そういった意味で面白いというか、どんどん心変わりしていく様相が、曲が生きているみたいでかっこいいなと思います。化石のような曲ではなくて、ちゃんと生きている、命がある楽曲たちになったなというふうに思います。
――そこに電影、映画というテーマが重なってくるわけですか。
宮崎:そうですね。まず、電影という言葉がかっこいいじゃないですか。しかも電影には稲妻、雷という意味もあって、中国語では映画の意味で、日本語だと雷みたいな意味合いなんですよ。実はCDのディスクの裏に種明かしというか、“なぜ恋が電影なのか?”ということを書いたんですけど、映画のようにずっと残り続けていくものでもあるし、稲妻は一瞬の、刹那の衝撃でもあるので、永遠性と刹那性とを兼ね備えているのが“恋”だなと思ったので、ぴったりじゃないかと思って名付けました。でも名付けたタイミングは恋をする前なので、自分の中でその意味合いがどんどんそこに近づいていくという、詞に心が近づいていくという言い方をしましたけど、アルバム全体に、作品に心が近づいていったなという感じがすごくしています。
――良い意味で深読みが楽しめる作品。歌詞をそのまま受け取ると、好きだったバンドが売れてしまって、昔と変わってしまったという寂しさと皮肉みたいなものを歌っている「ホットドッグ・プラネッタ」が、なぜリード曲なのか?も含めて。
宮崎:「ホットドッグ・プラネッタ」は、テーマをファンタジーというもので覆い隠しているので、ただ単純にこの曲をファンタジーとして受け取っていただいても大いに結構なんですけど、やっぱり確実に裏があるだろうという(笑)。バンドの歌をバンドが歌っている時点で、裏の思いがないわけがないので、そこに気づいてほしいのと、なぜそれが“恋”をテーマに冠したアルバムのリード曲になってるのか?という、テーマ的にもただの宇宙のおとぎ話じゃないよねというのは、できれば噛み砕いて聴いていただけたらなと思います。
――分析というよりも、想像力ですね。
宮崎:アルバム全体を通して聴くと、よりこの曲の真理みたいなものに迫れるんじゃないかと思います。「ホットドッグ・プラネッタ」と「それだけ」を、クジラ夜の街の歴史と一緒に聴いていただけたら、ポップなファンタジーの中に隠されているものをみつけてもらえるんじゃないかなと思います。
――さぁ、ライブはどうしましょうか。12月20日から、年またぎでリリースツアーが始まります。
宮崎:「ホットドッグ・プラネッタ」はもうライブでやっていますけど、めちゃくちゃ良くて、今までライブでやった曲たちの中で、初おろしの中で一番手応えがあったかもしれないと思うくらいで。音源の時には甘く優しかったサウンド感が突然牙をむいた感じがあって、すごく良かったですね。たぶん他の楽曲たちも、「雨の魔女」はどんどん進化してきていて、やればやるほど磨きがかかるだろうなと思うし、あとやってみたい曲は「End Roll」と「SHUJINKO」ですね。「せいかつかん」もすごく楽しみだな。ライブはたぶん絶対いいですよ、全曲。
――楽しみです。
宮崎:特に「End Roll」がどういうふうになるかは楽しみです。ドラムとベースが生じゃないんですけど、絶対バンドでやれるようにはしたいので、練習してもらいます。「End Roll」は、メンバーがみんな好きなんですよ。だからちゃんと愛を持って取り組めるんじゃないかなと思うので、早くやりたいです。

秦 愛翔(Dt)
――どうしますか。「End Roll」。
佐伯:新しいエフェクターを買おうかなと思ってます。シンセベースの音が出るエフェクターを探してて、いいのを見つけたので、それを買おうかなと。
宮崎:初めて聞いた。熱意があるね。
秦:「せいかつかん」も楽しそうだけど、やっぱり「End Roll」が楽しそうだな。打ち込みを生でやるって考えると難しいけど、でもライブで見た時の感動って、やっぱり迫力が大事だと思うので。今ちょっと考えているんですけど、この曲自体が同期(トラック)に音圧がある曲だから、そこにドラムをちゃんとでかい音でぶつけて、生で見た時に“おお、こんな感じになるんだ”と思ってもらえたらいいなと。で、それが無理だったら、DJします。
宮崎:行けるんじゃない?(笑) 佇まい的には。
秦:実は僕、あれができるんですよ、スクラッチ。練習したらできるようになったので。いつかライブでできたらいいなと思います。
宮崎:「出戻(Interlude)」とか「Saisei」とかでも行けそうだよね。
秦:でも「Saisei」でDJをやってると、誰もドラムがいなくなる(笑)。俺が二人いないと。
――それはその時考えるとして。夢が広がりますね、このアルバム。みなさんぜひ次のツアーへ、新しいクジラ夜の街の形が観られる可能性大です。
宮崎:楽しみですね。
――ツアーの途中で、もう2025年になりますから。2025年もクジラ夜の街をよろしくお願いしますということで。
宮崎:次にやりたいなと思う曲は、もうあるので。より自分たちが好きな楽曲で、やっぱり嘘をつかないことが一番いいということに気づいたので、これからも嘘をつかずにどんどんやっていきたいですね。

取材・文=宮本英夫 撮影=大橋祐希
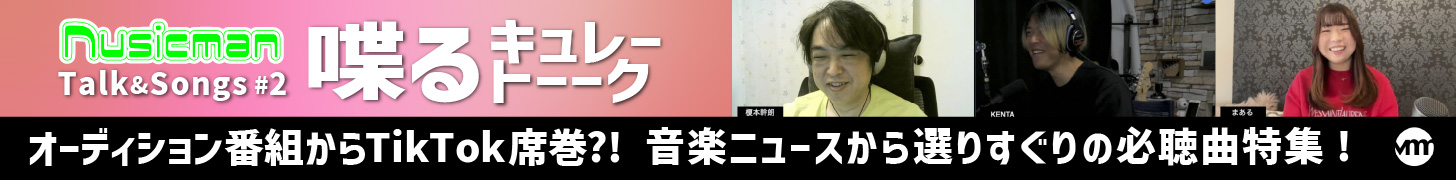

広告・取材掲載