
吉澤嘉代子
デビュー10周年イヤーを颯爽と走り抜ける、吉澤嘉代子から届いた謎解きゲームへの招待状。TVアニメ『誰ソ彼ホテル』オープニング主題歌「たそかれ」は、原作のゲームをやりこんで得た着想を元に、スリルとミステリーをたっぷり詰め込んだドラマチックなポップチューン。楽曲という名の物語を生み出し続ける、アーティスト・吉澤嘉代子らしさ満開の1曲だ。
リリース後の4月20日には、10周年イヤーを締めくくる二度目の東京・日比谷野外大音楽堂での記念ライブも控えている。10年目にして「歌えば歌うほど楽しくなっている」という、吉澤嘉代子の世界は広がり続けている。
――アニメ見てます。めちゃくちゃハマってますね。映像と曲調が。
ありがとうございます。自分でもハマってるなと思います。
――曲作りは、どんなふうに?
2年前なので、だいぶ前に作った感じもするんですけど。ゲームが元になっているということをお聞きして、ダウンロードして、夢中になってやりました。謎解きゲームなので、選択肢がいくつかあるんですけど、選択していなかった部分も全部クリアしたいと思って、課金しながら完全クリアしました。
――素晴らしい。それぐらい面白かったと。
謎解きは苦手なほうだったんですけど、お話がすごく面白くて、毎回ゲストのキャラクターが出てくるたびに、そのキャラクターがすごく魅力的だったりとか。人間模様が描かれていて、“これはどうなるんだろう?”というミステリーが楽しくて、どんどん進めていきました。
――ゲームには、いくつかエンディングがあるんですよね。
そうなんです。なので、アニメではどのエンディングを選ぶんだろう?というのも、気になっているんですけど。全クリした立場としては。
――ハッピーエンドにしてほしいですけどね。曲にする時は、どういう想像で書いていったんですか。
ゲームにはいくつもエンディングがある中で、一番ぐっとくるというか、『誰ソ彼ホテル』ファンの方には楽しんでもらえるんじゃないかな?というエンディングから着想を得て、作った楽曲です。謎解きゲームなので、歌詞にもちょっと難解な言葉を散りばめて、物語と共に歌詞の意味も徐々に明らかになっていく、という作り方を目指したんですけど、2年後になると、どれが何だったのか自分でもわからなくなって(笑)。なんでこういうふうに書いたんだっけ?と思ったんですけど、だんだん思い出してきました。アニメではワンコーラスが流れているんですけど、2番以降も、『誰ソ彼ホテル』ファンの方に聴いていただきたいなと思っているフレーズがたくさんあるので、感想をいただくのが楽しみです。
――アニメの物語が進むにつれて、歌詞の聴方も変わって来るという。
“これはそういう意味だったのか”みたいな、そういう作り方を目指しました。
――楽しいですよね、そういう作り方は。ソングライターとして。
楽しいです。いつも、お題があると生き生きしてきます。自分語りだったりとか、自分の身を削る歌は苦しくて筆が進まないですけど、物語があって、その作品に捧げるみたいなことはすごく楽しいです。
――弦楽器もふんだんに使って、スピード感とドラマ性に溢れるアレンジも素晴らしいです。さすが横山裕章さん。
私がデビューする前に最初に出会ったプロのミュージシャンは、たぶん横山さんです。19歳の頃からお世話になっているので。でもご一緒するのは久しぶりだったので、横山さんのレコーディングでの姿を見られて楽しかったです。
――曲を作った立場として、何かリクエストはしましたか。アレンジのキーワードとか。
舞台が、時間が止まったようなホテルなので、“大正浪漫”というテーマがあって。でも、それを音にするって難しいじゃないですか。大変だったと思うんですけど、 アニメの歌を自分が歌唱するのは初めてだったので、自分の中のアニソン像というか、絵が切り替わっていく情景を思い浮かべながら、ブロックごとに区切られていくというか、変化していくことを相談しながら作りました。
――ああ、それで、絵にすごく合ってるなと思ったんですね。なるほど。歌詞はどうですか。
歌詞は、下調べの時間が結構長かったです。まず“黄昏”という言葉があって、“黄昏時”とか、“逢魔が時”とか、そういう日本語を大事にしようと思って書いていきました。それと、麻雀のお話が出てくるので、“和了り(あがり)”とか、“如何様(いかさま)”とか、麻雀用語も入れたりして。今まで入れたことのない言葉も結構入ってます。

――麻雀といえば。CDジャケット(アニメ限定盤)でジャン卓を囲むキャラクターのイラストの中に、吉澤さんも入っているじゃないですか。これ最高ですよね。
あまりにも絵が可愛すぎたので、もっと輪郭を丸くしてくださいとか、もっと目を小さくしてくださいとか、そういうオーダーを二度ほどしました。
――めちゃくちゃ可愛いです。意外と、コミカルな面もあるアニメなので、似合ってます。この曲、もうライブで歌ってますよね。去年のツアーで。
そうなんです。「旅する魔女」というツアーで、ずっと歌っていました。2年前に録音したもので、ツアーで歌っているうちに歌唱もだいぶ変わってきて、この2曲目に入っている「ピアノと歌」バージョンは、ツアーが終わってから歌ったので、結構自分の中では変わったかなと思います。
――そうか。時期が全然違うんですね。
そうなんです。それを踏まえてオリジナルの「たそかれ」を聴いたら、すごく疾走感があってびっくりしちゃいます。

自分の中で、ミュージシャンという一つのもののプロフェッショナルとはだいぶ違う、“壁がすごくあるな”とずっと思っていた。
――そもそも、“ピアノと歌”バージョンで歌い直そうと思った理由は?
「たそかれ」はアニソンとして書いたので、普段の自分とは違う編曲にしたいと思っていたんですけど、自分のフィールドに寄せた編曲でもリリースしておきたいなという気持ちがあって、(リアレンジを)お願いしました。信頼の伊澤一葉さんにお願いして弾いてもらいました。
――入口が二つあるのはいいですね。アニソン吉澤から入っていただいた方は、さらにディープな世界が待っている。
ほかにも、おどろおどろしい曲も取り揃えているので。「たそかれ」から入った方は、そこからまた「地獄タクシー」とか、「シーラカンス通り」とか、いろいろありますので、ぜひ聴いていただけたら嬉しいです(笑)。
――それは素晴らしいPRです(笑)。 確かに吉澤さんの世界にはいろんな扉があって、めちゃくちゃ清純な、キュンキュンするものもあるし、地獄もあるし(笑)。いろいろありますよね。
いろいろやっていますので、何かに引っかかってもらえたら嬉しいなという気持ちです。
――もう1曲、カップリング曲「舞台」のお話も聞かないと。「たそかれ」とイメージ的に繋がるものがある曲調で、すごくいい組み合わせだなと思いました。
「舞台」は、は田村芽実さんに提供した楽曲です。芽実ちゃんの舞台俳優としての、ステージに自分の存在を刻みたい、突き刺したいというお話を聞いて作った曲だったんですけど、今回の「たそかれ」とも合いそうだなと思って。おどろおどろしさだったり、切実さだったりとかが合ってるかなと思って、セルフカバーしました。
――突き刺すって、かなり強い表現ですよね。
「ステージを見た人に何を感じてほしいの?」と聞いた時に 「深く突き刺したいです」と言われて、差し違える覚悟なんだなという、すごく強い意志を感じて、それをいただきました。
――このインタビューを読んでいるみなさん、こちらもぜひチェックを。そして、昨年4月からスタートして、現在進行中のデビュー10周年イヤー。1年やってきて、ファンの方の顔を見たり、昔の曲を歌ったり、色々してみて、今何を思っていますか。
たぶん今までで一番歌唱してきた1年になるかなと思います。元々、あんまり歌うことに自信を持っていなかったんですけど、歌えば歌うほど楽しくなっているなと気づいたのは、一人だからこそ、 いろんな人とご一緒できるじゃないですか。その演奏にうっとりしたり、その演奏によって自分の歌が変わることが楽しかったり。一番近いツアーでは、ピアノの梅井美咲さん、ギターの細井徳太郎さんと、3人で14か所を回ったんですけど、二人はジャズ出身のミュージシャンなので、毎回演奏が変わるんですよ。即興性がすごく高くて、“あ、今日はこうやってくるんだ”というものがあるんですけど、逆に二人にとっては、「歌が毎回違うから面白い」と言ってくれて。私の歌を面白いと思ってくれていたんだと思って、それがすごく嬉しかったんですね。
――そこは、自覚してなかったですか。
なかったです。自分の中で、シンガーソングライターというのは全部が中途半端な仕事で、ミュージシャンという一つのもののプロフェッショナルとはだいぶ違う、“壁がすごくあるな”とずっと思っていたので。認めてもらえたような気持ちになれた、ということがあって。やっと、ちょっと自信を持てたかなという気がします。
――10年にしてやっと。でもそれは謙遜のしすぎですよ。シンガーソングライター・吉澤嘉代子が中途半端だなんて、誰一人思っていない。
でもやっぱり、作詞家、作曲家、演奏家があって、全部やっちゃってるじゃん、みたいなのがコンプレックスではあったんですけど。自分の好きなミュージシャンが、自分の歌を好きと言ってくれているのが、心からの言葉だと感じたので、嬉しかったです。ほかにも、色々なミュージシャンとご一緒できた去年は、本当に豊かな1年でした。

今は(楽曲を)手放せるようになったというか、誰かの手に渡って変化することも楽しく思えるようになったなというのはあります。
――お客さんはどうですか。顔を見て、何か思うことはありますか。
この10年間、色々な時代があったんですけど、周りが全員敵に思えていた時もありますし、自分の楽曲は自分しか守れないと思った時期もありますし、でも唯一信じられたのは、今目の前にいるお客さん、私の歌を聴くために、決して安くはないお金を払って来てくださるお客さん、その場にいてくれるお客さんのことだけを、信じてやってこれたなと思っていて。ずっと応援してくださっている方はわかるし、新しく見つけてくれた方もすごく嬉しく思いますし、本当に、聴いてくださる方がいて自分がいるということはひしひしと感じます。
――ちょっと、聞いていいですか。周りが全員敵に思えていた時っていつ頃ですか。
最初はずっとそうでしたね。自分が商品になる前で、楽曲も自分だけのものだったので、その領域に侵入されるみたいな気持ちになってしまって。それが今は(楽曲を)手放せるようになったというか、誰かの手に渡って変化することも楽しく思えるようになったなというのはあります。いいこと尽くしですね。
――長く続けると、いいこと尽くし。良かった。その話で言うと、僕、昔、苦言を呈されたことがありますよ。吉澤さんに。
えっ。苦言ですか?
――インタビュアーの方は、歌の中の主人公を私だと思って質問してくるけど、それは物語であったり、演じたりしているものもあるから、全部私のことだと思われると困ります、みたいな。そんなきつい言い方じゃなかったですけど。
(笑)でも、そのぐらい強い気持ちで思ってました。確かに。
――だから、そうだよな、聞き方に気を付けないと、と思ったのをすごく覚えてます。
覚えていてくださって、ありがとうございます。でも、最初はそうでしたね。“美少女”はあなたのことですか?というところから始まって、でもずっとこういう作り方を続けていたら、“今回はどんな主人公なんですか?”とか、だんだん聞かれ方も変わっていったように思います。
――良かった。でもそうやって、こちら側も吉澤さんの表現方法を、だんだん理解していった部分もあるので。そもそも歌は自由ですもんね。何にでもなれるわけだから。
何にでもなれますね。
――話を戻して。いい10周年でしたね。まだ終わってないですけど。いろんなことが確認できたというか、再発見できたというか。
チームも新たになって、それもすごく大きかったです。ドラクエみたいな、どんどん新しい仲間に出会って強くなっていくみたいな、いつも今が一番楽しいと思えているのは、ありがたいなと思います。

野音はお祭りみたいな1日にしたいなと思って、色々考えています。 ちょっと寒いかもしれないので、あたたかくして来ていただけたらと思います。
――そして、10周年イヤーの締めくくりが、4月20日の東京・日比谷野外大音楽堂での記念ライブ。どんなライブにしたいですか。
10周年の始まりのLINE CUBE SHIBUYA(2024年5月)では、物語性の強い楽曲をセットリストに入れて、朗読をしながら進めていったので、結構内省的なライブだったんですけど。野音はそことはまた違ったアプローチをしたいなと思っていて、お祭りみたいな1日にしたいなと思って、色々考えています。
――野音は、思い入れのある会場なんですよね。
はい。17歳の時に野音でサンボマスターのライブを見て、音楽を仕事にしたいな、ステージの向こう側に行きたいなと思ったのが始まりでした。なので、特別思い入れがある場所です。そんな場所で、二度も開催できてすごく幸せです。
――2021年以来、4年振り、二度目の野音になりますね。2020年に決まっていたのが、コロナ禍で延期になって、翌年開催できて。あの時は、お天気はどうでしたっけ。
お天気、良かったです。2020年に最初に開催しようと思っていた日に、野音に一人で行ったんですけど、誰もいない真っ暗な野音に。その日は雨が降っていたんですよ。でも、翌年開催した日は快晴だったので、良かったなと思いました。今年はどうかな?という感じですけど、お花見の時期よりも、もうちょっとあったかいですかね。
――バンドメンバーは、ゴンドウトモヒコ、伊澤一葉、弓木英梨乃、伊賀航、伊藤大地。最高の演奏家であり、気心の知れた人ばかり。
クラシックメンバーですね。大好きなミュージシャンたちです。このメンバーの演奏を一番近くで聴けることがすごく幸せです。
――楽しみにしています。晴れますように。
ぜひぜひ、お待ちしています。ちょっと寒いかもしれないので、みなさん、あたたかくして来ていただけたらと思います。
取材・文=宮本英夫

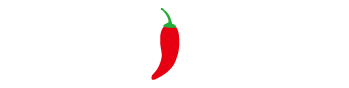
広告・取材掲載