
小菅優 (C)Takehiro Goto
2025年3月28日(金)紀尾井ホールにて、ピアニスト小菅優による『“ソナタ・シリーズ” Vol.4「神秘・魅惑」』が開催される。4回目となる「ソナタ・シリーズ」について小菅優に聞いた。
ーー「ソナタ・シリーズ」も4回目となりました。「ソナタ」というスタイルで曲を書いた作曲家、そしてその曲自身をこうして様々な“切り口”でまとめてみると、1つのスタイルでも音楽が実に多面的に発展してきたことに、改めて驚かされます。今回のVol.4のテーマは「神秘・魅惑」で、優さんは弾く曲目たちのことを「悪」あるいは「危険な」と表現されていますが、それにとても興味を惹かれます。まずは今回弾かれる曲の“全体”を通して、それらの言葉のイメージをどんなところに感じるか、お話しください。
まず、「神秘、魅惑」という言葉がどの曲にも当てはまると思います。今回、お客様をそれぞれの作品の世界に「誘惑」するようなところがあり、その美しさの中には官能的でどこか性的なところもあって、背徳感さえ感じられるかもしれません。でもそういった世界は人間にとって常に魅力的です。
スクリャービンとリストに関しては、作品のイメージやストーリーに悪、悪魔が存在するため、それらの残酷さ、不気味さを、そして悪魔は必ず人間にとって魅力的な提案をして交渉するので、その人間の弱みを握る危なさも伝えないと、と思っています。
ここまでのお答えで、すでに何だか危険な気配を感じませんか?(笑)

小菅優 (C)Takehiro Goto
ーー今回、1つだけ新作があります。優さんの今や盟友といってもいい藤倉大さんが作曲したソナタです。この作品は共通のご友人である長谷川綾子さんの委嘱ですね。実際に出来た作品について、どう思われましたか?また今回のテーマの流れの中にうまくはまりましたか?
大さんのピアノ・ソロ作品は短い曲が多いですが、このソナタは17分間も大さんの世界に浸れるわけです。構成がはっきりしていて、巡回するテーマがありながらたくさんの要素が詰まっている。でもやはり大さんの作品で素晴らしいところは、想像力を常に掻き立てるところ。このような壮大な作品でも、その“宇宙”に吸い込まれると、あっという間に終わってしまうと思います。
この曲は前回の「愛、変容」というテーマでも、今回のテーマでも、どちらにも合う曲だと感じています。とにかくハーモニーが美しく切ない。動きのあるところでも、美しく浮遊感があり、快感を覚えます。しかし、どこか危ないところもある。それは大さんならではの色彩で人々を誘惑する、エクスタシー的なところだと思います。どの作品でも、どうしてこう官能的なところがあるのか、大さんとよく話題になるのですが(笑)、聴いていただければどういうことだかわかると思います。
こんな素晴らしい作品が生まれたこと、そしてそれを演奏できるのは幸せなことです。綾子さんのような芸術に情熱を持って、新しい作品を委嘱したいと思ってくださる方がいることに、本当に感謝です。
ーー最後に弾く、リストのソナタは素晴らしく画期的な曲ですよね。巨人の音楽。「聖なる」要素と「悪魔的な」要素が常に隣り合わせになっているような緊張感があります。まさに危ない音楽だという気がします(笑)。なおかつ、それが少ない主題の展開からなる4つの部分(楽章)を1つに統合するという離れ業を実現した驚異の音楽だと思います。優さんは20代の頃この曲を演奏されたそうですね。今回は当時難しかったことを克服する、「リベンジ」と思っているとのこと。今はどのような理解や経験をもって自分の中に落とし込んでいったのでしょう? また弾いていて、この曲の“魔的”なところにとらわれてしまう瞬間があったりするのでしょうか? 「異界から戻ってこれない!」といったような(笑)
(笑)。まさしくそこが危ない……リストの作品は、ロマンチックな情緒に囚われず、意外と冷静でいないといけないところがあるんです。特にこのソナタは、天国的なところはセンチメンタルになりがちですが、客観的に見る必要もある。それぞれのテーマ、そしてのちにそれぞれ展開していくキャラクター(悪魔的、神々しい、愛苦しいなど)がはっきりしている上、それらを対話させる必要があります。そして“宿命”を語る語り手が存在すると私は思います。弾き分けるだけではなく、ハーモニーの変化と同時に心理的動機を捉え、一つの巨きな物語にする。それはコンサートにおいてライヴで弾くことをより楽しくさせる内容でもありながら、それ自体はとても熟していて演奏が難しいのです。作品の中に、20代の時には感じなかった情緒を今になって感じる、という面もありますし、必要なのは「理性」なのかな、とも思います。

小菅優 (C)Takehiro Goto
ーースクリャービンが自らの音楽を探求する果てにたどりついた「神秘主義」的な「黒ミサ」ソナタ、そして片や、将来には無調の劇的なオペラを書くことになるベルクのスタートとなったソナタ。これらについて考えること、弾いていて感じること等々、少し詳しく話していただけますか?
スクリャービンのソナタ「第9番」はもちろん神秘劇的なところもありますが、自身も語っているように基本的にはそこから外れている作品だと思います。第6番や7番に比べ、単純な構成に回帰していて、明確なソナタ形式を持つ単一楽章。ハーモニーもわかりやすい。でも感情的には最も複雑なソナタで、その細かい指示によって表現される心理的内容は詩的で深い。常に漂う悪夢、恐怖、倒錯の気配は人がもつ根源的なものでありながら中世の暗い影のよう。前に「悪魔的詩曲」作品36を演奏したことがありますが、その小悪魔的な情緒と違い、こちらの方は真の悪の顕現なんです。今回、リサイタルの初めに3度と6度の不気味な和声を響かせるのは、いきなり今回のテーマを紹介する、いわば呪文を唱えるような感じになります。
ベルクがシェーンベルクのもとで行った最後の勉強はソナタがテーマだったそうです。これはその頃の作品。そのため、言いたいことを凝縮して単一楽章に思い切り詰め込んでいる感じがします。後期ロマン派の匂いのするドロドロとした感情は常に官能的で、悲劇的でドラマチックな訴えがある。もうたまらない、と思うほどの妖艶なハーモニーが聴き手を魅了する、素晴らしい作品だと思います。
神秘、官能、エクスタシーという言葉がよく出てきましたが、つまるところ最終的には“人間”に辿り着くと思います。前回のテーマ「愛、変容」にも共通する、あらゆる感情が芸術に映し出され、その魅力が今回も皆さんの「音楽をライヴで聴きたい!」と情熱を燃やす気持ちへとつながると嬉しいです。
では皆様、会場でお待ちしています!

小菅優 (C)Takehiro Goto

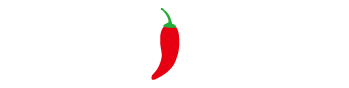
広告・取材掲載