「生成AIが著者の作品は米国で著作権保護されない」米控訴裁
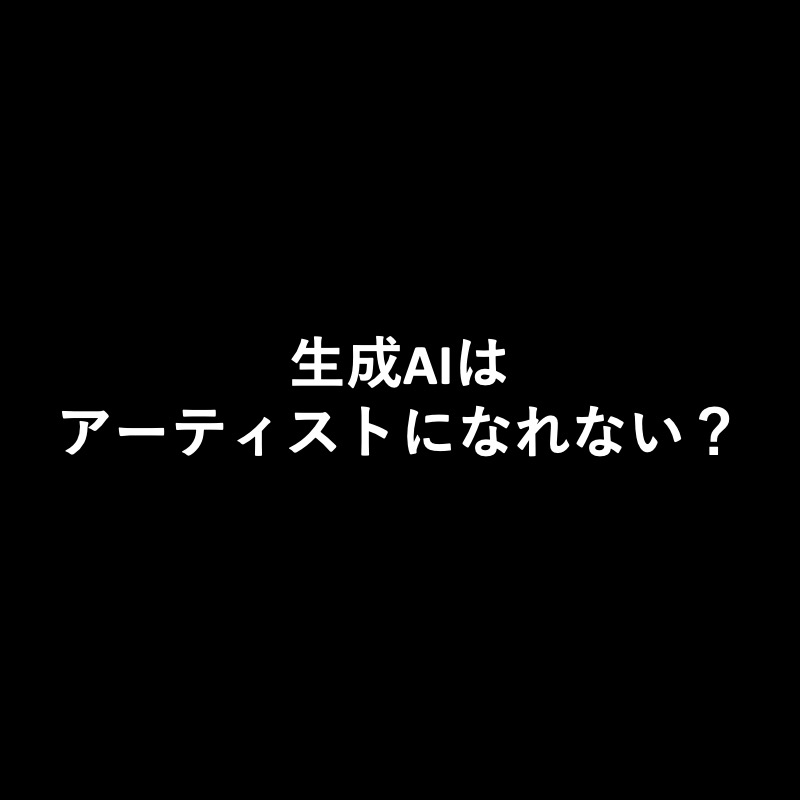
米連邦控訴裁判所は3月18日、人間の関与なしにAIが生成した作品は米国における著作権保護の対象にはならないとの判決を全員一致で下した。
コンピューター科学者のスティーブン・セイラー博士は生成AI「Creativity Machine」を作り、「A Recent Entrance to Paradise」と題した絵を生成。Creativity Machineを唯一の著作者として米国著作権局に登録申請したが、同局は「作品が人間によって著作されたものでなければならない」という要件を理由に、これを却下していた。
著作権局は、AIを利用した人間の著作者による作品の登録を認めている。AIが人間の著作者の作品にどれだけ寄与しているかという点が争点となったが、セイラー博士の場合、自分の生成AIを唯一の著作者として記載したことが決め手となった。
判事は、写真や録音物などもかつて目新しいものだったが、現在では著作権法が適用される技術だとした上で「著作権法を更新する鍵は裁判所でなく議会にある」と指摘した。
(文:坂本 泉)
榎本編集長「いずれ生成AIはかつてのレコードやCDと同じようにアーティスト自身を複製するメディアとなっていくが、そうしたことに関連する判決がアメリカであった。「人間の関与なしに」AIが生成した作品は米国における著作権保護の対象にはならないとした。と書けば当たり前ではと思うかもしれないが、今回はセイラー博士が自分で開発した生成AI「Creativity Machine」で絵を生成し、その著作者を自分ではなく「Creativity Machine」にしたケース。米著作権局はAIを利用した作品でも人間が創作に関与している割合が高ければ登録するのを認めているが、著作者の主体はあくまで人間でなければならない。この原則を覆すのは著作権法の改正が必要で、それは議会の判断することだとした。私も一冊目の本で触れたが、かつては録音というものも新技術であり、レコーディングには本のような著作権が認められてなかった。それが著作権法の改正で認められて現在の音楽ソフト産業が誕生し、アーティストはレコーディングでも稼げるようになった。連載で予測したようにアーティストAIが誕生しても、AIは作品であって著作者ではない方向にいくと私は見ている」
ライター:坂本 泉(Izumi Sakamoto)
フリーランスのライター/エディター。立教大学を卒業後、国外(ロンドン/シドニー/トロント)で日系メディアやPR会社に勤務した後、帰国。イベントレポートやインタビューを中心に、カルチャーから経済まで幅広い分野の取材や執筆、編集、撮影などを行う。

広告・取材掲載