ヒット曲の尺、短縮傾向に ストリーミング以外にも要因?
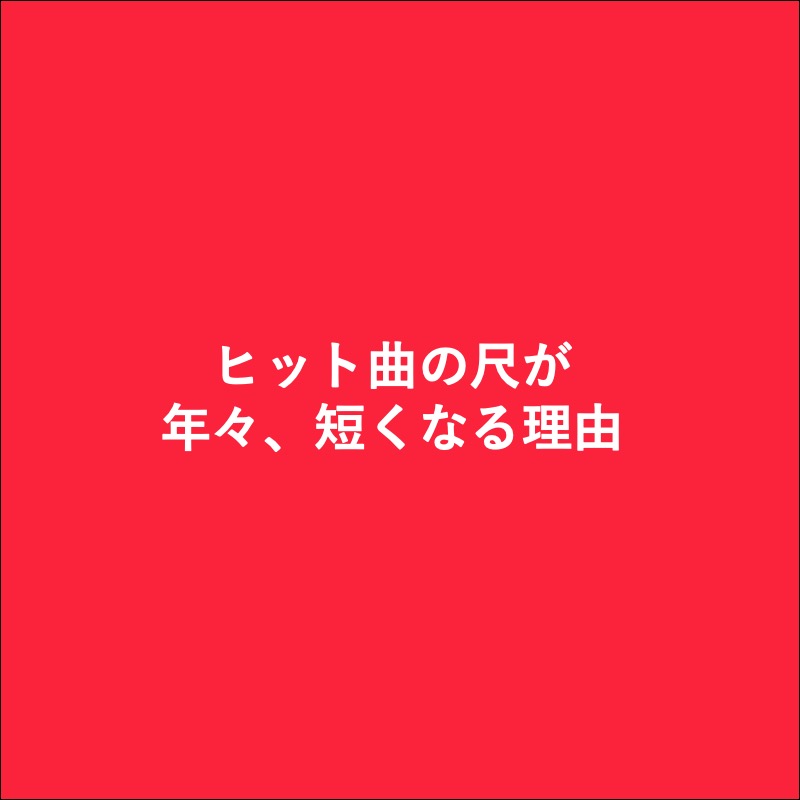
ヒット曲の尺が短くなっていることについて、かねて「ストリーミング時代におけるリスナーの注意力欠如」が要因に挙がる中、音楽ジャーナリストでニューヨーク大学の非常勤講師を務めるチャーリー・ハーディング氏は「歴史、ジャンル、曲作りのトレンドの進化など、想像よりも多くが絡んでいる」と分析している。音楽データ分析ツールを手がけるChartmetricが伝えた。
同社によると、Spotifyのチャートに入った曲の長さの平均は2024年に約3分となり、2023年比で15秒弱、2019年比では30秒それぞれ短かった。
歴史的に見て、曲の長さは、作曲の傾向や録音用メディアの変化に最も目立った影響を受けてきた。短い曲は目新しいものではなく、20世紀初頭から半ばにトレンドだった曲構成はAABA形式で、長さは平均2分30秒ほどだった。当時主流だった78回転レコードの音質維持の限界によるところもある。
1950〜1960年代にはヴァース・コーラス形式(ABAB形式)が台頭し、尺が徐々に拡大。カセットテープ、CDの登場でさらに伸びた。
ジャンルでは、アンビエント系やバラード系は長めで、ヒップホップやポップスは短めな曲が多い。
ストリーミング時代とヒップホップ人気、制作環境の変化(スタジオ録音→DTM)が、フック・ベースのソングライティングの拡大に貢献。また、Spotifyが30秒以上を1再生とカウントするなど収益面から曲が短くなっているとも指摘している。
ハーディング氏は今後、短編コンテンツの普及による疲労が、PhishやGrateful Deadのようなジャム・バンドの復活につながる可能性があるとみている。
(文:坂本 泉)
榎本編集長「ストリーミングの普及でヒット曲の平均時間が短くなるというのは連載で10年前にも伝えた気がするが、それはSpotifyが30秒以上聴いたら1再生になっているからというのが私を含む専門家の大方の見解で、実際そうなった。今回、ハーディング氏は「ヒップホップがチャートで増えたことも短尺化の要因になっている」と指摘。また、短尺疲れで今後、長尺の音楽が伸びると予想している。音楽産業100年の歴史を見ると、飽きる→逆の何かが流行るということをコンテンツやフォーマットともに繰り返している。それは「イノヴェーションのジレンマ」で有名なクリステンセン教授の理論にも合致するのは私の本でも書いたとおりだ」
ライター:坂本 泉(Izumi Sakamoto)
フリーランスのライター/エディター。立教大学を卒業後、国外(ロンドン/シドニー/トロント)で日系メディアやPR会社に勤務した後、帰国。イベントレポートやインタビューを中心に、カルチャーから経済まで幅広い分野の取材や執筆、編集、撮影などを行う。

広告・取材掲載