AI生成のコメント、ソーシャルメディアの死を誘発も
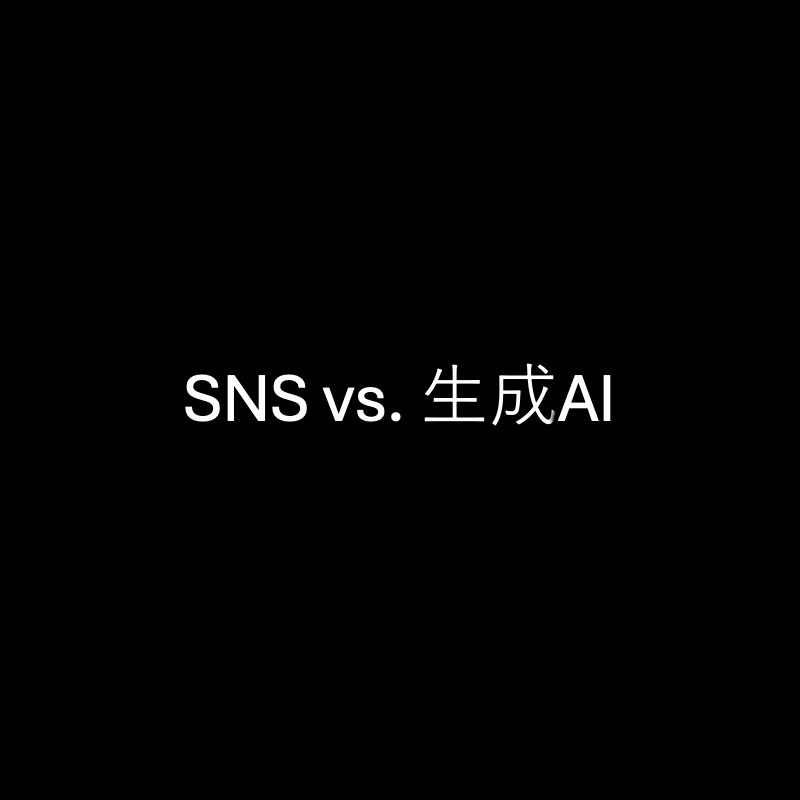
AI生成コメントの普及で、従来のソーシャルメディアが終わりを迎えるーー。音楽プロデューサー/エンジニアのボビー・オウシンスキー氏は、各社がAI機能の実装を進めるにつれ、ソーシャルメディアは従来の目的が損なわれると分析している。
ソーシャルメディアは現在、犠牲を払ってもエンゲージメントを高め、たとえ本物でなくても多くのインタラクションを提供することで、注目を集めることが目的の場に変化した。
コメントは「いいね!」と違い、常に真のエンゲージメントを示す主な指標で、フォロワーの良い指標だった。だが、コメントが本物だと信用できなければ、レーベルが興味を持ち、広告主が金銭を支払い、コメントにコメントすることも必要なくなり、プラットフォームへの関心は薄れていく。
報道によると、InstagramとFacebookはAIが生成するコメントを実験している。RedditとLinkedInのユーザーはAIが生成したコメントに苦言を呈しており、QuoraはAIが生成した質問で埋め尽くされ、YouTubeはボットによってコメントを分類。またメタは、自分自身のボットを作成する機能を提供している。
(文:坂本 泉)
榎本編集長「音楽で生成AIといえば楽曲の生成に目が行きがちだが、SNSマーケティングでも新たな課題を生んでいる。音楽のデジタル・プロモーションでもインスタやTikTok、YouTubeでアルゴリズムに取り上げてもらう際、重視されているのがコメント数だが、AIが生成したコメントが氾濫する兆候が見られる。オウシンスキー氏が指摘するように、このまま行けばSNS自体が信用を失うことになりかねない。検索エンジンもSEO対策した無内容な記事が氾濫して信用を失う中、SNSや生成AIで情報を調べる層が拡大した。技術が進めば何かが失われるが、それがまた新しいイノヴェーションが誕生する土壌となるのも事実なので、一見マイナスの兆候であっても冷静な視点を忘れずに見ておきたい」
ライター:坂本 泉(Izumi Sakamoto)
フリーランスのライター/エディター。立教大学を卒業後、国外(ロンドン/シドニー/トロント)で日系メディアやPR会社に勤務した後、帰国。イベントレポートやインタビューを中心に、カルチャーから経済まで幅広い分野の取材や執筆、編集、撮影などを行う。

広告・取材掲載