なぜ日本にはPandoraのようなネット放送が生まれないのか「未来は音楽が連れてくる」連載第28回
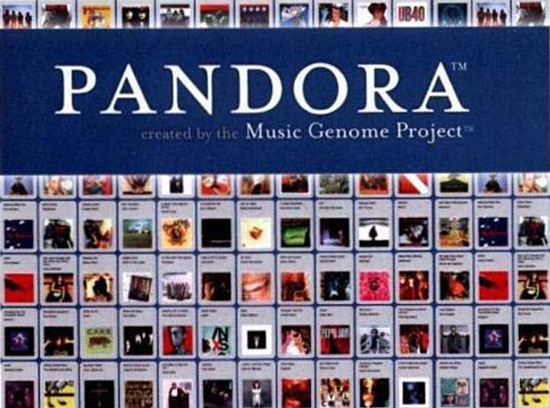
▲Pandoraのパーソナライズド放送は、無数のカスタム放送局を量産している。自分だけの放送局をいくらでも開局でき、リスナーひとりひとりのその時の気分に合わせ的確に曲を紡いでいくPandoraの「シード・ソング」は、ニッチだったインターネット放送にブレイクスルーをもたらし、全米で5,500万人の月間リスナーを持つに至った
Image : Pandora Official Blog
インターネット放送にブレイクスルーをもたらしたPandoraのパーソナライズド放送
かくてPandoraは開局した。
初対面からして、Pandoraは既存の放送とは装いが異なっていた。サイトを開くと画面の真ん中に、Googleのようなシンプルな検索欄が現れるのだ。
検索欄には「好きな曲名かアーティスト名を入力して下さい」と書いてある。
試しにRadioheadと入力すると、「Radioheadステーション」が立ち上がる。だが、必ずしもRadioheadのレパートリーがかかるわけではない。「Radioheadが好きなら、こういう曲がきっと好きでしょう」という選曲の番組多立ち上がるのだ。
まず、PortisheadのGlory Boxが始まり、次にRadioheadのLuckyがかかる、という具合で、その後、Ratatatという無名のアーティストが来た。Pandoraでは無名のアーティストがよくオンエアされるのだが、なぜかぴったり嵌る選曲になっている。
アルバムジャケットの下には「Why This Song(なぜこの曲がかかったの?) 」と出ている。クリックすると、
「基礎にロックソングのストラクチャーがあり、エレクトロニカ、R&Bの影響があり、コンプが効いた音作りが前の曲と共通しており、スタジオの録音経緯式、マイナーキー、といった特徴も共有していたからです」
と選曲の理由が出てきた。音楽のDNAが似通った曲を紡いでいる、ということだ。
かかった曲が気に入れば、サムアップ(イイネ!)ボタンを押すと、その曲に近い音楽が次にかかる。嫌いならサムダウン(嫌い)ボタンを押すと、選曲が改良されるのだ。ユーザーの好みに合わせて、種は独自の枝葉を茂らせてゆく「シード・ソング」の仕組みを、Pandoraの楽曲レコメンデーションエンジンは実現していた。
音楽の数だけ、そしてリスナーの数だけ放送局が存在しうる。
リスナーひとりが10局、20局とじぶんのカスタム放送局を次々と立ち上げていける。サムアップで個人の趣味嗜好が反映されるので、同じ「Rolling Stonesステーション」でも選曲は、その人ごとに全て違う。
だから、1000万人のリスナーが10局ずつ放送局を立ち上げれば、Pandoraには、1億局の放送局が誕生する。無限にチャンネルが増える究極の多チャンネル放送、ともいえる。
それはパーソナライズド放送と名付けられることになる、放送の全く新しい形であり、革命の始まりだった。
Pandoraの選曲力には魔力があった。
音楽好きなら一度使えば、まず感動し、誰かに教えずにはいられない。Pandoraの感動はレゾナンスを起こし、ソーシャルメディアを通じて急速に拡散した。開局からわずか1週間のあいだに、3度もサーバーのキャパを倍にする必要が出た。
瞬発力だけでない。Pandoraには中毒性があり、リピート率が半端でなかった。使えば使うほど自分にフィットした放送局になっていくので、使うほどPandoraから離れられなくなるのだ。
サーバとネットワークの拡張は、ひたすら続くことになった。
Pandora対Apple、初回はPandoraが完勝
うれしい誤算だけではすまなかった。
ウェスターグレンとCEOのケネディは、当初、Pandoraを「お試し期間ありのサブスクリプション・モデル」で運営しようとしていた。Emailアドレスを入力すると十時間まで無料で聴けて、時間を過ぎると「年間36ドル(約4,130円 114.7円/ドル)の有料会員のご案内」が届くという、ごくごく普通の発想だ。
だが、このビジネスモデルは開始早々、崩壊した。制限時間が来るとみんな、フリーのメアドを取り直して聴き始めたからだ。
YahooやGoogleを使えば、新しいアドレスなどすぐ取れる。正直、「どこか抜けてるのではないか」という気がしてくる失敗だが、これが結果オーライとなった。
「薄氷からジャンプすることに関しては、僕はプロですよ」
とウェスターグレンはインタビューで答えているが、サブスクリプションの薄氷から飛び移った先は、出資者であるヴェンチャーファンドの評判も上々だった。広告モデルに切り替えたのだ。
車社会のアメリカでは、ラジオ産業はレコード産業の4倍の売上規模を誇る大産業だ。 Pandoraという新しい人気放送局が、広告モデルで稼ぐ、というのはファンドマネージャーたちにもイメージがつきやすかった。
実は、ウェスターグレンとケネディが「ネットラジオをやる」と言い出したとき、ワルデン・ヴェンチャー・キャピタルの反応は芳しくなかった。
当時はEコマースの普及期で、Web2.0の流れからレコメンデーションエンジンは重要キーワードになっていた。それがPandoraに出資した理由だったのに、出資早々、いきなりニッチな「インターネットラジオをやる」といいだしたのだから、渋るのは当然だろう。頭をかかえたファンドマネージャーの姿が、目に浮かぶ。
しかもウェスターグレンのミュージックゲノムは、当時席巻していたWeb2.0理論と全く噛み合っていなかった。
Web2.0では「一般ユーザーの集合知が、少数のプロの知識を超えてゆく」というのがセオリーだが、Pandoraのミュージックゲノムは、プロのミュージシャンが集まって創り上げたデータベースだ。
しかもウェスターグレンが始めるという放送は、プロの専門知識を収めたDBが、番組のコンテンツを自動的に生成する、という。これは「消費者たちが手作りしたコンテンツの集合が、プロのコンテンツを超えていく」という理論にも反しているではないか。
以上が、ファンドマネージャーからの反対意見だった。
「理屈で説明できる状態ではありませんでした。実績で実証する必要があったのです」
ウェスターグレンは振り返る。そして実際に、ウェスターグレンたちは実証して見せた。Pandoraのリスナー数はわずか1年で、200万人(MAU)を超えることになったのだ。
これだけの人気を出せれば、インターネット放送というプロダクトも現実的だし、広告モデルも機能してくる。
「だけどほんとうは、こんなに人気が出るとは誰一人たりとも、予想してなかったです」
倒産すれすれの時代からスタッフだったリズコット-ヘイムの方は、そう振り返っている。オーナー側の意見と若干異なるが、両方とも真実だろう。要するにウェスターグレンたちは気合いと偶然で、結果オーライにしてしまったのだ。
Pandoraが開局した2005年7月、AppleのiTunesには300局近いインターネットラジオが集まっていた。
しかし、iTunesのラジオは、基本的には地上波ラジオをネットに同時送信したものを集めただけで、社会現象は特に起こらなかった。一方、音楽のDNAを自在に操るPandoraのパーソナライズド放送は、人類に前代未聞の放送形式をもたらしたイノヴェーションだった。
Pandoraは、iTunes時代にはニッチだったインターネット放送にブレイクスルーを起こし、開局からわずか1年で一躍、人気放送局になろうとしていた。
だがここで、Pandoraは最大の危機を迎えることになる。2012年の現在、AppleがPandoraクローンをやるかもしれない、というニュースで「Pandora最大の危機か?」と騒がれているか、2007年に訪れた危機は現在の比ではなかった。
行政機関がインターネットラジオを、事実上、潰す決定を下したのだ。
Pandora最大の危機。全インターネット放送が潰れる新料率が決定される


▲サービスインから半年後の2006年1月。「タウンミーティングします」とblogで告知すると全米の都市から開催の依頼が殺到し、ウェスターグレンはヴァンで全米を走り回る毎日となった。このときにできあがった全米に拡がる国民との繋がりが、2007年に訪れた最大の危機を救うことになる
(Image)
2007年3月。それはいつもどおり通勤バスに乗り、会社へ向かっている途中の出来事だった。
ウェスターグレンは、ケータイでニュースを読んでいたが、ある記事に目を通した瞬間、眠気が吹き飛び、すぐに電話をかけはじめた。バスの中、物静かな彼に似つかわしくない取り乱しようだったが、正直それどころでなかった。ウェスターグレンは、受話器の向こうのケネディにまくし立てた。
ウェスターグレンの電話を受けてケネディもニュースを検索した。そこには、合衆国の行政機関であるコピーライト・ロイヤリティー・ボード(CRB)が、インターネット放送の楽曲使用料(パフォーミング・ライツ使用料 Performing rights fee)を値上げする決定を下した旨が述べられていた。
もともとインターネット放送の楽曲使用料は、1998年のDMCA(デジタルミレニアム著作権法)の制定時、暫定的に定められ、いずれ正式に決定されることになっていた。
暫定料率は、1曲再生するあたり平均0.075セント(約0.08円)。相場的には、インターネット放送局の売上の3分の1ぐらいに相当する料率だった。
これを政府公認の非営利組織SoundExchangeが、一括でインターネット放送から強制的に徴収する。
かわりに、インターネット放送はレコード会社やアーティストから楽曲使用の許諾を得ずとも、お金さえ払えばどの音楽を放送に使える自由を得た。
SoundExchangeのおかげで、アメリカでははやくから様々なインターネット放送が立ち上がり、その中からPandoraのような放送のイノヴェーションが発生した。
だが、このSoundExchangeの徴収する楽曲使用料が、今後4年間で0.19セントに引き上げられる、という。これまでの2.5倍にもなる金額だ。この金額を決定した法的機関が、先のコピーライト・ロイヤリティー・ボード(CRB)だった。
CRBは、2004年の著作権料分配改正法(CRDRA Copyright Royalty and Distribution Reform Act)によって設けられた行政機関で、政府が任命する3人の裁判官で構成された評議会だ。
当時、アメリカの代表的な大手ネットラジオには、Pandoraの他、Yahoo!ラジオ、Live365、RealNetworksそしてMTV online Radioなどがあったが、これら大手ネットラジオの売上のうち、楽曲使用料が占める割合は33%だった。
単純計算で、これを2.5倍にすると、売上の82.5%だ。しかもこの楽曲使用料(パフォーミング・ライツ使用料。Perfoming rights fee)に加えて、通常の著作権料(作詞作曲)も払わなくてならない。これで、放送局がやっていけるはずがなかった。
独立系ネットラジオに至っては、新料率は売上の300%に相当していた。
さらに、新しいルールではネット放送局の一局あたり、年間500ドル(約59,000円118円/ドル)の最低使用料を徴収する、という。
一見、大した金額には思われないだろう。
だが、リスナーひとりひとりが何十局もじぶんのカスタム放送局を創るPandoraのようなパーソナライズド放送に、これは致命的だった。10万人のリスナーがそれぞれ10局ずつカスタム放送局を創ったとしたら、100万局だ。毎年590億円を支払わなければならない。
無理だ。
5年後の現在、Pandoraのパーソナライズド放送は、アメリカを代表するプロダクトとなり、NYの株式市場で世界の投資家に売買されているが、このとき、政府機関のCRBは事実上、インターネットラジオすべてを潰しにかかった、といっていい。イノヴェーションの国、そしてメディア大国のアメリカらしからぬ行政判断だった。
ウェスターグレンだけでなく、インターネット放送をやっている全ての事業家が、その日、呻吟したことだろう。
「ビジネスが空中分解した。…そう思いました」
CEOのケネディは、オーナーのウェスターグレンから、衝撃の報道について聴いた瞬間をこう振り返る。
ウェスターグレンはバスを降り、駆け足でオフィスに入るとすぐに、緊急役員会議を開いた。会議は紛糾した。タカ派は、CRBの決定に対し、徹底的に争うべきだ、という。だが、CRBは政府の認定した裁判官が構成する評議会だ。まともに議論して勝ち目があるのだろうか。
ハト派は、CRBの料率を無視するために、SoundExchangeを使うのをやめればいい、と主張した。つまり、SoundExchangeを飛び越して、すべてのレーベルと個別に契約を結べばいい、というのだ。理屈では確かにその通りだ。SoundExchangeは、楽曲の権利者たるレーベルの代理機関にすぎない。
だが、プランBの実行は不可能だった。
「メジャー、インディーの区別や、シングル曲、アルバム曲の区別なく、すべての音楽に出会いの機会を与える」というウェスターグレンの創業の志に基づいて、6,000に及ぶレーベルからPandoraは放送する楽曲を集めていたからだ。6000社と個別に交渉する道は、マンパワーと時間の問題から、非現実的なオプションだった。
ウェスターグレンの下した決定は、すさまじかった。
まず、インターネット放送をやっている全ての会社を組織する。MTV、Yahoo!、AOL、RealNetworksなど大手だけでなく、全国に数百局あるすべてのインターネット放送をだ。そして、アメリカ全土にいるインターネット放送のリスナーをオルグする。全国なら数百万人はいける。そして、その数百万人をもって、ワシントンの議会を動かす。
つまり、市民革命の道だ。
「オーナーのプランも相当、非現実的だ」と思った役員たちもいただろう。ウェスターグレン自身もそう思っていたかもしれない。ただそれは、いつものことといえばいつものことであった。
とまれ、やるしかなかった。他に道がない。どんなに希望の光が細くとも、そこへ向かわなければPandoraは消滅する他なかった。
なぜアメリカではインターネット放送が数千と育ち、日本では育たないのか

▲Google本社でウェスターグレンの話を聴くGoogle社員たち。2007年、Google本社で開催されるビュッフェスタイルの名物イベント、Googleplexにウェスターグレンは招かれた。究極の楽曲データベースを創った話は検索のプロたちにも好評だったようだ(Image)
ここまで読んで来て、どうにも解せない気分になっておられる読者もいらっしゃるだろう。
「行政機関がなぜ、インターネットラジオを事実上、全て潰すような決定を下したのか。レコード業界がそう決定するならまだ分かるが」と。
実は、「CRBの決定は事実上、レコード業界のしかけたものだった」と申し上げても過言でない。SoundExchangeとCRBが創設された経緯を追っていると、中立的に見てもそういわざるをえない部分がある。
今後、我が国でも、インターネット放送の育成にあたり、アメリカの事例が参考に挙がるようになってくるだろう。
アメリカにはインターネット放送の楽曲使用料(パフォーミング・ライツ使用料。作詞作曲とは別)を一括して徴収するSoundExchange(サウンド・エクスチェンジ)という公的組織がある。だからアメリカなら、SoundExhcangeに楽曲使用料を払えば、誰でもインターネット放送が出来る。
これが、SoundExchangeという公的機関の明るい側面であることは間違いない。繰り返し参考事例に上がる箇所となるだろう。
一方、日本は各レーベルからCD音源の使用許諾を取らなければインターネット放送はできない (※)。とてもハードルが高いためPandoraのような新しい音楽放送が誕生せず、音楽業界の停滞の一因となっている。そう、申し上げた。
(※ JASRACはこの問題と事実上、無関係。連載第8回参照)
しかしSoundExchangeの徴収する楽曲使用料を決定しているCRBは、「米国議会の高邁な理想の元に誕生した」とは言い難い側面がある。そのため、SoundExchangeには組織的欠陥があり、それが2007年に起きた「法外な楽曲使用料」という混乱をもたらした。
スマートフォンの普及を機に、我が国でも、インターネットを活用した新しい放送の需要が、現実味を帯びてきた。今後、アメリカの行政を参考にしつつ、より優れた仕組みを創るためにも、ここでSoundExchangeやCRBが誕生した経緯を書き記しておきたい。
まず、話の焦点になっているパフォーミング・ライツのことだ。
パフォーミング・ライツというのは、作詞作曲とは別に与えられる権利で、主にCDやレコードを放送に使用したときに発生する。ざっくり言って、インターネット放送をやる場合、作詞作曲の著作権と、パフォーミング・ライツのふたつを処理しなければならない。
アメリカの経緯を振り返る前に、このパフォーミング・ライツが日本ではどうなっているか、おさらいしておこう。
アメリカのパフォーミング・ライツ(Performing Rights of Sound Recordings)だが、日本では「商業用レコードの二次使用」という形で扱われているものがそれに近い。日本では、番組・CMにCDの音源を使った放送局は、レコ協・芸団協に「二次使用料」を払わなくてはならない。これがレーベルと、所属事務所の加盟団体を通過して、ミュージシャンに分配されている。作詞作曲の著作権料とは別の権利だ。
ややこしいのだが、「商業用レコードの(放送での)二次使用」は作詞作曲のような著作権ではないが、原盤権のような著作隣接権にもあてはまらない扱いのようだ(※)。
(※ 2012年11月13日修正。元弁護士で現在コロンビア大学法科大学院生の赤羽根大輝様より「商業用レコードの二次利用は著作権にもあてはまりません」とご指摘をいただき反映した)
隣接権でないので、放送局が音楽を流すのを、レコード会社やアーティストは禁止する権利(排他権)はなく、使用料を請求する権利(請求権)だけがある。だから、放送局はインターネットのようにレコード会社に許諾を得なくとも、どのCDでも放送に流すことができる。あとで決まった料金を支払えばいい。JASRACの仕組みとほぼ同じだ。
問題なのは、インターネット放送の音楽利用は「商業用レコードの二次使用」に該当しないことだ。
だから、インターネット放送に関しては、放送局とレコ協・芸団協が創った枠組みを使うことができない。作詞作曲の著作権だけですまないので、JASRACやE-Licenseと一括交渉することも不可能だ。
排他権の働くCD音源(原盤権)をネットに送信する、ということはCD音源の送信可能化権を使わせてもらう、ということになる。そうすると、CD音源の権利者であるレコード会社すべてと契約交渉をしなければならないのだ。レコ協に参加しているレコード会社の数だけで35社もある。
そのため、日本では交渉が錯綜して時のみが経つばかりで、アメリカのようにPandoraのような革新的なプロダクトがなかなか出てこない。以上が、我が国におけるIP放送の現状である。
さて、次にアメリカだ(続く)。
(※2012年11月16日 Perforiming Rightsの直訳「演奏権」の表記を、「パフォーミング・ライツ」に統一。次回第29回の注を参照)
著者プロフィール
榎本 幹朗(えのもと・みきろう)

1974年、東京都生まれ。音楽配信の専門家。作家。京都精華大学講師。上智大学英文科中退。在学中からウェブ、映像の制作活動を続ける。2000年に音楽TV局スペースシャワーネットワークの子会社に入社し制作ディレクターに。ライブやフェスの同時送信を毎週手がけ、草創期から音楽ストリーミングの専門家となった。2003年ライブ時代を予見しチケット会社ぴあに移籍後、2005年YouTubeの登場とPandoraの人工知能に衝撃を受け独立。
2012年より『未来は音楽を連れてくる』を連載・刊行している。Spotify、Pandoraをドキュメンタリーとインフォグラフィックの技法を使って詳細に描き、 日本の音楽業界に新しいビジネスモデル、アクセスモデルを提示することになった。 音楽の産業史に詳しく、ラジオの登場でアメリカのレコード産業売上が25分の1になった歴史とインターネット登場時の類似点 や、ソニーやアップルが世界の音楽産業に与えた歴史的影響 を紹介し、経済界にも反響を得た。
寄稿先はYahoo!ニュース、Wired、文藝春秋、プレジデント、NewsPicksなど。取材協力は朝日新聞、Bloomberg、週刊ダイヤモンドなど。ゲスト出演はNHK、テレビ朝日、日本テレビなど。音楽配信、音楽レーベル、オーディオメーカー、広告代理店を顧客に持つコンサルタントとしても活動している 。
Facebook:http://www.facebook.com/mikyenomoto
Twitter:http://twitter.com/miky_e

広告・取材掲載