【前半】『ニッポンの編曲家』出版記念インタビュー「熱い音楽をどうやって作っていくか」 川瀬泰雄×吉田格
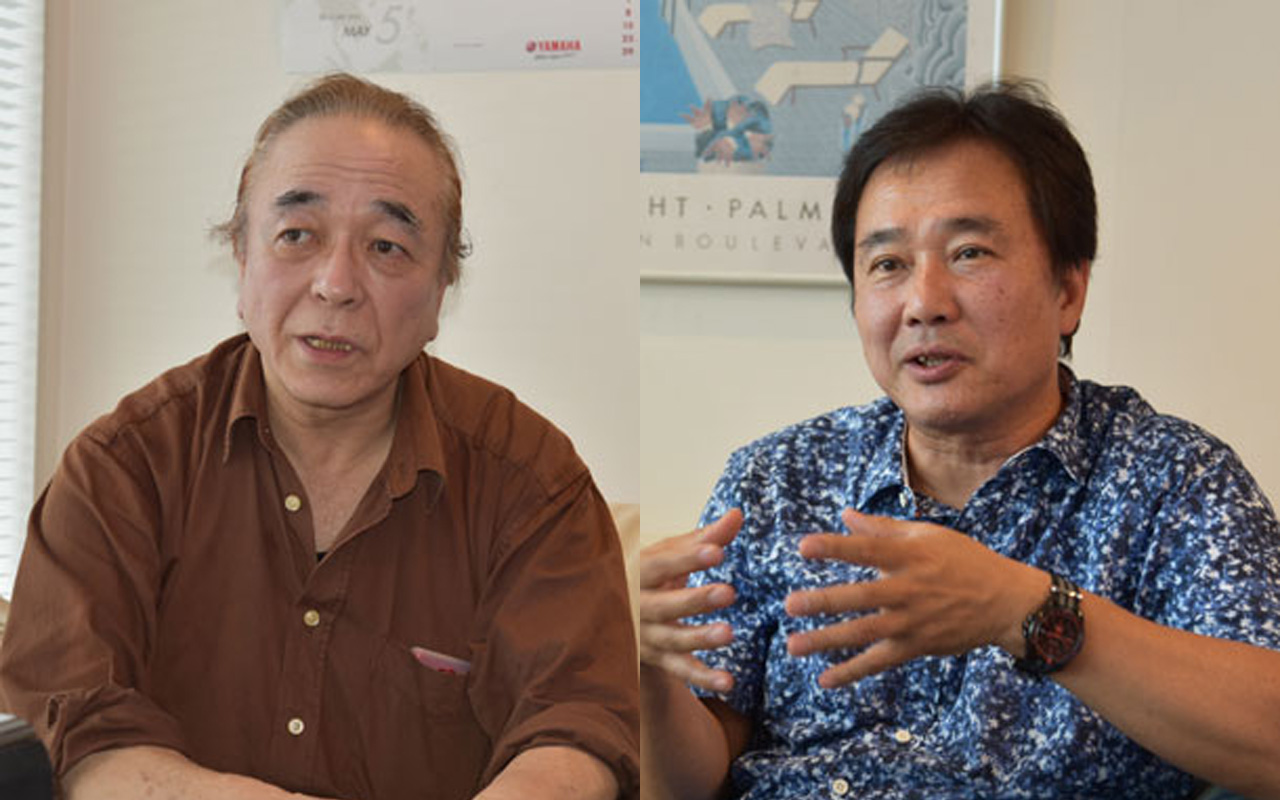
70〜80年代の活気に満ち溢れたレコーディング・スタジオで音と格闘を続けていた編曲家に焦点を絞り、たくさんの名楽曲を生んだ頭脳と、レコーディング時のエピソードに迫った書籍『ニッポンの編曲家』が話題だ。編曲家だけに留まらず制作ディレクターや、スタジオ・ミュージシャン、エンジニアの他、多方面から証言を収集した本書は、音楽業界人のみならず、業界を目指す若者やミュージシャン&エンジニアの卵、そして音楽ファンまで多くの人にとって興味深い内容になっている。Musicman-NETでは前後編に分け、著者インタビューを敢行。前編では川瀬泰雄さん・吉田格さんのインタビューをお送りする。
PROFILE
川瀬泰雄(かわせ・やすお)
1947年生まれ、神奈川県出身。大学を卒業後、東京音楽出版(ホリプロ)に入社。井上陽水、浜田省吾、山口百恵など、約40組の音楽プロデュースを担当。キティ・レコードに移籍後はH2O、岩城滉一など10数組、独立後は、松田聖子、岩崎宏美、裕木奈江などの音楽を制作。現在までに約1,600曲を手がけた。ビートルズ研究家としての顔も併せ持ち、『真実のビートルズ・サウンド』(学習研究社)、『プレイバック 制作ディレクター回想記 音楽「山口百恵」全軌跡』(学研教育出版)の著書もある。現在、音楽プロデュースの他、ビートルズやパブ・ロックなど、複数のバンド活動も行っている。
吉田格(よしだ・ただし)
1953年生まれ、奈良県出身。76年にCBS・ソニーに入社。78年より邦楽ディレクターとなり、SHOGUN、原田知世、To Be Continued、知念里奈らを担当。南野陽子ではオリコン8作連続1位を記録。郷ひろみを「GOLDFINGER’99」で再ブレイクさせた他、2002年からはソニー・ミュージックダイレクトにて山口百恵のトリビュート・アルバムや、太田裕美、大貫妙子、尾崎亜美、五輪真弓らを手がけた。アラフォー・アイドル“Blooming Girls”(南野陽子、森口博子、西村知美)のプロジェクトも彼の手による。現在はSpring Tune Inc.にて作家マネージメントや音楽制作を中心に動き出している。

『ニッポンの編曲家 歌謡曲/ニューミュージック時代を支えたアレンジャーたち』
著者:川瀬泰雄+吉田格+梶田昌史+田渕浩久
2016年3月発売
A5 / 336ページ / 並製
2,484円(税込)
DU BOOKS / 9784907583798 / JPN
Amazon/DU BOOKS
1.
——先日、発売された『ニッポンの編曲家』を読ませていただきまして、この業界の若い人たちにも、ぜひこの本を手に取ってもらいたい、こういう時代があったということを広くお伝えしたい、という想いから今回インタビューをさせていただくことになりました。まず、本を出すきっかけはなんだったんでしょうか?
川瀬:僕は2年半ほどラジオ日本で『川瀬泰雄のオトナジカン』という番組のパーソナリティをやっていたんですね。その番組で、昔、仲間だったミュージシャンやアレンジャー、作詞家・作曲家たち裏方をゲストで呼んでいたんですよ。アーティストも井上陽水さんが出演してから多くの方々が出てくれるようになりました。その番組の中で、しょっちゅう「当時のレコーディング現場は熱かったよね」という話になるんですよ。それで、ゲストの話をまとめた本を書こうかと思っていた矢先、(吉田)格さんがゲスト出演したときに、格さんもアレンジャーの本を出したいという考えを持っていたということがわかり、「じゃあ一緒にやろうよ」ということになりました。
——番組はいつ頃まで放送していたんですか?
川瀬:2014年の10月までです。
——わりと最近まで放送していたんですね。
川瀬:全部で125回くらい放送したんですが、スポンサーがついてない番組だったので、自分で電話して、「出てくれない?」と出演交渉をして、ゲストの全員がノーギャラで出てくれたんです。ミュージシャン仲間だった柳田ヒロさん、そこからバズの東郷(昌和)さん、ガロの大野(真澄)さんも出たし、星勝さんも昔から仲間だったので呼んだんですよ。その星さんとの放送を井上陽水さんが聴いていて「面白かったから僕も出してよ」って言ってくれて(笑)。ディレクター仲間だった小栗(俊雄)さんとか、酒井(政利)さん、松崎(澄夫)さんにも出てもらいましたよ。最初は半年程度の予定だったのが、ゲストがすごいから、あと半年、あと半年とやっているうちに2年半続いちゃって。
——何分番組なんですか?
川瀬:30分ですね。だいたい2週にまたがっていました。陽水さんのときなんて4時間くらい喋りっぱなしだったから、2週分でも、すごく余っちゃって(笑)。
——途中、曲もかけたりするんですか?
川瀬:もちろんかけます。僕はビートルズ・マニアで、ビートルズのカバー・バージョンをたぶん6,000曲くらい持っているんですよ。ビートルズって公式にリリースした213曲全曲でカバーが出ていて、一度、ビートルズのリリース順にカバーだけでアルバムを作ったら、本当に超一流のアーティストばかりのものすごい作品が出来ちゃったんですよ。レイ・チャールズが出てきたり、セリーヌ・ディオンが出てきたりするわけですから。これを本当にリリースしたいな、と思って何カ所か回ったんですが全滅でした。というのも、そのあたりに関してはレコード会社には色々な協定があるんですよ。だったらラジオをリスナーが録音するのは勝手だから、全部録音すると面白いものが出来るよと必ず1曲かけていたんです。それは番組が始まってから終わるまでずっと持っていたテーマでしたね。あとはゲストに応じて2〜3曲とトーク。たぶん格さんが出演したときは南野陽子をかけたのかな。
吉田:そうですね。あと自分のお気に入りの1〜2曲とビートルズでしたね。
川瀬:そのときに、昔の話になると、みんなそれぞれ熱く語るわけですよ。今はパッケージのセールスが落ち込み気味になっちゃって面白くないな、みたいな話にもなって。それであの時代の熱を本という形にしたいなと思ったわけです。
——書籍として残したいと。
川瀬:今の若い人たちって引き出しが少ないな、と思ったんですよね。僕より20歳くらい若いミュージシャンと一緒に仕事をしたとき、20歳若いと言っても40代後半くらいになっちゃうんだけど、その人たちですら打ち込みがメインだから、1人にアレンジを任せると、シュっとまとまっちゃうんですよ。僕たちみたいなのが横にいて、アドバイスすると一気に広がったものができるんだけど、何回かそういうことがあって、ミュージシャンたちがバトルをしながら曲を作っていた時代を知らないまま育っちゃっているんだなって思ったんですよ。
——1人のイメージの中だけで曲を作っちゃう?
川瀬:ポール・マッカートニーも、ビートルズが解散してすぐに、1人で全楽器を演奏して、歌も入れて作ったら、やっぱり小さくまとまった作品ができたじゃないですか。別にあれはあれでいいんですが、ポールですら、そこに陥っちゃうんですよね。だから、いかにミュージシャン同士のバトルが大事なのか、そこに僕たちがオブザーバーみたいに入って、一つテーマを与えると、またそれでアイデアが生まれる。そうやってみんな同じところに向かってやってきたからこそ、良いものに仕上がっていったんだなと再認識したんです。
——その時代の熱気をもう一度伝えたい?
川瀬:そうですね。何が大きく違うのかを伝えたいですね。ミュージシャン自体は変わりませんから。ただ、みんなが共通して言うのは予算の問題がそうさせてくれないんだというところですけどね。
吉田:予算の問題はかなり影響していると思いますよ。
——感覚としては当時使っていた予算と、今一曲に充てられている予算はどれくらいの差があるんでしょうか?
川瀬:ゼロひとつ違うかもわからないですね。5分の1から10分の1という。
吉田:僕がやっていた当時のシングルAB面で、大体350万から400万くらいの予算だったんですよ。でも今は10曲、12曲くらいのアルバムが400万くらいなので、もう極端に違いますよね。
——1曲あたり200万かけていた時代から、今は1曲40万ですか…。
川瀬:40万でも高いですけどね。山口百恵さんなんかが売れてきたとき、例えばシングルでオケを録るじゃないですか。その後、ちょっと歌を入れて「違うな」と思ったら、別アレンジでオケを録り直したりするわけですよ。そしたら、シングル1枚で600万、700万に平気でなっちゃうんですよね。そういうのが許された時代だったんですけど、今、その金額だったら完全にアルバムの値段です。
吉田:逆に言えば、コンピューターでいくらでもやり直しが利くっていうのもありますけどね。ミュージシャンが集まって、せーのでリズムを録って、そこにオーバーダブで弦が入ったりブラスが入ったりコーラスの人を呼んでみたいなことは今はまずないですから。
——そんな贅沢している人はめったにいないですよね。
吉田:売れている方は当然、今でもやっているんでしょうけどね。
川瀬:バンドだったらミュージシャン代もかからないし、セッションで合わせて熱いものが作れるんだけど、普通のアイドルみたいな作品だと、作詞、作曲、アレンジ、全部他人にお任せになるじゃないですか。そういう人たちはそんなことやって作っていられないですからね。
2.

——予算がなくなることで楽曲のクオリティが下がり、CDが売れなくなり、録音物がビジネスにならなくなってしまったと…?
川瀬:もちろんそれだけが原因じゃないですが、予算がないことで楽曲が小さくまとまっちゃうから、どんどんファンも離れて行った面もありますよね。もう一つの原因は洋楽を聴かなくなったことですよ。何年か前から、売れているアーティストはAKB48とかモーニング娘。で、日本国内だけで売れていく。でも、世界からしたら「それしかないの?」っていう感じじゃないですか。世界中の色んなジャンルの音楽を知らないまま育っちゃって、こんな世界でいいのか?となっちゃうわけですよ。
——ますますドメスティックというか、内向きの作り方になっていっているんですね。
川瀬:まだ、K-POPのほうが世界を見ていますから見込みがありますよね。東南アジアに進出したりスケールが違うじゃないですか。お金のかけ方も違うし、育て方も3〜4年ずっと練習だけやらせて、残った人たちがやるからすごく洗練されているんですよ。
吉田:作曲家も作詞家もそうでしたけど、みんな当時は若い才能を育てていましたよね。作家さんの事務所でコンペがあったりしながら、今回この作詞家さんとやって良ければ次に繋がるし。みんな一生懸命、上を向いていた。今はもう作詞家っていう職業がなくなっている気がするんですよね。作詞家だけでは食えないですし。作曲の人もアニメかコマーシャルで多少はやっているんだけど、本当に若い作曲家で「いいのが出てきたね」っていうのはいないですからね。それも含めて我々のような、メーカーのディレクターもいなくなっている時代ですし、いろんなものが消滅して、育っていくというフィールドがもうないですよね。ひょっとしたら、他の世界も同じなのかもしれませんが、それが余計、音楽離れ、洋楽離れになってしまいます。
——この本の時代は凄かったということは誰しもが認めるところですし、理想的な音楽の作り方ができていた時代だと思うんですよ。でも、現実に「じゃあ。今からどうしたらいいんだ?」というのが誰も答えを見いだせていないですよね。ライブをやっているミュージシャンはどうなんでしょうか?
吉田:ライブはライブで絶対なくならないものじゃないですか。今までスタジオでやっていた人たちが、時代の変化と共(とも)に仕事が減少して、ライブに移ってきているというのもあるんですが、全員ベテランの一流ミュージシャンがやっていて、若い人がきてもあまり出番がなくなっていますよね。少しずつ変わってはいるんですけど。
——プレイヤー寿命が長いですよね。
吉田:僕たちと同年代の方が未だに現役でやっているわけですからね。でも、そこに若い人たちが自力で入ってくるしかないんです。いつの時代もそういう競争ってあったわけですしね。ギターやサックスのような微妙なタッチで全然音が違っちゃう楽器は、やっぱり生でやるべきですし、打ち込みがベースだったとしても、そういうのが混ざってくれば、熱さも伝わってくると思うんです。安上がりだから全部打ち込みでやろう、ということ自体が音楽じゃないよなって気がするんですよね。
——バックミュージシャンの競争率の高さも、若いミュージシャンが場数を踏めない、成長できない理由ですよね。
吉田:自身がライブ活動しない間にメンバーが散り散りになった事もあり、山下達郎さんは 積極的に若いミュージシャンを入れていますけどね。ドラムの小笠原(拓海)くんは、達郎さんのレパートリーを毎年ずっと特訓していて、200何曲あるんだけど、8割方叩けるようになったって言っていました。彼は本当に上手くなっています。サックスの宮里陽太くんも若いですし、達郎さんがミュージシャンを育てているんですよね。宮里くんは「エグゼクティブプロデューサー:山下達郎」でアルバム作ったりしていますし、佐橋(佳幸)くんも自分の作品のドラムは小笠原くんにお願いしたりしています。だから、そういった交流を見てると、まだ捨てたもんじゃないなと思うんですよ。今はCDが売れなくてもコンサートやっている人はいますからね。そこで、新たなミュージシャンが育ってくるというのはあるのかなって気はしますね。
川瀬:逆に言うとそれしかないんですよ。若い人でも上手い人は入ってきましたよね。当時、スタジオ・ミュージシャンは1回認知されると、ものすごい仕事の量になるわけですよ。
——ミュージシャン同士の横の繋がりで仕事が回っていましたよね。
川瀬:スタジオ・ミュージシャンで同じ力量の人はいっぱいいたけど、人間関係が上手くできなくて仕事ができなかったってミュージシャンもいますよね。
吉田:人間関係で仕事が決まることが多かったですからね。技量はみんなすごかったけど。あの頃って、アレンジャー同士のネットワークが強くて、隣のスタジオで誰がやっているとか、誰が良かったっていう情報交換ができていて、人づてで仕事が増えていきましたよね。アレンジャーの人たちもそうですから。コーラスの広谷順子さんの、あの頃のスケジュール帳を拝見させてもらったら、すごかったですね。もう、毎日真っ黒で。
川瀬:一番乗っているときに、みんながそうさせちゃったのがいけないんだけど、ダビング1回するごとに同じ金額とるみたいなことになって。例えば、アメリカなんかだったら、1セッションいくらだから、その時間内ならどうダビングしたって変わらないじゃないですか。
——日本では3回ダビングしたから3倍みたいな。
吉田:バブルというか、潤沢でしたよね。
——キーボードとシンセとかスタジオに積み上げるのが1台いくらみたいな時代もありましたし。
川瀬:ギタリストもギターとかアンプのレンタル料を請求していましたよね。バイオリニストはバイオリン代請求してこないのに。バイオリニストは可哀想だったな。家買うかバイオリン買うか迷うくらいの高いもの使ったりするのに、かたや、10万くらいのベース持ってきてベース代請求して、そんな馬鹿な、と思いましたね(笑)。
——何となくまかり通っていましたね。
川瀬:「楽器だったら、俺が持ってきたやつを貸してやるよ」って言いたいくらいでしたよね(笑)。
3.

——当時、すでに海外レコーディングもされてましたよね。
吉田:そうですね。たまたまロンドンレコーディングのときに山田直樹くんってエンジニアが、「海外のエンジニアのレコーディングを見たい」って言ってついてきて、僕らのセッションやっているとき以外もずっとスタジオにいたんですよ。それで帰国したら全然レベルが上がっていましたね。それから、エンジニアの藁谷(義徳)くんもついて来て、帰ってきてからユーミンの専属になっています。エンジニアも海外を見ると見ないとじゃ、吸収力が全然違うんだなと思って。
川瀬:最初にアメリカに行ったとき、エンジニアもミュージシャンなんだなと思いました。メーターを振り切るからダメとか言う人は一人もいないんですよ。ドラムのセッティングを見ても、バスドラの前にめちゃくちゃ古い過去の遺物みたいなマイクを置くわけです。今度はハイハットのところに小さい細いマイクがあって、場所によってマイクが全部違うんですよ。日本では全部同じのを使っていたのに。そのときに全然発想が違うなって思ったんですよね。
吉田:エフェクターの使い方も全く違いますよね。海外は1個のエフェクターを120%使おうとするんだけど、日本のエンジニアって、スマホなんかと一緒で色んな機能はあるけど、一部しか使ってない。彼らは100%以上、さらにどうしたら面白くなるか、みたいな考え方なんですよ。あれはすごかったですね。まずモノラルで聴いていい音か確かめるんですね。それから、スタジオの入り口とかセンターとか端っことか裏側に行っても同じ音に聴こえるかチェックして。そのとき「日本でもラジオで音楽が流れるだろ? 1個のスピーカーでどう聴こえるかも、大事にしたほうがいいんじゃない?」って言われて。ああ、そういう感覚でトラックダウンするんだ、って驚きましたね。
川瀬:だから、帰ってきてみんなカセットに落として聴き始めたじゃない?
——あれは海外の影響なんですか。
川瀬:そうですね。オーラトーンっていう小さなスピーカーをカセットで鳴らして、全部の音が聴こえるかとか、バランスを聴いて、全部聴こえたからでかいのでやろうっていうことを、何度もやっていましたね。
吉田:一番いいのは車の中で聴いたときに心地良いかどうかだから、カセットに録って、車の中行って、駐車場で聴いて確かめて。大瀧(詠一)さんもそうしていました。
——打ち込みをするのでも、音楽を知ってするのと知らないでするのとでは全く違いますよね。あの時代に戻ろうと言っても戻れないけど、音楽から吸収することはできるはずなので、目一杯音楽を聴き込んだ素養を元に、本物に近づける打ち込みをするとか、そういった方法でも広げていってほしいですよね。
川瀬:例えばストリングスのアレンジも、ただコードを弾くんじゃなくて、コントラバスからちゃんとアレンジしていけば、打ち込みでもそれなりのサウンドになるんですよね。それこそ、亡くなった冨田勲さんは、それだけでオーケストラを作ったわけだから。そういうところまで、細かく作っていけばそれなりのサウンドになるんですよ。以前、ストリングス・アレンジのスコアを萩田(光雄)さんに書いてもらったんですよ。萩田さんも面白がって。ストリングス全部1本1本聴いてくれて、それを打ち込みでやったんですね。そしたら、本物のストリングスみたいに聴こえてくるんですね。こうやれば十分いけるじゃないって。
今までコードでごまかしていたと思うんですね。だからアレンジャーもきちんとアレンジして打ち込んでいけばいいんですよ。若いミュージシャンがそういうことやらなかったら、すでに当時の人たちに負けていますよ。当時のミュージシャンと十分戦えるくらいの技量をつけていかなかったら、やっぱり古い人たちを抜くことはできないですよね。すでにアメリカなんかだと、打ち込みは一つのジャンルとしてあるんだけど、やっぱりミュージシャンが活躍しているじゃないですか。
吉田:打ち込みが主流になってもミュージシャンが出てこられる場所もあるってことですね。
——一流の人は60代になっても変わらず第一線でやれているじゃないですか。ミュージシャンもエンジニアも。
吉田:その年代は大活躍ですよね。いい音出してくれるし、引き出しがいっぱいありますからね。
川瀬:その頃のディレクターって、たぶんエンジニアよりいろんな音楽を聴いて勉強していたじゃないですか。「こういう音が欲しいんだよ」と言えば、そのエンジニアもまたそこから勉強する。毎日そういう戦いだった気がしますよね。
——もしお二人が今20歳だったとして、音楽制作するならどうしていると思いますか?
川瀬:僕は本当に音楽が好きなので、まず、仲間でバンドを作ってやっているでしょうね。それで食っていくという発想じゃなくて、コンビニでバイトしながらでもやっていたと思いますよね(笑)。
吉田:今そういう問われ方をしたら僕も川瀬さんと同じように、許される限り自分が納得するものを面白おかしく作っていると思います。無駄な時間であっても、自分が納得できるものを送り出したいし、そうでないと、自分が消化不良になっちゃいます。当時もそうだったから、ここに至っているんだと思いますけどね。
4.

——一緒にこの本を書かれた梶田さんは、中学生の頃から裏方のミュージシャンに興味を持っていたそうですね。
川瀬:彼は、日本テレビの局員なんです。最初はYMOのファンから入って、そこからスタジオ・ミュージシャンに興味を持って、島村英二さんのドラムにはまって、島ちゃんの追っかけみたいになって。
——スタジオ・ミュージシャンのおっかけが存在していたんですね。
吉田:珍しいですよね。しかも、中学くらいから島ちゃんも公認で、スタジオに遊びおいでって言うので、島ちゃんのスタジオで色んなミュージシャンを知って、自分でメモするようになって。シングル盤とかに何もクレジットがない頃から、「このアレンジは○○さんだ」「このドラマーは○○さんだ」みたいなことをずっとやっていたんですよ。
——そういう経歴をお持ちの方は見たことがないです。
川瀬:彼と出会ったのは、僕がラジオをやっていたときなんですけど、ラジオ日本って日本テレビグループなんです。当時、日テレから来たラジオ日本の編成局次長の倉林由男さんから、「部下にものすごいスタジオ・ミュージシャンマニアがいるから川瀬さんに連絡させてもいいか?」って聞かれて、「いいですよ」って言ったら電話がかかってきて、会うことになって。それで色々話を聞いてみると本当にミュージシャンに詳しいんですよ。ストリングスだとか、コーラスだとか、スターみたいな活動をしてないようなミュージシャンにも興味を持っていて。
——業界側の川瀬さんみたいな方が語れるのはわかりますけど、そうじゃない人がここまでと。
川瀬:そうなんです。ですから、格さんと2人でこの本を作ろうと思ったときに、声をかけたんですよ。
吉田:本人は編曲家本というよりミュージシャンの履歴の本を作りたかったようなんですが、一人では無理ですし、ここに相乗りさせてもらって、自分のページを下さい、みたいなところで思惑が一致して。われわれも当然、ミュージシャンのページが増えるならいいんじゃないかということで、一緒にやることになりました。彼が凄いのは、島ちゃんが参加したものは、何を聴いてもわかるんですよ。ミュージシャンは必ずそうらしいんですけど、自分の足跡っていうかクセを残すって言うんですよね。
——そんなにミュージシャンが好きなのに音楽業界には入らなかったんですね。
吉田:あえて業界に入らなかったってことですよね。入っちゃうと好きなことができないので。
川瀬:それと、親しいミュージシャンから「入るな」って言われたそうです。放送局の社員で仕事をした方が良いからって。
——梶田さんが誰も興味を持たないようなことを細かく記録していたのが、今となっては役に立ったということですよね。弾いた本人も忘れているわけですよね。M1、M2って順番に弾いているだけで、誰の何を弾いたかも覚えてないみたいな時代ですよね。
川瀬:よくミュージシャンに「これって俺が弾いたやつだっけ?」って言われましたよ。
——お二人も自分が作ったものはわかっても、人が作ったものは全然わからないですよね。
川瀬:自分で作ったものだって、タレント3人、4人同時に進行していくじゃないですか。どのアレンジャーでどのミュージシャン使ったかまでなかなか覚えてないですよ。
——しかも10年、20年経ったらわからないですよね。
川瀬:下手すりゃ1週間経ったらわからないですよ(笑)。
——それを全て記録していた男ってことですね。素晴らしいですね! 彼の存在なくしてこの本は誕生していなかった。
川瀬:それもインペグに電話して聞いたりしたって言うんだから、もうマニアもいいところですよね。僕たちもクレジットするようになって初めて、インペグに「あのときのギター誰だっけ?」って聞くようになるくらいで、それまではクレジットする習慣がなかったですからね。
——改めて、この本はどのような人に読んでもらいたいとお考えですか?
吉田:専門学校や音楽大学でアレンジを勉強している方、ミュージシャンやエンジニアを目指す方にも読んでもらいたいですね。そして、一つのものを作るための連携みたいなものを感じ取ってもらいたいなって思います。部屋で1人で作る音楽も、それはそれでいいものがあるんだろうけど、音楽は、作詞家、作曲家、編曲家がいて、そこに歌が乗っかって、それに対してミュージシャンが演奏して、その複合体の良さみたいなところをちゃんと感じてもらって、彼らにも体現してもらえたら嬉しいですね。
——最後に、このインタビューを読んでいる学生さんや業界関係者の方にメッセージをお願いします。
川瀬:結局この本で何を伝えたいかと言うと、昔に戻るということではなくて、熱い音楽をどうやって作っていくかがテーマなんですね。
——熱を持った若者に出てきてほしい、ということですか?
吉田:そうですね。僕はアイドル系をよくやっていましたが、斉藤由貴さんや薬師丸ひろ子さんがライバルだったんですよ。ライバルがいて、向こうがこの作詞家を使ったら、あえて違う作家を使っていた。素人でもバトルしながらコンペさせてもらって、そこから亀田(誠治)くんのようなすごい作家とかアレンジャーも出てきたりして。そういうフィールドを僕も作っていたし、彼らものし上がりたいという気持ちを持っていた。やっぱり残るものってみんなが熱を持って作ったものだと思うんですよ。
川瀬:でも今は妙に冷めちゃっている気がして。なにか目標があれば熱くなれるだろうし、音楽にもっと魅力を感じてほしいと思っています。

広告・取材掲載