第51回 糟谷 銑司 氏 株式会社アイアールシートゥコーポレーション 代表取締役
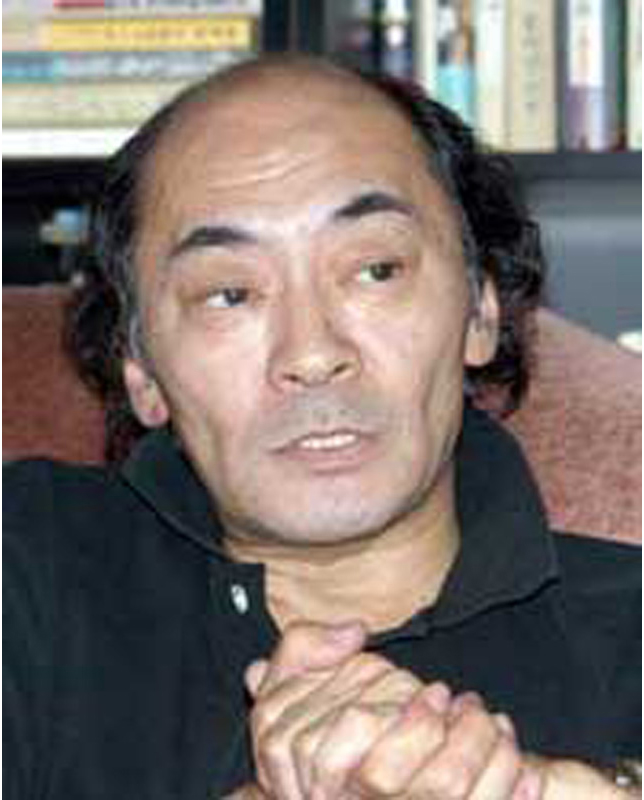
株式会社アイアールシートゥコーポレーション 代表取締役/ 社団法人音楽制作者連盟 理事長
中村伊知哉氏の紹介で、今回ご登場頂いたのは、株式会社アイアールシートゥコーポレーション 代表取締役/ (社)音楽制作者連盟 理事長 糟谷銑司氏です。
ユイ音楽工房時代は長渕剛やBOφWYをビッグスターに育てられ、アイアールシートゥコーポレーション設立後も布袋寅泰や今井美樹との仕事で輝かしい実績をあげられている糟谷氏。そのご経歴を伺うと共に、現在、(社)音楽制作者連盟 理事長として、音楽業界の発展のために尽力されているお立場から、業界が直面する問題や、今後の課題について伺いました。
プロフィール
糟谷 銑司 (かすや・せんじ)
株式会社アイアールシートゥコーポレーション 代表取締役/社団法人音楽制作者連盟 理事長
昭和24年9月22日生 愛知県岡崎市出身
昭和50年11月 株式会社ユイ音楽工房入社
昭和52年 3月 明治大学経営学部中退
昭和63年 3月 株式会社アイアールシートゥコーポレーション設立
代表取締役就任
平成 3年 3月 株式会社アイアールシートゥスタジオ設立
代表取締役就任
平成10年 2月 有限会社ヘールボップ設立 代表取締役就任
平成15年 7月 社団法人音楽制作者連盟 理事長就任
- 突如、運動神経に目覚めた少年時代
- ビートルズの衝撃と映画三昧の日々
- 暗中模索の大学時代
- 入社4年目の転機〜長渕 剛との出会い
- 前例のない東京ドーム公演〜BOφWYの大成功
- 夢を与えるスーパースターが生まれる環境を作りたい!
1. 突如、運動神経に目覚めた少年時代
--まず最初に、前回ご登場頂いた中村伊知哉さんとのご関係を伺いたいのですが。
糟谷:音楽制作者連盟(以下 音制連)は、我々の主張や考え方を政府・行政に理解して頂くための研究と、音楽ビジネスや実演家の権利に対して音制連が権利者の一人としてどう考えているのか、広くプロパガンダしていくために総合研究所を作ったのですが、その所長に中村さんが任命されたわけです。ですから中村さんとは、もう5、6年のお付き合いですね。
総合研究所ができた当時、僕も音楽ビジネスの行方について、非常に興味がありました。例えば、20年前の音楽業界は今よりもシンプルで、もうちょっと手数が少なかったので、数年先の予測がしやすかったんですね。また、我々も無名であったし、若々しいといいますか、僕も含めて音楽業界全体が活気に満ち溢れていた時代でしたから、先の時代に対して夢を見られたんです。
しかし、ここに来てミュージック・ビジネスも複雑になり、音楽出版社とレコード会社とプロダクションが手に手を携えて、同じところへ向かうというわけには、なかなかいかない部分も出てきています。そういった非常にわかりにくくなりつつあった時代と、音楽配信などに代表されるメディアの多様化によって、音楽ビジネスは将来どのようになっていくのかを考える上で、知識がないと何もできないのではないか? という思いがだんだん出てきまして、そのための研究所であり、中村さんだったわけです。
--つまり中村さんは、シンクタンクのブレーンだったわけですね。
糟谷:そうです。2年前に僕が音制連の理事長に就任したときに、新しいミッションを中村さんと一緒に考えました。中村さんの人脈や物の考え方に素晴らしいものがありますし、情報通信の世界がどのような考えのもとに今日に至っているのか? 間違っていなかったのか? これからどうなっていくのか? ということに対して、適切なジャッジメントを頂けるので、非常に感心している次第です。
なおかつ彼は大学時代にミュージシャンをやっていて、僕らスタッフとも同じような体温がありますから、話が合うんですね。ですから、ミーティングをしても食事をしても話は尽きないです。そこで話すテーマは、音楽業界の将来の事だけでなく多岐に渡るんですが、彼と話すのは非常に面白くて、ためになります。また、我々の提案に対する理解力も素晴らしいので、音制連として大変信頼しているブレーンの一人です。
--では、ここからは糟谷さんご自身のことをお伺いしたいと思います。まず、ご出身はどちらですか?

糟谷:愛知県の岡崎市です。
--家族構成は?
糟谷:両親と父方の祖母、母方の祖父、妹2人と僕、あと母の弟2人の9人が岡崎の下町の小さな家に同居していました。ですから、いつも家には誰かしら人がいる生活でした。
--まさに昭和の大家族ですね。
糟谷:今から考えればそうですね。収入は父の稼ぎだけですから、家も小さかったですし、不自由なこともたくさんあったのですが、人間的な暖かみは多かったですね。
--糟谷さんはどのような少年だったのですか?
糟谷:体も大きくなく、痩せていて、どちらかというと体は弱い子供でした。よく風邪をひいたり、かけっこをしても一番ビリ、草野球をやってもライト8番みたいな感じでしたね。草野球をするときは、腕力の強い奴がジャンケンでメンバーをとっていくわけですが、僕の場合は一番最後まで残されて、負けた方が僕を取るんですよ(笑)。打てない、守れない、走れないというどんくさい少年でした。
--勉強の方はどうでしたか?
糟谷:勉強は草野球に集まっていた悪ガキの中では、一番できた気がします。だから余計いじめられました(笑)。ただ、小学6年生くらいから急に運動神経が目覚めたんですよ。
--そういうことってあるんですか。
糟谷:例えば、昨日まではドッチボールをやっても、一番最初にぶつけられて、最後まで外にいる感じだったのですが、誰かが投げた球を無我夢中で受け取ったのを境にガラリと変わりました。
--その時に何かが目覚めたと。
糟谷:きっとそうなんでしょうね。その時は周りから「おー」と歓声があがりました(笑)。次の日から、かけっこはクラスで一番早くなりましたし、草野球をやっても、ピッチャーで4番になって、マラソンをやっても校内で2、3番くらいになりましたからね。
--そんなことってあるんですね。やはりその日を境に性格も変わっていきましたか?
糟谷:そうですね。もともと誰かに付いて歩くのは、好きではなかったのですが、物事に対して自分から率先してやるようになったと思います。
2. ビートルズの衝撃と映画三昧の日々
--音楽との出会いはいつ頃だったのですか?

糟谷:中学ですね。やはり一番衝撃を受けたのは、中学校に入ったときにデビューしたビートルズです。近所の兄貴分はベンチャーズを聞いていたり、石原裕次郎がヒーローだった時代ですね。
--その当時は何か楽器を演奏されていたんですか?
糟谷:中学校ではブラスバンドでトランペットをやっていました。でも、全然上手くなかったので、一番末席で演奏をしていただけなんですが、たまたまトランペットのパートに2年生がいなくて、3年生4人と1年生が2人という構成でした。僕が下手だったから余計そう思ったのかもしれませんが、3年生はとっても演奏が上手い人たちだったんですね。なので、その人達の後をついていっただけなんですが、1年後にその人たちは卒業してしまったわけですよ(笑)。そうすると僕らがやらなくてはいけないのに、全然できない(笑)。
--先輩たちのやっていたことができないと(笑)。
糟谷:それでブラスバンドのキャプテンが「このままだと形にならない」と、春休みに朝から晩まで学校へ行って、猛特訓を受けました。それで練習が終わってから、家に帰ってビートルズのレコードを聞いたりしていましたから、今から考えるとあそこまで音楽漬けになったのは、あの時期しかないですね(笑)。
--(笑) やはりビートルズの存在は大きいですか?
糟谷:ビートルズは一発で気に入りましたね。周りにはベンチャーズとか色々流れていたんですが、とにかくビートルズの衝撃がすごかったですね。
--まさにビートルズ世代ですね。
糟谷:そうです。あの頃、ブラスバンドはともかく、音楽を聴いている奴は不良でしたからね。映画観ている奴も不良です。先ほども話に出ましたが、母の下の弟が高校をすぐに辞めて、職を転々としていたんですが、最終的に映画館に拾われたんです。なので僕は小学校4年から高校を卒業するまで、その映画館で毎週タダで映画を観ていました。この話をすると、よく「“ニュー・シネマ・パラダイス”みたいですね」と言われるんですが、全く同じような感じでしたね。
もちろん高校に入ってからもブラスバンドをやっていたんですが、しばらくして「自分はブラスバンドのメンバーとして、そんなに上手くない」ということはすぐにわかるわけです(笑)。中学校の時は誰もいなかったので、特訓されて半分リーダーみたいなかたちで頑張っていたんですが、高校になると近隣の中学から上手い奴が集まってきますから、「これはもう駄目だな」と思いました。その頃は音楽よりも映画の方が好きでしたし、心の中のどこかで「映画監督になりたい」と思っていました。
--その当時は、どのような映画をご覧になっていたんですか?
糟谷:通っていた映画館は洋画館だったので、洋画を観ていました。もちろんアメリカ映画もあったんですが、どういうわけか、あの頃はフランス映画やイタリア映画といったヨーロッパの映画が多かったですね。
話は少しずれますが、僕が大学生の頃に、小田急ハルクの裏の名画座でチャップリンの大特集を1日5本立てで2週間やっていたんですが、朝一で行って、5本全部見て、次の日もというようなことを2週間ずっと繰り返していました。それで、その時に観た映画の半分以上は一度観たことのある映画でしたから、多分岡崎にいるときに観ていたんでしょうね。
--まさに映画少年ですね。
糟谷:個人的には映画少年です。ブラスバンドも高校2年になった頃に、周りに上手い奴がいたのと、新しく入ってきた後輩の中にもっと上手い奴がいて、「ここにいてもしょうがないな」と思い、辞めてしまいましたから。
--プレイヤーとしての道はそこで諦められたわけですね。
糟谷:ちっとも上手くなかったですし、やっていて全然楽しめなかったですからね。
--そこまで映画を観ている少年は、岡崎という地方都市には、糟谷さん以外にいませんよね?
糟谷:映画館のせがれ以外では、なかなかいないでしょうね(笑)。
--一番多感な思春期に、洋画からものすごく影響を受けられているわけですよね?
糟谷:ええ。子供が観ちゃいけないと言われている映画もありましたしね。そういった映画は客席で観ていると通報されて補導員に捕まってしまうので、イタリアのお色気映画なんかは、いつも映写室から観ていました(笑)。
--でも、いくら叔父さんが映画館に勤めていても、映画自体が嫌いだったら行きませんものね。
糟谷:最初に父が映画館へ連れて行ってくれたときは、映画館の空気で頭が痛くなったんですね。その頃はもしかしたら嫌々連れられて行っていたのかもしれませんが、中学校に入ってからは一人で率先して行くようになりました。僕の両親は、家で音楽を聴いていると「勉強しろ! 音楽なんか聴いているんじゃない!」と怒りましたけど、映画だけは何も言いませんでしたね。
--それは恵まれた環境ですね。
糟谷:おそらくなんですが、音楽を聴いていると「レコードが欲しい」って、金がかかるじゃないですか? でも映画はタダだったので、文句言わなかったんでしょうね(笑)。
3. 暗中模索の大学時代
--大学に入られて、上京されるわけですが、その時は何か志を持って上京されたのですか?
糟谷:大きな志があったわけではないですが、高校まで映画漬けの毎日でしたから、映画に関する仕事ができたらいいなとは思っていました。ただ、日本大学に芸術学部があって、映画のコースがあるとか、全く情報がなかったですし、もっと言ってしまえば、観ていた映画がほとんど洋画だったので、日本で映画の仕事をする気分ではなかったんですよ。なのでアメリカやフランス、イタリアに行って…というようなことを勝手に夢想していましたね(笑)。「アメリカ留学したいな」と思っていましたけど、家に金がないので国公立の大学にしか行かせられないと言われて、試験を受けたんですが、軒並み落ちまして、最後に潜り込んだのが明治大学でした。仕送りは3ヶ月に1回1万円くらい送ってくるだけで、大学に入ったら即自給自足の生活が始まりましたね(笑)。志どころではありませんでした。
--その当時はどのような場所に住んでいたのですか?
糟谷:小石川にあった愛知県出身者の学生寮に住んでいました。そこには中学校の同級生や先輩、高校で知り合った仲間とか知り合いが多かったので、その寮で生活すること自体は何の問題もなかったです。
--その頃はどのような生活パターンだったのですか?

糟谷:大学の仲間と過ごしている時間と、寮の仲間と過ごしている時間が、約半分で後の半分はバイトです。バイトは、寮の先輩がずっと引き継いでやってきたバイトがあるんですね。
--糟谷さんはどのようなバイトをなさっていたんですか?
糟谷:もう、何でもやりましたね。数えたら50とか100くらいあるんじゃないんですか?
--その中で印象に残っているバイトは何ですか?
糟谷:田舎に帰ったときにやった、大きな工場の夜警のバイトですとか、あとはお寿司屋さんが印象に残っていますね。
--お寿司を握っていたんですか!?
糟谷:いや、おいなりさんを作っていました。水道橋にあるお寿司屋さんが、中山と府中の競馬場に出す「助六弁当」を作っていたんです。僕は学生でしたから、海苔巻きを巻くのは無理なので、油揚げに酢飯を詰めていました。金曜日の夜と土曜日の夜にその作業をやっていたんですが、作業は夜中にかかるので、時給が良かったですね。あと寮から歩いて行ける距離だったので、先輩や仲間と職場までゾロゾロ歩いていきました。ただ問題だったのは、おいなりさんを1ヶ月も握っていると油揚げの臭いが身体に染みついてしまうんですね。それで周りから「お前、油臭いぞ」と言われたりしましたね(笑)。
--糟谷さんのご経歴を拝見すると、大学に8年行かれていますよね? この間はずっとバイトをされていたんですか?
糟谷:そうですね。大学4年で同級生が卒業してしまっても、同じゼミの後輩とかがいたので学校に行っていたんですが、大学6年目には知り合いもいなくなってしまいました(笑)。ですから7年目、8年目は学校に2日か3日くらいしか行ってないですね。
--大学4年で同級生が去っていった後、糟谷さんの中に焦りみたいな気持ちはなかったんでしょうか?
糟谷:その時は、何かをやりたいという具体的なものがなかったんですよ。アメリカへ行って、映画関係の仕事をするという志も、すでに賞味期限を過ぎていましたしね。
--今で言う「フリーター」みたいな感じだったんですね。
糟谷:そうかもしれませんね。その日その日というよりも、「一週間暮らし」みたいな感じでした。
--そういった生活の方が、その当時の糟谷さんにとって、自分の将来を決めるよりも居心地が良かったんでしょうか?
糟谷:いや、「決められなかった」ですよね。そもそもチョイスもなかった。もちろん「電通のディレクターになりたい」とか、「テレビ局のプロデューサーになりたい」とか思ったとしても、何の繋がりもないですからね。しかも25歳を越えて、まだ単位もゴロゴロ残っていましたから、入社試験を受ける資格すらないです(笑)。
--ちなみにその頃はまだ寮にいらっしゃったんですか?
糟谷:大学2、3年の時に、友達が「一緒に住もうか?」と言ってきたので、寮は出てしまいました。立川の米軍ハウスに住んでました。まあ、一緒に住むというよりも、居候みたいなものですね。
--そのお友達というのは大学のご友人ですか?
糟谷:いや、その友達というのが、GAROの大野真澄君で、彼は中学時代の同級生なんです。まだGAROで売れる前は、新宿厚生年金会館の裏のアパートに住んでいたんですが、少しずつお金も入ってくるようになったので、もう少し広いところに引っ越そうとしていて、「半分出してくれるか?」と言われたんですが、「とてもそんな金はない」と言ったら、「じゃあ、2割くらい出してくれればいい」という感じだったので、大野君と一緒に住むことになったんです。それからしばらくして、立川と福生の間にある米軍ハウスだったら、同じ値段で広い一軒家を借りられるというので、そこに引っ越しました。あの当時、立川や福生は演劇をやっている人や、ミュージシャン、デザイナーとかが、ヒッピーのコミューンみたいなものを形成していて、独自のサブカルチャーがあったんですね。そこへ移ったとき僕は大学5、6年くらいだったんですが、そのことによってますます学校に行かなくなりましたね(笑)。
--学校まで遠いですしね。
糟谷:そうですね(笑)。そんなことをやっているうちに、ある航空会社の下請け会社が人員を募集していると知ったんですね。その会社に入って、2年くらいすれば航空会社の正社員になれる可能性があるという話だったので、「もし正社員になれれば、世界各国に行けるチケットが手にはいるかもしれない」と思って、そこに入社しました。先ほどもお話ししましたが、「映画関係の仕事をするんだったら、アメリカに行きたい」という思いが、やはり心の奥底にあったんでしょうね(笑)。一応入社試験として、英語の試験があったのですが、評価が15段階に分かれていまして、一番上は管制塔要員で、一番下が機内食の皿洗いだったんですが、僕はちょうど真ん中ぐらいの成績で入社しました。
--入社後、どのような仕事をなさっていたんですか?
糟谷:飛行機が羽田に来ると、免税品がどれだけ売れたかをスチュワーデスがチェックして、僕たちはそのチェック用紙を受け取り、足りない分を補充するという、いわゆる「サプライ」という仕事をしていました。それで、その航空会社の社員になるつもりで、仕事をしていたんですが、1年半くらい経った頃に、仕事がどんどん休みになるんですね。不思議に思って、会社の人に聞いてみたら「ストライキだ」と言うわけですよ。その当時、会社の調子が良くないので、本国も含めて大リストラが始まっていたんです。
--糟谷さんが働いていたのは、外資系の航空会社だったんですね?
糟谷:ノースウエストです。それで「2年くらいで社員になれるという話はどうなったんですかね?」と聞いたら、「なれるわけないだろう」と言われたので、「だったら、こんな仕事をしているのも嫌だな」と思い始めました。また季節がちょうど夏でしたから、日が照り返した飛行場で朝から晩まで働いているとヘトヘトになるんです。だから、家に帰ると死んだように寝てましたね。それも「2年後には正社員になって、ロンドンやパリに行くぞ!」と思っていましたので(笑)、我慢できたんですが、そういう話を聞いて結構ガッカリしてしまいました。
そうなると45℃のコンクリートの上をはいずり回るのがすごく苦痛になってしまい、「ここにはとてもいられないな」と思っているときに、大野君が「自分の知り合いが帽子屋をやっていて、バイトを探しているからそっちに行かないか?」と持ちかけてきたんです。それで「夏の1ヶ月はこれでしのげるな」と思っていたんですが、その話が「社員にならないか?」という話になってきたんですね。でも、夏休みのバイトくらいだったらいいですけど、帽子屋の社員になるつもりはなかったので「困ったな」と思っていたら、帽子屋の旦那さんが「ちょっと会いたいから、時間を取ってくれないか?」と連絡してきたんですが、その帽子屋の旦那さんが、実はかぐや姫の山田パンダさんだったんです。
--そうだったんですか!
糟谷:それ以前に、大野君を通じてパンダさんに紹介されたりしていたんですね。それでパンダさんと会ったら、急に「俺のマネージャーをやってくれ」という話になったんです。かぐや姫はすでに解散して、メンバーそれぞれで活動されていたんですが、パンダさんはメンバーの中で一番年上で、スタッフへの要求も厳しかったので、なかなかマネージャーが長続きしないというので、パンダさん自身で探そうと思っていたみたいなんです。でも、僕は帽子屋さんになるつもりもなかったですし、マネージャーになるつもりもなかったんですが(笑)、「一週間くらい時間をあげるから、考えなさい」と言われて、他に選択肢もなかったのでマネージャーを引き受けました。
--それでユイ音楽工房に入社されたわけですね。
糟谷:そうです。26歳を越えるか越えないかという頃です。
4. 入社4年目の転機〜長渕 剛との出会い

--ユイ音楽工房に入られるまでは、音楽業界に進もうと考えたことはおありだったのですか?
糟谷:確かに音楽は好きでしたが、仕事にしようとは思っていませんでした。マネージャーが何をするかも全くわかりませんでしたしね。
--その頃、大野さんは「学生街の喫茶店」でブレイクしていたんですか?
糟谷:していましたね。でも大野君と自分を較べて、へこたれるということはなかったですね。子供の頃からの仲間ですし、中学以降は一番の親友でしたから、お互いの立場が変わろうが友達気分に変わりはなかったですね。それは今もそうです。
でも、さすがに25になっていましたから「これから自分はどうなっちゃうんだろう…」と哲学的なことは考えて始めましたけどね(笑)。だって25歳の倍だったら50歳ですからね。昔の50歳といえば、もう大人もいいとこですし、下手したら爺さんみたいな感覚じゃないですか? その半分を過ぎて、自分はまだ何も始まっていない感じというか、世の中の歯車と全くかみ合っていない感じがありました。恐怖感も、焦りもなかったんですが、やりようもなかったという感じでしたね。
--そうなりますと、音楽業界に来たのはまさに数奇な運命だったのですね。
糟谷:そうですね。
--実際に音楽業界へ入ってみて、どのように感じられましたか?
糟谷:単純明快だなと思いました。「どんな仕事をするんですか?」と聞いたら、「この人を売るのがお前の仕事」みたいな感じですね。それで「どうやって売れば良いんですか?」と聞いたら、「お前が考えるんだ。それがマネージャー」と言われて(笑)。
--そう仰ったのが、後藤由多加さんですか?
糟谷:後藤さんもそうでしたし、吉田拓郎さんのマネージャーも 、南こうせつさんのマネージャーも、イルカさんのマネージャーもそこにいるマネージャーは、みんなそんな感じでした。
--大変失礼な質問なんですが、最初のお給料はどのくらいだったんですか?
糟谷:実はノースウエストにいたときは、結構もらっていたんです。ですから、それよりも全然良くなかったですね。ちなみに入って最初の3ヶ月は月6万円でした。
--では金銭的に言えば、最初はたいした給料ではなかったわけですね。
糟谷:初めは「やらなきゃよかった」と思いました。でも、「ノースウエストにいればよかったな」と思ったのは、最初の給料をもらったときだけで、次からは忘れていましたね(笑)。
--この仕事は自分に向いているなとか、やりたかったのはこれだったんだと自覚するまでにはどれくらいかかったんですか?
糟谷:4年くらいかかりました。
--では、4年目までは半分嫌々な気分だったんですか?
糟谷:「自分で考える」ということに対しては自由でしたから、そこには不満がなかったんですが、考えても、考えても売れないんですよね(笑)。そうそう素人が考えて売れるものではないので、そういう状態がずっと続くと「人の面倒を見ている」という感じになるわけです。10時の新幹線で大阪へ行くとなると、8時くらいに電話で起こして、荷物があれば迎えに行くわけです。まあ、当たり前と言えば、当たり前の話なんですが、「人の面倒を見ている」感じというのが心のどこかにあって、「この仕事は自分に合ってないな」という気持ちがずっとありました。
--では、その4年目に何か転機になるようなことがあったんですか?
糟谷:まずその前に、パンダさんと上手くいかなくなってきたんですね。パンダさんにしてみれば、えらく期待をしてユイに入れたにもかかわらず、だんだん実績が下がっていってしまい、僕も色々アイディアを出すんですが、ことごとく空振りするわけです。そんな状態をミュージシャン、マネージャーが喜ぶわけがないですし、僕も限界みたいなものを感じてしまって、「向いていないんじゃないか?」と考えたんです。
しかも、周りの色々な人たちから話を聞くと、ラッキーな要素がすごくあるんですね。例えば、南こうせつさんのマネージャーをやっていたある方は、何故こうせつさんのマネージャーになったかというと、高校生時代の同級生だったからという、そういうケースってあるじゃないですか? そういうラックが今後自分に降りかかってくるとも思えないわけです。
それでパンダさんとも意見が合わなくなってきて、仕事も辛くなってきたときに、「新人がいるからお前やれ」と言われたのが、長渕剛なんです。後藤さんにこの話をすると全然憶えていないんですが、僕が「どんな奴ですか?」と聞くと、「全然言うことを聞かない奴だ」と言うわけです(笑)。それで「何で僕がやるんですか?」と聞いたら、「お前だって言うこと聞かないから、ちょうど良い」と言われて(笑)、長渕の担当になったわけです。
--長渕さんの第一印象はどうでしたか?
糟谷:非常にわかりやすい奴でしたね。「何をやりたいの?」と聞いたら、「ギター一本で日本全国ツアーをやりたい」と言ってきて、それだったらできそうな気がしたんです。「大ヒットを作りたい」と言われても、大ヒットを作った経験なんてありませんでしたから、多分どうやって作ったらいいかわからなかったと思います。でも、「ギター一本で日本全国ツアー」だったら、逆算ができるじゃないですか? 例えば、渋谷公会堂でやるには2,000枚のチケットを売る→2,000枚のチケットを売るには1,000人くらいの会場が2日間満員になれば行けるかもしれないみたいなイメージができたんですね。それを最初は50人くらいから始めて、積み重ねていくわけです。
その後、レコード会社の宣伝会議に参加したんですが、この週はラジオのオンエアー週で、その前は各出版社でインタビューとキャンペーンをやりましょうというような、僕がパンダさんをやっているときと同じ話になるわけです。でも、パンダさんの時にレコード会社の言う時系列に沿ったプランをやってきた結果、思った数字が出てこなかったので、同じことをやっても数字が出ないんじゃないか? と思っていたわけですよ。売れている人はこれでいいのかもしれないけど、まだ売れてない人を同じようにやっても売れないと強く思いました。
それで僕が「2年くらいかかるかもしれないけど、日本全国の大ホールをギター一本でコンサートできるようにすることが、この男の一番望んでいることなんですよ!」と言ったら、「まあ、それは事務所でやってもらって…」と言われて、またすぐにレコードの話になってしまったんです。
--結局、レコード・プロモーションの話に終始してしまったわけですね。
糟谷:結局そのまま宣伝会議が終わってしまったんです。でも、僕は長渕とツアーの約束をしちゃいましたから、内心「まずいな」と思いました。そもそも、長渕はその約束を守ってくれたら、僕の言うことを聞くと言っていたんですよ。「それならできそうだから、俺の言うことを聞けよ」と言って臨んだ宣伝会議で、周りの連中は「その話は別で」と言っているんで、「売れなかったら俺のせいだな…」と思いだして、そこからやる気が出たといいますか、自発的にやるようになりました。
--その長渕さんとのツアーの約束はどうなったのですか?
糟谷:宣伝会議で決まったことを僕が全部持って、会議に出ていた集英社の担当やニッポン放送の担当といった人たちに「全部僕がやりますから!」と言ったんです。
--つまり何も手を出すなと。
糟谷:極端なことを言うとそうですね。あの人達の言い方で言われちゃうとかなわないと思ったので、「全部やりますから!」と言い出したんです。今同じことをしたら、大問題になると思いますけどね。あとキャンペーンも、宣伝課長に「あなたが行くより、俺が行った方がちゃんと説明できるから、俺の分の旅費も東芝で出してくれ」と掛け合って、日本全国駆け回りました。
--それはすごいですね! 普通、レコード会社の宣伝部が出てきてしまうと、そこまで強く出られないですよ。
糟谷:そのときは不思議にそんなことを思わなかったですね。
--それで結果が出てくるまでに、どのくらい時間がかかったんですか?
糟谷:1年半から2年くらいかかりましたね。
--その間はやはりライブ中心で全国を回られたんですか?
糟谷:そうです。ありとあらゆるところでライブをしました。東北での話ですが、レコード屋さんの2階にピアノのレッスン場があって、そこでお客さんが3人の中でライブをやったりもしました。ライブというより演奏会ですか。でも、そのうちにお客さんが誰もいなくなってしまって、長渕は「客がいないんだからもういいんじゃないの?」と言ったんですが、レコード屋の店主さんとか、宣伝してくれた放送局のディレクターさんとかが観てくれていましたし、僕も曲をよく知らなかったので、「何か曲やってよ」と言ったら、ブツブツ言いながらも歌ってくれましたね(笑)。
--あの長渕さんにもそんな時代があったんですね…。
糟谷:それはありましたよ(笑)。売れるきっかけとなったのは、庄野真代の全国ツアーの前座でした。庄野真代もユイ所属で、その頃は「飛んでイスタンブール」が大ヒットしていたんですが、長渕が30分の前座を終えて楽屋に引っ込むと、お客さんのアンコールが鳴りやまないんですよ。庄野真代にしてみたら気に食わないですよね(笑)。だから打ち上げも僕と長渕だけ行かなくて(笑)、「何か嫌われちゃったみたいだけど、しょうがないんじゃないの?」みたいな感じで、駅に戻って立ち食いそばで食事してました。あの頃は「いつか寿司食おう!」それが夢でした。(笑)。
--(笑) その頃、長渕さんはおいくつだったんですか?
糟谷:僕と7つ違いで、その頃僕は30歳ですから、剛は22、3ですね。それから地方の「○○会館」みたいなところで一人でライブが出来るようになって、その後、こうせつさんが「面白いじゃないか」と言ってくださって、全国ツアーの前座にしてくれたんです。
--やはりユイにいたことが大きかったのかもしれませんね。
糟谷:そうですね。長渕本人はまだ若かったので、「こうせつさんのフォークの世界と俺は違う!」と思ってますから、「チャンスをありがとうございます」みたいなへりくだった気分がなかったですけどね(笑)。でも、そこでもアンコールが鳴りやまなくて、でもこうせつさんはすごく喜んでいましたね。それから、こうせつさんのオールナイトニッポンでコーナーをもらって、そのコーナーから独立して、2部をやりだしたんです。そして、2部を卒業して1部になった頃から一番最初に計算した「500人収容の会場が一日で売り切れる」、「800人収容の会場が一日で売り切れる」ようになり、秋のツアーでは2日間のライブが1日で売り切れるという現象が起こってきたんです。
その頃に宣伝のトップをやっていた新田さんが、「アルバムの中にある『順子』をシングルにしたらどうだろうか?」と提案してきたんですね。実はこの「順子」という曲は、コンサートでは冗談ソングだったんです。「お客さんがわーっと受けた後に、非常に切ない歌だったら染みるんじゃないの?」みたいな演出もどきがあって、そのための冗談ソングだったんですね。なので本人は「あの歌をシングルで出していいのかな?」と言っていたんですが、新田さんは「絶対いける」と押しきってくれました。これが大ホームランだったんです。そこからは数字もどんどん上がっていきましたね。今でも新田さんに感謝してます。
5. 前例のない東京ドーム公演〜BOφWYの大成功

--長渕さんをスターに育てられ、その後、BOφWYを手掛けられるわけですが、彼らとの出会いは?
糟谷:中原めいこという東芝と契約していたアーティストを、ユイがマネージメントを引き受けるという話になって、うちの部が担当になったんですね。それで僕は中原めいこのコンサートの手伝いをしていたんですが、ある時に中原めいこの新曲キャンペーンに駆り出されまして、その一環で名古屋に行ったときに、東海ラジオの加藤さんから「このテープを聴いてくれ」と渡されたのが、BOφWYのテープだったんです。
それでそのテープを持って東京へ帰ってきたら、その当時のめいこのマネージャーだった重松が「このバンド、すごくかっこいいですよ」と言ってきたんです。それで僕も聞いたら、確かにかっこよかったので、本人達に会って、何回か話をする中で契約することになったんです。
--その頃のBOφWYはメジャーデビューをしていたんですか?
糟谷:ビクターで1枚、徳間ジャパンで1枚アルバムを出していたんですが、あまり上手くいってなかったので、事務所も辞めて、自分たちで新宿ロフトへ出たりしていたんです。あの当時の周りの連中に言わせると、BOφWYは売れてなかったけれど、すごく人気があったバンドみたいで、ライブはいつもお客さんが一杯でしたね。
--歯車が上手くかみ合っていなかったんでしょうか?
糟谷:タイミングですかね。でも、知り合って1年くらいはどうやったらいいか、わからなかったですね。当時もよく言っていたんですが、何故このバンドが他へ行かずにうちの事務所に来たのか、不思議な感じがしました。彼らは僕より一回りくらい年が下でしたが、4人とも頭がよかったので、本当に不思議な関係でした。
--それはBOφWYがすでに完成していたということなのですか?
糟谷:いや、それはまだまだでした。やはり、そこから1年半くらいかかっていますからね。
--まだ荒削りではあったけど、光るものがあったと。
糟谷:それはありましたね。僕は何もないところから、何かを生み出す人間でもないですしね。長渕の時に経験した成功のパターンじゃないですが、ライブを繰り返している中で、東北の「ロックンロールサーキット」という夏のイベントがあって、そこに出したらいきなり人気が爆発したんです。秋にコンサートを何本かやろうと話し合っていたのですが、イベンターから「当初予定していた秋田の小ホールから秋田県民会館に会場を変えたい」と言ってきたんです。小ホールはキャパ800人に対し、県民会館は2,000人くらい入るんですよ。なので「そんなのできるわけないだろう」と言ったんですが、このチケットが1、2日で売り切れてしまったんですね。
--東北でそれだけ売れたというのはすごいですね!
糟谷:すごかったです。先ほどお話した「ロックンロールサーキット」の印象が強かったんでしょうね。結果的にレコードセールスも東北はよかったですからね。
--やはりライブで売ったバンドなんですね。
糟谷:初めはそうでした。そのうちにヒット曲が出てきて、最後は大変な人気になってしまいましたね。
--東京ドームでの解散コンサートもすごかったですよね。
糟谷:そうですね。解散コンサートはありとあらゆることがありすぎて、かえって憶えていないことが多いですね。東京ドームのこけら落としのイベントの一つだったんですが、前例がなかったですから、消防法をどういう形でクリアすればいいのかわからなかったり、舞台設営や会場周りだとか照明、PAといったことが全くゼロの状態だったので、ものすごく大変でした。精神も肉体も限界を超えてしまっている感じだったので、音楽を楽しむ状態ではなかったと思います。ちょっと前に解散コンサートのDVDが出たんですが、それを観て「こんな曲順だったっけ?」というくらいに、憶えていませんでしたからね(笑)。
--ここまでお話を伺ってきますと、長渕さん、BOφWYと糟谷さんが手掛けられたアーティストに外れなしですよね。
糟谷:まあ、そうでしたね。ただそういうものは長い間続くものじゃないんですよ。ある一時期の何年間で、フラッシュのようにパッ、パッと来るので、未だにパッ、パッと光っているわけではないです。やはり大きな波があると思います。
--いくら糟谷さんといえども、5年置きくらいにそういうものをずっと作り続けるのは、やはり難しいですか?
糟谷:大変難しいですね。自分自身でも思うんですが、この20数年間で長渕というアーティストと一緒にいたり、BOφWYというバンドと一緒にいたり、今、布袋と一緒にいたりということをやり続けている人たちって、そう多くないじゃないですか? そういう意味では、自分がやれてきた幸せな部分が、間違いなくあるんだろうなと思いますね。
--運とタイミングがよかったということですか?
糟谷:運がよかったとしか言いようがないですね。もちろん自分も一生懸命やってきました。いつも何かの必然をずっと繰り返している中で、本当に偶然のようなタイミングが重なってブレイクするわけですから、ただルーティンワークをやっていて、それがそのままブレイクやヒットになったりすることは絶対あり得ないです。ですから、そういったものは、そうそう何度も来るものじゃないですね。
--その後、12年間在籍されたユイ音楽工房から独立されるわけですが、きっかけは何だったのですか?
糟谷:それはBOφWYの解散ですね。BOφWYが解散をすることが決まって、そのまま音楽の業界にいて、また全然違うものを同じようにやっていこうという気持ちは、ほとんど無かったですね。どこかで「もういいかな」という気持ちがありました。何ができるかわかりませんでしたが、「他のこともできるかな?」と漠然と考えていたので、BOφWY解散がきっかけとなって独立しました。
--独立されたものの、そこから先のことはまだ何も決まっていなかったんですか?

糟谷:そうですね。音楽のエンジンは布袋だったんですが、その頃バンドが解散すると、作曲能力があって、どんなに優秀なギタリストでも、最終的にはミュージシャン・プロデューサーになっていくみたいなところがあって、「ロックスターになるのはヴォーカリスト」みたいな感覚があったじゃないですか? そういう意味で「自分たちが頑張って、本当にできるのかな?」という気持ちはすごくありました。
そんな時に布袋のファースト・アルバムをアビーロードで作っていたんですが、そこで初めてちゃんと彼のヴォーカルを聴いて「こいつ滅茶苦茶歌が上手いんだ!」とすごく感じたんですね。それまではギタリスト、作曲家だと思っていたんですが、布袋寅泰というアーティストは音楽の塊みたいな奴で、歌ってもすごいんだと思いましたね。特にロックンロール系を歌うと滅茶苦茶すごいんだという事実を、毎日のレコーディングで新しく発見したような気がしました。
--実は布袋さんの本当の実力を把握しないまま、新しい事務所をスタートさせたということですね。
糟谷:そうですね。僕はマネージメントの専門で、制作の専門ではないので、彼みたいに制作面を全て自分でできるアーティストと、たまたまコンビを組めたというのは、僕にとっても本当にラッキーでした。
--そのことによって糟谷さんはマネージメントやビジネス面に専念できたわけですね。
糟谷:もし制作を僕がやらなくてはいけなかったら、上手くいったかどうか自信がないですね。
--そこもまたラッキーでしたね。
糟谷:ええ。でも、あれだけの才能がある奴と一緒に仕事ができていること自体、恵まれていると思います。
--ちなみにこの「IRc2コーポレーション」という名前の由来は、どこから来ているのですか?
糟谷:これは星の名前です。「IRc2」とは「強烈な赤外線を発する2番目の天体」という意味で、僕らがやっていくのは音楽であるし、作りたいのはロックンロール・スターなので、「星の名前はかっこいいな」と思っていたんです。
--かっこいい響きですよね。そこから先はもう皆さんご存じの活躍ですね。
糟谷:まだ相変わらずやっているというレベルですかね。そろそろくたびれてきたぞと(笑)。
6. 夢を与えるスーパースターが生まれる環境を作りたい!
--ここからは音楽制作者連盟 理事長のお立場からお話をお伺いしたいと思います。まず音制連の成り立ちについて、ご説明頂ければと思います。
糟谷:70年代の後半にウォークマンが登場し、今まで家の中で聴いていた音楽が、外で聴けるという革命的なことが起きたんですね。おそらく、その前の時代というのは100人が音楽を楽しむには、100枚のレコードが必要だったんです。それがウォークマンができたことによって、テープにコピーするという現象が起きてきた。そうするとレコードは安いものではないですから、数百円で借りてきて、テープにダビングしたわけです。
そして、ハードとメディアが進化し、音楽が爆発的になったところに、「より廉価で楽しむ」システムができあがった。それが貸レコードですが、たまたま法律的に貸レコードというビジネスを禁止する法律がなかったので、そこに「貸与権」ができ、それを徴収して分配するために音制連は設立されました。
--ただ未だにそのレンタルの問題は引きずっていますよね。
糟谷:本来、CDができた瞬間に「デジタルライツ・マネージメント」がなくてはいけなかったんですね。そのロジックはその時代になくてはいけなかったのに、誰もそこに思いを馳せずに、古いロジックの中で僕らは頑張ってきたわけです。今、文化庁を始め、各関連団体のトップが集まって、話し合っても、あちらを立てれば、こちらが立たずではないですが、なかなか話が進みません。
--どちらかというとバトルロイヤル的な様相を呈していますよね。
糟谷:例えばレンタルの問題、レコード会社・プロダクションの在り方など、これからはものすごく変わっていくんじゃないのかなと思います。もっと言えば、変わらないと駄目だと思うんです。つまり、こんな混沌とした状況の中を生き抜いていけるタフな精神と、卓越したアイディアを持った人間だけが成功すると思います。これまで僕らが培ってきたノウハウだけでは、江戸時代の士農工商みたいなもので、全く通用しないでしょうね。

--ただ、その新しいロジックなり、アイディアをまだ誰も見つけられていないという現状でもありますよね。
糟谷:そもそも音制連の理事長をやっているからって、僕に答えを求めること自体間違っていますよ(笑)。僕にもそれはまだわからない。 実はこの間、ある都市へ「日本の音楽の現状と未来」という講演をしに行ったんですが、その都市はありがたいことに「音楽を軸にしながら、若い人たちと街の発展の可能性を見つけよう」と考えているんですね。それで「是非、プロパガンダを!」ということで送り込まれたんですが、内心は「俺が教えて欲しいよ」と思っていました(笑)。
--(笑)。
糟谷:個別のことでしたら、いくらでも話せると思うんです。つまり1章、2章とチャプター的には話していくことができるんですが、それが全部で12章となったときに、一つの物語としてどのような変遷を持ち得るんだ? ということに対して、誰も答えを持ち合わせていない感じですね。
--音制連としての今後の課題は何でしょうか?
糟谷:先ほどお話ししましたが、昔は100人が音楽を楽しむには、100枚のレコードが必要だったんですが、今は下手したら、1,000人で10枚のCDがあれば済んでしまうわけです。ということになると、CDというメディアがどういう風に推移していくかどうか、僕ははっきりとわからないんですが、少なくとも5年、10年先には音楽配信が全盛になる。そこで著作権や実演家の権利がきちんとしていれば、より拡がっていく可能性があるんじゃないかと考えています。
今の音制連にとっての最大の課題は、送信可能化権というのが制作者と実演家に与えられていて、基本的には1対1なわけですから、今のレコード契約の中で解釈される送信可能化権の置かれ方と違うんではないのか? ということなんですね。そういったネットワークが拡がっていく中で、最終的には作詞家や作曲家、レコード制作者、実演家の権利をどういう風に確立させていくか? ということが、音制連にとってもここ1、2年での急務なのではないかと思っています。
--まさにそうですね。
糟谷:送信可能化権という権利が実演家に与えられているわけですから、それをいかに行使するかは、我々にかかっているんです。ですから、音制連の各プロダクション、及び一緒に仕事をしているミュージシャンやアーティスト達がその知識を持ち、意識を統一して、どこかで権利を主張しなくてはなりません。ただ、音制連が権利の圧力団体として機能するわけにはいかないので、色々なPRやプロモーションを使いながら、まず実演家がはっきりとした送信可能化権を獲得するというのが、今後の音制連の課題です。
--その「送信可能化権」はまだ獲得できていないんですか?
糟谷:法律では認められたんですが、それを実際に行使するということですね。実演家もレコード契約があるから行使しづらいということもあるでしょうしね。あとネットワーク時代が来たときには、個別の指し値ではなく、著作権と同じように一定の料率というような考え方で成立させるという方法論もあると思います。
今までは日本政府や文部省、文化庁の指導に対して、大きな不満を持ちながらやってきたんですが、我々の権利が法律的に認められているにもかかわらず、我々が使っていないというところに差し掛かっているので、我々が積極的に取り組んで行かなくてはならないでしょう。
ただ世の中がどう変わっても、この一曲を聴いて人が夢を見るような、また勇気が涌くような楽曲を体現してくれるようなスーパースターたちが、どんどん出てくるような環境をどうやって作れるかが、とても大事だと思います。
--本日はお忙しい中ありがとうございました。
(インタビュアー:Musicman発行人 屋代卓也/山浦正彦)
「マネージャーが何をするかも全くわからなかった」糟谷氏が、アーティストと目線を同じにし、共に成長していく中で生まれた一体感が、成功の秘訣なのでは? と強く感じました。その根底には、音楽に対する強い情熱があったことは、言うまでもありません。余談ですが、取材場所としてご提供頂いた糟谷氏のオフィス内の蔵書量には、本当に驚かされました! そこに並べられた様々なジャンルの本に象徴されるように、糟谷氏の強さは、あらゆるものを吸収していこうという貪欲な姿勢にあるような気がしました。
さて次回は、著作権等管理管理事業法の成立を受けて、2000年11月に音楽出版社11社の出資により設立された(株)ジャパン・ライツ・クリアランス 代表取締役社長 荒川祐二氏です。お楽しみに!

広告・取材掲載