第88回 村井 邦彦 氏 株式会社ヴィラス ミュージック 代表取締役会長/作曲家
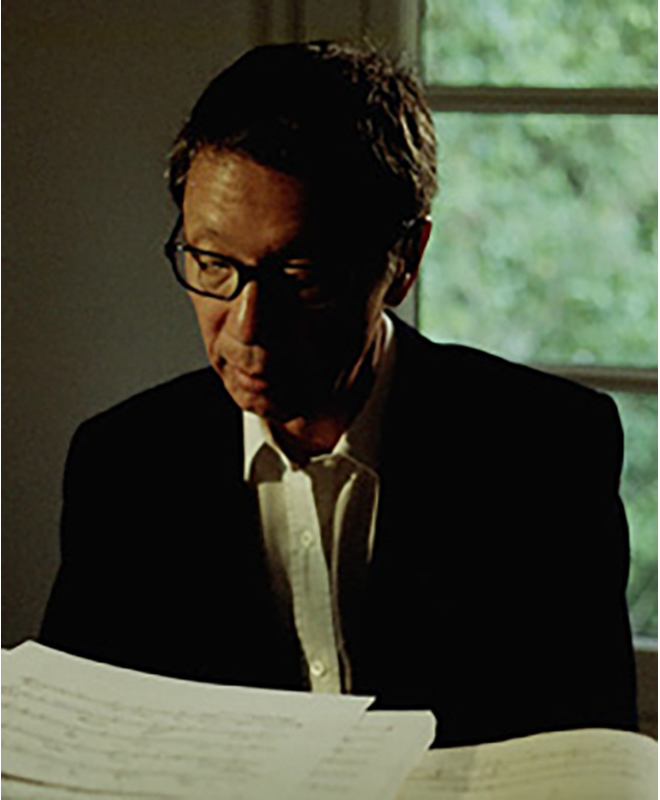
株式会社ヴィラス ミュージック 代表取締役会長/作曲家
今回の「Musicman’s RELAY」は松任谷正隆さんからのご紹介で、ヴィラスミュージック代表取締役会長の村井邦彦さんのご登場です。慶應義塾大学在学中に名門バンドサークル「ライト・ミュージック・ソサエティ」に所属し、大学3年のときにはレコード店を経営。その後ヴィッキーの『待ちくたびれた日曜日』の作曲を担当し、同楽曲がチャートインしたことがきっかけで作曲家へ。以降「翼をください」などの名曲を世に送り出しました。その後、名曲「マイウェイ」の権利を買い付け若干24歳にして音楽出版会社アルファミュージックを設立し、ビッグアーティストを抱える海外レーベルの権利を次々と取得。72年にスタジオAを設立した後、荒井由実の「ひこうき雲」を手がけアルファレコードを設立。さらにYMOでは国内だけでなくA&Mレコードから全米デビュー、翌年には世界ツアーを成功させました。現在もTVドラマ音楽など作曲家としてご活躍される村井さんの今日に至るまでの様々なお話をお伺いしました。
プロフィール
村井 邦彦(むらい・くにひこ)
株式会社ヴィラス ミュージック 代表取締役会長/作曲家
1945年生まれ、東京都出身。
慶應義塾大学在学中に名門バンドサークル「ライト・ミュージック・ソサエティ」に所属。大学3年で赤坂にレコード屋「ドレミ商会」をオープン。
67年にヴィッキー『待ちくたびれた日曜日』の作曲を担当し作曲家としてデビュー。
69年にパリ・バークレー音楽出版社と「マイ・ウェイ」などの出版権利を契約し、音楽出版社アルファミュージックを設立。
77年にアルファレコードを設立し、荒井由実、YMO、赤い鳥、ガロ、サーカス、吉田美奈子などをプロデュース。
事業の海外進出を期に92年に活動の拠点をアメリカに移す。
現在はアメリカと日本を行き来し、ヴィラスミュージック代表取締役会長として、また、作曲家として活躍中。
1. レコードに囲まれた少年時代
−−最初に前回ご登場いただいた松任谷正隆さんとの出会いや印象などをお伺いしたいのですが。
村井:彼は慶応大学の後輩なんですが、僕と松任谷を引き合わせたのは細野晴臣なんです。細野にユーミンの『ひこうき雲』のプロデュースを頼んで、ティン・パン・アレーに松任谷が入っていたことでうちのスタジオに来るようになって、その後はプライベートでも会ったりしながら現在に至っています。彼は僕より七つ年下だから昔は「若い」と思っていましたけど、最近あまり年下な感じがしないですね(笑)。
−−もう40年来のお付き合いということになりますね。
村井:そうですね。そんなにベッタリ一緒にいないですけど、節目節目では会っていますし、ずいぶん僕の曲をアレンジしてくれましてね。彼はすごくいいアレンジャーですよ。
−−ここからは村井さんご自身のことをお聞きしたいのですが、ご出身は東京ですか?
村井:そうです。
−−ご家庭内には現在に繋がるような音楽的環境はあったんですか?
村井:家族とか親戚とか周りにいる人たちで音楽家は一人もいないんですよ。ただ、父親と叔父が趣味で秋葉原あたりに部品を買いに行って、電気蓄音機を組み立てていましたね。
−−いわゆるオーディオマニアだったと。
村井:それほど大げさではありませんでしたが、とにかくそのおかげで家にレコードはたくさんあったので、子供の頃から興味を持ってクラシックから流行歌まで色々なものを聴いていました。それが家庭での音楽との最初の出会いですね。
−−昭和20年生まれとお伺いしていますが、その頃としては相当垢抜けた環境のご家庭だったんじゃないですか?
村井:そうかもしれないですね。音楽家はいなかったですが、僕のおじいさんも含めてみんな音楽好きでした。僕も小学校1年生のときにバイオリンを習わせられるんですが、それが嫌で嫌で・・・(笑)。近所のバイオリンの先生にところへ行くんですが、先生が電話で席をはずしている間に、2階から木を伝わってさーっと逃げるんです(笑)。そんなわけでバイオリンは1年も経たないで辞めてしまうんですが、中学になってベニー・グッドマンのレコードを聴いてクラリネットを吹きたくなったんです。それで学校のブラスバンドに入ってクラリネットを吹き出して、その辺から音楽が好きになっていきました。
−−クラリネットから本格的に音楽を始めたわけですか?
村井:そうですね。もっと本格的に始めたのが中学3年か高校1年のときで、最近休刊になってしまった『スイングジャーナル』を読んでいたら、コマキ楽器という浅草のほうの楽器屋さんでプロのジャズミュージシャンが楽器を教えると書いてあったんです。講師はドラムがジミー竹内さん(※1)という当時のスタードラマー、サキソフォンが吉本栄さん(※2)でした。僕は「吉本栄さんにサックスが習えるなんて面白いな」と思ったので、親と一緒にコマキ楽器へ行ってアルトサックスの中古を買ってもらって、譜面の読み方とか音楽の基礎を吉本さんに習いました。
−−ピアノはなさらなかったんですか?
村井:ピアノは家にありましたから、誰かに教わったわけではないんですが、子供の頃から遊びで弾いていましたね。
−−なるほど。高校時代は音楽三昧ですか?
村井:そうですね。高校は暁星だったんですが、吉本栄さんのところに慶応高校の連中が3、4人習いに来てたんですよ。その慶応高校の連中が、慶応ライトミュージックソサエティの高校部門のオーケストラを作った時期があって、学校の枠を越えて、そこでアルトを吹いていたんです。当然慶応高校の人たちはそのまま慶応大学へ行ってライトに入るということで、僕も慶応を受験してライトに入りました。
−−オーケストラに入るために慶応に入ったということですか?
村井:そうですね。
※1. ジミー竹内(1930年6月29日 – 2009年12月29日)
ジャズ・ドラマー。
原信夫シャープス&フラッツ、小原重徳&ブルーコーツ、鈴木章治とリズムエース、渡辺晋とシックスジョーズ、世良譲トリオなど、ビッグ・バンドに参加。
※2.吉本 栄
ジャズ・サックス奏者
吉本栄とバードランド・ファイブなどを結成。
2. 慶応大学ライトミュージックソサエティでの日々
−−慶応大学ライトミュージックソサエティは有名ですが、どのくらいの歴史があるんですか?
村井:日本が戦争に負けた1945年の12月からライトは始まっています。ライトを始めた高浜先輩は、今もお元気でテナーを吹いているのですが、普通部の時にジャズバンドを作っていたんです。でも、だんだん戦争が激しくなると、ジャズは敵性音楽ということで禁止されるようになって、軍楽隊みたいなことをやってお茶を濁してたんですが、戦争が終わって「これでジャズができる」とライトを始めたんです。
−−慶応大学ライトミュージックソサエティは錚々たる方々を輩出していますよね。
村井:諸先輩ですと古くは北村英治さん(※3)、ピアノの三保敬太郎さん(※4)、鈴木邦彦さん(※5)。僕が直接教えてもらったのは、ルパン三世を書いた大野雄二さん(※6)ですね。僕のちょっと前くらいまではポピュラー音楽っていうのは、アマチュアとプロの境目があまりなかったんですね。ジャズを学校で教えるようになったのは、バークレー音楽院というボストンの職業訓練所みたいな学校から始まって、ヤマハがそのメソッドを使って教え出したんですが、それまではポピュラー音楽を教えるところはほとんどなかった。でも学生バンドっていうのは、先輩が後輩に教えていた。ライトみたいなところが当時はポピュラー音楽を教えてもらえる場所だったんです。そこからプロが何人か生まれてきたのです。
−−慶応大学ライトミュージックソサエティはポピュラー音楽の学校みたいな場所だったんですね。
村井:そうですね。あと早稲田にはハイソっていうのがあって、東大にはイーストハードというコンボのバンドがありました。
−−当時ライトミュージックソサエティには何名ぐらいいらっしゃったんですか?
村井:当時のレギュラーメンバーが17人で、それに2軍が倍ぐらいいたかな。
−−村井さんは一年生のときからレギュラーメンバーだったんですか?
村井:大野雄二さんがレギュラーのピアノだったんですが、大野さんは大学4年でもうプロになって、藤家虹二さん(※7)というクラリネット・プレイヤーのバンドでやってたんですが、そうすると仕事で彼はいつもいないので、代わりに僕がピアノを弾いていました。
−−その頃ライトミュージックソサエティはどういう活動をされていたんですか?
村井:当時、大学対抗のバンド合戦というコンテストをTBSラジオでやっていて、それに勝つというのが一つの目標でした。練習は週一回レギュラーでやって、その他に夏と冬に合宿がありました。山中湖に体育会の山荘があって、そこで合宿していると、隣は空手部で「オリャー」と掛け声が聞こえてきて、こっちはジャズやってるようなすごい環境でね(笑)。夏休みは日本中の三田会が催しものをやって僕たちを呼んでくれるので、日本中演奏旅行ですよ。
−−それは楽しそうですね。
村井:楽しいですよ。4年生ではもうレギュラー活動してなかったですが、1年生から3年生の間に日本中の都市に行きましたよ。そのときに培った土地勘は、あとでレコード会社をやったときに役に立ちましたね。
−−ほとんどプロのバンドマンの生活ですね。ちなみにギャラって出るんですか?
村井:交通費程度ですね。やっぱり交通費がないと移動できないですから。あと宿泊代も出してくれました。
−−完全にツアーですね。
村井:そう。ツアーですね。
※3. 北村英治(1929年4月8日 -)
ジャズ・クラリネット奏者
アメリカはもとより、ヨーロッパ、オーストラリア等の大ジャズ祭に数多く出演し、世界的ジャズクラリネット奏者として活躍。
※4. 三保敬太郎(1934年10月17日 – 1986年5月16日)
作曲家、編曲家、ジャズピアニスト
国内外を問わず、演奏、作曲、編曲の各分野で活躍。日本ジャズ界の作・編曲分野に大きく貢献し芸術祭奨励賞を受賞。テレビ番組「11PM」のタイトル曲の作曲者でもある。
※5. 鈴木邦彦(1938年 – )
ピアニスト、作曲家、編曲家
西城秀樹、ザ・ゴールデン・カップス、ザ・ピーナッツ、黛ジュン、桜田淳子など多くのアーティストの作曲や『NHKのど自慢』などTV番組テーマ曲も作曲。1968年「天使の誘惑」で第10回日本レコード大賞受賞。
※6. 大野雄二(1941年5月30日 – )
ジャズ・ピアニスト、作曲家、編曲家
白木秀雄クインテットを経て、自らのトリオを結成。解散後は、膨大な数のCM音楽制作の他、「犬神家の一族」「人間の証明」などの映画やテレビの音楽も手がけ、数多くの名曲を生み出している。その代表作「ルパン三世」「大追跡」のサウンド・トラックは、70年代後半の大きな話題をさらった。
※7. 藤家虹二(1933年9月2日 – )
ジャズ・クラリネット奏者。
平岡精二クインテット、セクステット、池田操とリズムキング、南部三郎クインテットを経て藤家虹二クインテッを結成。L.A.ジョンアンソンフォードシアターでの「ブルーノート50周年記念ジャズフェスティバル」に日本人唯一のグループとして招待され出演した。
3. 伝説の飯倉キャンティでの「実地学習」

−−川添象郎さん(※8)とはいつ頃出会われたんですか?
村井:高校時代に飯倉のキャンティ(※9)というレストランに出入りをするようになってからですね。僕と一緒にサックスを習っていた山田君っていう人が川添の弟と仲良かったんですよ。それでキャンティに出入りするようになったんです。そのとき象ちゃんはニューヨークにいたから直接は会ってないですが、僕が大学に入る頃になると、象ちゃんはニューヨークでフラメンコ・ギターを勉強して、さらにスペインのマドリードへ行ってから帰国して、フラメンコの舞踊団を作るんですよ。僕はその公演の手伝いをしたり、川添の親父さんが作った映画に川添と一緒に音楽をつけたり、ライトとは別の流れで、キャンティを中心とした川添ファミリーとの付き合いで色々なことをやっていました。
−−その頃のキャンティっていうのは、錚々たる文化人が集まっていたんですよね。
村井:そうですね。もともとは川添の両親の友達が集まるところで、年代的には文学者でいうと三島由紀夫とか安部公房(※10)、建築家でいうと村田豊(※11)や坂倉準三(※12)、音楽だったら黛敏朗(※13)、絵だと今井俊満(※14)と、今生きていれば90歳と100歳の間くらいの芸術家たちのサロンでした。
僕たちは大人がしている難しい話を横で聞いていた子供たちといったところで、そこには加賀まりこや安井かずみ、かまやつひろしさんもいました。こっちはグループサウンズをやっていて、あっちは前衛音楽やってるような黛さんみたいな方がいて、と大人と子供が混ざっているようなところでしたね。
−−そういうところは、後にも先にも飯倉のキャンティしかなかったんじゃないですか?
村井:日本ではそういうのって珍しいですよね。
−−キャンティのような特殊な環境で得たものはなんですか?
村井:今はだいたい同じ年代で固まっちゃうじゃないですか? でも、あの頃のキャンティでは僕より30歳か40歳上の人たちと並んで、こっちは聞く一方でしたけど、そういう人たちと話ができるっていうのは貴重ですし、そういう人たちが一体なにを考えているのかってこともわかります。それはもう学校より全然勉強になります。
川添の親父さんは戦前パリに住んでいたので、海外の友人がたくさんいて、そういう人たちがお店に来るんですよ。例えば、日生劇場で『ウエストサイドストーリー』のオリジナルキャストをニューヨークから呼んできて公演するとき、振り付けをしたジェローム・ロビンス(※15)と会いました。もちろん本を読んでジェローム・ロビンスの経歴とかはわかりますけど、実際にその人の横に座って、その人がなにを言っているか、なにを考えているのか、どういう佇まいでいるかとか、それを直接見聞きするという経験はすごくよかったですね。
−−本当にすごい環境ですね。しかも、ただの大人じゃないわけですからね。なんかこう昔パリの街に芸術家が集まって・・・みたいな環境ですね。
村井:そうですね。すごく得るものがありましたね。将来ものを作るようなときの実地の勉強みたいでした。そのときは勉強と思っていませんし、ぼんやり立って聞いてるだけですけどね。なんか門前の小僧みたいな感じですよ(笑)。
−−(笑)。キャンティでの刺激的な日々は何年くらい続いたんですか?
村井:中学、高校、大学ですから全部で10年くらいですね。
−−すごい青春時代ですね。学校の普通の友達とか家の近所の友達とは、なにか違和感を感じていたりしたんじゃないですか?
村井:いや、そんなことはないですよ。学校は学校でライトの連中とは年中一緒にいましたし、いまだにずっと付き合っていますしね。クラスの友達で音楽とは関係ない人たちとも仲良くしていましたよ。
−−やはり時代ですよね、今考えると。一つの文化ですよね。
村井:そうですね。まぁ、日本にまだなにもなかったですからね。そういう活動が生き生きとしていた時代だったんでしょうね。
※8. 川添象郎(1941年 – )
音楽プロデューサー。
村井邦彦とともにアルファレコードを立ち上げ荒井由実(松任谷由実)やYMO、近年では、着うたフルで史上初のダウンロード数200万件を突破した、青山テルマ feat.Soulja「そばにいるね」などをプロデュースした。
※9. 飯倉キャンティ
イタリア料理店。1960年の創業以来、各界著名人が利用するレストランとして知られる。オーナーである川添浩史は川添象郎の父親。
※10. 安部公房(1924年3月7日 – 1993年1月22日)
小説家、劇作家、演出家。
代表作は、『壁』、『砂の女』、『他人の顔』、『燃えつきた地図』、『友達』、『箱男』、『密会』など。
※11. 村田 豊
建築家。
飯倉キャンティの設計を手がけた。
※12. 坂倉準三(1904年5月29日 – 1969年9月1日)
建築家。
パリ万国博覧会では日本館の設計を手がけた。その他、神奈川県立近代美術館、岡本太郎記念館、渋谷駅、国際文化会館、新宿駅西口地下広場、小田急百貨店なども手がけている。
※13. 黛 敏郎(1929年2月20日 – 1997年4月10日)
作曲家。
20世紀日本のクラシック音楽・現代音楽界を代表する音楽家の一人。『題名のない音楽会』の司会としても広く知られ、現代音楽の作曲家として多方面な活躍を見せた。
※14. 今井俊満(1928年5月6日 – 2002年3月3日)
洋画家。
パリでアンフォルメルの旗手として活躍。代表作に大原美術館所蔵「馬」、滋賀県立近代美術館所蔵「東方の光」などがある。紺綬褒章、フランス芸術文化勲章(コマンドール)を受賞している。
※15. ジェローム・ロビンズ(1918年10月11日 – 1998年7月29日)
アメリカ合衆国のバレエ・ダンス振付家。
ミュージカル『王様と私』、『ウエスト・サイド・ストーリー』、『屋根の上のバイオリン弾き』など多くのヒット作品の振り付けを手がけトニー賞を受賞。『ウエスト・サイド・ストーリー』が映画化された際にはロバート・ワイズと共に監督を務め、アカデミー賞監督賞他9部門を受賞した。
4. 23歳で売れっ子作曲家に〜ひたすら曲を書き続ける日々
−−村井さんが仕事として音楽に携わるきっかけはなんだったんですか?
村井:僕がこの商売を始めるきっかけは、ライトの先輩の今尾さんなんです。今尾さんは日本コロムビアの洋楽部で働いていて、僕は学生の頃よく遊びに行ってたんです。それで4年になると周りは就職活動をするわけですが、僕は就職する気がないので「どうしようかな?」って今尾さんに相談しに行ったら、今尾さんが「レコード屋でもやったらどうだ?」って言ったんですよ。「コロムビアの特約店の契約とってやるから」って。
−−今尾さんはなぜ「レコード屋やれば?」と村井さんにアドバイスされたんでしょうかね?
村井:なんだったんでしょうね(笑)。
−−「コロムビアに来いよ」とはおっしゃられなかった?
村井:「コロムビアに来いよ」とは言わなかったですね(笑)。どうして「レコード屋やれ」って言ったんだろうな・・・。
−−でも、「レコード屋やれ」と言われて「やってみようかな?」と思う村井さんもすごいですよ。
村井:それはレコードが大好きで、毎日レコードを聴いていられるからという単純な発想なんですよ(笑)。あと、毎日満員電車に乗って決まった時間に会社に行くのがちょっとつらいなと思って。レコード屋だったら自分の好きな時間帯で自分の好きなようなことができるから。
−−村井さんのレコード店(ドレミ商会)はどんなお店だったんですか?
村井:赤坂のホテルニュージャパンの隣に、ちょっとしたデパートみたいなものがあったんですが、そのデパート前がパリにあるようなカフェで、そこのオーナーの息子と友達だったんですよ。それでそのカフェに行ったら来ている客がレコードを買いそうな客層だったので、「場所を貸してくれ」ってお願いしたんです。僕がレコードを仕入れてきて売って儲かったら、儲けの半分を君に渡すからって。
−−ずいぶん軽いタッチですね(笑)。開店資金はどうされたんですか?
村井:前から親父から「自分の好きなことを見つけて、好きなことをやりなさい」と言われていたので、「好きなことを見つけて好きなことをやるんだけど、お金出してくれる?」ってお願いして貸してもらいました。
−−ちょっと話は前後するんですが、音楽をやっていた人が学校を卒業すると普通は就職の選択肢の他に「ミュージシャンになる」という選択肢もあると思うんですが、村井さんはそちらの選択はなかったんですか?
村井:幸か不幸か、僕は自分のピアノを弾く能力について自信がなかったんです。学生時代はホテルニュージャパンのラウンジでピアノを弾いてずいぶんいいお金を貰っていたりしたんですが、それを一生やってもと思っていましたし、ピアノの演奏では僕より上手い人がたくさんいますから、競争にならないと思ってました。
−−学生時代は色々なことをされていたんですね。
村井:TBSラジオでジャズのラジオ番組のディスクジョッキーもやっていましたからね。たまたまTBSラジオの人と知り合って「お前やらないか」って言われて。
−−それも大学時代ですか?
村井:そうです。大学時代はホテルニュージャパンでピアノを弾いて、ディスクジョッキーもやって。でも、どれも生業にするには大変だなと思って、レコード屋を始めたわけです。
−−レコード屋を始めた村井さんが曲を書き始めるきっかけはなんだったんですか?
村井:レコード屋をやってるときに、それまではジャズとかクラシックしか聴いてなかったんですが、売れるのはヒットソングじゃないですか? 当時売れていたのが『帰ってきたヨッパライ』や『ブルーシャトー』とかで実際にどんどん売れていく。それで「なんで売れるんだろう?」と思って、家に持って帰って聴いたりしているうちに「こんな曲なら書けるんじゃないか?」と思って、曲を書き始めました。それで小学校からの同級生の川村君という人が、当時シンコー楽譜に勤めてたんですよ。
−−全部友達で済んでしまうんですね?(笑)。
村井:そうそう(笑)。その川村君に「曲書かせてよ」って頼んだら、フィリップス・レコードの本城(和治)さんを紹介してくれたんです。それで本城さんのところで最初に書いたのが、ヴィッキーというギリシャの歌手の『待ちくたびれた日曜日』という曲で、これがチャートインしたんです。次に本城さんに頼まれて書いたのが、テンプターズの『エメラルドの伝説』で、大ヒットしました。
−−いきなり売れっ子作家ですね。まだ大学の出たての頃ですよね?
村井:そうですね。僕は’67年卒業で『エメラルドの伝説』が’68年ですね。
−−『エメラルドの伝説』以降は外れなしですか? この時代は。
村井:いや、やっぱり外れることのほうが多いですよ。
−−でも打率はいいわけですよね?
村井:3年ぐらいの間に300曲書いて、ナンバーワンが少なくとも4、5曲あったから、結構打率はよかったですよね。
−−それはすごいことですよ。曲はふとひらめく感じなんですか?
村井:ふとひらめくというよりは、どんどん注文が来るから、それをこなしていくしかないんですよね(笑)。とにかく大変ですよ。寝る時間なんてないですから。
−−ちなみにレコード屋も並行してされていたんですか?
村井:たまたまお店が入っていたデパート自体が売られてしまって、それもあって止めてしまいました。
−−23歳にして売れっ子作曲家としての生活が突如始まってしまって、そこに戸惑いみたいなものはなかったんですか?
村井:いや、戸惑っている暇すらないですからね。注文がどんどん来ちゃって・・・。
−−ひたすら曲を書く生活ですか?
村井:もう書くしかない(笑)。本城さんのところで曲が当たって、その後、ナベプロから誘いがくるんですよ。「タイガーズに曲を書いてくれ」とか言われてね。本城さんのところはすごく洋楽指向でしたけど、ナベプロでは辺見マリとか、いわゆる歌謡曲っぽいものをずいぶん書いていたんですが、そのうちに「自分が興味のある音楽をやりたい」という気持ちが大きくなって、それで制作にシフトしていったんです。
5. 著作権ビジネスの開拓

−−‘69年には川添さんたちとパリに行かれていますね。
村井:ええ。加橋かつみがタイガースを辞めたあと、戦前パリにいた川添の親父さんの繋がりで、フランスのバークレーレコードという会社に移籍することになったんです。それで川添と僕と一緒にパリで加橋かつみのレコードを作りました。その間にバークレーレコードの出版部門の人と会って、音楽著作権の仕事は将来性があると思っていたので曲の買い付けもしたんです。その中の一曲が『マイウェイ』です。
−−シナトラで有名な『マイウェイ』ですか?
村井:そうです。
−−それが24歳のですよね? 村井さんは作曲家としても超一流で、その上、ビジネスマンとしても先見の明があったんですね。
村井:その頃の日本は権利ビジネスと言いますか、著作権だとかまだ未成熟な時代でしたからね。
−−単純な疑問なんですが、24歳の若者が『マイウェイ』の権利を獲ってこれるものなんですか?
村井:どうなんでしょうね。今だったら難しいかもしれませんけどね。
−−「まだ誰も買ってなかったんですか?」みたいな話ですよね。
村井:そう。誰も買ってなかったから買えたんですよ。なにしろ当時のアメリカやヨーロッパの音楽業界で日本人を見たことある人が少なかったんですよ(笑)。
−−(笑)。
村井:これ、本当の話ですよ(笑)。
−−つまり日本人だから珍しがられて・・・ということですか?
村井:そうです。「おー、お前日本人か!」とか言われてね(笑)。当時、日本のレコード会社って電機メーカーの子会社が多かったので、割と普通の会社っぽくて、社員もサラリーマンっぽい人が多かったんですが、海外で音楽の仕事やってる人は音楽屋が多くて、僕は作曲家だから肌が合うんですよ。例えば、アーメット・アーティガン(※16)みたいな人と音楽の話で盛り上がったりね。
それで’69年にパリで『マイウェイ』を買って、翌’70年にはスクリーン・ジェムズという当時の出版最大手の日本における権利を獲りました。そこにはキャロル・キングとかニール・セダカ、バード・バカラックなどのカタログがありました。
−−なんでその大カタログを買えちゃうんですか? 売ってくれと言って二つ返事で売ってくれるわけではないんですよね?
村井:当時、日本は高度成長期で、世界中から注目はされていたけれど、アメリカやヨーロッパのほとんどの人が、日本も中国も韓国も区別がつかなかったんですよ。あとシンコーとか僕より前からやっている音楽出版社はあったけれど、そのほとんどが手紙のやりとりだけだったんですね。
−−実際に現地へは行ってなかったんですか?
村井:行くこともあったでしょうが、そう年中じゃない。僕は身軽でしたから、なにかあるとパリやニューヨークにすぐに飛んでいってました。フランスの同業者がアメリカの出版社を紹介してくれて、そこで僕はすぐに飛んでいくわけですよ。まだ24、5ですけど、音楽好きでカタログの音楽も知ってるし、「こいつ面白いからやらせてみよう」ってことで、やらせてもらった感じですよね。
−−お金の力じゃなくて人脈で権利を獲っていったんですね。
村井:そうですね。人脈とスピードですね。
−−そして実行力。
村井:今はインターネットがありますからリアルタイムでできますけど、昔は海外が想像以上に遠かったんです。僕は距離をもろともせずに、一日だけのためにニューヨークへ行っては帰ってきていましたからね。
−−それと村井さんは日本でヒット曲をたくさん書いていたことによって、自己紹介もしやすかったんじゃないですか?
村井:それも非常に強かったと思います。
−−ちなみに‘69年当時のパリとかニューヨークはどんな感じだったんですか?
村井:今でこそ日本もずいぶんシャレてますし、ご飯もおいしいし、だいぶよくなりましたけど、’69年当時はやっぱりパリのほうが何倍も格好いいわけですよ。だから、日本の全てが野暮ったいなと思っていましたね。当然、音楽も向こうのほうが全然いいですしね。
※16. アーメット・アーティガン(1923年7月31日- 2006年12月14日)
R&B/ジャズの名門レーベル、アトランティック・レコードの創設者。アメリカン・ミュージックの歴史に多大な功績を残した。
6. ユーミンとの出会いとスタジオA

−−24歳のときにアルファミュージックを設立されていますが、創業メンバーは村井さんと川添さんですか?
村井:音楽出版部門のアルファミュージックは僕と山上路夫さん(※17)、スタジオと制作会社のアルファアンドアソシエイツは学校の先輩であるヤナセ株式会社の梁瀬次郎さん(※18)との合弁会社です。
−−梁瀬さんとはどういう経緯で一緒に会社をやることになったんですか?
村井:ヤナセの子会社でTCJというコマーシャルを作る会社の専務をやっていた日比谷さんという先輩がいて、その日比谷さんが映画スタジオを田町の駅前に作ったんですよ。そんなに大きいものじゃなくて、ちょっとしたコマーシャルを撮るくらいのね。
−−撮影用のスタジオですか?
村井:撮影用のスタジオなんですが、「その上に録音用のスタジオを作ろうという案があるんだけど、村井君どう思う?」って相談を受けたんです。で、その仕様を見たら、古いスタジオ機材そのままだったので「これでは駄目ですよ」って言ったんです。
当時、世の中はちょうどマルチトラックに移行し始める頃だったので「まずマルチトラックだよね」って話になりました。それまでに僕はパリやロンドン、ニューヨーク、ロスで録音していましたし、その中でスタジオの変遷を見ていましたから、小ぶりなマルチトラックで、ハコがよく鳴るスタジオが日本にないから、そうゆうのを作ろうってことになったんですが、日比谷さんには合弁でやろう、ついては社長に一度会ってくれって言われて、それで梁瀬さんと初めて会いました。梁瀬さんとは親子ほど年が違うんですが仲良くなっちゃって、いろんなことを教えていただきました。
−−そのスタジオがスタジオAですね。
村井:そうですね。その後、YMOとか細野君たちが打ち込みをやっていると他のアーティストがスタジオを使えないので、ここ(LDKスタジオ)を作って細野専用にしたんですよ。
−−スタジオAの最初期の作品が荒井由実さんの『ひこうき雲』ですか?
村井:そうですね。スタジオがオープンしてすぐにユーミンのレコーディングを開始したと思います。
−−どのようなきっかけでユーミンのレコーディングをすることになったんですか?
村井:加橋かつみのパリで録音した作品も本城さんの仕事なんですが、パリ録音の次のアルバムを日本録音で作ることになって、本城さんに曲を依頼されて僕も1〜2曲書いたのかな。その録音にビクターの青山スタジオに行ったら、僕の前に録音した曲をかけていて、それがすごくいい曲なんですよ。「これいい曲だね。誰が書いたの?」って聞いたら、「これはユーミンっていう若い子の曲」って言うんですよ。それで加橋かつみにユーミンを紹介してもらって「あなたは才能があるから、うちの作家になりませんか?」って声をかけたんです。
そうしたらユーミンはまだ高校生だったので、半年か一年ぐらいして彼女が多摩美に入ってから作家として契約しました。当時は毎日学校が終わると渋谷からバスに乗って、三田のアルファミュージックに来て曲を書きためていました。だからスタジオができあがる頃には持ち曲が15曲とか20曲とかあったと思います。それで、かまやつさんのプロデュースで東芝(現EMIミュージックジャパン)からシングル盤を一枚出したんですが全然売れなくて、今度は細野に頼んで『ひこうき雲』の録音に入るわけなんですね。
−−最初、ユーミンは歌うつもりではなかったらしいですね。
村井:最初の出会いは作家としてですからね。歌だってそんなに上手いわけではないし。でも、なんか彼女独特の魅力があったんですよね。あと、シンガーソングライターの時代にだんだん変わっていくときだったのも大きいですね。そういう自然な成り行きで彼女自身が歌うことになりました。
−−『ひこうき雲』の中身に関しては、細野さんに任せて、村井さんはそんなに口を出さなかったんですか?
村井:いや、すごい出しましたよ(笑)。まず一番の大枠はティン・パン・アレーと一緒にやるということで、スタジオでのやり方はA&Mの小さいスタジオで、プロデューサーのルー・アドラー(※19)がキャロル・キングとアルバムを作ったりする様子を見ていたので、そのやり方を参考にしました。
−−A&Mのスタジオで得た手法をユーミンのレコーディングでそのまま使ったと。
村井:そうですね。ただ、僕も他の業務が色々ありますから、四六時中立ち会ってるわけにはいかないので、スタジオではディレクターの有賀恒夫とエンジニアの吉沢典夫が立ち会ってずっとやっていました。それで僕はときどきスタジオに行っては「これはダメ」とか「これはこうして」とか言ってね。
−−ちなみに細野晴臣さんとはいつ頃出会われたんですか?
村井:川添が『HAIR』というミュージカルを演出したときに、小坂忠が『HAIR』に出ていて、細野は小坂忠の友人だったんです。彼とはその頃からの知り合いで、僕は彼のミュージシャンとしての能力に非常に惹かれていたわけです。最高のベースプレイヤーでね。だから最初はミュージシャンとしての細野との付き合いで、僕のセッションに彼を連れてきてベースを弾いてもらうとか、赤い鳥のバックで彼が弾くとかそういうことをやっていたんですが、そのうちに彼自身もアルバムを作るようになって、ユーミンのレコード作るときには真っ先に細野に相談したんですよ。
−−そうしたら細野さんがティン・パン・アレーのメンバーを連れてきたと。
村井:そうですね。
※17. 山上路夫(1936年8月2日 – )
作詞家。
村井邦彦とともにアルファミュージックを設立。赤い鳥「翼をください」を始め、アグネス・チャン、天地真理、麻丘めぐみ、岩崎宏美、沢田研二、小柳ルミ子、野口五郎、ザ・ワイルドワンズなどの作曲を手がけた。
※18. 梁瀬次郎(1916年6月28日 – 2008年3月13日)
自動車ディーラー、株式会社ヤナセの二代目会長。父はヤナセ創業者の梁瀬長太郎。
※19. ルー・アドラー(1933年 – )
ダンヒル・レコードの創設者。バリー・マクガイア、ママス&パパス、グラスルーツ、スリー・ドッグ・ナイトといったアーティストを輩出し、フォーク・ロック時代に大きな足跡を残した。その後キャロル・キングをプロデュースする。
7. アルファレコードの成功と挫折

−−その後、アルファレコードを設立されますね。
村井:この時代、ユーミンでやったのはいわゆる原盤制作なんですね。ユーミンが当たってずいぶん儲かったんですが、やっぱりレコード会社を作らないと大変なんですよ。なんで大変かというと、当時東芝でユーミンのレコードが一枚売れると、そのうち10%か12%が原盤使用料なんですね。だから収入はアルバム一枚売れて200円かそこらですね。ということは100万枚売れて2億円ぐらいになるんですが、制作費とかいろいろな経費を考えると2億円ぐらいかかっているわけですよ。だから全然割に合わない。
−−100万枚売れて割に合わないんでは、どうしようもないですよね。
村井:それで思ったのが、このままやっていったって制作部門であるアルファアンドアソシエイツの事業は難しいだろうということで、制作だけじゃなくてマーケティングまで自分たちでやろうと考えたのです。それでアルファレコードを設立しました。
−−当時の日本にはそういうスタンスのレコード会社って他にはなかったんじゃないですか?
村井:そうですね。アルファレコードの他には、ほとんど同時期にできたフォーライフとキティくらいですかね。全世界的にはアトランティックなんかは古いですけど、アイランドとか小さいレーベルから始まったレコード会社がいっぱい出てきた時期ですね。
−−そしてアルファレコードはYMOへ繋がっていくわけですね。YMOも細野さんから始まっているんですよね。
村井:そうですね。海外で通用するというか、要するにワールドワイドで売れるものを作りたいという想いをずっと持っていて、細野もそう思っていたわけです。それで色んな企画を考えてたどり着いたところがYMOなんです。
−−「こういうものだったら世界で勝負できる」という分析を色々されたんですか?
村井:そうですね。まず言葉の問題があるとかね(笑)。
−−では、YMOのヒットはきっちりとマーケティングした結果?
村井:いや、実際は試行錯誤でしたよ。まず細野が日本語でしか歌えないシンガーを海外に売るのはなかなか難しいだろうと言うので、リンダ・キャリエールという歌手を見つけてきて、一枚レコードを作ったんですが、歌があんまりよくなくてお蔵になっちゃう。その次に彼は『はらいそ』っていうYMOの前身のアルバムを作ったんですが、それも2,000枚ぐらいしか売れなくて失敗に終わるわけです。それで最後にたどり着いたのが、細野、坂本龍一、高橋幸宏のイエロー・マジック・オーケストラだったんです。
−−その頃、村井さん自身は作曲されていない時期で経営とプロデュースに専念されていたんですよね?
村井:その頃はアルファレコード以外にA&Mレコードのライセンスを獲ってきてやってましたからね。当時、スティングがいたポリスとかリタ・クーリッジ、カーペンターズとかそういうアーティストたちのレコードを宣伝して日本で売らなきゃいけないでしょう?
−−曲を書いてる暇なんてなかったと。
村井:もう、全然ないですよ(笑)。
−−スクリーン・ジェムスのライセンスを獲ったのと同じようにA&Mレコードのライセンスを獲ったというニュースは業界中を驚かせましたよね。そのときはお幾つだったんですか?
村井:まだ30歳そこそこぐらいですね。
−−それからロサンゼルスに拠点を移されるわけですが、そのきっかけはなんだったんですか?
村井:アルファレコードの最盛期が’80年ぐらいなんですが、その頃に僕が夢見たのは海外進出でした。アルファレコードを全世界で成功させようということで、ロスにアルファアメリカという会社を作って、そっちのほうに仕事を集中していったんです。ところがバックアップ体制がよくできていなくてね・・・。つまり、当時の取引銀行に僕たちの仕事が充分に理解されていなかったんですよ。その頃の日本の会社って自動車を作るとか、テレビを作るとかで、そういう会社には銀行の理解があるんですが、僕たちみたいな当たるか当たらないかわからないような商売は信用してもらえないんですよ(笑)。
それでとりあえずアメリカで会社をスタートするだけの資金は調達してすぐ始めたんですが、1年ぐらいやって、これからってときに「もうこれ以上お金は出せない」ってことになって、結果としてアルファアメリカは大失敗するわけです。そのときに出していたビリー・ベラっていうアーティストのレコードがアルファアメリカをたたんだ後に1位になったので、あと2年か3年続けられる資金があれば、もうちょっと様になっていたんですけどね・・・。
−−資金はあと幾らくらい足りなかったんですか?
村井:30億だったか60億だったかそれぐらいかな(笑)。やっぱりアメリカで仕事するとすごくお金がかかるんですよ。国が大きいし、マーケットも大きいですから。
−−全てが大きいんでしょうね。その分見返りも大きいんでしょうけど。ちなみに他の銀行から借りることはできなかったんですか?
村井:リスキーな種類の仕事に銀行がお金を貸すということはあり得ないですね。
−−では、ここで初めて挫折を味わうわけですか?
村井:そう。大挫折です。途中は省略しますが、結果、その失敗によって僕は自ら作ったアルファレコードを退きました。その後もLDKスタジオはずっとやっていましたけど、’80年代に今度はアメリカで音楽出版社を始めるんですよ。その会社はB.B.キングやフリートウッド・マックといったアーティストのワールドワイドの著作権を所有する会社で、’91年頃からだんだんアメリカでの生活が長くなったので、‘92年に家族を連れてアメリカに引っ越しました。
それで’01年にその会社を売却して、もう一回作曲の仕事をしようと思って日本に帰ってくることが多くなりました。今はヴィラス・ミュージックをベースに作曲や制作をやっていこうと思っているんですが、ご存じの通り、レコード業界の景気が悪いですから(笑)、なかなか大変なんですけどね。
−−今でも活動の本拠地はアメリカなんですか?
村井:まだ向こうが本拠地で行ったり来たりしています。向こうで曲を作っていることがすごく多いですから。
−−最近はプロツールスかなにかでお作りになっているんですか?
村井:いや、僕は相変わらずピアノで作っていますよ(笑)。
8. やっぱり音楽が一番!〜魅力のある音楽を生み出したい

−−今はインターネットによって音楽産業はCDという主力商品を失いつつあるわけですが、今後どう手を打っていけばいいと思われますか?
村井:それが分かれば苦労しないんですよ、本当に(笑)。色々な側面がありますが、まず認識しなくてはいけないことは、今は大変革期にあるということですよね。デジタルやインターネットの技術は、恐らくグーテンベルグが印刷を始めたこととか、それぐらいインパクトのある出来事なわけですから、今までの延長線で考えちゃいけないっていうことだと思うんです。では、今までの延長線じゃなくてなにがあるのか? と考えたときに、この混乱の中ではそんなに見通しが利かないから、みんな困っているんでしょうね。
今までの価値観で壊されている一番大きなものは知的所有権ビジネスで、権利がタダ同然みたいになってきてるから大変です。これは音楽だけの問題じゃなくて、今はたいていのものがインターネットでタダで手に入ってしまう。結局みんな戻っていくところはライブです。知的所有権とかそういう問題じゃなくて、入場料やグッズの販売でお金を取るわけだからキャッシュ収入になりますよね。そういう野蛮な状態に戻っているのが現状でしょうね。
−−音楽産業がコンテンツの中でも真っ先に被害を受けて、これから映画はもちろん、テレビ、出版、新聞と続くのでしょうね。アメリカなんて新聞がボロボロだそうです。
村井:日本だってボロボロですよ(笑)。出版社、テレビ局、電通、博報堂なんかの現場で数字見ている人たちは、驚愕の数字を見ているんだと思いますよ。
−−本当に衝撃ですよね、今の状況は。
村井:そこで考えるのは「音楽そのものはどうなっているんだろう?」ということなんですよ。20世紀は今までなかったような音楽、例えば、ジャズが生まれたり、ロックが生まれたり色んな音楽が生まれてきましたよね? 今まではなかったものだから、みんなびっくりするぐらい興奮して聴きました。そういうものが今生まれているかどうか、生まれてくるとしたらどこから生まれてくるか。そういったことにも興味がありますね。
とにかく魅力のある音楽ができてくれば聴衆はみんな熱狂すると思うんですよね。ただ、それをCDの形で買うかはわからないですが、その音楽にみんな寄ってくると思うんです。そして、そこにはなんらかのビジネスチャンスが生まれてくると。でも最近テレビやラジオ、iTunesでちょっと聴いても、びっくりするような曲ってあまりないですよね。
−−ないからそういうものを自ら生み出したいというお気持ちはありますか?
村井:ありますね。ただ僕の場合は潰れないようにして作ってるんですよね (笑)。生き延びて作り続けていれば、そのうちなにか生み出せるかもしれません。
−−最近ではどんな音楽を聴いてらっしゃいますか?
村井:ヴィラス・ミュージックの共同経営者は上野隆司っていう発明家なんですが、この人は親子二代にわたってクラシック音楽をサポートしてきたんです。どういうサポートしてきたかというと、お父さんはストラディバリウスというバイオリンをたくさん持っていて、若くて優秀な音楽家に名器を貸し与え、その演奏家が世界で活躍する。息子はワシントンDCに住んでいて若い芸術家を助ける基金を持っていて、毎年賞を出して助けているですね。それを二代にわたってやってるからクラシック界にすごい人脈があるんです。その上野家が育ててきた演奏家はクラシックの人が多いので、そういう人たちの音楽を今聴いています。最近、僕が聴いたのでは小菅優という27歳くらいの滅茶苦茶上手いピアニストですが、彼女の演奏会を聴きに行って感動しました。クラシックを聴く機会がすごく多いです。
これは自分の肉体的かつ生理的なことですが、最近電気で増幅した音にすごく弱くなったというか嫌なんですよね。その点クラシックは生で音が聴こえるでしょう? 書くほうもクラシックのピアニストのためのピアノ曲とか、お付き合いがどんどんそっちに広がっています。あとはテレビドラマの音楽を書くとか、そんなようなことをやっています。とにかく生き延びて作り続けるしかないですよ(笑)。
−−村井さんは開拓精神が旺盛と言いますか、スピリッツがお若いですね。
村井:(笑)。興味のあることをずっとやってると面白いですしね。クラシックは昔から嫌いじゃなかったですが、仕事が絡んでくると聴き込むようになりますからね。
−−そして、どんなに苦しい状況になっても村井さんは音楽からは逃れられないと・・・。
村井:それはもう(笑)。やっぱり音楽が一番ですよ。
−−本日はお忙しい中ありがとうございました。村井さんの益々のご活躍をお祈りしております。
(インタビュアー:Musicman発行人 屋代卓也/山浦正彦)
とてもおおらかで笑顔を絶やさない村井さん。人柄の良さがにじみ出ており、お話をお伺いしている私たちも楽しい気持ちにさせていただきました。今回のインタビューでは、山あり谷ありの波瀾万丈な半生にも関わらず、「やっぱり音楽が一番ですよ。」と微笑む村井さんの姿が印象的で、本当に音楽がお好きなんだなと感じました。現在も作曲家としてTVドラマ音楽の制作など精力的にご活躍されている村井さん。今後も心に残る素晴らしい楽曲を作り続けてくださることを期待しています。

広告・取材掲載