元『ヤング・ギター』編集長・山本隆士氏インタビュー【前半】

中央大学在学中から新興楽譜出版社社(現シンコー・ミュージック・エンタテインメント)のジャズ誌『ダウンビート』でバイトを開始し、『ミュージック・ライフ』の副編集長を経て、1969年に『ヤング・ギター』を創刊。以後、98年まで30年の長きにわたり編集長を務めた山本隆士さん。同時にライヴイベント、TV・ラジオ番組制作、レコーディング・プロデューサーなど幅広く活動されてきました。まさに山本さんのキャリア=日本のロックの歴史とも言えるシーンの重要な語り部です。
また、1968年にいち早く渡米し、以後、英米の有名ミュージシャンとも数多くの親交を持つ山本さんに、その膨大な記憶の中から当事者でしか感じ得ない時代の空気も含めて、お話を伺いました。
中学時代に浴びたロックンロールの洗礼
──本日は、時間がいくらあっても足りないのは重々承知の上で、山本さんの膨大なキャリアをかいつまんで伺っていきたいと思います。
山本:最初に断っておくと、僕よりもデータ的に詳しい人は、いくらでもいると思うんですよ。
──ですが、山本さんは50〜70年代の空気を肌で知っている人なわけじゃないですか? その山本さんの発言は大変貴重だと思います。
山本:確かに僕はその時代を生きて、匂いを嗅いじゃった人だからね(笑)。あの時代の空気って強力な匂いなんですよね。それをどう表現したら良いのかというのが難しいけどね。僕はライターでもないので。
──そこを読者の方々に少しでも感じてもらえたらと思います。まず、山本さんの生い立ちから伺いたいのですが、千葉県の生まれだそうですね。
山本:1942年3月7日、千葉県生まれです。3歳までは目黒不動尊のそばで育ち、終戦の年の5月に千葉の片田舎に疎開のような形で引っ越したんですよ。
──小さいときから音楽には親しんでいたんですか?
山本:父親が作曲家だったから、音楽は身近でしたね。1955年くらいにはギターを弾いていたんじゃないかな。でも、その時代は良いギターなんてなくて、鉄弦ギターしかなかった。それで先輩たちが弾いていたギターを見よう見まねで弾いてね。
──クラシックギターに鉄弦を張って?
山本:クラシックギターとも言っていなかったし、ただ単に鉄弦を張った粗悪なギターって感じですよね。それで、春日八郎や三橋美智也の曲を弾いたりしましたね。
──音楽は主にラジオからですか?
山本:そうですね。中学校のときからラジオを聴きながら洋楽のチャートをメモってね。文化放送の「100万人のポップス」とか。それで中学の終わり頃に当時、アメリカのラジオDJ アラン・フリードが「ロックンロール」と呼び始めて、それが世界中に定着したきっかけとなるのが映画『暴力教室』の主題歌であるビル・ヘイリー&ヒズ・コメッツの「ロック・アラウンド・ザ・クロック」だったんだよね。そうして「ロックンロール」が広まっていったわけですよね。その後、出てきたのがエルヴィス・プレスリー。
──日本ではロカビリーなんて言われましたけど。
山本:あれは、カントリー&ウエスタンをやっていた連中と、ハワイアンをやっていた連中がロックンロールを演奏して、神仏融合じゃないけど(笑)、ロカビリーというものができあがってきちゃったわけですよ。もちろんアメリカが発祥なんだろうけどね。
──ロカビリーとは日本独自のもの?
山本:正確にはカントリーの中のヒルビリーとロックンロールが融合したものじゃないのかな。
──そういったライブを実際に見ていたんですか?
山本:うん、ライブハウスに入り浸りですよ。千葉から東京・有楽町へ出て、友達と一緒に銀座ACB、三原橋・ニュー美松とか結構行きましたね。
──それっていわゆる不良ですよね?(笑)
山本:不良ですよ(笑)。とにかくロカビリーは大ブームでしたよね。客席は男の子も女の子もたくさんいたけど、女の子たちは大興奮でね。だってパンツを脱いでステージに投げちゃうんだから(笑)。失神する子たちがいくらでもいたよ。もうギターなんて鳴らなくていいんですよ。ステージにテープがお客さん100人ぐらいからバンバン投げ込まれているんだから、まともにギター弾けるわけないしね。
──それが高校生の頃ですか?
山本:そうですね。1958年のときが最大のブームだったね。ポール・アンカ、ニール・セダカ、デル・シャノンなどが世界的にブームになっていて、その中でもロカビリーの王者のようなポール・アンカが初来日して浅草国際で公演を行った頃が全盛時代だったね。和製ポップのブームがあって、それは海外のポップスの訳詞を手がけてブームにしたのが漣健児(注1)だったんだよね。
──坂本九の「上を向いて歩こう」がアメリカでビルボードNo.1を取ったのが1963年頃ですよね。
山本:うん。そうだね。「スキヤキ」でね。
──テレビ番組の「夢であいましょう」とか「シャボン玉ホリデー」もよく観ていたんですか。
山本;うん。ほかに観るものもなかったしね。今ふと思ったけど、1958年って時代の転換点という意味では、10年後の1968年によく似ているんだよね。1968年にGSが終焉してたから、翌1969年に日本のフォークとロックの黎明期になるわけでね。アメリカもそうですよね。1969年に色々なシーンにロックが生まれてね。「ウッドストック」もあったし。
(注1)草野昌一(1931-2005):シンコーミュージック・エンタテイメント元会長。父が経営する新興音楽出版社(現:シンコーミュージック・エンタテイメント)から雑誌『ミュージックライフ』を復刊し初代編集長を務めた。1960年に音楽出版業務を開始、1965年には音楽出版社として日本で初めて原盤制作を行うなど、日本の音楽出版ビジネスの先駆者。また、「漣 健児」のペンネームで数多くの訳詞を手がけた。
バイト時代のシンコーでの仕事は植草甚一氏の原稿取り
──大学で東京に出てきたんですか?
山本:そう。大学入学とともに上京して、何もせずにブラブラしていたら夏休みになっちゃって、「休みの間、何かしなきゃなんないな」と、シンコーミュージックでバイトを始めたんですが、あの頃は人手がとにかくいなくて、いきなりジャズ雑誌『ダウンビート』の原稿取りに行かされてね。
今日、ここに来るときに小田急線に乗って懐かしくなったんだけど、豪徳寺に植草甚一(注2)さんが住んでいて、そこへ原稿を取りに行ったんですよ。そうすると「山本君、夕飯食べていきなさいよ」って親切にしてくれてね。それで、ごちそうになって植草さんが「山本君、これから僕は新宿に出るから一緒に行こう」って、新宿のジャズ喫茶「木馬」とかに連れて行ってくれたんですよ。
──『ダウンビート』はジャズ雑誌ですが、そのときはジャズがお好きだったんですか?
山本:好きになったんだね。東京に出てきたときには「もうロカビリーじゃないだろう」という気分がありましたし、モダン・ジャズを聴くのがかっこよかったんだよね。それであちこちのジャズ喫茶に入り浸ってね。上野・イトウ珈琲、巣鴨・KADO、新宿・DIG、木馬、渚、き〜よ、渋谷・オスカー、横浜・ダウンビート、有楽町・ママ、お茶の水・ニューポートとか、とにかくたくさん行きましたね。
──植草甚一さんのご自宅に行けるなんてうらやましいです。
山本:本当だよね。シンコーの日本版『ダウンビート』はすごくかっこいい雑誌で、それに憧れてバイトを始めたんだよね。それで初めてジャズのライブを観たのが、アート・ブレイキー&ジャズメッセンジャーズの来日公演。1961年の正月に来日したんですよ。東京都体育館だったかな。当時、友達たちとジャズサークルを作っていて、お金がなかったから「おまえ、今月はこのレコードを買え」ってレコードをそれぞれで買っては貸し借りしてね。
──大学時代はずっとシンコーミュージックでバイトですか?
山本:正直いって途中で辞めようと思うこともあったんだけど、辞めさせてくれないんですよね(笑)。当時桜井ユタカ(注3)もシンコーで一緒にやっていたんですよ。その後独立して音楽評論家としてご活躍されましたけどね。僕はクラシック音楽系もやったんだよね。クラシックピアノの小品集とか。上手に弾けるハノン、とか。ベンチャーズがブームになった頃はパート譜も作ったし。
それで『ミュージック・ライフ』に移って、やっぱり大きかったのは1966年のビートルズ来日ですよね。来日中はホテルに張りついてね。あの頃はビートルズやウォーカー・ブラザーズがすごい人気で、ウォーカー・ブラザーズなんてスライド・コンサートをやったんですが、その座長が僕ですよ(笑)。スライド・コンサートをひっさげて全国を回るんだから。「ポール対スコット」の時なんて、すごかったなぁ。
──フィルム・コンサートは知っていますが、スライド・コンサートって聞いたことがないです。つまり写真を見ながら音楽を聴くんですか?
山本:うん(笑)。のちにレコード会社に16ミリのフィルムがあると分かって、フィルム・コンサートと合わせてやるようになりましたけどね。ビートルズだって長谷部宏さん(注4)が撮った『ミュージック・ライフ』の写真しかない時代ですし、写真自体が貴重だから、すごく人が集まるんですよ。天賞堂へ行って、一番大きい幻灯機を買って、長谷部宏さんが撮った写真と通信社の写真を大写しして、音楽を爆音で鳴らしてね。それはウケましたよ。女の子達、キャーキャーですよ。ロカビリーの再現かと思いましたね。
──長谷部宏さんってありとあらゆる来日アーティストの写真を撮っていましたよね。
山本:そうですね。星加ルミ子(注5)さんが初めてアビーロード・スタジオでビートルズと会ったときの写真が長谷部さんだよね。それが1965年の『ミュージック・ライフ』の表紙になった。ローリング・ストーンズのジャマイカ・レコーディングの様子も撮ったりね。もともとは映画雑誌の『スクリーン』で写真を撮っていた人なんだよね。で、草野昌一さんと古い友達で。
──世界でもロックミュージシャンを撮った数はトップなのではないでしょうか。
山本:おそらくトップだね。本当にすごい人ですよ。
(注2)植草甚一(1908-1979):映画・ジャズ評論家、随筆家。1935年に東宝に入社しプログラムや字幕スーパーの作成に携わるが、1947年東宝争議をきっかけに退社。以後、映画やジャズ評論、海外文学の翻訳・紹介、月刊「宝島」の刊行など、あらゆるカルチャーに精通し、幅広い執筆活動を行なった。
(注3)桜井ユタカ(1941-2013):音楽評論家。法政大学卒業後、新興楽譜出版(現シンコー・ミュージック・エンタテインメント)に入社。「ミュージック・ライフ」「ティーンビート」「ヤングミュージック」等の音楽誌編集に携わった後、独立。ソウル・ミュージック、R&Bを中心に雑誌、ライナーノーツなどを多数執筆した。
(注4)長谷部宏(1930- ):近代映画社でカメラマンのキャリアをスタートし、1960年代から1990年代まで、多くの洋楽ミュージシャンを撮影した。1965年に、日本人カメラマンとしては「ミュージック・ライフ」で初めてビートルズを撮影したことで知られている。
(注5)星加ルミ子(1940-):音楽評論家。1961年、新興楽譜出版社(現シンコーミュージック・エンタテイメント)入社、ミュージック・ライフ編集部に配属される。1965年、ロンドンに渡り、日本人ジャーナリストとして初めてビートルズとの単独会見に成功。1975年、シンコー・ミュージックを退社まで編集長として活躍。以後、フリーの音楽評論家として活動。
https://www.musicman.co.jp/interview/19237

「落ちているゴミまで違う」1968年のアメリカ体験
──山本さんは1968年、26歳のときにアメリカへ行かれていますね。あの時代のアメリカに行ったというのはすごくうらやましいです。
山本:「ウッドストック」の前年ですからね。ヒッピー、フラワームーブメント真っ盛りの頃でね。実はその前年1967年に亀渕昭信(注6)さんが「モンタレー・ポップ・フェスティバル」に行っているんだよね。それで「ウッドストック」を観ている日本人は成毛滋(注7)一人。吉成伸幸(注8)はグレイトフル・デッドのライブを観ている。
──どのくらいの期間行っていたんですか?
山本:45日ぐらいだったかな。もうとにかくショックだったよね。行く前と後では人間が変わるくらい(笑)。逆に日本が見えるんだよね。対比するわけじゃないけど、あまりにも違うし、たった45日間なんだけど、そのときに吸った空気と嗅いだ匂いはすごいものだったんだよね。
──何が一番違ったんですか?
山本:もう、なにもかもだよ。ゴミまで違うものね(笑)。
──(笑)。そもそもアメリカへ行った目的は何だったんですか?
山本:研修!(笑)一応はね。当時、1ドル360円で観光ビザだと一人500ドルしか持っていけないのに、僕たちは研修で行くから、一人2,000ドルまで持っていけたんだよね。やっぱり、このアメリカ行きから何かが始まったような気がするよね。
──観光もされたんですか?
山本:どうせだったら北米大陸を横断しようと思ったんだよね。ステーションワゴンで。あの頃は行けども行けども車はいないし、砂漠地帯を抜けて山を越えるとまた同じような風景でね。
すべてそうなんだけど、とにかくスケールが大きい。特にグランドキャニオンを観たときには圧倒されたよね。それでペイジというところで宿を取って、ザイオン国立公園の中を通って、ルート66に入りソルトレイクシティー、そこからロッキー山脈に入り、デンバーで車を返して、飛行機でニューヨークだね。ニューヨークでは、それこそティン・パン・アレイ(注9)とかで研修をやったんですよ。
──ニューヨークでは他にどこへ行かれましたか?
山本:グリニッジ・ヴィレッジに行きました。当時、日本人で行ったのは僕たちしかいないと思う。その年の秋くらいに横尾忠則さんが行ったんじゃないかな? 横尾さんのニューヨークの映像を観て「あ、行ったところだ」と思ったからね。当時のグリニッジ・ヴィレッジはフォークタウンで、ボブ・ディランがデビューする前にライブハウスで飛び入りしたとか、そういうエピソードのある街だよね。
──ちなみにフィルモア・イーストにも行きましたか?
山本:行ったんだけど、ここのところだけ記憶が曖昧なんですよ。ニューヨークの後は、ナッシュビルに行ったんだけど、そこにシンコーの著作権契約会社があったんですよ。ハンク・ウィリアムスの権利を全部持っているエイカフ・ローズという会社で、同じ場所にヒッコリーというレコード会社があってね。そこでも色々なお勉強をして、そこからサンフランシスコへ向かいました。
──ハイトアシュベリーにも行きましたか?
山本:行った。これはやっぱり強烈な体験だったね。センム(草野昌一氏の愛称)とかは「危ないから行くな!」って言うんだけど、僕なんかそっちの方が興味があるわけでね(笑)。だから夜、各自部屋へ戻った後に、一人でこっそり宿を抜け出して行ったんだよ。サンフランシスコはわかりやすい街だしね。それで行ったらヒッピーたちがすごく良くしてくれてね。
──当時、シンコーにはたくさん社員がいたと思うんですが、なぜ草野さんは山本さんを連れて行ってくれたんですか?
山本:いや、解りません。あの頃、社員はたくさんいないよ。だから、僕みたいなやつでも連れて行ってくれたんだよね(笑)。やっぱり、あの旅が一番良かったなと今でも思いますよ。それでサンフランシスコからハワイへ行って遊んでから帰ろうと。センムは意外と遊びたいんだよ(笑)。それでサンフランシスコ最後の夜もヒッピーたちに会いに行って、あの頃は片言の英語だったけれど、それが逆に良かったんだよね。
(注6)亀渕昭信(1942-):1964年 ニッポン放送入社、番組制作部に配属。1966年から一年間の米国留学を経たあと、約4年間、オールナイトニッポン・パーソナリティーを担当。その後、おもに編成業務をこなし、1999年、ニッポン放送代表取締役社長就任。2008年 ニッポン放送退社後もラジオDJ、音楽評論家として活躍。
(注7)成毛滋(1947-2007):ギタリスト、キーボーディスト。フィンガーズ、ストロベリー・パス、フライド・エッグなど1960年代後半から1970年代を中心として国内のロックシーンで活躍した。元祖天才ギタリスト。
(注8)吉成伸幸(1948- ):音楽評論家。立教大学在学中にサンフランシスコ州立大学に留学、1969年から1972年まで3年間を過ごす。卒業後、音楽雑誌の編集、レコード会社、音楽出版社勤務などを経た後独立し、自らの音楽出版社を設立する。
(注9)ティン・パン・アレイ:アメリカ合衆国ニューヨーク市マンハッタンの28丁目のブロードウェイと6番街に挟まれた一角の呼称。音楽権利出版社や演奏者のエージェントが多く集まり、楽曲の試演を行っていたため、まるで鍋釜でも叩いているような賑やかな状態だったことからこの名がついた。

時を超えてロビー・ロバートソンと。
読者にギターを弾かせよう〜『ヤング・ギター』創刊
──アメリカ45日間の旅を終えて、帰国したときどんな心境でしたか?
山本:ぶっ飛んでた。と同時に日本のシーンを冷静に見つめていた。そして今まで気がつかなかった日本が見えた。アメリカにすぐ帰りたかった(笑)。日本の匂いは薄かったのかな。空気は重いが、強烈なロックの匂いもしないじゃないですか。あの頃の日本って刺激がなくてね…。この時一番よく聴いていたのがレッド・ツェッペリンIIだった。「Whole Lotta Love(この胸いっぱいの愛を)」とかね。
とはいえ日本でも何かがやっと出てきた時代でもあるんだよね。本気で何かをやろうとしていた人たちが、いつの間にか「GS」というメジャーのベルトコンベアにのっちゃって、「自分たちは本当はどんな気持ちで音楽をやりたかったんだっけ…?」と考え直した時代かもしれない。
GSってマスコミによって踊らされたといわれていたけど、本職の作詞家、作編曲家が作品を作っていたから、いい曲ばかりだったんだよな。シンコーでも草野さんがカーナービーツにゾンビーズのカバー「好きさ好きさ好きさ」をやらせたりしていたね。草野昌一の訳詞ネームが漣健児で一世を風靡していた人だから。
GSの中でも演奏もしっかりしているグループもいたし、それぞれ雰囲気を出していたな。ゴールデン・カップスにはミッキー吉野、柳ジョージとか実力ある人が入っていたり。スパイダースも良かったよね。井上堯之さんも海外を意識したものを作っていたし、かまやつひろしさんは元カントリーシンガーだったけど、センスのいい人だから良い曲をたくさん作ってたよね。どのバンドもそれぞれの個性があって今でも愛されているんじゃないの。
──そのあたりから日本も歌謡曲から脱していったと。
山本:そうだね。一方フォークだよね。シンガーソングライターと言われる人たちも出てきて。
──ちなみにザ・フォーク・クルセダーズの「帰って来たヨッパライ」は1967年ですね。
山本:あとURC(アングラ・レコード・クラブ)ね。URCはもともと高石音楽事務所だったんですよ。それを秦政明さんが買って、アート音楽出版を作り、URCとして手持ちで売っていたんだよね。高石さんももともとはカントリーシンガーだったんだよね。そのURCの秦さんが中心になって全日本フォークジャンボリー(中津川)を開催して、それが日本の屋外コンサートの走りだったんだよ。ウッドストックも同じ年に開催したよね。それとELECのインディーズとしての存在もあった。
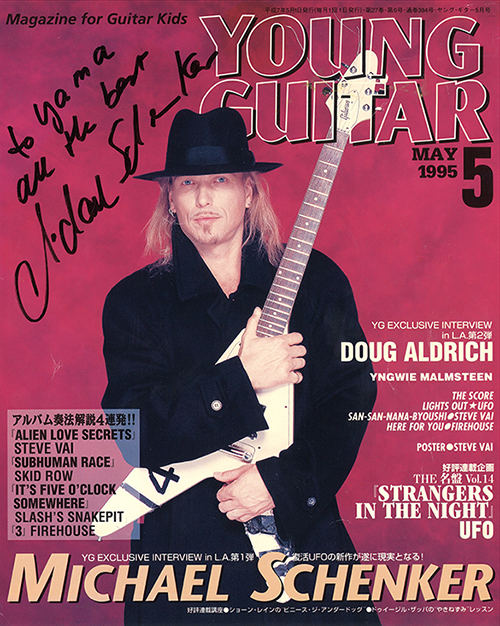
『ヤング・ギター』
──そして、1969年に『ヤング・ギター』を創刊されますが、当初はどのような構想だったんですか?
山本:『ヤング・ギター』の始まりは結構いい加減だったというか、まずは売れなくてはいけなかったんですよ。草野さんは売れなかったら「即止めろ!」の人でしたから。それで、まずは読者にギターを持たせよう、弾かせようと思ったんですよ。そこで理論は紙面の1/5くらいにして、あとは「この曲を弾きたい」と思うような曲を紹介してこうと考えました。
あの頃『平凡』とか『明星』の付録として歌本がついていたんですよ。ところがあれではギターが弾けないんですよ。レコーディングをするときのボーカルのキーに合わせた楽譜だから、シャープとかフラットが5つくらいついてるんだよ。
それでPPM(ピーター・ポール&マリー)のコンサートのときに、彼らがカポタストをつけて弾いているのを思い出して、カポタストを付けることを考えたの。そうしたら誰でも知っているコードで弾けるじゃないですか。それと、PPMフォロワーズが作ったPPM奏法(朝日ソノラマ)、エレキギターは「グレコの付録(成毛滋)」を参考にした。
──私もカポ付けて弾いてました(笑)。
山本:そうしたら本も売れてね。
──当時『ヤング・ギター』はどのくらいの部数が出ていたんですか?
山本:創刊号が完売しちゃったんだよね。
──専門誌でいきなりそれはすごいですね。
山本:僕は月刊誌なんて考えていなくて、季刊誌でいいと思っていたんだけど、売れたもんだから、草野さんが「すぐ月刊にしろ!」と(笑)。僕の身体壊れちゃいますといって隔月刊にしてから月刊にしたんです。
──『ミュージック・ライフ』はモンキーズとかもよく取り上げていましたよね。
山本:モンキーズもやっていたね。モンキーズで思い出したけど、アメリカに行ったときにマイク・ネスミスの家に行ったら、メイドが間違ったかちゃんと家の中に入れてくれたんですよ。現地では小林さんというアメリカ在住の女性がケアしてくれたんだけど、その人がいたから、後に僕がはっぴいえんどのロサンゼルス・レコーディングをコーディネートしたときにもお世話になったんだよね。
──その小林さんは現地のコーディネーターなんですか?
山本:いや、銀行員です。レコーディングとかには一切関わらないんだけど、お金の出し入れとか管理を頼んでいたんだよね。ミュージシャンのギャラを払うためにチェックを切ってもらったり、それは助かりましたね。一番肝心なことですから!
▼後半は11月5日公開予定!
関連リンク
関連リンクはありません

広告・取材掲載