第174回 株式会社フライングドッグ 代表取締役社長 佐々木史朗氏 インタビュー【前半】
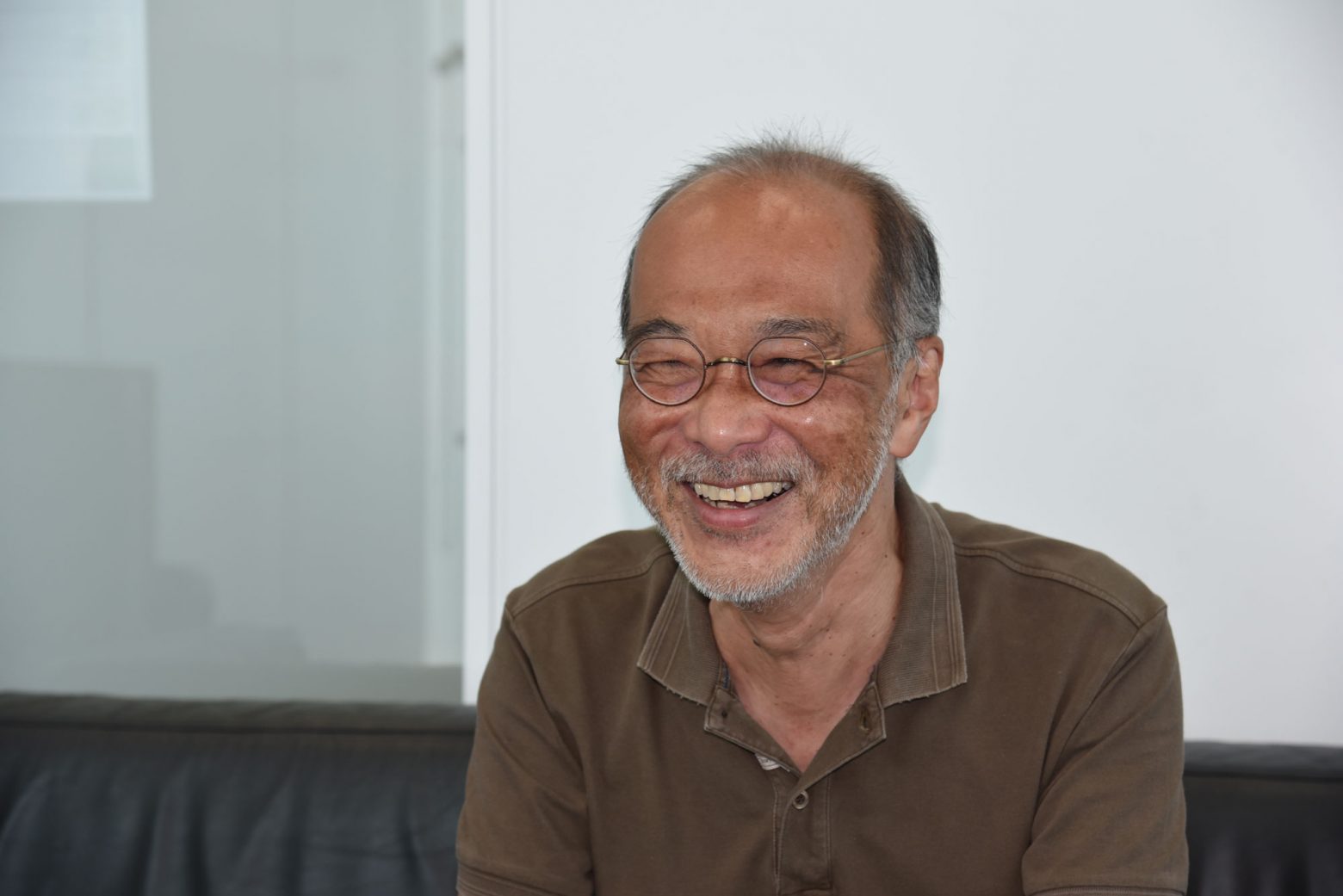
今回の「Musicman’s RELAY」は土橋安騎夫さんのご紹介で、株式会社フライングドッグ 代表取締役社長 佐々木史朗さんのご登場です。
高校、大学でバンド活動に熱中した佐々木さんは、その後、裏方を志し、1982年にビクター音楽産業(現ビクターエンタテインメント)に入社。
3年の大阪営業所勤務を経てアニメ音楽制作ディレクターとなり、以降『AKIRA』『トップをねらえ!』『マクロス7』『カウボーイビバップ』『創聖のアクエリオン』『マクロスF』『この世界の片隅に』など数多くの音楽プロデュースを担当。2009年にはフライングドッグ設立と、長年にわたり日本のアニメ音楽を牽引されてきました。
そんな佐々木さんにご自身のキャリアのお話から、アフターコロナにおけるアニメの可能性まで、じっくり伺いました。
(インタビュアー:Musicman発行人 屋代卓也/山浦正彦)
プロフィール
株式会社フライングドッグ 代表取締役社長 佐々木 史朗(ささき・しろう)
1982年ビクター音楽産業(現ビクターエンタテインメント)入社。
3年の大阪営業所勤務を経てアニメ音楽制作ディレクターとなる。『AKIRA』『トップをねらえ!』『マクロスプラス』『マクロス7』『逮捕しちゃうぞ』『MEMORIES』『勇者シリーズ』『エスカフローネ』『カウボーイビバップ』『X』『カードキャプターさくら』『ラーゼフォン』『人狼』『攻殻機動隊STANDALONE COMPLEX』『創聖のアクエリオン』『マクロスF』『Panty & Stocking with Garterbelt』『この世界の片隅に』等の音楽プロデュースを担当。
2009年1月、株式会社フライングドッグを設立。
2017年3月、株式会社アニュータを設立
想像力が豊かだった少年時代
──前回ご登場いただいた土橋安騎夫さんとはどのようなご関係なのでしょうか?
佐々木:土橋君は、立教大学のときの後輩なんですよ。同じサークルではなかったんですが、隣の音楽サークルに彼はいて、年は2つぐらい下なのかな? 当時、彼はシンセとベースとドラムのトリオみたいなことをやっていて「面白いことをやっているな」と思っていました。
大学卒業後、僕はビクターに入社して、すぐに大阪の営業所へ転勤になったんですが、シンコーミュージックに入社した別の大学のバンド仲間が、「レベッカという新人バンドをマネージメントすることになった」と。それで「大阪にライブで行くから観に来てよ」と言われて、観に行ったんです。そうしたらキーボードで知ったような顔がいるなと思ったら土橋君で(笑)。
──(笑)。
佐々木:僕はそのマネージャーに呼ばれて行っただけで、土橋君がレベッカというバンドにいるのも知らないで行っていたんです。会場は大坂のバナナホールというライブハウスだったんですが、終演後に楽屋へ行って「土橋ー!」って声をかけて(笑)。
──学生時代からの付き合いなんですね。
佐々木:そうです。そのうちレベッカが人気バンドになって、ヒット曲を連発して、解散したあとぐらいにアニメの主題歌で一緒に仕事をしたんですよ。その後フライングドッグでも、アニメの劇伴をうちの部下のディレクターが土橋君に頼んだりもしましたね。
──今でも仕事をご一緒することがあるんですね。
佐々木:そうですね。なので、本当は「土橋」なんて言っちゃいけないんですけどね。彼は偉い先生なんですけど、つい癖で「土橋」って言っちゃいます(笑)。最近もクラブのOB会みたいな飲み会に呼ばれて行ったりすると、彼がいたりしますね。
──この先は佐々木さんご自身のことを伺っていきたいのですが、ご出身はどちらですか?
佐々木:東京です。実は、父が都の職員だったもので生まれは新宿なんです。父の通っていた都のオフィスが新宿にあって、親父が「通うのが便利だから」と新宿のアパートを借りて、そこで生まれました。ですから僕は大久保病院で生まれたんですよ(笑)。
──華やかなところでお生まれになったんですね。
佐々木:青線のそばだったらしく、隣に怪しげな人が住んでいたり銃声が聞こえたりみたいな・・・ただ小さいときなので全然記憶がないです。その後、荻窪に移ったんですが、記憶にあるのはその荻窪時代からですね。
──お生まれは何年ですか?
佐々木:昭和33年、1958年生まれの戌年です。まあフライングドッグもその戌年から付けたんですけどね(笑)。
──そうだったんですか(笑)。
佐々木:山口百恵とかの中三トリオと同級生です。あとマイケル・ジャクソンとマドンナとプリンスと同い歳という、なかなかすごい世代で(笑)。
──(笑)。ご家庭には現在のお仕事につながるような環境があったんでしょうか?
佐々木:父は音楽が好きだったので、家の中ではハリー・ベラフォンテとか、そんな音楽がかかっていましたね。あと、これは聞いた話なんですが、父は若い頃バイオリンをちょっと習っていたようで、家はそんなにお金持ちとかではなかったですが、私も一応小学校のときにバイオリンを習っていました。でも、中学校ぐらいで嫌になって辞めて、ギターとかに走っちゃうんですけどね。
──ピアノじゃなくてバイオリンだったんですね。
佐々木:そうですね。親父がバイオリンをやらせたかったのかはわからないですけど。特に自分が何をやりたいと言わないままに、バイオリンを習っていたという感じですかね。
──佐々木さんはどんな少年だったんでしょうか?
佐々木:色々な想像するのが好きだったですね。もちろん友だちとも遊んだりはしていましたけど、結構1人遊びが好きだったかもしれないです。なんか色々とお話を考えたり、妄想をしたりとか。
──アニメを観たりとかもしていましたか?
佐々木:アニメは観ていましたし、漫画も好きでしたね。アニメは中学になってパタリと観なくなるんですが、小学校のときはちょうど『鉄腕アトム』や『鉄人28号』とか色々なアニメが出てきた最初の時代だったので、夢中で観ていました。あと漫画も横山光輝の作品とかすごく好きで読んでいましたね。僕があまりにも漫画しか読まないので、親が怒って漫画を捨てたりして、大泣きしたような覚えもあります(笑)。
──その頃、最も印象に残っているアニメ作品はなんですか?
佐々木:小学校の2年とか3年ぐらいだと思うんですが、『鉄人28号』が異様に好きで、「正太郎マーチ」という曲があるんですが、その曲が流れるとテレビの前でスキップをしていたようです。「進め進め 空へ海へ」という曲ですね。
ビクターの大阪営業所でアニメの勉強をする
──先ほどバイオリンを止めてギターを弾くようになったとおっしゃっていましたが、きっかけは何だったんですか?

佐々木:ちょうど小学校のときにグループサウンズが流行っていたんです。当然まだ楽器は弾けないんですが、近所の斜向かいに住んでいる大学生のお兄ちゃんがベンチャーズのコピーバンドみたいなのをやっていて、自分の家にメンバー集めて演奏していたので、うるさかったんですね。そのお兄ちゃんはドラムを叩いていたんですが、近所迷惑になるというので、親に「車を買ってあげるから、ドラムをやめて」って言われてやめさせられたんですが(笑)、彼に影響されて、ボール紙とか模造紙みたいなのをエレキギター型に切って遊んだりしていました。
──まだギターは弾いていなかった?
佐々木:ええ。そのときは、まだギターを弾くとかいう意識が全然なかったんです。ギターを弾くのはそのあと中学の2年とか、フォークが流行りだしてからですね。それで中3の卒業するときぐらいからバンドを始めました。
──パートはギターですか?
佐々木:ギターとちょっと歌を歌ったりもしました。中学のときは同学年にグランドファンクやディープ・パープルをやるバンドがいてヒーローだったのですが、僕らははっぴいえんどとCSN&Yとか、そういうバンドの曲をやっていて、全然受けないんですよね(笑)。
──ちょっとマニアックな(笑)。
佐々木:マニアックでしたね。高校のときは軽音の同好会があったので、そこに入っていました。結構プログレみたいなこともやっていたんです。あと高校が久我山にあったので、吉祥寺のジャズ喫茶に行くようになって、ジャズも好きになりましたね。
──学園祭とかでも演奏されたんですか?
佐々木:やってましたね。高校のときも立教大学のときもステージには出ていました。
──当時は「音楽でやっていこう」と考えたりしましたか?
佐々木:大学のときにコンテストはいくつか出たりはしていたんですが、まあ「自分は才能ないな」と思ったり、ミュージシャンの道へ進むのに腰が引けたのもありまして、どちらかというと裏方の仕事がしたいなと思うようになり、運よくビクターに入ったという感じです。
──でも当時のメジャーレコードメーカーへの就職というのは、とてつもない倍率だったんじゃないですか?
佐々木:そうですね。現に他のレコード会社はいくつか落ちました。当時のビクターってちょっと変わっていて、ハードの方の社員と一緒に採用するんですよね。それで入社式は子安(横浜市)の工場で青い作業着を着てみたいな。だからレコード部門に行けるとは限らないんです。
──もちろん、佐々木さんはレコード制作がしたくて入社されたわけですよね?
佐々木:ええ。で、運よくビクター音楽産業に入れたんですが、最初の配属は営業で、大阪に3年半ぐらいいました。
──営業のお仕事はいかがでしたか?
佐々木:今考えるとすごく楽しかったですね。同期が全部で10人ぐらいいたんですが、僕以外全員東京で僕だけが大阪でしたので、「早く東京に戻りたい」という気持ちはありましたが、それ以上にただ必死でやっていたような感じですね。大阪でも仕事をしながらバンドをやっていたりもしていたんですけどね。
──大阪とのカルチャーの違いは感じましたか?
佐々木:大阪ではやはり言葉の壁ですよね。一番最初にお店に行って、確かそのときは7月とか8月の新譜の説明をしたんですが、説明をし終わったらレコード屋さんの店長に「お前、生意気やな」って言われたんです。要するに大学出たての若造が東京弁でもっともらしくしゃべったことで生意気に見えたみたいなんです。それで「なるべく早く関西弁を覚えないと」と思いました。両親が四国出身だったもので、そういう意味ではなんとなく関西のイントネーションはわかってはいたんですけどね。
──それ以外のカルチャーショックはありましたか?
佐々木:当時の大阪ってまだ、電車とかホームで並ばなかったんですよね。ドアが開いたらみんな一斉にワーって(笑)。あとはエスカレーターの歩く列が左右逆だったり。
──でも、少し慣れると大阪の人は楽しいですよね。
佐々木:そうですね、面白かったですし、普通の会話がボケたりツッコんだりがジャズのセッションみたいというかね。ピアニストがこうきたら、それに合わせてドラムがこう叩くみたいな(笑)。会話がそういうセッションになっていますよね。
──では入社から3年は大阪を満喫されていた。
佐々木:「いつになったら東京に戻れるんだろう」というあせりはありましたけどね。
──それで3年ほど経って東京に戻られたんですか?
佐々木:ちょうど僕が入社した年に『超時空要塞マクロス』というアニメがすごくヒットしたんです。当時、ビクターに制作4部という、アニメを作るセクションができたばっかりで、その『マクロス』の大ヒットで軌道に乗ったんですね。それで、そのヒットからビクターのアニメが結構増えたんですが、大阪営業所のセールスマンって僕以外はみんな30以上で、僕だけが23とかだったので、圧倒的なペーペーなんですがアニメのことなんか誰もわからないから「佐々木、お前がアニメを勉強せえ」みたいな話になったんですよ。
──アニメの勉強ですか?

佐々木:そうです。要するにセールスマンのおっちゃんたちが「アニメはようわからん」と言うのは、売れるのか、売れないのかがよくわからないんですね。なにが当たるのか、なにが売れているのかを「お前が勉強せえや」と言われて、ペーペーの僕が大阪のセールスマン時代にいろいろなアニメ雑誌を仕事のために読んだら、なんとなく「このアニメはこういうことで人気があるんだな」というのがわかるようになったんですね。
そうこうしているうちにアニメの歌い手さんとかがキャンペーンで大阪に来たときに、司会をやったりするようになったんですが、そこで本社のアニメセクションの方と知り合いになって、自分が持っているチェーン店とかで「アニメのファンクラブを作って、そこで月に一度くらいイベントをやりましょう」みたいな提案もしました。
アニメは大学や高校のときは全然知らなくて縁がなかったんですが、「アニメの制作がやりたいです」って言ったんですよ。そのほうが早く東京に帰れるだろうなというズルい計算もあって(笑)。それでとりあえず「アニメに行きたいです」なんて言って、アニメのセクションの人、当時の課長さんも「じゃあ来い」という感じで東京に戻ることになりました。
──でも、小さいときはアニメがお好きだったとおっしゃっていましたよね。
佐々木:音楽が好きになってからは、アニメはほとんど観ていませんでした。僕がちょうど大学生の頃に『宇宙戦艦ヤマト』や『機動戦士ガンダム』『うる星やつら』とか、第一次オタク世代が誕生したんですが、そのムーブメントには全然参加していなかったです。傍から見て「こんなのがあるんだ」と思っていた感じです。
「絵にさえ合っていれば何をやってもいい」アニメ音楽の自由さに惹かれる
──再びアニメに触れられて、どのような感想を持たれましたか?
佐々木:マニアって同じじゃないですか? 例えば、音楽で「あのアルバムの2曲目のイントロのここがいいよね」というのと、画面をコマ送りで観て「ここがいいよね」というのは結構似ているというか、そういう意味ではファンやマニアのアプローチに共感できたので、違和感なくアニメの世界に入れました。「アニメ好きはプログレ好きに似ているかも」みたいな(笑)、そんな感じのイメージはありました。
──しかも、段々とアニメにスポットが当たってきて、市場が拡大するタイミングですよね。
佐々木:そうですね。当時、社内の制作部の中でヒエラルキーみたいなのがあったんですよ。邦楽、ロックがトップで、アニメはヒエラルキー的に言うと制作部の中で一番下みたいなね。
──大変失礼ながら、そういう見え方でしたよね。
佐々木:学芸のディレクターって、そういう流行歌とかをやり終えていらっしゃる方とかが結構多かったんですよね。ベテランになって「じゃあそろそろアニメの学芸をやりなさい」みたいな人たちが多かったかもしれません。
──佐々木さんはその状況を分かった上で、東京に戻ってアニメを担当になったわけですよね?
佐々木:そうですね。その制作4部というのがアニメの音楽のセクションだったので、そこにディレクターとして入ったという感じですね。
──最初はどのような仕事をされたんですか?
佐々木:最初は、先輩ディレクターのカバン持ちみたいなことから始まりました。当時はある意味、徒弟制みたいなものでしたから。僕は永田さんという『マクロス』のディレクターにくっついて、1年2年ぐらいアシスタントみたいなことをやっていました。
映像の劇伴、いわゆるBGMを作るというのは初めてですから、新鮮でびっくりしました。特にアニメの劇伴、2クールもののテレビアニメの劇伴って、下手すると60から80くらい曲を録るんですが、そんなに予算がないので、80曲を1日で録ったりするんですね。そういう意味ではマルチで録っている時間はないんです。もちろんマルチはありましたが、大切な曲だけマルチを回して、それ以外の曲は2チャン一発で録ったりね。
──すごい世界ですね。
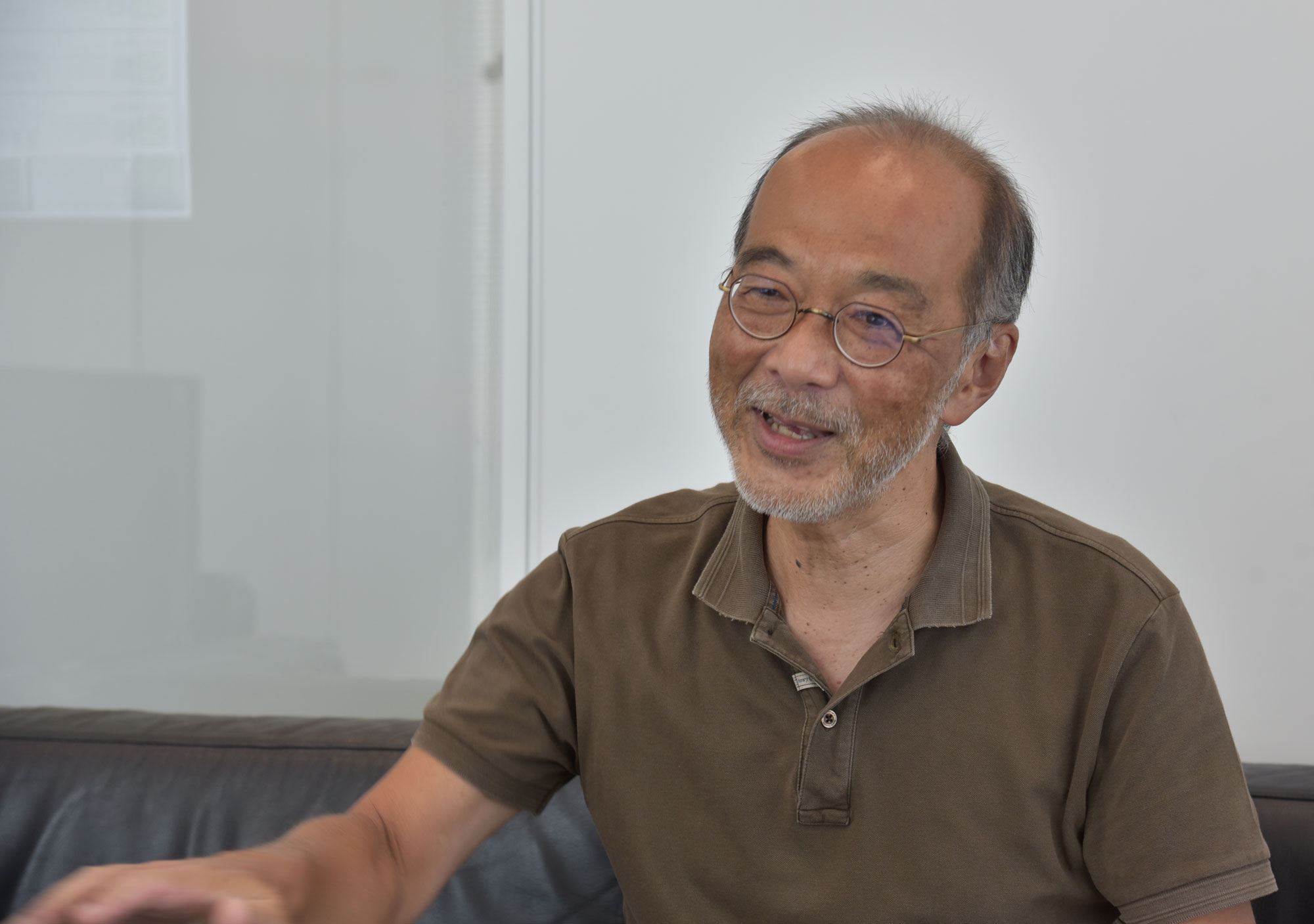
佐々木:あと、映像に音楽を当てて台詞と効果音でミックスするという作業を現場で見させてもらったりできて、それは面白かったのですが、音楽の編集に対する仕事観というか、要するに小節数が合わないとかコード進行がおかしくなっちゃうところで編集されたりとか結構あったんです。テレビの劇伴ってシーンに合わせて録っているわけじゃないですから、要するに作ったBGMを編集して映像に尺を合わせるんです。お皿を持ったシーンからお皿が割れるシーンまでが35秒とか。そうすると曲にハサミを入れて35秒にするんですが、4分の4の曲にいきなり4分の3が入ったりとか(笑)、いきなり合わないコードが入ったりとかっていう編集のされ方をされたりして、「もうちょっと音楽的にしてくれたらいいのにな」みたいなストレスがありました。
また、当時はフィルムのサウンドトラックの部分のモノラルの音をそのまま放送で使っていた上に、テレビアニメは予算がなくてフィルムも16ミリなので、音のレベルが低い上に音質が悪いんです。で、アニメが終わってCMになると急にレベルが高くなってステレオのいい音になるので、ビックリしたというか、「なんとかならないのかな?」と思ったりもしました。ディレクターはベテランの方々が多かった世界だったので、いわゆるロックを経ている人たちがいないというか、70年代に盛り上がったロック以前の音楽が青春時代に好きだった方々が制作をやっていたので、「アニメでロック的な音楽ができないかな」と思ったりもしましたね。
──不満がいっぱいあったんですね。
佐々木:そうですね(笑)、アニメを観ながら、仕事をしながら色々感じていましたね。
──逆に新しい血を導入もできるチャンスだと。
佐々木:できる余地はあるなと。やりながら楽しくなったのは「絵にさえ合っていれば何をやってもいい」というか、ジャズをやってもいいし、プログレをやってもいいし、民族音楽をやったっていいという自由さを感じたんですよね。
いわゆる流行歌のポップスをやると、そのときに流行ったビートや音色でと、それしかできないですが、僕らは全然関係ないことまでできるというのがすごく面白いなと思いだしたんです。そうなってくると流行歌やロックのセクションに帰りたいとは思わなくて「アニメが面白いのでずっとアニメがいいや」という気持ちになりました。
──自由度が色々と高い。
佐々木:そうですね。あとは、関わっている人がものすごく多いのも面白いというか、例えば、TVアニメを1本作るのに何百人という人が関わっているわけです。だから打ち上げとかに行くと、背景だけ描いている人とか、効果音を作っている人とか、そういう色々なジャンルの人たちと交流できるのも面白かったですね。
映画『AKIRA』のインパクトと『マクロス7』の成功
──佐々木さんご自身がメインの仕事で、「これは上手くいったな」と最初に思えた仕事はなんですか?
佐々木:なんでしょうね…もちろん自分の力だけじゃないんですが、芸能山城組が音楽を担当した映画『AKIRA』は上手くいったなと思いますね。当時、芸能山城組はビクターのアーティストだったので、村木さんという担当ディレクターがいて、『AKIRA』は芸能山城組のアルバムと『AKIRA』のサントラの2枚を作らないといけないという状況で、村木さんと一緒に芸能山城組のレコーディングをずっとやったんですが、それはすごくインパクトがあり、勉強になりました。その後の自分にとても大きな影響を与えてもらったかもしれないですね。
──今考えても芸能山城組を持ってくるというのはすごい企画ですよね。
佐々木:なぜ芸能山城組だったかというと、原作者であり監督の大友克洋さんが、ものすごく音楽をよく知ってらっしゃる方で、打ち合わせの中で「山城組がいい」と、大友さんがおっしゃったんです。そうしたら講談社のプロデューサーがいくらかかるか知らないで(笑)、「いくらかかってもいいから山城祥二先生でやってください」と言っちゃったんですよ。
──うわあ(笑)。
佐々木:徹底的に音にこだわる山城先生を指名してしまったものだから(笑)、本当に際限なくレコーディングをしていましたね。
──予算は大丈夫でしたか?
佐々木:それは講談社さんのお金だったので…(笑)。映画の製作費ですから。ただ、通常の日本の映画音楽の予算からすると何倍ものお金はかかってますね。ガムランとかジェゴグという楽器を録るために、アンビエントの衝立を立てるんですが、衝立を立てるだけで徹夜したりしていましたからね。
──バリ島の楽器ですか?
佐々木:そうです。そういう意味では「ここまでやるんだ」「ここまでやっていいんだ」とか、いい意味でのクレイジーさですよね。そのあと僕も音楽だけじゃなくて、アニメの監督とか漫画家さんとかも知り合いになると、そういうクレイジーさってすごく大事なところで、会社の論理や一般常識とかで「いや、そんなことやっちゃ駄目だよ」って言うんじゃなくて、そのクレイジーさとどう向き合うかみたいなものは『AKIRA』ですごく勉強になりましたし、例えば、菅野よう子さんと仕事をやるときにも、『AKIRA』での経験がすごく役に立ちました。
──やはり山城先生の要求は大変でしたか?
佐々木:もちろん一番大変だったのは講談社さんだったり村木さんだったと思うんです(笑)。僕はペーペーでしたから。山城先生は不可聴音域が脳にどう影響があるかという研究をされている方ですから、人間に聴こえない音のことを言われるんですよ。高周波とか低周波を「もうちょっとブーストして」とか。
──それまたすごいですね。
佐々木:まあ、面白かったですね。もう1つは『AKIRA』をやったおかげで、世界中の人が『AKIRA』を知っているので、そういう意味では世界中の人と「『AKIRA』をやったんだ」という話ができるのは名刺代わりになって助かりますね。
──『AKIRA』は世界的なヒット作品ですものね。その後は、立て続けにヒット作を?
佐々木:いや、そうでもないですね。94、5年くらいにやっと『マクロス7』というテレビのアニメと、菅野さんとやった『マクロスプラス』というビデオのアニメがヒットしました。そこでオリコンの左ページにボンボンボンボンと載るようになった感じですね。
──海外へ録音に行かれていたのもその頃ですか?
佐々木:そうですね。菅野さんが海外のオーケストラを録るのが好きだったんですよね。僕もその前に、モスクワのオーケストラで劇伴を録る仕事とかもしていました。
──傍から見るとすごく贅沢な旅行な感じですね。
佐々木:当時90年代頭は円高だったんです(笑)。ですから、意外と安上がりというか、国内に毛が生えたぐらいで海外旅行ができるという。
──実はそんなに贅沢じゃない?
佐々木:そうですね。通常のロックとか歌謡曲だったらロスやニューヨーク、ロンドンなんでしょうけど、僕らはヨーロッパ、しかも共産圏のオケってバイアウトができるので、それこそモスクワもそうですし、チェコやポーランドのオケとかと仕事をしていました。ちなみに菅野さんと初めてやったのは共産圏じゃなくてイスラエルフィルだったんです。菅野さんと「イスラエルフィルがいいらしい」という話になって、イスラエルに行きまして録音しました(笑)。
──イスラエルは今だとなかなか行けないでしょうね。
佐々木:昔はゆるやかだったので、全然許してくれていましたけど、今だったら世情が不安定だったりしたら行けなかったかもしれないですね。でも実際に行ってみたら怖いことはなくて。ただ空港のチェックで1時間ぐらい質問をされたりとか、入国も出国も手間はかかりましたが、イスラエルフィルはすごくいいオケでしたね。
▼後半はこちらから!
第174回 株式会社フライングドッグ 代表取締役社長 佐々木史朗氏 インタビュー【後半】

広告・取材掲載