ポストサブスクとは?『音楽が未来を連れてくる』出版記念 榎本幹朗氏インタビュー
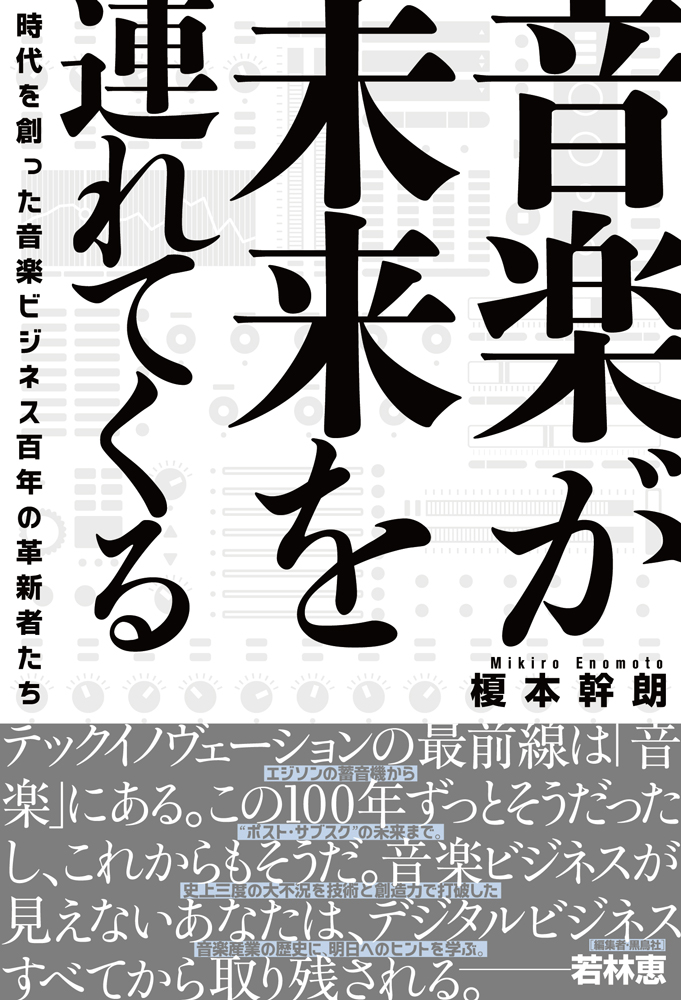
2012年5月、現スペースシャワーネットワーク 取締役 常務執行役員 案納俊昭氏から持ち込まれた1本の原稿。一読して、まるで長崎の出島で欧米列強の最新情報に触れた江戸時代の日本人のように強い衝撃を受けたMusicman編集部は、即座に連載を打診。同年7月よりMusicman(当時Musicman-NET)でスタートしたのが榎本幹朗氏の連載『未来は音楽が連れてくる』だ。
今回、連載開始から約9年の時を経て、音楽業界がコロナ禍で苦しむ中、大幅に加筆・修正を加え、装いも新たに書籍『音楽が未来を連れてくる』として2月12日にDU BOOKSより発売される。
エジソンの蓄音機からラジオ放送、ウォークマン、CD、ナップスター、iTunes、iPod、着うた、Spotify、そして“ポスト・サブスク”の未来まで、壮大なスケールで語られる本書は、多くの業界人に考えるヒントとともに、勇気と希望を与えるはずだ。著者の榎本幹朗氏に連載時に抱えていたジレンマから出版に至るまで話を聞いた。
プロフィール

榎本幹朗(えのもと・みきろう)
1974年東京生。作家・音楽産業を専門とするコンサルタント。上智大学に在学中から仕事を始め、草創期のライヴ・ストリーミング番組のディレクターとなる。ぴあに転職後、音楽配信の専門家として独立。2017年まで京都精華大学講師。寄稿先はWIRED、文藝春秋、週刊ダイヤモンド、プレジデントなど。朝日新聞、ブルームバーグに取材協力。NHK、テレビ朝日、日本テレビにゲスト出演。
連載から沈黙へ至った理由
──当然Musicmanでの連載(連載時は「未来は音楽が連れてくる」)を読ませていただいてきたので、書籍『音楽が未来を連れてくる』もある程度知っている内容なのかなと思っていたのですが、後半は初めて読む話ばかりで驚きました。
榎本:去年の1月にDU BOOKさんを紹介していただいたときは、ポスト・サブスクの未来について語る予定はありませんでした。しかし、コロナ禍の席巻で「サブスクとライブに続く新たな答えを提示しなければならない」という使命感が生じ、大幅に書き足しました。
サブスク時代の到来を告げたあの連載から9年近く経ちましたが、結果的には最も必要とされるタイミングで出版できるようになったと思います。
──サブスクで終わりではないんだということですよね。
榎本:僕はあの連載でも「サブスクの時代が来るけれど、サブスクだけじゃ足りませんよ」「その次を考えていきましょう」と書いていました。もう一度説明すると「CDの値段や音楽の消費額が欧米より高い日本では、サブスクだけでは足りない」ということは計算上はっきりしていました。
Spotifyの生まれた欧州でCDアルバムの値段は15ユーロほどですね。サブスクの月額は約10ユーロ。年間で120ユーロほどとなり、CDアルバム8枚分にもなる。ならば国民の4人にひとりが有料会員になればCD時代に匹敵する稼ぎを生み出すことができる。そして当時、Spotifyはスマホの普及をきっかけに4人にひとりが有料会員になりつつありました。だから、「スマホの普及でサブスクは救世主に変わる」と予言した訳です。
──しかし日本は再販制度でもともとCDが高かった。
榎本:CDの値段が2、3千円と高かった。平均2500円で考えるなら、月額1700円弱にするか、国民の3人にひとりを有料会員にするかでようやく欧米と同じロジックが成立します。
──どちらもむずかしいですね。
榎本:あの頃、すでにソニーのMusic Unlimitedとか、日本にもサブスクはあるにはありましたが、月額1980円ぐらいだったでしょう?それで、苦戦を重ねていました。スマホ・アプリで再販制度の適用は見込めない。その上、デフレの進行したこの国で月額1700円は難しい。
その後、スウェーデンやノルウェーでは国民の半分近くがSpotifyの有料会員になったようなので、国民の3人にひとりというのも全く不可能ではないのですが、世界一少子高齢化の進むこの国ではやはり厳しいものがありました。
だから「Spotifyは答えそのものではなくて、答えに至る大事な過程なんですよ」と2012年に連載で書いたんです。
ところがあの頃、連載を読んでいただいて「話を聞きたい」と訪ねてきた業界の方々は、皆さん「僕も日本でSpotifyやPandoraみたいなことをやってみたいんですが、どう思いますか?」とおっしゃるんですね。それはそれで嬉しかったんですが、僕としては「ちょっとまずいな」という気持ちがどんどん強くなっていきました。
──つまり榎本さんの意図が上手く伝わっていなかった?
榎本:ええ。「サブスク+α」を考えなくてはいけないと、焚きつけるつもりで書いたのに、気づいてみたら「とにかくSpotifyを真似ればいいのね」みたいな風潮になってしまった。
実は僕も日本でサブスクが立ち上がった2014年頃、裏でいくつか手伝っていて、「サブスク、もう少し工夫してみませんか?」「定額制+αの部分を作りませんか?」と結構言っていたんですが、その辺はあまり聞いてもらえなかったし、僕も強く言えませんでした。
それは別に音楽業界人の頭が固かったからとかそういう話ではなくて(笑)、サブスクの実現に向けて、レコード会社、音楽事務所、アーティストさんで話をまとめるだけでも本当に大変だったんですよ。2013、2014年のあの状況ですと、僕が「何か新しいことを追加してやりませんか?」と提案してもハードルが高かったんです。
──確かにそうでしたね。
榎本:もともとサブスクをやること自体、日本ではハードルが高いのに、さらに海外でも事例のないことをやりましょうというのは難しい状態になっていました。その頃、月額980円では大変だろうなというのは、事業企画する方々も十分認識されていたとは思いますが、「とりあえずCDと併売すればいいかな?」みたいな話に落ち着いちゃったんですよね。
僕は「まあ、CDを先行販売するのならそれもありかな」と思っていたのですが、そうしたウィンドウ戦略もなし崩し的に消えていきました。ちなみに中国はウィンドウ戦略で成功しています。
それで結局、日本は「サブスクが始まったはいいけれど…」みたいな感じになってしまいましたよね。楽曲は全て揃わなくて、無料のYouTubeの方が人気曲もそろっているみたいな状態になってしまって。これを恐れていたから2013年に「2001年にアメリカで立ち上がったときのサブスクの失敗を繰り返してはならない」と連載であらかじめ警告してたんですが、それも聞き流されてしまいました。
──コロナ禍でCDの売上も激減しましたね。かわりにサブスクに参入する大物アーティストが増えました。
榎本:スタジオ録音が滞りリリースが遅れたのもありますが、ライブ会場でCDを売る「グッズ化」の流れも裏目に出ました。もちろん、コロナ禍は僕も全く予想していなかった出来事ですが、「サブスク+α」も無いままCDから月額980円のサブスクに切り替わっていったら大変なことになってしまう。
それは僕が懸念していた通りであり、それを防ぐことができなかった。だから連載に対する自己評価は60点なんです(笑)。書いた予測はたぶん全部当てましたので、そういう意味では100点なのかもしれないですし、連載によって日本におけるサブスクの導入を1年くらい早めることができたかもしれない。
でも結局、「始まったけれどグダグダ」という時間が1〜2年生まれたのを防
──それで沈黙したんですね。
榎本:はい。「早く答えを教えてくれ。真似するから」というマインドを結果的には強めてしまった気がしたからです。「サブスク+α」を創出するにはクリエィティブなマインドが必要でした。だけど、答えを知って真似しようとするマインドと、答えを自分たちで創ろうとするマインドは真逆なんですよ。
その後、「サブスクの次の答えは、僕がしゃべるより、現場の皆さんがじぶんたちで見つけていったほうがよい。そうしないとクリエィティブにならない。いずれ時期が来る」と思ったので沈黙を選んだわけです。
──しかしコロナ禍の惨状にいたたまれなくなり、沈黙を破った。
榎本:そうです。僕はサブスクの次の答えを知っても黙っていました。だけど新型コロナで、僕も全く想像できないかたちでいきなりライブが壊滅して、「サブスク+α」が無ければ業界が死んでしまう状況が来てしまった。僕も音楽業界に育ててもらった人間ですから「仲間たちが苦しんでるのに、答えを知っている自分が黙っている訳にはいかない」と思い直し、本の構成を1年かけて変更しました。
結果的には、かつての自分の失敗を克服した内容に出来たと思っています。次の答えであるポスト・サブスクを単に提示するだけでなく、クリエィティブな精神を鼓舞する内容を併せ持つものにできたと自負しています。
クリエイティブの魂を鼓舞するために
──連載開始当時は当然、日本にサブスクは存在しませんでしたし、CDは落ち目とはいえまだまだ行けると業界内は思っていたわけじゃないですか? でも、ラジオができたときと同じように、テクノロジーの力で音楽産業が再生しないと終わってしまうよと榎本さんは書かれたわけですよね。
榎本:いや、テクノロジーだけじゃ駄目なんです。テクノロジーをクリエィティブに使う魂がなければ結局、乗り越えられないんですよ。
僕自身がそれに気づいたきっかけが、ラジオが普及したときの破局と克服をその短編で書いたときだったんです。あれは2013年で、PandoraやSpotifyについてまとめた本を出して「これから数年でサブスクの時代が始まりますよ」と世に知らせようとしていた時のことでした。まだ、音楽産業の復活が近いと信じ切れない音楽業界の仲間たちに希望を持ってもらうために、最終章として書いたんですね。
そうしたら、思いがけず音楽業界を超えてバズりまして、それで「ああ、そういうことか」とようやく僕も気づいたんです。「ジャーナリスティックに『次の答えはこれだ』と伝えてしまったのがいけなかったんだ」と。「ジャーナリストは自分の仕事ではない」と思っていたにも関わらずです。
それで出版は一度中断して、いちから書き直すつもりで連載を方向転換しました。小説の手法を取り入れて、物語の力で、日本人のクリエイティブな精神を鼓舞するものに変えたんです。
──それが今回の本の前半ですね。
榎本:そうです。僕は「日本の音楽がサブスクだけで救われないのは、ある意味チャンスだ」と思っていたんですよ。「必要は発明の母なり」と言うように、サブスクだけで救われない日本だからこそ、Spotifyよりも新しい「サブスク+α」を創造する必要があったからです。
アメリカは、Napsterでどこよりも早く違法ダウンロードの猛威に晒されたからこそ、iTunesミュージックストアを生み出しました。スウェーデンも、そのiTunesミュージックストアがからっきしだったからSpotifyが誕生しました。それを物語形式で書きました。
海外の真似ばかりを考えるのは、「日本人にはもう新しいものは生み出せない」と自信を失っているからだと思ったので、ソニーの井深さんや盛田さんがいかに世界の音楽産業を変えてみせたかを物語に描きました。
特に大賀典雄さんの物語では「ミュージシャン出身の日本人で、これほど世界の音楽を変える企業家になった人がいたんだぞ」と伝えたかった。
──その上でポスト・サブスクの答えを書いたと。
榎本:そうです。魂を鼓舞する土台があった上で、僕に見えている『ポスト・サブスクの見取り図』を提示すればよかったんですね。
皆さんそろそろ忘れかけてますが、僕が連載を始めた2012年当初、世の中は「サブスクなんていうニッチなものが主流になんてことがあるの?」みたいなノリでしたよね。実際、サブスクという存在自体はすでに2001年くらいには誕生してずっとニッチでした。
でもSpotifyは『変数』をいくつかいじることで、つまらなかったサブスクを救世主に変えていたんです。あの時、僕が誰よりも早くSpotifyを紹介したわけじゃなかったでしょう?もうニュース系ブログなどで「海外でこんな新しいものが流行っている」みたいなテイストで紹介されていました。
でも、それがエジソンの蓄音機の発明以来続く音楽産業のビジネスモデルを根本的に変えるものだとみんな気づいていなかった。僕が指摘したのは、そこでした。今回も同じです。
──ポスト・サブスクも全く同じことが起こっていると。
榎本:そうです。内容は読んでのお楽しみにさせていただきますが、答えを聞きかじっただけでは「え?こんなのがライブやサブスクに匹敵する存在になるの?」となるはずです。でもSpotifyがそうだったように、パッと見ただけでは気づかないわずかな違いの部分に、世界を変える新しい時代のうねりが潜んでいるものなんです。
結局、Spotifyが欧米で救世主になったのも、Spotifyそのものが偉かったわけではないですよね。Spotifyといえばフリーミアムモデルですが、2008年の誕生からしばらくはそのフリーミアムモデルは全く機能していませんでした。
それを変えたのが、ジョブズのiPhoneです。「スマホで外でも自由に聴くことができるためには有料会員になってね」という仕組みにしたら、Spotifyは有料会員がすごく増えたわけです。
そこで僕はスティーブ・ジョブスに関しても、連載で結構深く掘り下げたんです。彼は相当日本に影響を受けている人で、日本がなかったらiPhoneは誕生していないです。ジョブズが若い頃、Sonyの盛田さんにかわいがってもらっていたのは有名ですが、Appleから追放後、今度はトヨタにも大きく影響を受けているのはAppleフリークも知ら
──トヨタのどこに影響を受けたんですか?
榎本:経営スタイルです。ジョブズはピクサーを経営していた時、キャットムルやラセター監督がトヨタ方式を映画作りに導入して、クリエィティブなアイデアが常時、制作プロセスに反映されるようにしていました。それを見てジョブズは衝撃を受けました。ここから彼の経営スタイルは変わっていきます。
現CEOのティム・クックはトヨタのカンバン方式のパソコンの分野での専門家です。ジョブスはそういう人を右腕にしたり、iPhoneの開発時も、現場からクリエィティブなアイデアが彼のところへ常にフィードバックされる組織を組み上げました。
iPhoneの誕生物語は本当に面白くて、娘との関係改善など、彼の人間的な成長も強く関わっていて、イノヴェーションは決してアイデアや技術だけで起きるものではないことが如実にわかる事例でもあります。その話はもう原稿に起こしてあるんですが、それを収録すると本が
──日本の着うたもiPhoneの誕生に繋がったと書いてますね。
榎本:そうです。連載を始めた2012年当時、「日本は音楽配信の後進国」といろんな人が言っていましたね。例えばソニーがiTunesに参加しなくて「このままではダメだ」みたいな。僕は「もうiTunesの時代は終わるし、iTunesにソニーの音源があっても、
ソニーは着うたフルとウォークマン携帯を今度は世界に広めて、iPodでやられたものを全部ひっくり返してやろうと狙っていたんですね。ジョブズはもともと携帯電話に手を出すのは反対していたんですが、この報告を受けて「やっぱり携帯電話やるか」となり、iPhoneを作ることになったという風に、とにかく日本に大きな影響を受けているんです。
このように「日本というのは、決して海外での新しい動きを物真似するだけの国ではなかったはずだ」ということを、連載で強く伝えたかったんです。
なぜかというと、日本ではサブスクが普及した時点で、今度はサブスクだけでは足り
──しかし警鐘を発したら、みんな模倣に走った。そこで連載する意味を見出せなくなり、一旦沈黙され、そして先ほどお話にあった「カデンツァ」という部分を大幅に加筆された上で今回の書籍出版に至ると。
榎本:そうですね。おそらく本1冊分くらい書き足しているんですが、それって次の答えなんですよ(笑)。これ、どんな言い方をしてもトゲが出てしまうのですが「結局、僕が答えを言わないといけないのかな」と…。
──(笑)。
榎本:9年前と全く同じです。ひとつひとつの情報はもうニュースに出てるんですよ。だけど、どの情報が社会を変革する力を持っているか、それはなぜなのか。英語、日本語含めて記事を書いている人たちがちゃんと気づいてない。ポスト・サブスクの動きは何年も前から始まってるんですが、コロナ禍で大変なことになっているし、誰も言わないなら僕がやっぱり言うしかないかなと。
──“次の答え”に関しては、「実際に本で読んでください」としか言えないのですが、私は読んで救われた気がしました。
榎本:そう言っていただけると嬉しいですね。結局、情報というものは時代の大きな流れが分かってないと、単に会議で小話に使うおしゃれなニュースになるだけで、世の中を変える力にならないんです。
これは自慢と思わないでほしいのですが、僕は5秒でピンと来たことを、何年もかけて言葉を尽くして説明することを繰り返してきました。これじゃきりがないし、事業や制作に関して僕より優秀な方々はたくさんいるわけですから、僕が孤軍奮闘とするより、優秀な方々が各自、時代を読み取るカンを身に着けてくれた方がこの国はずっとクリエィティブになります。
ですから僕は歴史的な視点、地球的な視点を持つコツを伝えたいと思って、この星の音楽産業の過去・現在・未来に至る物語を書きました。
──そこを飽きさせずに読ませるのは榎本さんの筆力の成せる技だと思います。ただのビジネスリポートみたいに書かれたら、みんな最後まで読まないと思うんですよね。
榎本:とにかく長いので、物語にする必要があったんですが、もう一つは魂を鼓舞しないとダメだと思ったんですよね。クリエイティブなことって結局、魂に関わることなので、そういう部分はいわゆるジャーナリスティックな文章では伝わらないと思っていました。魂を鼓舞するためにも小説の手法を使いました。

次の答えはちょっと手を伸ばせばそこにある〜テンセントミュージック
──「魂を鼓舞する」ですか・・・素晴らしい言葉ですね。
榎本:ありがとうございます。最終章で扱っているテンセントにしてもセッションズにしても、煎じ詰めると「オンラインチケット」と「投げ銭」になるですが、そうなると「え、もうやっているじゃん。あらためて言うことあるの?」という話になってしまうんです。でも「投げ銭がサブスク以上に儲かると言ったらどう思いますか?」と言うことなんですよね。
これも9年前と同じなんですよ。「え、サブスクなんて古くてニッチなものがなんで今さら救世主になるの?」と。なぜそのようなことが起こりえるのかと。
実は投げ銭という文字面が良くないと思っていて(笑)、僕は「ギフティング」という言葉をそのまま使った方が良いと思っているんですが、ギフティングには我々が思っている以上のパワーがあると中国が証明してしまったわけです。これはもう欧米の音楽産業の首脳陣も把握しています。
オンラインチケットも、「無観客でライブをやる」ということだけで捉えてしまうと、コロナワクチンが普及した時点でニッチなビジネスとして収まっていくだけだと思うんです。ですが、ライヴ配信ってライブビジネスが持っていた様々な構造的な問題を劇的に改善するパワーを持っているんですね。
現状ライブはコストが高すぎて、中堅以下のミュージシャンにとって大変な負担ですし、それを個人事務所でやったりすると大変な借金を抱えるわけじゃないですか? しかも今回のような天変地異的なことが起こると億単位の借金をミュージシャンの方々が背負ってしまうみたいな仕組みですよね。
──その問題をライブ配信は解決してくれるかもしれないと。
榎本:ええ。ライブビジネス自体の改革にもなりますし、サブスク+αの部分においても、サブスク以上の稼ぎを作り得る可能性を持っているということを、本質的な部分から伝えなくてはいけないと思って、最終章に書きました。
──サブスク以上の稼ぎといえば、テンセントの件は驚きました。
榎本:テンセントミュージックは上場しているので、『ソーシャル・エンタテイメント売上』なる謎の稼ぎについて時々、英語でビジネス系の記事にはなっていたのですが、その実態をポスト・サブスクとしてしっかり研究した文は無かったと思います。
詳細は本に譲りますが、要するに中国はサブスクにカラオケを組み合わせた。そして、そこにLINEスタンプのようなギフティング(投げ銭)を付けたらサブスクの倍以上稼ぐようになってしまったんですよ(笑)。
実はこうしたアイデアは日本でも2014年頃、議論されていたんですよ。あの頃、サブスクの立ち上げを手伝っている時、ときどきそんな話になりました。「榎本さん、サブスクだとどんなに頑張っても1人980円じゃないですか。ソシャゲみたいなこと、音楽でもやれませんかね」と。
僕は「月額のポイント制にしたら、ポイントでLINEスタンプみたいなことも出来るようになりますよ」と言っていましたが「そっちの方向にいずれ行くだろうな」という確信があった他は、アイデアとしては特に独創的とは思っていませんでした。
中国の面白かったところは、いわばLINEスタンプにカラオケを組み合わせて、C2Cの音楽配信を実現してみせたところです。
──日本でもやろうと思ったらすぐできそうですよね。
榎本:その通りです。だから本で「次の答えはちょっと手を伸ばせばそこにありますよ」と書きました。スタジオ音源でカラオケをやって、それに対してギフティングを受け付けて、それを配信業者が3割、レコード会社が3割、歌い手さんが4割で配分みたいな感じですね。ここまできっちりした仕組みは中国も用意してませんから、実現すれば日本オリジナルになりますよ。
──今まで音楽業界、ミュージシャン、作家がカラオケ業界に奪われていたものが取り戻せるということですよね。
榎本:これは「着メロ→着うた」の流れで成功体験があることなので、伝わりやすいと思うんですよ。カラオケって5,000億円くらいの市場規模があると思いますが、音楽業界側に入って来るお金は120億円くらいでしょうか。カラオケ事業者がJASRACに払っているお金が入ってくるだけですからね。ざっくりと言って「カラオケ産業に近い売上が新たに生まれて、そ
──今まで歯がゆい思いをしてきた人も多いですからね。
榎本:それで中国は大儲けをし始めちゃったわけです。Joyyという企業をご存知でしょうか?ニューヨーク株式市場に上場して、世界一のライブ配信企業になっていますが、元々トゥイッチのようなゲームのライヴ配信の会社でした。
あるとき、「ライブ配信のチャットルームで人気のゲームはなんだろう」と彼らは社内調査したんですが、そうしたら、かわいい女の子がカラオケで歌ってるのをライブ配信してるのが一番、人気だったんですよ。ゲームでなくて。そこから、彼らは女の子たちにLINEスタンプのようなデジタル・ギフティングをプレゼントする仕組みを用意したら、それこそ一度で200万円も貢ぐようなフォロワーが続出した。それで中国は「これだ!」と気づいたんです。
──AKBの握手券商法のような…。
榎本:「握手券商法のデジタル版だ」と欧米の証券アナリストは分析してます。まあ、僕が昔、見立てた通りだったわけですよ(笑)。
中国では、ライブ配信ってコロナがあったから始まったことではなくて、4〜5年前から中国ではブームが起こっていて、カラオケがフックになっている。これって、中国に勢いがあるからとか、日本よりITのテクノロジーが高いからとかそういう理由ではないと僕は思っていまして、単純に著作権の管理がゆるゆるだったからですね(笑)。
彼らはカラオケ音源を別に作っていたわけじゃなくて、スマホで聴いている好きな音楽のボーカルトラックをアプリで自動的に消しちゃえばカラオケ音源になるじゃないですか?それに乗せて素人が歌ったものをアップロードして投げ銭をもらって、配信業者が一部をもらって、ということですよね。これ、日本で無許可でやったら裁判沙汰ですよ。でも中国はゆるゆるだったのでどんどん進んで、既成事実として成り立ってしまったんですね。
──でもそれって本来、音楽業界が自らやるべきことですよね。
榎本:そうですね。実際、着メロのときに近いんですね。最初に携帯のi-modeのキラーコンテンツになったのは着メロだったんですが、音楽業界に入るお金は微々たるものだったので、それに対抗するために着うたを作ったわけじゃないですか? ちゃんと原盤権収入を得られるようにしようと。だから「手を伸ばせばすぐそこに答えがある」と僕は書いたんです。
セッションズの画期的なプロモーションエンジン
──歴史を振り返ると、最初は非合法みたいなところからスタートして成功するサービスって多いじゃないですか?アメリカだとYouTubeとかナップスターとか。今それがやりやすかったのが中国だったと。
榎本:そういうことです。短い動画に音楽をつけまくったTikTokもそうですよね。そもそも先進国のメジャーレーベルは45秒ぐらいのものは無料で提供していましたし、TikTokは広告もつけず、商売をやっていなかったので「まあ、いいか。45秒だし」と黙認していたら、気がついたときには音楽系SNSとしてはYouTubeと並ぶ最大のSNSになってしまいましたよね。
そのようにグレーゾーンの自由な部分でイノヴェーションが進むというのは歴史の鉄則みたいなものですから、それで日本が遅れてしまったことに対して負い目や劣等感を持つ必要はないんです。それなら、ソーシャル・カラオケやそれ以外で、日本も新しいことをやったらいいじゃないかと。実際、アメリカはそうしました。
Pandoraの元創業者が始めたセッションズというのがありまして、セッションズの場合は素人のカラオケじゃなくてミュージシャンにフォーカスして、ミュージシャンのためのライブ配信をやっているんですね。今ライブ配信ってどこでもやっていますが、セッションズが新しかったのはその裏なんです。
プロモーションエンジンというものを作って、セッションズがプロモーション予算をもって、YouTubeやインスタのようなSNSで宣伝をして、ライブ配信にお客さんを集めてあげるんですね。そこで集まったギフティングやオンラインチケットの売上を、ミュージシャンとセッションズでシェアしましょう、というビジネスモデルなんです。
──ライブ配信と音源配信だとちょっと違うかもしれませんが、例えば、既存のデジタル・ディストリビューターとは違うんですか?
榎本:全然違いますね。そういった業者を使えば誰でもSpotifyやApple Musicに配信できますが、無名の人は誰も聴いてくれないですよね。そこで「自分でYouTubeやインスタ、Twitterで発信しなさい」と。これをみなさん、ソーシャルマーケティングとおっしゃっていますが、無名の人がそんなところに投稿してもSNSが飽和している今、ほとんどの場合、スルーされるだけでしょう?いいものなら必ず自然と広まるなら誰も苦労しませんよ。
やはりそこは宣伝をかけないといけないのが現実で、セッションズはその現実から逃げなかった。「いろんなメディアでミュージシャンの宣伝をやりますよ」と積極的にその仕組みを創った音楽配信メディアは、セッションズが初めてだと思います。
──セッションズで配信してもらうには、セッションズ側のお眼鏡にかなう必要があるんですか? お金を払えば誰でもってわけではない?
榎本:ではないですね。そこも今までのやり方と違って、キュレーションをやっているということですよね。最初始めたときは150組だけだったんですが、その半年後に500組まで増やしたのかな。結局、宣伝をかけても、売れてくれなかったらセッションズの儲けが出ないので、アーティストの数を絞っているんです。これって今までレーベルがやっていたことなんですよ。
──プロダクションやレーベルがやっていたことですよね。
榎本:才能がある人を見つけてきて、その人にプロモーション予算を付けて、その売上をシェアするという仕組みを、セッションズは音楽配信として成り立たせたわけです。
Pandoraから音楽のレコメンデーションエンジンが出てきたときは本当に革命的でした。が、それって結局Pandoraの中での宣伝だったんですよ。Pandoraを聴いている人に「こういうのが好きならこれがいいんじゃないの?」って、Spotifyもそうですね。でも、それだとSpotifyに楽曲を登録しただけだと何も起こらないんです。
しかしセッションズは、他のSNSにかなりの規模で宣伝して、効果も出せています。あるワーナーの新人歌手をセッションズのプロモーションエンジンで宣伝したら、iTunesでナンバーワンを獲ったり、非常に精度が高い対外プロモーションをやっています。
──既存のデジタル・ディストリビューターを見ていると、手数料をもらって登録するだけみたいなところがありますよね。でもセッションズは違う?
榎本:要は配信業者が売上金を割いて、ちゃんと宣伝してあげるってこと
セッションズだと100人ぐらいお客さんを集めれば1時間の公演で、10万円ぐらいミュージシャンにお金が入ります。ですから月に4回ライブ配信すれば結構な額になりますよね。もちろん毎週100人を集めるのは、それはそれで大変ですけど、それだけ人を惹きつける才能を持っていれば、しっかり収益になると言うことです。
セッションズをやってるPandoraの元創業者は「Pandoraで失敗した」と悔いていました。Pandoraはミュージシャンにオーディエンスをつけることに成功したけど、収益化の仕組みを提供できなかった。それで再起して、セッションズを創ったわけです。
──セッションズでのライブって何曲くらいやるんですか?
榎本:配信時間が1時間だったら、30分ぐらいが音楽の時間で30分はトークなんです。それぐらいがちょうどいいというのがわかっていて。それだと配信できるのは5、6曲か、もう少し多いかもしれません
──つまり1回10万円もらえる客の入りが保証されて、気持ちよくライブができるライブハウスみたいな感じでしょうか。
榎本:しかも自分の持ち出しはほとんどないという。最高でしょう?(笑)。チケットの買い取りノルマもないし、
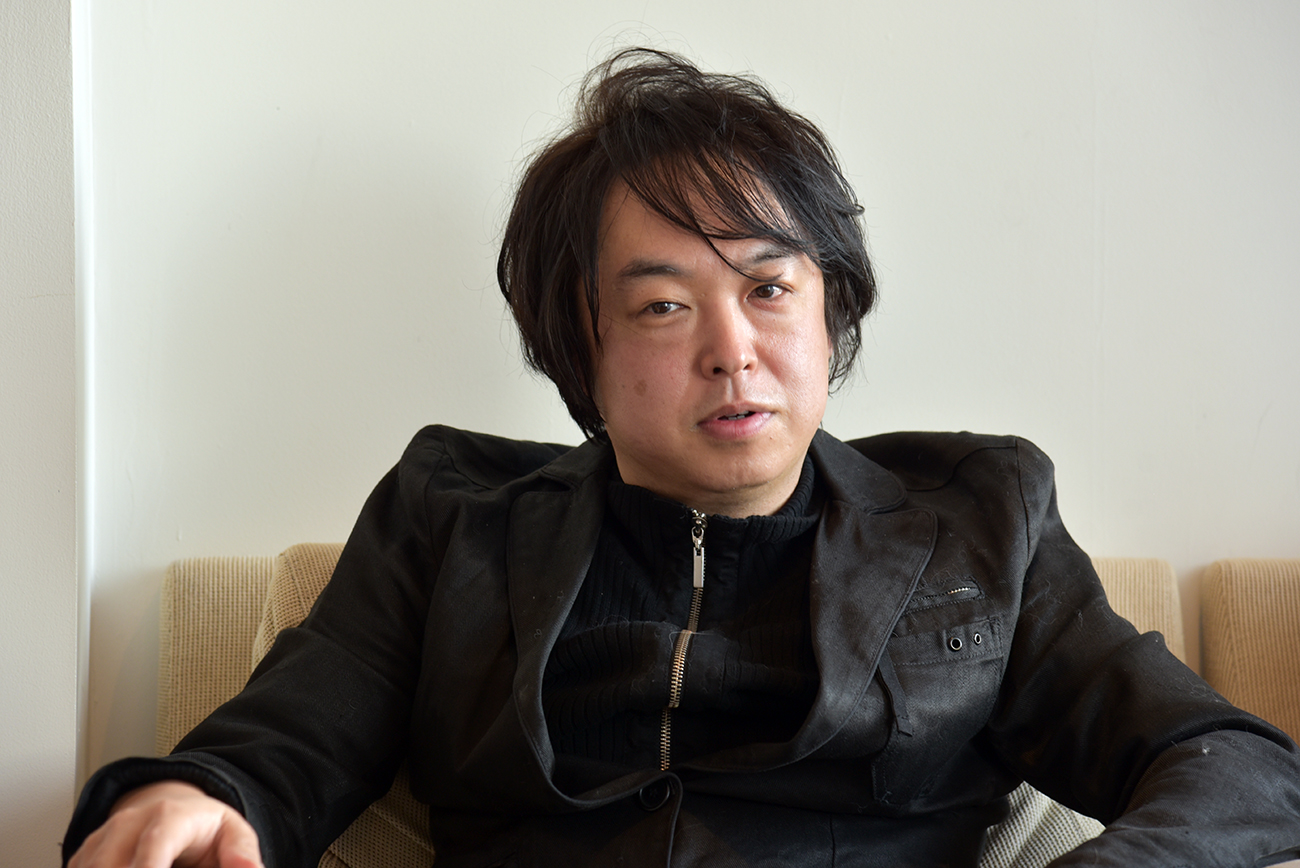
マスメディアは絶対に無くならない〜プロモーションの合理化
──つまり日本でもセッションズみたいなシステムを立ち上げたらいいじゃないかってことなんですか? それともセッションズに参加すればいいじゃないかということなんですか?
榎本:本質的なところで言えば、それはどっちでもいいと思うんです。もちろん自分たちでやってみれば新しい工夫ができますし主導権も取れるので、そういう意味では自分でやったほうがいいと思うんですが。例えばテンセントとセッションズを上手く掛け合わせるだけでも、オリジナルなものができます。
──セッションズに参加できれば、ワールドワイドに活動できる可能性があるということなんですか?
榎本:それも不可能じゃないと思います。東欧で弾き語りをやっていたミュージシャンがセッションズでアメリカにファンを獲得して、食
セッションズってアーティストを宣伝してあげるためのものだという観点からすると、例えば、BTSくらいまで行ってしまったアーティストには必要なくて、やはり中堅や新人アーティスト、あるいは無名のアーティストをいかにプロモーションし、収益化してあげられるかなんですよね。
確かにSpotifyやPandoraはたくさんのオーディエンスをつけてくれるようになったんですが、SpotifyやPandoraだけで食っていくには1億再生とかいかないと食っていけないです。少なくともメジャーレーベルと契約してやっていく場合は。
──それはハードルが高いですよね。
榎本:これ、2012年にPandoraを扱ったときも書いているんですが、日本と欧米ではメジャーレーベルの意味合いが違いますよね。日本の場合って今5,000枚売れたらもうメジャーアーティストじゃないですか。今では5,000枚すら厳しいかもしれないですが、それってセッションズが課題にしようとしているミュージシャンたちなんです。
つまり、日本にこそセッションズみたいなものって必要なんですよ。メジャーレーベルと契約して、一体何してくれるのか?ってよく話題に出るようになりましたよね。大型契約じゃなかったら、宣伝といっても大したことをしてくれないし、制作といっても今の時代、自分たちでやれるし、音楽ビデオもそんなに凝らなかったらYouTubeに自分たちで上げられる。それなのに取り分は5%以下みたいな。
これはどういうことなんだと思っている方も多いと思います。セッションズが素晴らしいのは、売上の3割をセッションズがとるかわりに、それできちんとプロモーションをやってくれるということと、アーティストは4割と一番多くもらえることなんですね。
──そのプロモーションというのは日本で言うところのテレビやマスメディアも含まれているんですか?
榎本:いや、現状はSNSに限ってです。ただプロモーションエンジンの対象にテレビやラジオが入っていてもいいと思うんです。例えば、欧米のメジャーアーティストも中国へ進出する際にテンセントへ相談に行きます。それは「中国で配信してくれ」という話ではないんですね。別に配信はメジャーレーベルと契約していれば、自動的にテンセントへ配信されるので。そういうことじゃなくて、プロモーションしてほしいと相談に来るんです。
そのときにテンセント側の強みになっているのが、何千というテレビ番組に出稿したり、番組自体を制作していることなんです。中国の場合、テレビってオワコンではなくて、まだ歴史が始まったばかりの新しいもので、すごく勢いがあります。
テンセントはそこでも宣伝してくれますし、テンセントってLINEがめちゃくちゃすごくなったような会社なので、当然SNSでも宣伝してくれます。そういう事例を考えると、セッションズのプロモーションエンジンの、宣伝対象の1つに既存のメディアが組み込まれても全然おかしくないと思います。
──なるほど。
榎本:僕は、マスメディアは絶対に無くならないと思っています。マスメディアという存在自体が人間の本質に根ざしていますから。人間というのは大衆化する社会的な動物なので、大衆が1つになるためのメディアという存在を必ず求めます。
この役割はなくならないですから、レーベルの方々もこれまで通りマスメディアへのプロモーションをやっていったらいいんです。みんなで番組を見て、視聴体験をライブ感覚で共有するというのも、本質的にネット時代の流れと適合しています。
でもこれからはSNSマーケティングもきっちり大体的にやっていかないといけない。もちろん今も現場の人たちは一生懸命やっていると思うんですが、プロモーションエンジンはそこを合理化して進めることができる仕組みなので、今みたいに手作業に頼らずテクノロジーの力を上手く活用すればいいじゃないかという話ですね。
次の答えを真似するのではなくて考えてほしい
──本書『音楽が未来を連れてくる』は全音楽業界人が読むべき一冊だと思いますし、音楽ビジネスに携わる人たちがここに書かれた歴史と状況、推察、予測を読まずにいるのはもったいないなと思います。
榎本:そう言っていただけるとありがたいですね。「サブスク、ライブに続く第3の柱が音楽産業には必要だ」ということで、“ポストサブスク”と僕が呼ぶ仕組みをこの本で提案しています。ただ、「これが次の答えね」って、また真似しないでほしいんです(笑)。
先ほどお話したセッションズは、中国のライブ配信がうまくいっているのを見て「じゃあ俺たちはどんな新しいことをやろうか」と始めたサービスなわけですからね。読者の方々は僕なりの次の答えを読むと思うんですが、それをそのまま真似するんじゃなくて「じゃあ俺たちだったらどんなことをやってやろうか」ということを考えていただきたいです。
それと僕の予想が外れたら、僕のことを笑っている場合でなくて「チャンスだ」とすぐに動いてほしいんです。経営の神様ドラッカーも言っているように、予想外の出来事が一番のイノヴェーションのチャンスなんです。技術革新やアイデアよりもね。そんな事例をいくつもこの本で描いています。
──予想外の出来事を見破る基準に「答え」をむしろ使ってほしいということですね。
榎本:やはり自分たちの国の特殊性ってあると思うんです。日本は特殊だからとか、島国だからとか色々な言い訳に使われてきましたが、逆に言うとそれは新しいことを考えるチャンスでもあります。
例えば、テンセントでソーシャルエンタメ売上が育ってきた理由というのは、中国って最初は違法コピー天国だったじゃないですか? ミュージシャンにはライブ以外の稼ぎがないという状況をどうにかしようと「中国版のSpotifyを作ろう」と始めたのがテンセントミュージックのサブスクだったんです。
だけど、中国ではSpotifyの真似をしても全然うまくいかなかった。そこで「あれ?おかしいぞ」と思って、あれこれやっているうちにカラオケと音楽配信の融合という新しい形が生まれてきたんです。
僕は、中国の真似をしろと言ってるのではありません。日本は日本で中国とも欧米とも違う色々な事情を抱えています。何度も申し上げたように日本は欧米と違ってサブスクだけでは稼ぎきれない。さらに新型コロナでライブもできない。ライブ会場で手売りしていたCDも売れなくなった。
だからこそ今、中国とも欧米とも違う新しい答えを創るチャンスがある。そういった気概を鼓舞しようと本を書き上げました。
──連載から少し時間が経った今、このタイミングで本を出すことになったのは天の配剤だと思いますね。
榎本:まあ、次の答えを書かざるを得なかったので、大変でしたけども(笑)。それに「真似をするな」と言う以上、僕自身の作品もオリジナルでなければならないという責務がありました。この本は海外のどこを探しても無い、世界水準の、唯一無二の内容にできたと自負しています。産みの苦しみと言うか、もう本当にきつかったです(笑)。
Musicmanでの連載部分もしっかり書き直しましたし、CDアルバム一枚分の値段ですが4冊分の分量
──Musicmanがこの書籍の誕生のきっかけになれたこと光栄に思います。本日はありがとございました。
書籍情報
『音楽が未来を連れてくる 時代を創った音楽ビジネス百年の革新者たち』
- 著者:榎本幹朗
- ページ数:656ページ
- 発売日:2月12日
- 価格:2,500円+税
- 発行元:DU BOOKS
- 『音楽が未来を連れてくる』購入

広告・取材掲載