「TOKA Songwriting Camp 2022」開催、TOKA代表・小袋成彬氏インタビュー ──コライトと海外楽曲のピッチは、日本の音楽業界に風穴を開けるための第一歩

株式会社TOKAと株式会社フジパシフィックミュージックが昨年共同で主催した「TOKA Songwriting Camp」が、今年は期間を延長して開催となった。この企画では、フジパシフィックミュージック内のKilaスタジオにボーカリスト、ラッパー、プロデューサー、トラックメイカーなどが集まり、グループに分かれて楽曲を共同制作するライティングセッション=“コライト”の手法を取り入れている。
さらに、今年は新たな取り組みとして、マネージメント・レーベルA&Rなど音楽関係者を招いた「Demo Pitch Day」も開催。海外作家・アーティストによって作られたハイクオリティな楽曲デモを、日本のアーティストやシンクロの機会へ提案するという。少しハードルが高いと思われている海外デモ曲の使用を身近なものにする試みだ。
海外で主流の制作方法を日本に取り入れたり、海外の楽曲をピッチすることで、洗練された新しい音楽が生まれる。そういったクリエイティブ面への期待はもちろんあるが、このキャンプを開催する理由はそれだけではない。小袋成彬氏がアーティスト・作家として感じていた日本の音楽業界への疑問がロンドンでの生活で確信に変わったことによる、海外のビジネスシステムの普及が背景にあった。
世界水準のクリエイティビティを持つTOKAと大手音楽出版社・フジパシフィックミュージック両者だからこそ実現可能な未来へのビジョン、解決すべき今の音楽業界の課題までTOKA代表・小袋成彬氏とフジパシフィックミュージック 三浦圭司氏に同席いただき話を伺った。
取材日:2022年6月6日 取材:柴田真希 編集・文:柴田真希
◾️ 「TOKA Songwriting Camp」
海外でのソングライティング・セッションを通じて、日本にはない自由でオープンマインドな空気でクリエイティブ且つ刺激的な楽曲制作工程を体感しているTOKAの創業者である小袋成彬氏とYaffle氏が、実際の経験で得た知見と感動を多くのアーティストやプロデューサーと共有し、クリエイティビティを最大化できるような場所を提供、世界標準のソングライティング文化を日本の音楽業界へ紹介することを目標として昨年からスタートした企画。関連リンク:TOKAとフジパシフィックミュージック、「TOKAソングライティング・キャンプ2022」を開催 精鋭10組のアーティストがライティング・セッション
ビジネス面の成功よりも、純粋に新しい音楽が生まれてほしい──TOKA Songwriting Campの独自性
──今年で2回目の開催となりますが、昨年初めて開催されたときの手応えはいかがでしたか?
小袋:シンプルに楽しかったし、僕以上に参加者が喜んでくれたのが嬉しかったですね。去年はコロナで人に会う機会がそもそも少なかった中でスタジオセッションの場を設けたので、初めましての人と一緒に曲作りをすることがより一層刺激的だったのかもしれません。
──実際に初回のソングライティング・キャンプからDaoko x Yohji Igarashi「escape」など4曲がリリースされ、J-WAVE「SONAR MUSIC」でも特集が組まれるなど成果もありましたが、昨年と変わった点はありますか?
小袋:昨年は全体で3日間開催、個々のチームは1日の作業期間だったのが、今年は1週間で2日間に渡るセッションを行うチームも作ったりしましたね。2日連続でスタジオに入ってもらうことで、徐々に場慣れもしてクリエイティビティを発揮しやすくなるんです。そういった細かな調整を行いました。
──他にも意識したことはありますか?
小袋:人と人の相性があると分かったので、アーティストとプロデューサー、お互いにとって良いシナジーが生まれそうな組み合わせを厳選して考えました。たとえば何でも受け入れる柔軟な人もいれば、こだわりが強い人がいたり、「リリースするほどじゃないかな」と控えめな人もいるんですよね。
──組み合わせは小袋さんが決められるのでしょうか。
小袋:フジパさんとTOKAのスタッフと話し合って決めています。「歌える人と組みたい」、逆に「トラックメイカーと組みたい」など参加者の意向も考慮しています。今日*参加しているshowmoreさんはトラックメイカーと組みたいと言っていたので、Gimgigamさんを紹介しました。GimgigamさんはTOKA内でいろんなトラックを聴く中で候補に上がった方なんですけど、偶然フジパさんとの繋がりがあって、声をかけていただきました。

取材日はソングライティング・キャンプ初日
──開始1時間で「EPができそう」というくらい盛り上がっていましたね!日本でこれまでにソングライティング・キャンプの実例もありますが、今回のキャンプの独自性はどういった部分でしょうか?
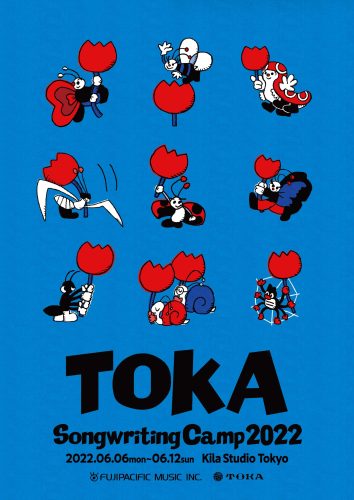
「TOKA Songwriting Camp 2022」ポスター 参加者がモデルとなっている
小袋:従来国内で開催されてきたソングライティング・キャンプは、今ある音楽のトレンドに合わせて曲を仕込んでいく商業的な側面が強かったと思います。それに対してこのキャンプが特徴的なのは、僕たちTOKAが10年間やってきた「今まで聴いたことのない音楽を作りたい」というマインドを持っていることです。ヒットソングを生む以上に「こんな曲聴いたことない!」と新鮮な驚きを感じる楽曲が生まれるといいと思っています。
三浦:攻めてますよね。
小袋:僕は経営者というよりも、完全にパーソナリティがアーティストなんですよ。新しい顧客を作るのがビジネスの基本ですし、新しい世界を作ることがアーティストの役割でもあるので、どちらも同じような意義を感じながら楽しんでいます。今回も新鮮なイメージを固めるために、ポスターを作ったりもしました。
三浦:参加するアーティストもビジネス的な側面より、新鮮な出会いへの期待や「この人とセッションしてみたい」という興味が強いと思います。
小袋:それこそカルチャーの始まりなので、ピュアな気持ちで参加してもらえるような運営を大切にしています。それに、僕自身が宇多田(ヒカル)さんとか80KIDZとかに引き上げてもらったように、まだ誰も注目していない人をフックアップして、もっと上の世界に引き上げたいという想いもあります。
海外デモ楽曲の門戸を広く開き、ハードルを下げる
──改めてお伺いしたいのですが、このキャンプは2社がどういった経緯で一緒にやることになったのでしょうか。
小袋:フジパさんとは、7、8年前ぐらいから個人としても会社としてもお付き合いがありました。僕たちTOKAには、フジパさん所属でもあるYaffleというクリエイターがいます。彼は海外のテイストを取り入れてJ-POPに落とし込む作品をつくるのが得意で6、7年ほどやってきましたし、フジパさんは業界内の繋がりを持っているので、うまくシナジーが生まれるクリエイティブな企画をやろう、という話から始まりました。
三浦:僕は、海外の作家や出版社と契約して日本でプロモーションをする立場なんです。だからコロナ前は毎年MIDEMやADEにも行っていましたし、そういった繋がりを生かして、最初は海外の作家と日本のアーティストのコライトをやろうとしていました。
──それがコロナ禍で難しくなってしまったと。
三浦:はい。それで昨年は日本にいるミュージシャンだけで開催しましたが、思いのほか反響があったので、今年も開催しました。ゆくゆくは海外の契約作家にも来てもらおうと思っています。日本のミュージシャンの方が海外からの刺激を受けて、より格好いいもの、海外にも通用するクオリティの高い作品を生むお手伝いをしたいです。
──今年始まった「Demo Pitch Day」では、海外の未発表のデモ曲を色んな関係者に聴いてもらい、使用までのステップなどについても説明が受けられるんですよね。
小袋:今までは海外のデモ曲を持っている音楽出版社と繋がりを持っている、メジャーのアーティストだけが海外楽曲を歌う機会がありました。でもそれだけでは使われない楽曲も多く勿体ないので、インディペンデントなアーティストにも門戸を開きたいと思ったんです。
三浦:海外作家の曲を歌うことは、未だにハードルが高いんですよね。でも今回は小袋くんや弊社のスタッフが海外楽曲の扱い方、日本人のアーティストが海外作家の曲を歌うときのプロセスや、権利処理の手続きなどビジネス面の話を実体験、失敗談も含めてお伝えしたいと思っています。
──これまで海外の楽曲デモが盛んに使用されなかった理由として、一番大きなハードルは、何だったのでしょうか?
小袋:単純にタッチポイントがなかったんですよね。
三浦:実は、そういったデモを出版社が持っているということは、音楽業界の方でもあまり知られていないと思うんです。弊社の他にも海外楽曲の著作権を扱っている音楽出版社は色々あります。そういったところには、契約している海外のオリジナル・パブリッシャ―から「ピッチして欲しい」と楽曲のデモが送られてくるんです。たとえば「この曲を日本のアーティストさんにピッチしてください」「K-POPのアーティストにピッチしてください」というアーティストへのピッチから始まり、「「テラスハウス」での楽曲使用をコーディネートして欲しい」というシンクロへのピッチまで、楽曲の売り込みが世界中から来ています。
──そうやって溜まっていた楽曲デモを、活用できるということですね。
小袋:まさにそうです。事前にデモを聴いて「これは僕たちっぽいよね」とか「これはアイドルに提供したほうが活きるよね」と会議しながら、選定しました。海外と僕たちの界隈を繋げる企画ができたので、日本の音楽業界にも刺激になってくれたらいいなと思います。
日本のアーティストは、自分自身の楽曲をコントロールしていない
──ステートメントで「世界と日本の音楽文化をもう一度繋ぐ」といった表現をされていましたが、「もう一度」ということは過去に一度繋がっていたということでしょうか。
小袋:レコードを沢山出していた70年代から80年代は資金が潤沢にあったので、音のクオリティも海外と遜色なかったと思います。そういう意味で、日本がグローバルスタンダードだった時代があると思うんです。でも今のJ-POPが海外と同じレベルでやれているかというと、違うと思う。
──シティポップが世界で流行っていることもそうですけど、海外の音楽ファンが注目してくれるのは今の日本ではなく、その年代なのが象徴していますね。
小袋:そうなんですよ。今はオリジナリティもあまりないですね。少なくとも前ほど海外との繋がりやクオリティの競争がなくなっていると思うので、もう1度グローバルスタンダードに戻したいという想いです。90年代でCDが売れてきて、タイアップの概念が出てきたときに、徐々に世界と離れてガラパゴス化していったんですよね。また海外と同じレベルにするには、今度はシステムから変えていかないといけない、と考えています。
──それは、小袋さんがロンドンにお住まいになって感じた問題意識があるのでしょうか?
小袋:外から独自の論理で動いてガラパゴス化している日本の音楽業界を見ていて、海外からの刺激を入れる必要があると思いました。
──それはどういった点で特に感じますか。

小袋:まず、楽曲のクレジットの形ですね。日本で楽曲の権利を作詞・作曲で分けるのは、日本の著作権の登録システムがそうなっているからなんです。海外だと、たとえば3人作家がいたら単純に3分の1等分する。今の日本でそれをやるには、一手間かかるんですよね。それに、そもそも「参加した人数で等分しよう」という思考がないから損している人も沢山います。たとえば作詞作曲両方に名前が入る人は得をしている一方で、僕もアレンジの仕事をやることがありますが、アレンジャーとしては権利が一切もらえない。日本の音楽業界は「スコアを書ける人=作曲」みたいな文化が残っているんですよね。
三浦:トラックメイカーも、日本だと編曲家のような扱いになります。でも本来、楽曲を制作するソングライターとしてカウントされるべきですよね。海外ではプロデューサーも、作家として参画している。
小袋:アーティストとして自分が働いた分はちゃんと権利を主張するべきだと思います。だから今回は海外のやり方をそのまま持って来ていて、スタジオに入ったらまず「3人で入ったら3等分」と明らかにした上で制作を始めます。僕は経営者の立ち場としての旨味はないにもかかわらず、このキャンプのオーガナイザーとしてアーティストに「君たちは3分の1もらっていいんだよ」という考えをシェアしているので、かなり良心的でエッジが効いた企画だと思います。
──実際、昨年参加されたアーティストさんや作家さんにそういったお話をされて、反応はどうでしたか?
小袋:本人たちはあまり気にしてないような気がする(笑)。アーティストが自分自身の楽曲をコントロールしていないのも、問題なんですよ。業界の慣習として、レーベルに自分の楽曲の権利周りを全部任せている。本人たちは自分がどのくらいもらっているか気にしてないので、「3等分」と言ってもすんなり受け入れてくれます。でもあえて僕たちからそれを提示していかないと、アーティストが育っていかない。
三浦:アーティストの立場でそこまで考えているのは、小袋くんぐらいじゃないかな。
小袋:マジでいないと思います(笑)。ラッパーのビジネスはアメリカの文化がそのまま日本にきて、日本の音楽文化とは全く別の文脈から出てきているから、期待できますね。ライターズシェアに対してちゃんと考えている人たちが多い気がします。
──連名での楽曲リリースも多いですもんね。
小袋:そう、多いですよね。ラッパーは楽曲を自分たちで管理するし、自分たちでメディアを持って、プロモーションもSNSを使ってできるようになったので、レーベルもこれから必要なくなっていくと思うんです。アメリカでもまさに自分たちで楽曲の権利を持つ文化が起こっている。ゲームチェンジャーはそういうインディペンデントな、草の根の活動な気がします。
まずは日本と海外をコネクトさせるために、輸出するよりはまず輸入する。それが第一歩
──クレジット以外にも、日本独自の慣習はあるのでしょうか?
小袋:タイアップという考え方がありますよね。
──宣伝効果を期待して、ドラマの主題歌やCM曲として楽曲を提供する契約ですね。
小袋:海外ではその考えは全くないんですよね。例えばCMタイアップって、僕たちアーティストはタダで楽曲をあげることもあるんです。1円ももらわないケースもある。
──どうしてそういった慣習になっているのでしょうか?
小袋:昔はテレビの影響力も今より強かったので、タイアップしてTVで楽曲が流れることでCDが売れることで、両者にメリットがあったんです。でもSNSが流行ってCDも売れなくなった時代に、まだ同じことをしている。今すぐ止めるべきです。海外だと、使われたらその分の使用料が支払われます。
──海外で支払われる使用料は、どういった項目ですか?
三浦:たとえばCM、映画とかで楽曲が使われるときは、シンクロ・フィーと言われる、映像に音楽をシンクロさせるときの楽曲使用料が著作権(音楽出版社)と原盤(レコード会社)両方に対してかかります。でも日本ではタイアップという名のもと、邦楽曲は著作権使用料ゼロ、原盤使用料ゼロ、要はタダで使えるケースがあります。僕は海外の出版社とやりとりの中でタイアップの話をしたら「じゃあどうやってお金を儲けるの?」と言われます。以前はその分CDが売れるから、という言い訳がついたんですけど、今はCDが売れないし、答えられないですよね。
小袋:だから、たとえば今回の「Demo Pitch Day」でピッチングした楽曲がCMに使われることになったら、海外の作家は当然のことながら「タダは駄目」と言うと思うんです。そういった摩擦が起ってほしい。刺激がないとみんなその問題に気が付かないと思います。
──そういったところからこれまでの慣習に疑問を持つことが必要ですね。

小袋:自分たちの価値は自分たちでちゃんと決めるべき。「音楽の価値ってなに?」とか「僕たちが作る対価はなに?」という本質的な問いをはっきりさせるのが、僕がアウトサイダーとしてやるべきことだと思っています。それをただみんなに言ったところではぐれ者だから、海外のスタンダードなシステムをビジネスとして提示するのが僕らのやり方です。しかも今までのやり方でやってきた人ではなく、これからの時代を担う新しいミュージシャンに伝えていく。でも、やっている内容はすごくシンプルです。単純に「いい曲作ろうぜ」ということだけ。
──参加する側としては、ラフな気持ちで参加した結果、日本にいながら海外のスタンダードに触れることができるのが魅力ですね。今後も続けていくかと思いますが、年に1回ぐらいのペースでしょうか?
小袋:年に2回やれたらいいですけど、あまり焦らずにやろうと思います。半年で業界が変わるわけではないので(笑)、地道に続けた先に何かあるというのを信じています。
──今思い描かれている、具体的な目標は何かありますか。
小袋:今はコロナで難しいけど、来年は海外のプロデューサーとかが日本に来て、日本のアーティストと一緒に曲を作ることができたら、音楽業界としてもニューチャプターが始まると思います。僕たちが海外の曲を真似するのではなくて、海外の作家と日本人のアーティストが対等にやる形の実現ですね。
──お話を伺っていると、海外の人に日本の優れた作家を紹介するというよりは、どちらかというと海外の優れた作家を連れてきて日本の作家と交流させるということで、日本の音楽業界に目が向いていますね。
小袋:その逆は、正直現状の日本の楽曲のクオリティだと難しいと思います。それに、日本はずっと昔から海外から色々取り入れて発展していった歴史があるんですよ。漢字だってそうだし、三権分立だってそう。だからまずは日本と海外をコネクトさせるために、輸出するよりはまず輸入する。それが第一歩だと思います。
──このソングライティング・キャンプが続いていくことで、少しずつ日本の慣習が変化することへ期待をしています。
小袋:そうしたい。僕はゲームチェンジャーとしてありたいし、ロンドンにいるのは、きっと神様が僕にこの2022年において、海外に門戸を開く使命をくれたってことだと思っているので。最後に言いたい、タイアップ、もう一度考えて。
──やはりそこですね(笑)。
小袋:ソングライティング・キャンプと関係ない話でいえば、問題はもっと沢山あります。それはまた次の時に「小袋くんが物申す」みたいなコーナーを作ってくれれば(笑)。

広告・取材掲載