【特別取材】TuneCore Japan 野田威一郎代表インタビュー「日本の音楽を世界に広めたくてTuneCore Japanを創った」― “音楽の民主化”を目指して(前編)

Photo:TOKYO Takashi
アーティストへの還元率100%で旋風を巻き起こすTuneCore Japan。野田威一郎代表は、サービス開始10周年を経て、いま改めて“All for Independence”の思いをさらに強めている。起業の原体験となった香港で過ごした少年時代から、TuneCore Japanを立ち上げた経緯まで、これまでの思いを語ってもらった。
(インタビュアー:Musicman発行人 屋代卓也、Musicman編集長 榎本幹朗 取材日:2024年5月16日)
プロフィール
野田威一郎(のだ・いいちろう)
チューンコアジャパン株式会社 代表取締役社長。1979年生まれ。東京都出身。香港で中学、高校(漢基国際学校)時代を謳歌し、1997年に日本に帰還。クラブでイベント企画、デザイナーをしながら、慶應義塾大学を2004年に卒業。同年、株式会社アドウェイズに入社、メディアディビジョンマネージャーとして上場を経験。2008年に独立しインターネットサービスでクリエイターを支援する会社「Wano株式会社」を設立。2012年には TuneCore Japan K.Kを立ち上げ、現在に至る。
大学時代、clubasiaで働き音楽業界を目指す
榎本:初めてお会いしたのが2013年で、TuneCore Japanを創業したばかりの頃でしたね。
野田:はい。まだSpotifyが日本に上陸していませんでした。
榎本:2016年に上陸ですから、今振り返ってもほんとうに早いですね。
野田:会社の立ち上げは2012年で、当初取り扱っていたのはiTunes Music StoreとAmazon MP3だけでした。
榎本:野田さんはそれ以前、何をしている方だったのですか?
野田:2008年にWano株式会社を創業しました。日本の文化を世界へ届けるITサービスを目指していて、2012年にアメリカのTuneCoreとジョイントベンチャーでTuneCore Japanを立ち上げました。
榎本:学生時代は?
野田:学生時代の間、足掛け6年ほど渋谷のclubasia(クラブエイジア)でバイトとして働いていました。向かいにあった系列のVUENOS TOKYO(ブエノス東京)の立上げやイベントオーガナイズをやっていて、昼間は学生イベントや対バンのブッキングをしたり、夜はクラブイベントをやったり。学生の間ずっとやっていました。
榎本:あの頃、クラブシーンが盛り上がってて、インディペンデントのアーティストが活躍してましたね。
野田:はい。アーティストもキャラの立ってる面白い人が多くて、一緒にいて楽しかったので「将来、こういう業界で働きたいな」と。元々、中学生から自分で音楽もやっていたんで。
榎本:音楽業界志望だったんですね。どんな音楽をやっていたんですか?
野田:最初はロックですね。中高時代、親の転勤で香港に住んでいたので入りはJ-POPではなくGuns N’ Rosesでした。そこから速弾きのハードロックに行って、邦楽だとXのhideが好きでカヴァーしたり。
榎本:ギタリストだったんですね。
野田:それで日本に帰ってきて、帰国当初はまだVUENOS TOKYOはなかったのですが、clubasiaの代表に気に入ってもらって。学生だったのですが自由にやらせてもらって、ダンス・イベントの立ち上げ、クラブ自体の立ち上げなどもやっていました。そうやって音楽がいつも近くにあったのが後に影響してきます。
榎本:卒業後、就職はどちらに?
野田:2004年にアドウェイズ(インターネット広告企業)へ就職しました。当時、20人ほどのベンチャーで2年後に上場しましたが、上場する前の2年、上場後の2年の約4年間ほど在籍していました。当時、代表の岡村さんは日本最年少での上場となり、会社自体は今は1100人を超える企業になっています。
榎本:まだガラケーの時代ですよね。
野田:Gree(グリー)やDeNA(ディー・エヌ・エー)が出てくるちょっと前ですね。
榎本:社員時代は何を?
野田:Webサービスを作る部署を立上げて部長として、プロデューサー的な仕事をしていたり、当時まだ成功報酬型の広告会社が少なかったので、その啓蒙や、代理店営業などデジタル・マーケティング全般を担当していました。
榎本:独立したのはなぜ?
野田:30代までには起業したいと思っており、やっぱり音楽を忘れられなくて。身につけたITのノウハウを使って音楽業界やアーティストに貢献できないかと思って起業しました。
原点となった少年時代 香港には日本があふれていた
屋代:香港で育った経験というのは今に影響してますか?
野田:色んなところで、影響していると思います。ひとつは日本の音楽が当時、香港でも今よりは強かったという感覚ですね。僕が香港にいたときは日本のテレビ番組や音楽は、今の韓国ドラマやK-POPのようにアジア圏で比較的視聴されていました。
あと僕らが身につけていた日本のファッション・ブランドやSONYのCD Walkmanなどの電化製品などに現地の中学生たちがすごく興味を持っていたのも覚えています。今思うと、その90年代初頭は日本企業がグローバルでまさに影響力を持っていた時代なので。
榎本:90年代に日本の音楽が香港で聴かれていたのが原体験としてあるわけですね。
野田:はい。その後、アジア諸国が発展して、日本企業の勢いが失われたことで日本の文化的影響が徐々に落ちていきましたが、「日本の音楽はもっといけるはずなのに。昔、日本語でも聴かれていたのだから、今でも絶対いけるはずだ」という確信のようなものはあって。
榎本:それがTuneCore Japanを創業した動機になっている?
野田:そういった日本の文化を世界へというのは、起業のモチベーションでもあり、TuneCore Japanを創業した2012年当時から「あなたの音楽を世界へ」と「インディペンデント支援」というのが、僕らのひとつのコンセプトでした。今ではみなさん言っていることかもしれませんが。
榎本:パイオニアですよね。
野田:いえいえ、もちろん業界の大先輩方はもっと前からやっていらっしゃったから、僕が香港にいた頃も邦楽が流れていたわけですし、日本のアーティストがライブにも来ていたので。
榎本:この前、Billboard JapanとLuminateのセミナーで聴きましたが今、香港でJ-Popのシェアは6.9%で、K-POPの半分くらいみたいですね。
野田:TuneCore Japanを始めた当初より、随分高くなったと思います。
榎本:野田さんが香港にいた頃はJ-POPがもっと聴かれていた?
野田:当時のシェア率はCD時代ですし、数値ではわからないのですが、J-POP自体が認知されていた感覚がありますね。中国のアーティストとか日本の曲を多くカバーしていたと思います。日本のドラマやアニメが海賊版だったけど普及していたことで、認知拡大が自然的に起きていた。これと同じ現象を韓国は国家施策としてお金をかけてアジア、東南アジア向けに行ったのだと思います。
日本の音楽を世界に広めたくてTuneCore Japanを創った
榎本:少年時代、香港でJ-POPが人気だったことが原体験としてあるわけですね?
野田:はい。「日本の音楽は絶対に広げられるはずだ」と。アジア圏で負ける気はしてなかったし、海外の仲間と話しても、日本の音楽のクオリティが低いとは誰も思っていない。単純に知らないだけではないか、という感覚があります。
屋代:だから世界に発信されていない日本の音楽をTuneCore Japanから届けようと。
野田:僕らは世界に配信できますし、当時もYouTubeを使って世界に公開できましたが、それを、しっかりと音楽ビジネスのコンセプトにして言うことが大切かなと思っていました。
あともうひとつ、インディペンデントのアーティストたちが平等に機会を与えられていないと感じていたこともTuneCore Japanを立ち上げたきっかけになっています。「それをやるのにインターネットを使おう。インターネットを使ったら世界にも目を向けよう」というのが順番だったかな。
榎本:アメリカのTuneCoreに野田さんから接触したのですか?
野田:はい。
榎本:ちょうどスマホの普及が始まったあたりですね。
野田:まさにそのタイミングだったので、僕はそれをIT側で見ていたんです。ガラケーでも着うたフルのような音楽配信はあったし、聴き放題もありましたし。
榎本:洋楽中心でしたが、ドコモで夏野さんが音楽サブスクをやっていましたね。
野田:Yahoo!もやってましたよね。それとTSUTAYAなどレンタルでCDを借りてリッピングするのが日本のスタイルでした。
榎本:そうでしたね。
野田:そこにスマホが出てきて「ガラケーでもなく、レンタルCDをリッピングするPCベースでもないWebベースの世界に変わっていく」と勝手に思ったんです。なので「大きな波が来るぞ。このタイミングを逃すと音楽シーンやアーティストに貢献することができないかもしれない。今こそ音楽に携わるサービスを考えよう」と。
榎本:なるほど。
野田:海外の情勢も見ていたのですが、もうストリーミング配信も出てきていて。
榎本:iPhoneの日本発売が2008年。翌年、ヨーロッパの一部の国でSpotifyがiPhoneアプリに登場しました。
野田:音楽の世界から4年ほど離れていたのですが、昔の仲間、アーティストたちにヒアリングすると、例えばヒップホップだとCDをお店に並べてもらうことすら大変でメジャーでのリリースとなるとハードルが相当高い、そういう課題を聞いていたんです。
それとiPhoneでApp Storeが登場して(2008年7月)、アプリを作る個人クリエイターが盛り上がった時期がありましたよね。アキネーターとか、自転車のミニゲームとか……
榎本:個人クリエイターが作った音楽アプリだと、turntable.fmが音楽業界で流行ってましたね。
野田:クリエイターがアプリを作ってスケールする、ああいう世界観の音楽版が出来ればいいなと当初、思っていたんです。
単身アメリカへ飛び、TuneCoreと話をつける
榎本:もうひとつ。大学時代、clubasiaで働いたことが野田さんの起業家としての原点になっているんですね。
野田:はい。
榎本:日本だとクラブミュージックもヒップホップも売上規模的にインディーズが基本じゃないですか。確かにCDを出すとなるとメジャーとサイズ感が合わなくなる。別にその音楽が劣っているからCDに出来ないという訳でもありませんでした。
野田:「マスに売れるものを売りたい」というのはビジネスとしては当然ではあるのですが、例えばヒップホップだったら当時でも海外ではちゃんと売れていた訳ですし。だから、そういう人たちが利用できるサービスにしたいな、というところに行き着いたんですね。それで、そういうサービスってないのかなと検索したらもうあったんですよ。
榎本:それがTuneCore。
野田:TuneCoreが他と「圧倒的に違うな」と思ったのは、アーティストに売上を100%還元するという点です。「素晴らしい。話を聞きに行きたい」と思ったのが始まりです。それでいろんなところで「TuneCoreって知っている?知り合い、いる?」と尋ねてまわったら、たまたま繋がっている方がいて、紹介してもらいました。それが2011年の5月。
榎本:野田さんは香港の中学高校で英語を使っていた?
野田:そうです。それが僕のメリットだったかもしれませんね。Skypeでリモート打ち合わせしたら「一度、こっちに来てほしい」という話になって、アメリカに行きました。
当時はジョイントベンチャー云々というのではなく、状況を探りに行くのが主な目的でした。もちろんプレゼン資料は持っていったんですが、その頃、TuneCore(US)は30人ぐらいの会社だったんですよ。創業が2005年だから5年目でそれくらいのベンチャーだったんですね。まだビジネス的に初期の段階だったので、日本やアジアのことなんか彼らは全然考えていなくて、やっとアメリカで事業が走り出したぐらいのタイミングでした。
僕らは「日本もスマホの普及が始まって、これから絶対変わるから。でも絶対、あなたたちだけじゃ無理だから自分にまかせてよ。ライセンスしてください」とまるで日本のバリバリの音楽業界人みたいに語って(笑)。帰ったら「ジョイントベンチャーならいいよ」と返事が来て、その後、進めていったという経緯ですかね。
榎本:30人の頃からということは野田さんも初期メンバーみたいなものですね。
野田:今となってはアメリカ含めて僕も相当の古株になっています。
アーティストへ100%還元。TuneCoreはインディペンデントのヒーローに
屋代:当時TuneCore(US)の創業メンバーたちは野田さんと同世代でしたか?
野田:上でしたね。ジェフ・プライスが創業者で、彼は当時、サウス・バイ・サウスウエストとかでインディペンデント・アーティストたちのヒーローになってました。インディペンデントのイベントに出まくって壁を突破した人で。
屋代:売上の100%をアーティストに還元するというのでヒーローになった?
野田:そうです。当時、音楽配信売上のアーティストへの還元率の低さがもう問題になっていて。
榎本:ジェフさんという人は元々、何をしてた人?
野田:レーベルにいた人です。それでアーティストがもらえる料率の低さに納得いかなかったらしく、「独立して自分でやる」と言ってAppleと交渉したのかな。
榎本:革命家魂を持った人ですね。
野田:そうですね。ジェフはアメリカでもパイオニアだったと思います。当時、TuneCoreも僕らのWanoもベンチャーですし「餅は餅屋でやる」ということで、一緒にやろうという形になりました。
榎本:AppleさんとはTuneCore Japanで契約したのですか?
野田:そうです。僕らは直接の契約です。相手がグローバル企業であっても、すべてのストアと直接契約しています。
榎本:その時は取り扱いアーティストさんがいなかったんですよね?
野田:なので、USのTuneCoreブランドを使わせてもらう必要があったんです。システムはスクラッチで、一からこっちで作り直して、契約は紹介だけしてもらってアメリカと別契約でAppleとAmazonの二社と契約を結んで、始まりました。
「音楽の民主化」を目指して
榎本:国内の配信業者は?
野田:当時はMTIさん、ドワンゴさん、レコチョクさんなど、着うたの名でガラケーにダウンロード配信があったんで、ドアを叩きに行ったんですがハードルが高かったんですよ。
榎本:それはどうして?
野田:僕らはサービス業なので利用者全員の作品を平等に配信します。作品のクオリティ自体には関与しません。そして、それまではCDも音楽配信でもどこかの事務所やレーベルに所属しなければ作品をリリースできなかったのを、音楽作品のリリースを民主化して開放した。それが僕らの一番の貢献だと思っていて。ただ、当時それに対してリスクと感じられていた面もあったようで、当初は大変でした。最初は今のように有名なアーティストが多く利用していたわけではありませんでしたし。
屋代:運送業でいえば荷主を選ばないということですね。
野田:もちろん最低限の利用ルールやテクニカルなルールは守っていただきますが、クオリティを僕らが判断することはないというコンセプトでやっています。最近、話題になっている不正ストリーミングには当然対処していますが、ルールに則った上でのクリエィティヴィティは担保されていますし、「どんな人が曲を作っても第三者の権利を侵害しなければその人の作品です」というスタンスです。
「音楽の民主化」がまさに起業の志です。以前は本当にインディペンデントのアーティストたちや、特定のジャンルは作品をリリースするのが大変だったと思うので。僕らは今でこそヒップホップやボカロに強いと言われますが、一定のアーティストやジャンルがチャートを独占して硬直化していた少し前の時代においても水面下ではロックやヒップホップ、ボカロ、その他様々なジャンルの音楽をやっている人たちはずっといたじゃないですか。
榎本:なるほど。あの時代、抑圧された音楽ジャンルがたくさんあってTuneCore Japanが誕生する土壌ができていたんですね。
※後編:TuneCore Japan、国内ストリーミングシェアでユニバーサル、ソニーに次ぐ国内3位の存在感 「単なるディストリビューターを超えて」野田威一郎代表が語る次のヴィジョン に続く
著者プロフィール
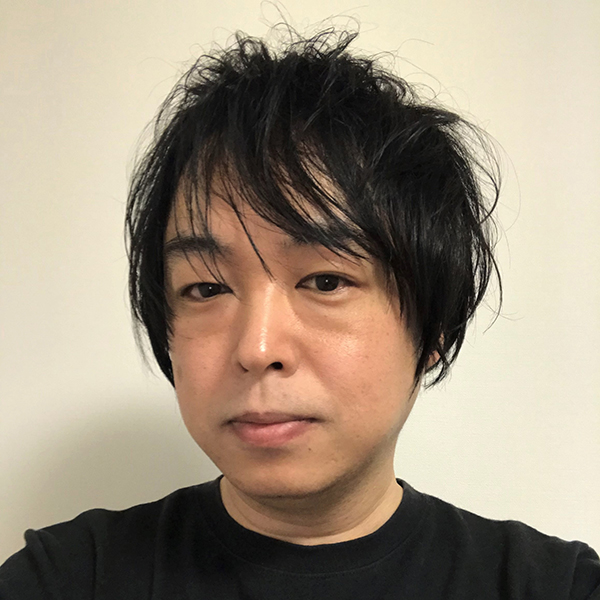 榎本幹朗(えのもと・みきろう)
榎本幹朗(えのもと・みきろう)
1974年東京生。Musicman編集長・作家・音楽産業を専門とするコンサルタント。上智大学に在学中から仕事を始め、草創期のライヴ・ストリーミング番組のディレクターとなる。ぴあに転職後、音楽配信の専門家として独立。2017年まで京都精華大学講師。寄稿先はWIRED、文藝春秋、週刊ダイヤモンド、プレジデントなど。朝日新聞、ブルームバーグに取材協力。NHK、テレビ朝日、日本テレビにゲスト出演。著書に「音楽が未来を連れてくる」「THE NEXT BIG THING スティーブ・ジョブズと日本の環太平洋創作戦記」(DU BOOKS)。現在『新潮』にて「AIが音楽を変える日」を連載中。

広告・取材掲載